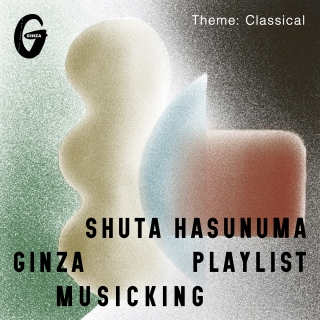音楽を軸にしながら、アート、舞台、広告などで自由自在な活躍を見せる蓮沼執太さんのプレイリスト&コラム連載。毎回、知っているようで知らないちょっぴりコアなテーマを深堀り。蓮沼さんと一緒に、あたらしい音楽の扉を開きましょう。
蓮沼執太のMUSICKING|Playlist vol.2「クラシック」
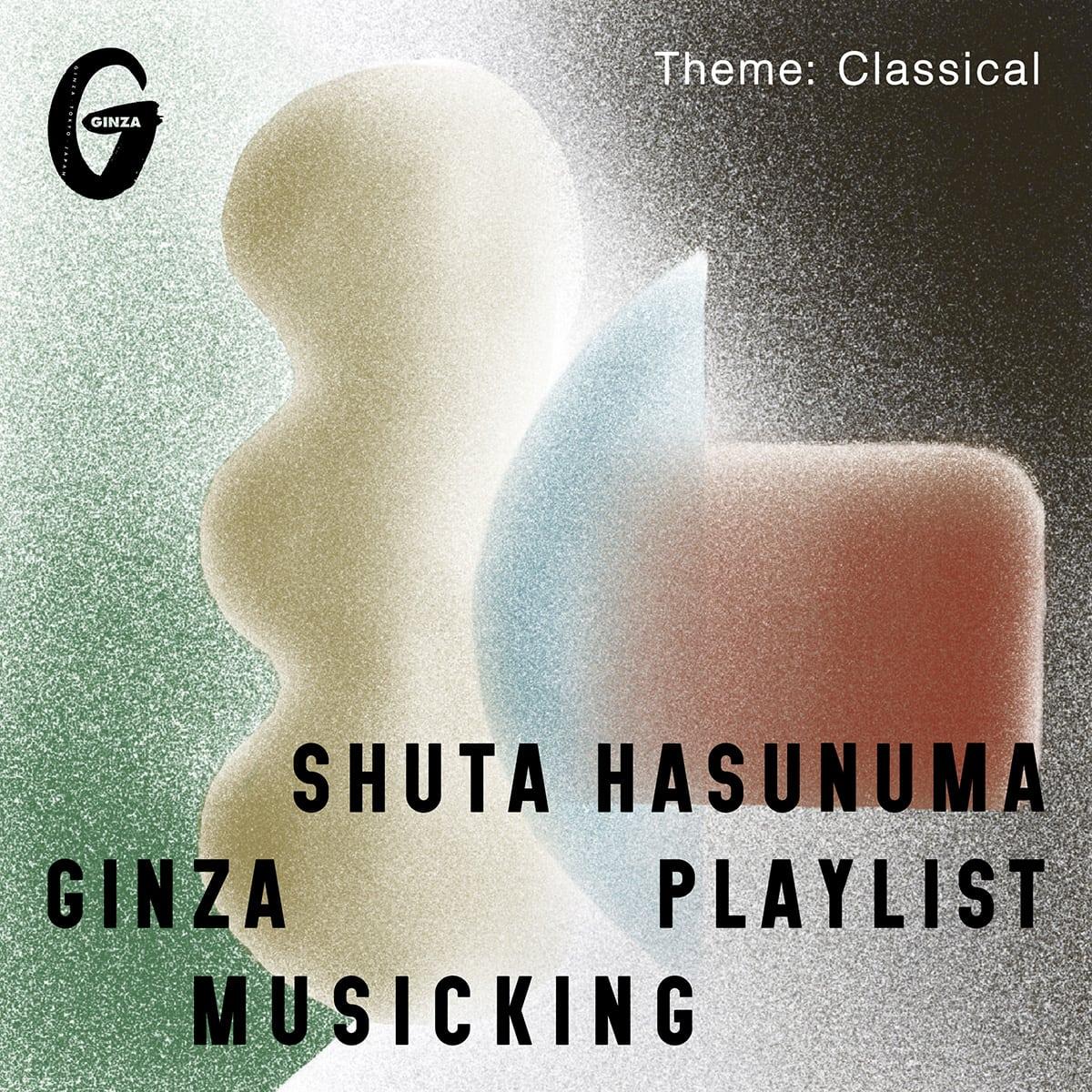
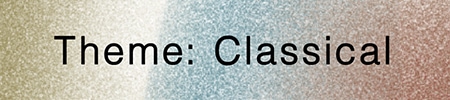
プレイリスト「デトロイト」を
Apple Musicで聴く
Spotifyで聴く
「クラシカルな音楽は『クラシック』という一言で括れないほど、どんどんジャンルが派生してきています。例えば『ポストクラシック』というジャンルがあったりして、それはエレクトロニカやニューエイジから生まれました。エレクトロニック・ミュージックの文脈の中でクラシックを再解釈することで、逆に生楽器が持つ響きや空間、そして音の質感を重視するような音楽です。
そんな風に年々、新しい解釈が生まれているクラシック。今回は現代を生きるクラシカルな音楽の形として、僕が気に入っている曲をまとめてみました。曲順は、それが生まれた場所や時代などで緩やかに繋がっています。秋にぴったりな雰囲気もあると思うので、ぜひ楽しんで聴いてください」

#1 Max Richter / Mercy
「ドイツ生まれのイギリス人作曲家マックス・リヒターが、ノルウェーのヴァイオリン奏者マリ・サムエルセンとコラボレーションした楽曲。リヒターが1948年の国連総会で採択された『世界人権宣言』にインスピレーションを受け、10年構想したというニューアルバム『VOICES』から」
#2 Hildur Guðnadóttir / Elevation
「アイスランドのチェリストでもあり、作曲家のヒドゥル・グドナドッティル。映画『ジョーカー』のスコアでも知られています。この曲は2009年の作品で、深海を漂うような弦の響き、重なりが幻想的です」
#3 Valgeir Sigurðsson / Communication
「またもアイスランド出身の音楽家、プロデューサーのヴァルゲイル・シグルズソンによる楽曲。サム・アミドン、ティム・ヘッカー、そしてビョークらの共同プロデュースなども行なっている彼が担当した、ドキュメンタリー映画のサウンドトラックから」
#4 Nico Muhly / Clear Music
「シグルズソンのレーベル『Bedroom Community』に所属している、ニコ・マーリーの初期作品を1曲。ミニマルに展開するアレンジ、室内楽的なアプローチがタイトに響きます」
#5 David Lang /
Love Fail: Right and Wrong
「さらに、ニコ・マーリーと親交が深いデヴィッド・ラングによるシアターピースのサウンドトラックを。言葉が丁寧に配置された声楽曲」
#6 Johann Johansson /
Part 1 / IBM 1401 Processing Unit
「2006年にアイスランドの音楽家ヨハン・ヨハンソンが、イギリスのインディーレーベル『4AD』から発表した楽曲。この作品以降、映画音楽の仕事が増えていったんですが、すでにどこか映像的な描写があります。エレクトロニカの文脈から登場してきたヨハンソンの新しい一面が垣間見れた、素晴らしい1曲」
#7 Goldmund / My Neighborhood
「ヘリオスやミント・ジュレップの名でもコンスタントに活動中の、キース・ケニフによるプロジェクト・ゴールドムンドが、2005年にリリースした楽曲。アップライトピアノをミュートさせて演奏することで、弦を叩くハンマーのアタック音までも音響的に取り入れる手法がこの15年くらい流行っていますが、このアルバムではそれがいち早く取り入れられていました。トレンドの手法を、西洋的ではない朴訥としたメロディーと組み合わせることで、ポップとしての完成度を高めています」
#8 Gérard Grisey (Barbara Hannigan & Ludwig Orchestra) /
Quatre chants pour franchir le seuil for Soprano & Ensemble: Prelude – 1. la mort de l’ange by Gérard Grisey
「ムードを変えてジェラール・グリゼー作の楽曲を、エーテボリ響首席客演指揮者に就任した、ソプラノ歌手でもあるバーバラ・ハンニガンのコンセプチュアルな作品集から。荘厳な音像は聴き手の集中力をかきたてます」
#9 Dai Fujikura / Secret Forest
「藤倉大さんによる楽曲は、特殊奏法やノイズ的なアプローチも感じさせる一方、随所の旋律が美しく、独特な音空間を作り上げています」
#10 Laraaji / Prana Light
「一転して、ララージのピアノ作品から。彼はブライアン・イーノとのコラボレーションでも知られ、ツィターやムビラなどの奏者でもある。この曲は2020年に発表されたんですが、先述のように流行りのミュートされたピアノ作品かな、と思ったら、鍵盤を弾きまくっている動的なアンビエントを展開していました」
#11 Aki Takahashi, Hiroshi Koizumi, Yoshiaki Suzuki, Avoko Shinozaki, Yasunori Yamaguchi /
Breathing Field for Flute, Clarinet, Harp, Percussion and Piano
「さらにさらに一転して八村義夫さんが作曲した室内楽の中から、高橋アキさんなどの演奏による1981年作の作品を」
#12 Hilmar Jesson, Arve Henriksen and Skuli Sverrisson /
Undan
「再び場所を北欧に戻し、ノルウェーのトランペット奏者アルヴェ・ヘンリクセン、アイスランドのギタリストのヒルマー・イエンソン、ベーシストのスクーリー・スヴェリッソンによるトリオ作から」
#13 Lucy Railton / For J.R.
「チェリストでもあり、先進的なサウンドワークを展開するルーシー・レールトンのデビューアルバムより。チェロの音はもちろん、フィールドレコーディングや言葉の断片などで『インダストリアル』と形容される音像ですが、その奥にある旋律の構造にはとても落ち着きがある」
#14 Giuseppe Ielasi /
01 (Five Wooden Frames)
「最後の楽曲はイタリアのサウンド・アーティストのジュゼッペ・イエラシの新作から。アコースティック・ギターの音が素材となっているそうですが、それらしい音色はまったく聴こえてこない。でも宙に浮くような音像には、確かに生楽器の質感を感じます」
🗣️
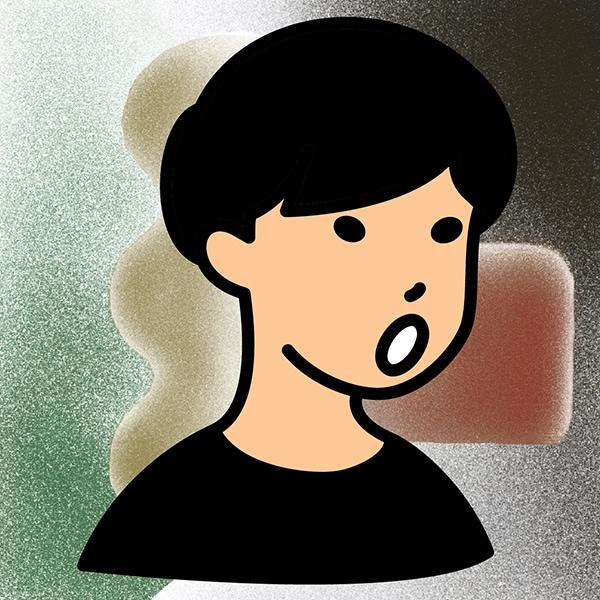
蓮沼執太
音楽家・作曲家。1983年生まれ、東京都出身。蓮沼執太フィルを主宰し、国内外でのコンサート公演をはじめ、映画、演劇、ダンス、CM楽曲、音楽プロデュースなどを多数手掛ける。また作曲という手法を応用して、彫刻、映像、インスタレーションを発表し、展覧会やプロジェクトを活発に行う。最新アルバムに、蓮沼執太フィル『FULLPHONY』(2020)。個展『 ~ ing』(東京・資生堂ギャラリー 2018)では、『平成30年度芸術選奨文部科学大臣新人賞』を受賞。
shutahasunuma.com
@shuta_hasunuma
Design & Illustration: Kohji Fukunaga, Mana Yamamoto Edit: Milli Kawaguchi