間を取る、間合い、間抜け、間が良い、間違い。 時間・空間は、西欧からTimeとSpaceに、どちらの意もある「間」をあてたもの。「間」には、どうも日本特有の都合良さがある。でも、うまくやれたら、キツキツな毎日にもちょっと余裕ができそうだ。変幻自在の「間」の根っこを求めて、キーワードをあげながら徒然なるままに解いてみる。
東京でみつけた「間」代官山ヒルサイドテラス

―代官山ヒルサイドテラス―
 旧山手通り沿いの奥。モダン建築と樹々が織りなす景色のレイヤーが幾重も重なる。
旧山手通り沿いの奥。モダン建築と樹々が織りなす景色のレイヤーが幾重も重なる。
旧山手通りの奥
代官山の旧山手通り沿いには、低層のマンションのような建物と鬱蒼とした樹々が織物のように編まれた景色が続いている。「代官山ヒルサイドテラス」(*4)と名のついたこの建物群は、1969年以降、まるでアメーバのようにじわじわと増築されている。その変化はあまりに自然過ぎて、気づかない人は多いだろう。建物といっても、全体像はよくわからない。それは映画のように、いくつかの場面が連なったシークエンスの記憶として残る。大きな樹と建物の向こうには小さな広場があり、その向こうには小路が抜けている。奥へ奥へと視線は吸い込まれるが、手前にある樹が邪魔をして判然としない。あの向こうにあるのは、秘密の園だろうか。
 ガラスと壁の間に見つけたジグザグ。行き先を決めず、ただ目の前の小路をたどるのもいい。
ガラスと壁の間に見つけたジグザグ。行き先を決めず、ただ目の前の小路をたどるのもいい。
見えたり隠れたり
奥に進むとは、中心やある目的に向かうより、先がわからぬまま真相へと近づくことだと思う。道はカクカクと曲がって、その度に風景は変わり、いつしか方向感覚さえ失う。この不安と楽しさが入り混じる見え隠れは、実は各地の町並みに共通する。
はるか昔、桂離宮での遊びは、庭に引いた人工の曲水(小川)に小舟を浮かべ、曲がりくねった川を流れながら、お酒を呑み呑み移ろう景色を楽しむものだった。そんな優雅な道行ではないけれど、現代の初詣の醍醐味は混雑した参道での買い食いやおしゃべりだったりする。もうすぐ境内に入れると思ったら、列はヘアピンカーブをなして、ゴールはまだまだ先だ。でも、それってほんとにゴールなのかな?
深める一冊
『見えがくれする都市 ―江戸から東京へ』
槇 文彦、若月幸敏、大野秀敏、高谷時彦 (1980 鹿島出版会)
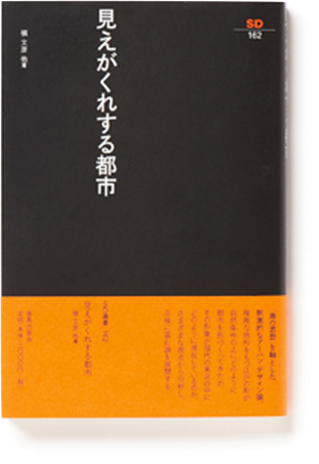
ヒルサイドテラスの設計者・槇文彦による「奥の思想」を軸に、東京に潜在する江戸を解析した都市論。



























