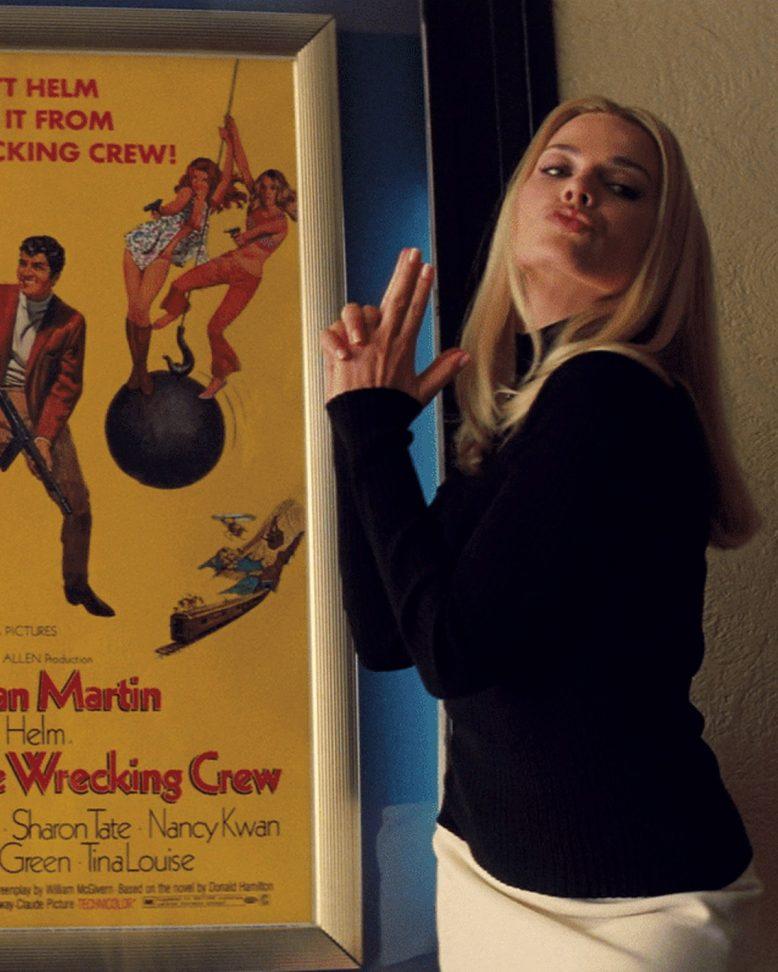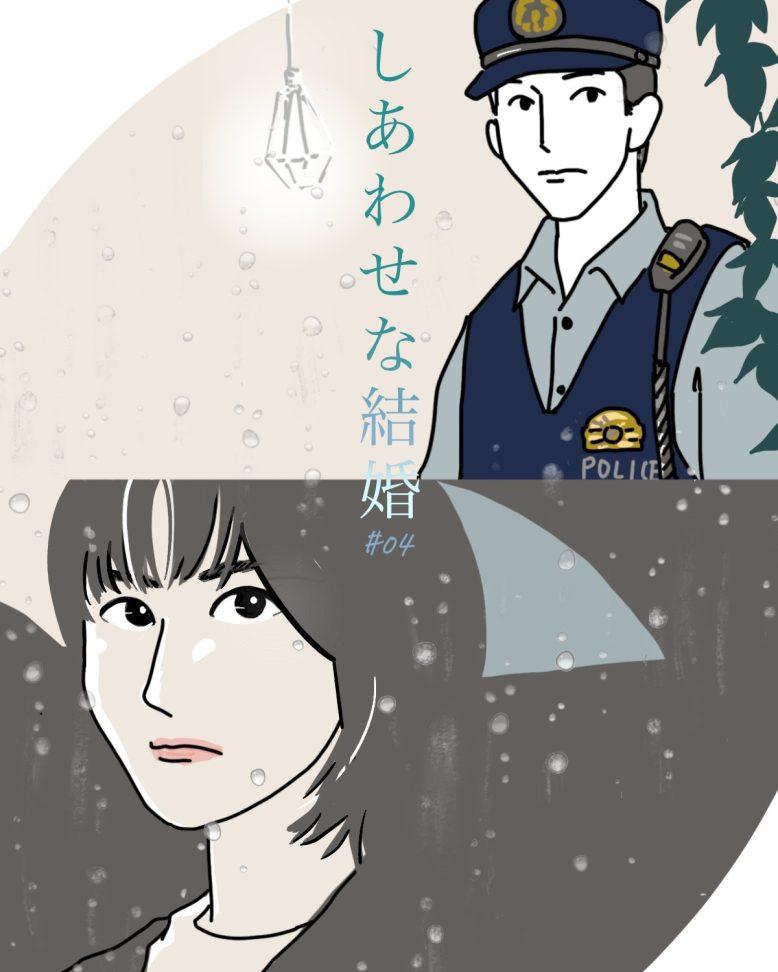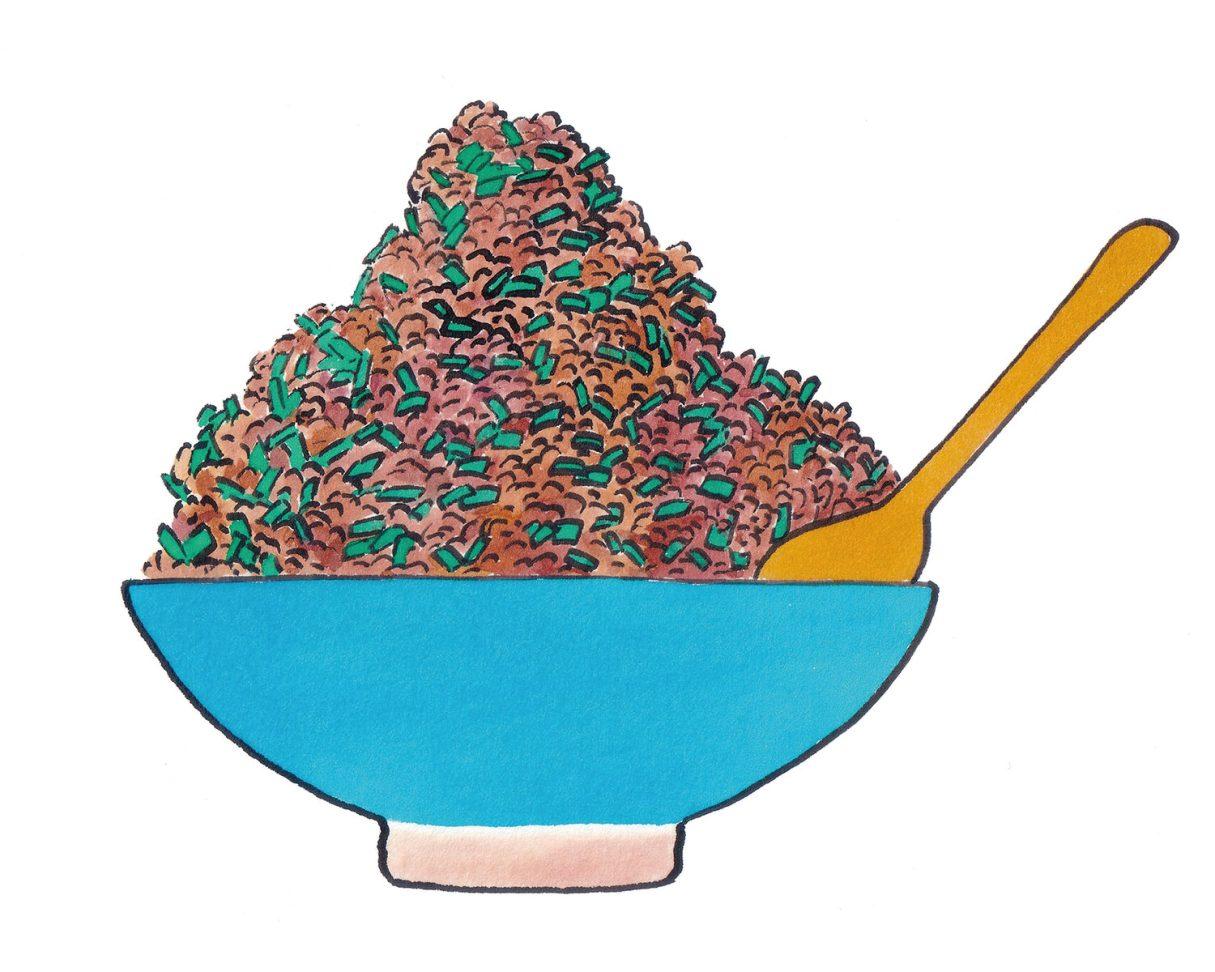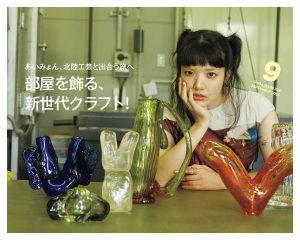クリエイターが描く理想とは?“ワードローブの部屋”にまつわる、夢のかたちを聞きました。
建築家・藤本壮介のクローゼット哲学「服が見え隠れするくらいが魅力になる」

しまい込まない隠さない
服が見え隠れするくらいが魅力になる
パリと東京の2拠点で活躍する建築家の藤本壮介さん。昨年末には全体設計・改修を担った群馬県前橋市の[白井屋ホテル]が完成し、注目を浴びている。過去にはユニークな住宅を手がけている藤本さんにとって、クローゼットとはどんな存在なのだろう?
「大抵の人は収納家具やクローゼットを、家の中にある散らかったものをきれいにしまうためのもの、隠して見えないようにするためのものと捉えていますよね。僕のクライアントも同じく、ものをすべて収納して、インテリアをすっきりと見せることを希望される方が多いのは事実です。もちろん、家の中が雑然としているより、整頓されている方が望ましい。けれども同時に、あまりにもクリーンでミニマルに、何もかも隠してしまうよりも、ちょっとだけその人の服や持ち物が見えているほうが、人となりが感じられて素敵なんじゃないかなぁとも思うのです。雑然と散らかっているか、完璧に整頓されているかの二択ではなくて、その中間の〝生き生きと整頓されている〟という状態がいいなぁと。たとえば、建築の近代化に重要な役割を果たした20世紀の巨匠建築家ル・コルビュジエの作品集を見ると、図面や写真の他に彼自身が描いたパースの絵や室内のスケッチがたくさん載っています。そこに描かれたクローゼットや収納戸棚の絵が、みんな半分ぐらい扉や引き戸が開いていて、中に洋服や食器が入っている様子まで描いているんですよ。当時は彼の代表作である[サヴォア邸]のように、モダニズム建築と新しい生活様式が生まれた時代です。前時代的な装飾を一切削ぎ落とした幾何学的な建築に、あえてこういう生活感のある絵を描き残したということは、コルビュジエは住む人の趣味性や生活スタイルが垣間見えて、それが引き立つような家のあり方を大事にしたのではないかと思ったのです」
なるほど。具体的に思い浮かぶ理想のクローゼットはあるのだろうか?
 アイリーン・グレイが1929年に南仏カップマルタンに建てたヴィラ[E-1027]のゲスト用ベッドルーム。作りつけのクローゼットの中はセルロイドの内装にガラスの棚板で、開け放しても美しい。左端に回転式の引き出しが3つ付いている。
アイリーン・グレイが1929年に南仏カップマルタンに建てたヴィラ[E-1027]のゲスト用ベッドルーム。作りつけのクローゼットの中はセルロイドの内装にガラスの棚板で、開け放しても美しい。左端に回転式の引き出しが3つ付いている。
「コルビュジエとも親しかった女性家具デザイナーであり建築家のアイリーン・グレイが南仏カップマルタンに建てたヴィラ[E-1027]を4〜5年前に見学しに行ったことがあります。クローゼット自体がどうだったか記憶が曖昧ですが、棚や収納やランプなどいろいろなものが凸凹と壁から出たり引っ込んだりしているような設計なのです。ちょっとしたアルコーブ(窪み)があって物を置けるようになっていたり、クローゼットの角の柱部分が回転して引き出しが出てきたり。まるで家そのものが作り付けの家具のようなのです。そこには、扉で隠しておかなければならないものは何もなく、むしろ生活がいろんな形で現れてくることこそ美しいのだという彼女の哲学が感じられました。僕もそこに共感し、服やお皿やタオルといった生活の痕跡が家の中でひょっこりと顔を出すようなデザインが魅力的だと思うのです。以前手がけた[House NA]は部屋ごとに壁で仕切らず、異なる床レベルの空間が組み合わさっている棚のような家で、いろんなところに居場所がちりばめられていますが、ここのクローゼットは完全にオープンです。どこからでもアクセスできるし、持ち物も人間と一緒に生き生きと暮らしに参加している感じです」

©IWAN BAAN
藤本壮介設計の住宅[House NA]。「いろんなところに居場所があると面白いね」という施主との会話から、空間が積木のように重なった家が生まれた。棚のように組み合わさった空間の一部、左上にオープンクローゼットが見える。
しかし、その人らしさが垣間見られるようなインテリアは、実は高いレベルのセンスが問われるのではないだろうか?
「僕自身、偉そうなことは言えないぐらい、実は生活者としてはまだまだ未熟です。5歳の息子ともども散らかしては、妻に怒られています。でも、アイリーン・グレイのヴィラみたいな、初めから半分ぐらい見せることを想定したデザインをクローゼットにも応用すれば、僕のような生活下手な人間にとって便利かもしれませんね。持ち物全部をオープンにして見せようとするとハードルが高いですが、半分だけなら表向きの体裁と親密さのうまい釣り合いがとれそうです」
🗣️
藤本壮介
1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。東京とパリに事務所を設立。仏・モンペリエの集合住宅[L,Arbre Blanc]、[UNIQLO PARK 横浜ベイサイド店]など国内外から注目を集める。