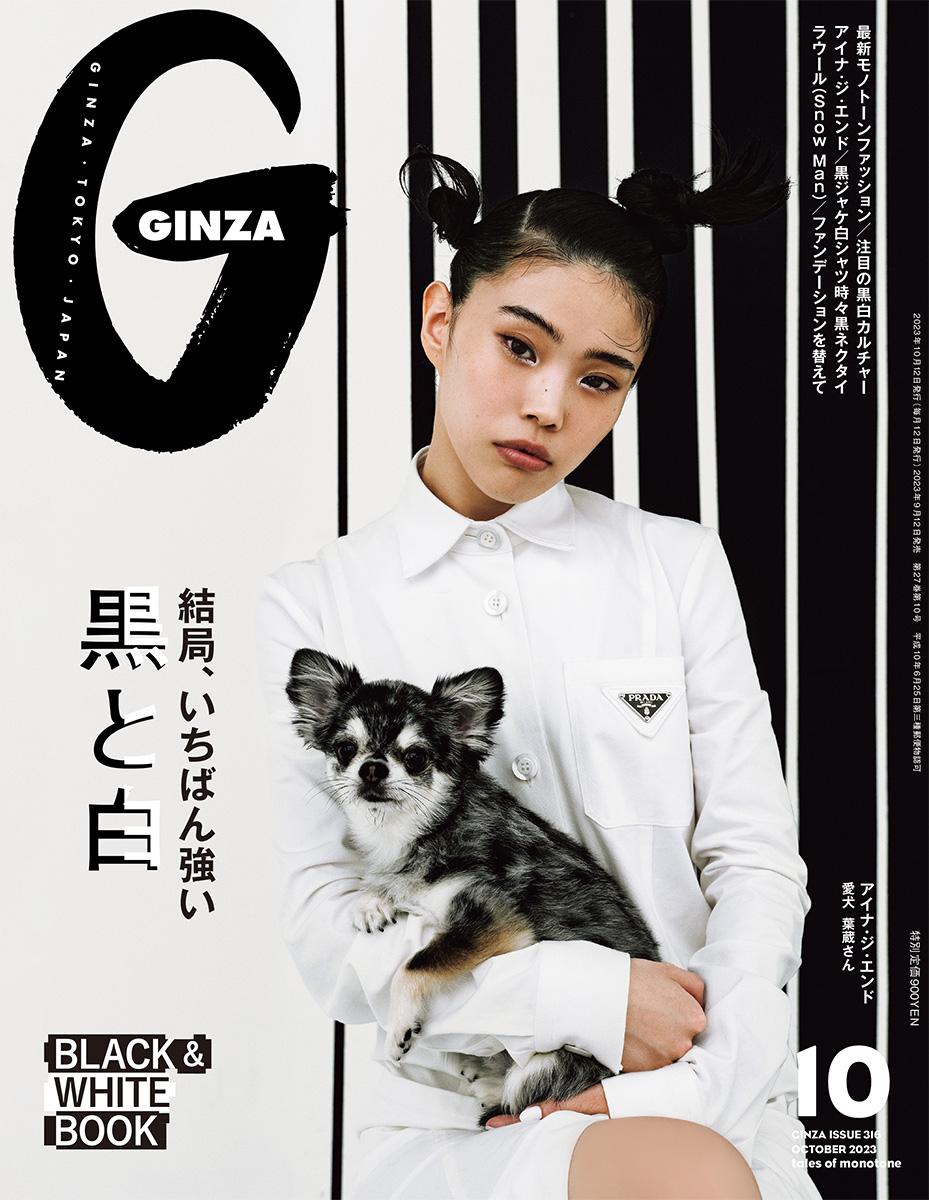どこか神秘的で、どんな鮮やかな色よりも、ときに雄弁なメッセージを帯びる黒と白。歴史と文化的視座から永遠の定番色を考察する。
西洋画と東洋画、日本の服飾史における“黒と白”の変遷
歴史と文化的視点から“色なき色”を読み解く
西洋画と東洋画、日本史上の黒と白の捉え方
数多ある色彩の極地に存在する、黒と白。古の人々はふたつの色に、どんなイメージを重ね合わせたのか。西洋と東洋(日本)における変遷をたどるべく、まずは美術史家の宮下規久朗さんのもとを訪ねた。
「キリスト教世界では光は善、つまり神を意味し、影は闇や悪を意味することから、白はポジティブで黒はネガティブなイメージが連想されがちです。しかし、黒と白が意図することは文化圏によって異なるため、一概には言いにくいところがあります」
白が持つ、汚れのない無垢なイメージは、原罪を持たずに生まれたとされる聖母マリアと重なり、ネガティブな色として捉えることはほぼないが、複雑なのは黒のほう。
「宗派にもよりますが、聖職者は黒の衣をまとっていますし、王侯貴族の衣装も歴史的に黒が多く、フォーマルな装いの定番でもあります。どちらも〝色がついていない〟という意味では、純粋さや誠実さを表すことにつながっていたのでしょう。西洋美術史において、白と黒は対等であり、モノクロームとポリクロミー、つまり単色か多色かという分け方をよくやります」
絵画でモノクロームといえばデッサン。
「西洋絵画の基本で、イタリア語ではディセーニョといいますが、素描という意味のほかにコンセプトやアイデアという意味も。ルネサンスでは、モノクロームで描くグリザイユという技法があり、[ヘントの祭壇画]のようにひとつの絵画にモノクロと多色の部分が共存する場合、モノクロは神のお告げや、夢の中の情景などを表現することが多く、神聖なものとされていました。
ファン・エイク
[ヘントの祭壇画] 1432年
![歴史と文化的視点から〝色なき色〟を読み解く 西洋と日本の黒白の変遷 [ヘントの祭壇画]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.ginzamag.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F09%2F1-pic.jpg&w=3840&q=90)
時代とともに、色彩に重きを置く議論も出てきますが、それを排除するほうが純粋であり、イデア(理想)に近づけるという伝統的な考え方があったのです」
Text_Ikuko Hyodo