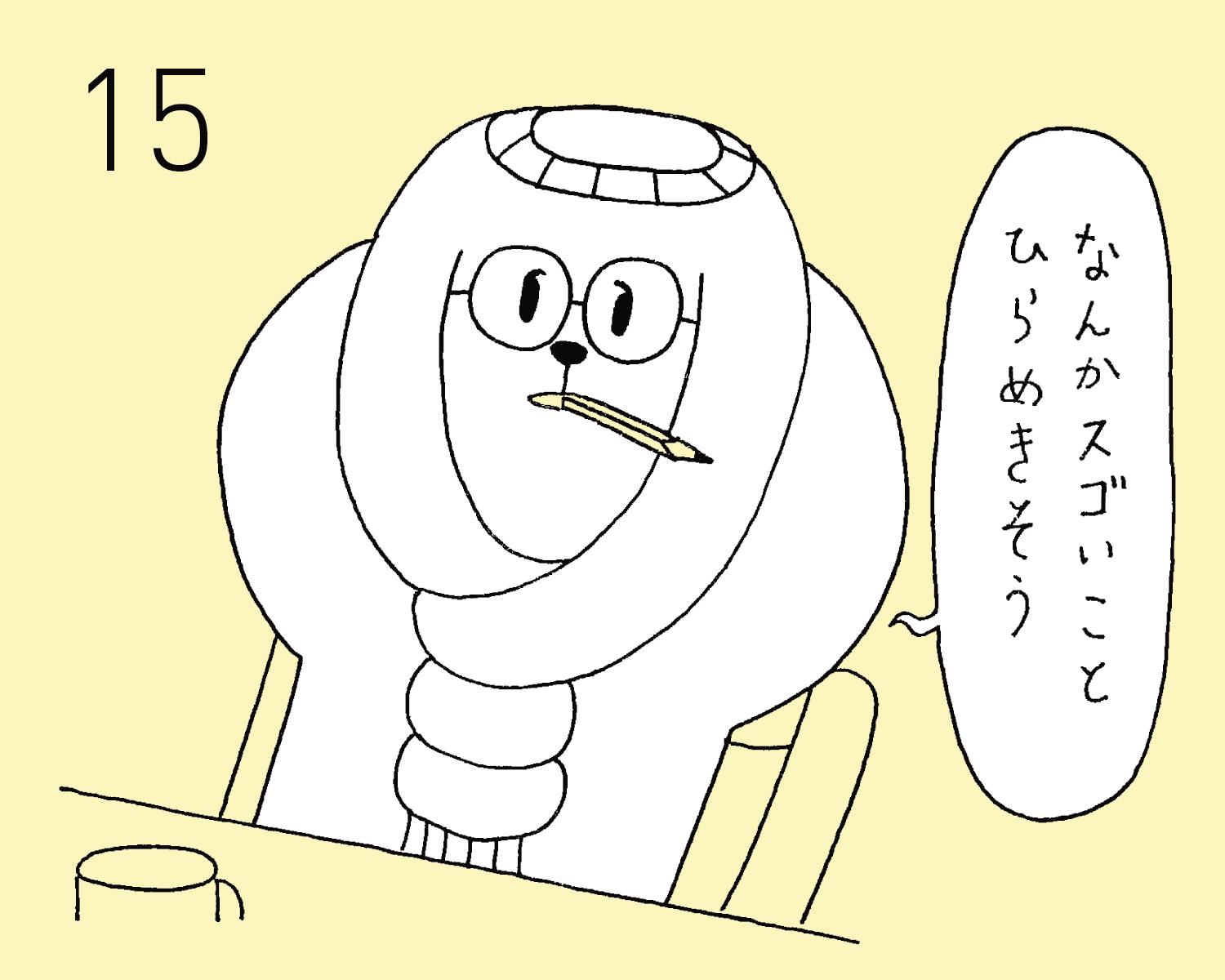結局、インターネットは私たちをどう変え、どこに連れていくのか
美術館で探る、ポスト・インターネットの行方

インターネットが日常に浸透し、リアルとヴァーチャル空間がシームレスにつながり、人工知能などのテクノロジーの進歩が新しい世界の扉を…というような枕詞は、この20年の技術革新を語る上でよく聞く言葉である。実際、そのような進歩は人間にどんな影響を与えてきたのだろう。その問いに応答するような2つの展覧会が開催中だ。
1つ目は、水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催中の『ハロー・ワールド ポスト・ヒューマン時代に向けて』展。この展覧会では、映像史やメディア史への考察を背景にデジタルによる監視社会の矛盾などをテーマに作品をつくるヒト・シュタイエルをはじめ、ブロックチェーンの技術とその影響に焦点をあてたサイモン・デニーなど、近年の技術革新や社会に鋭く応答した、計8組のアーティストが作品を出展。どの作品も人間や社会の未来を予見するものとして興味深い。
『ラファエル・ローゼンダール: ジェネロシティ 寛容さの美学』
開催中〜5月20日/十和田市現代美術館



Much Better Than This, Times Square Midnight Moment, New York, 2015 Photography by Michael Wells, Christina Latina Nova, Museo Image E Son, Sao Paulo, 2012
作家にとって世界初の公立美術館での個展。鮮明な色と形による動く絵の作品が16本連続して現れる大型映像インスタレーション、グーグルなどの有名なウェブサイトの構図を抽出したジャカード織でつくられたタペストリー作品、英語で書かれた「俳句」作品、インタラクティブな映像作品などが、美術館のリアルな空間に出現。
2つ目は、十和田市現代美術館で開催中の『ラファエル・ローゼンダール: ジェネロシティ 寛容さの美学』展。ローゼンダールは、インターネット空間を発想と表現の場とし、リアルとヴァーチャルの場で活躍するアーティストである。年間5000万アクセスを誇る彼のウェブサイトは、色彩豊かで詩的なプログラム映像であふれている。ネットを通じてアクセスできる作品のオープンネスは、まさに「寛容さの美学」という彼の作品に通底する思想だ。彼の作品を見ると、インターネットの素晴らしさが、個々の思想の多様性を認める自立分散性にあったことを思い出させる。
『ハロー・ワールド ポスト・ヒューマン時代に向けて』
開催中〜5月6日/水戸芸術館現代美術ギャラリー


写真上: レイチェル・マクリーン[大切なのは中身]2016 Commissioned by HOME, University of Salford Art Collection, Tate, Zabludowicz Collection, Frieze Film and Channel 4. 写真下: サイモン・デニー [ブロックチェーンの未来予測/フェア用ブースと特別郵便切手: イーサリアム(リンダ・カンチェヴとの共作)]2016 展示風景: 第9回ベルリン・ビエンナーレ、ドイツ、2016 撮影: Hans-Georg Gaul Commissioned and coproduced by Berlin Biennale for Contemporary Art Courtesy of the artist and Galerie Buchholz Cologne / Berlin / New York(参考図版)
技術革新がもたらす社会への影響を考える作家8組による展示。セシル・B・エヴァンス(アメリカ)、小林健太(日本)、エキソニモ(日本)、デヴィッド・ブランディ(イギリス)、ヒト・シュタイエル(ドイツ)、谷口暁彦(日本)、サイモン・デニー(ニュージーランド)、レイチェル・マクリーン(イギリス)といった国際舞台で活躍するアーティストがずらり。
どちらの展覧会も、技術革新に伴う社会の変化、またはアートの存在について考えさせられるものである。と同時に、注意深く作品に向き合うと、技術革新の荒波の中で、変わらない人間の本質や思想も垣間見えてくる。目に見える変化に踊らされることなく技術の進歩と向き合うこと、その方法をアーティストたちは静かに提示してくれているのである。
Text: Shintato Maki