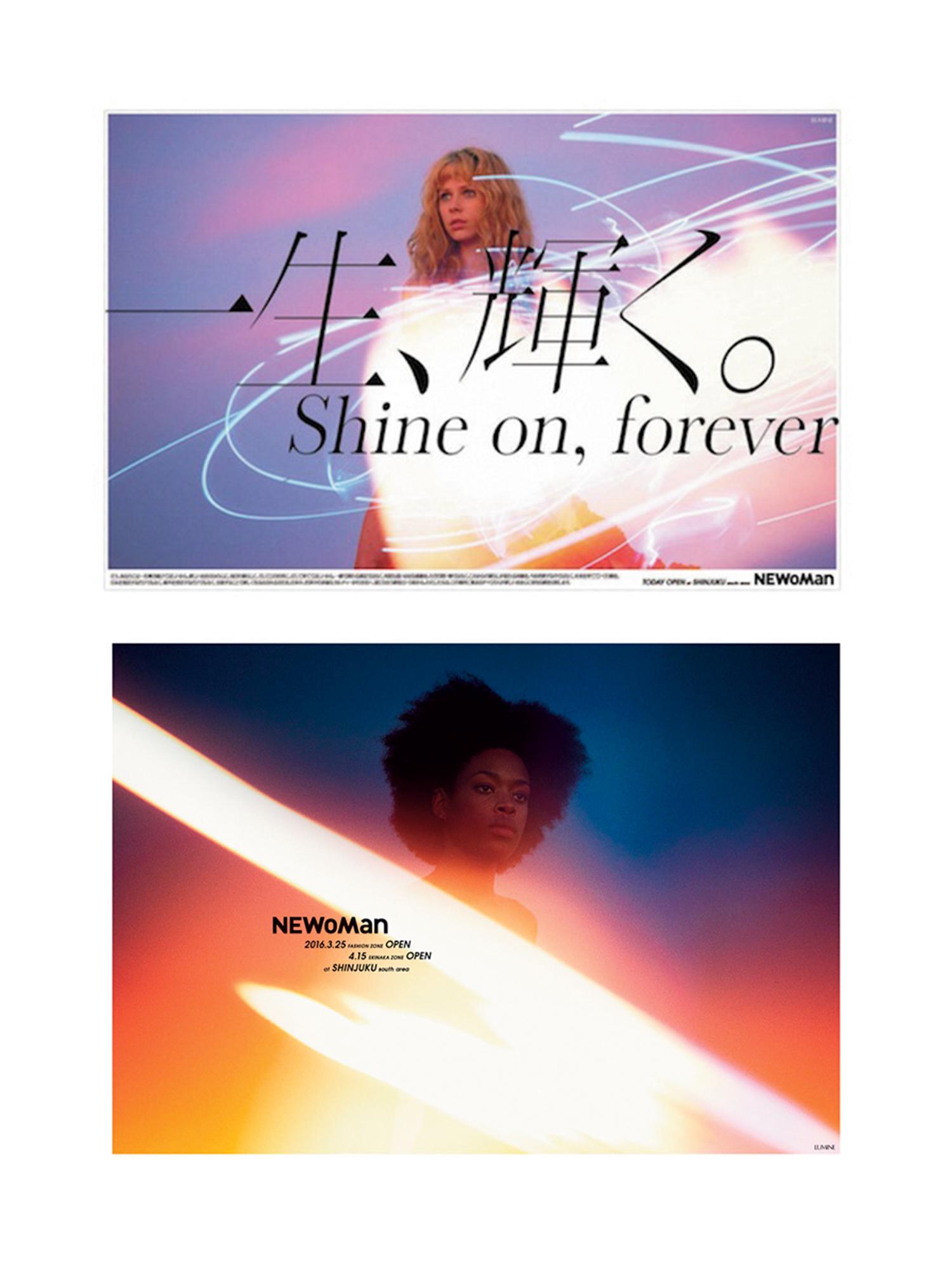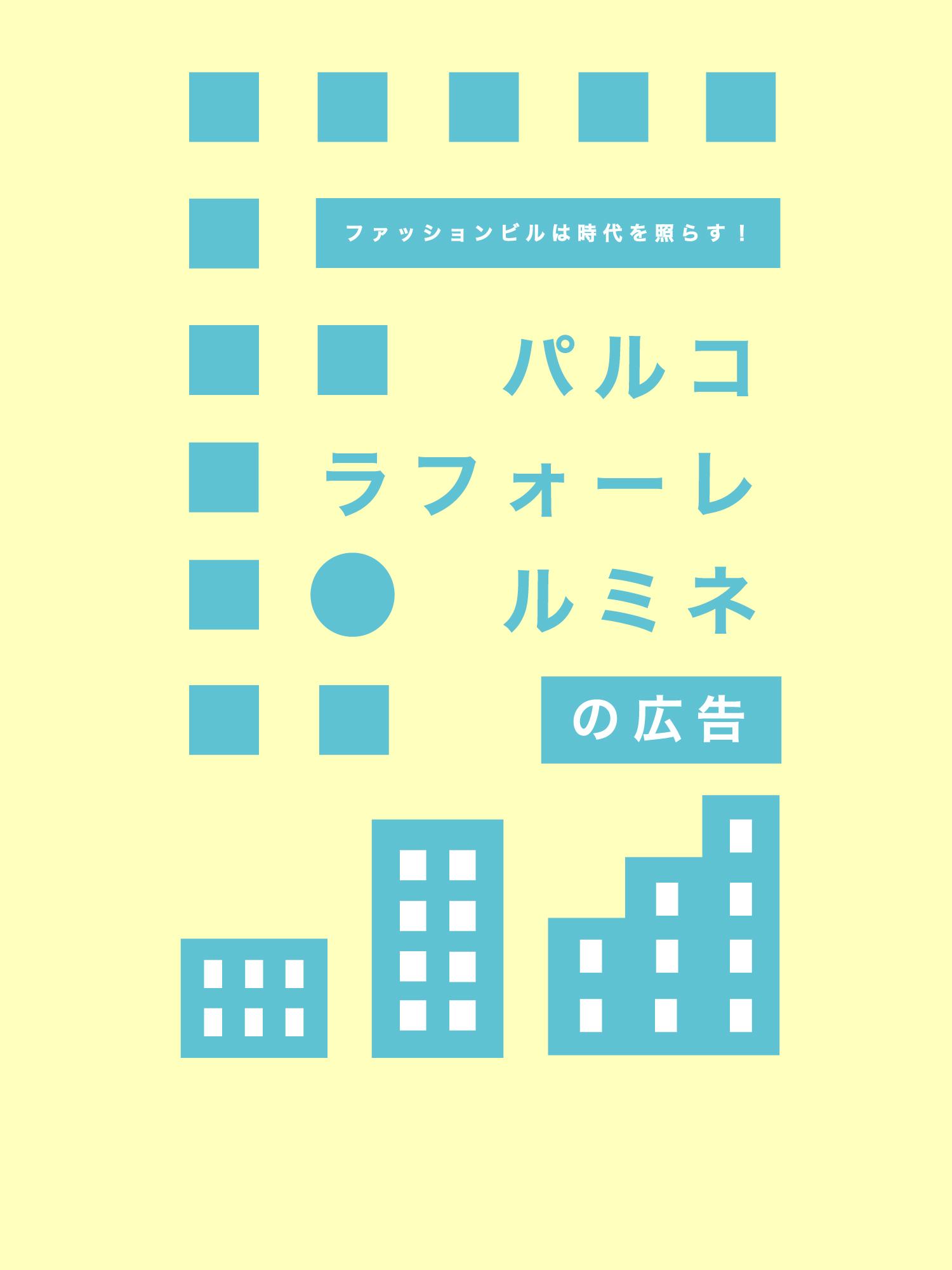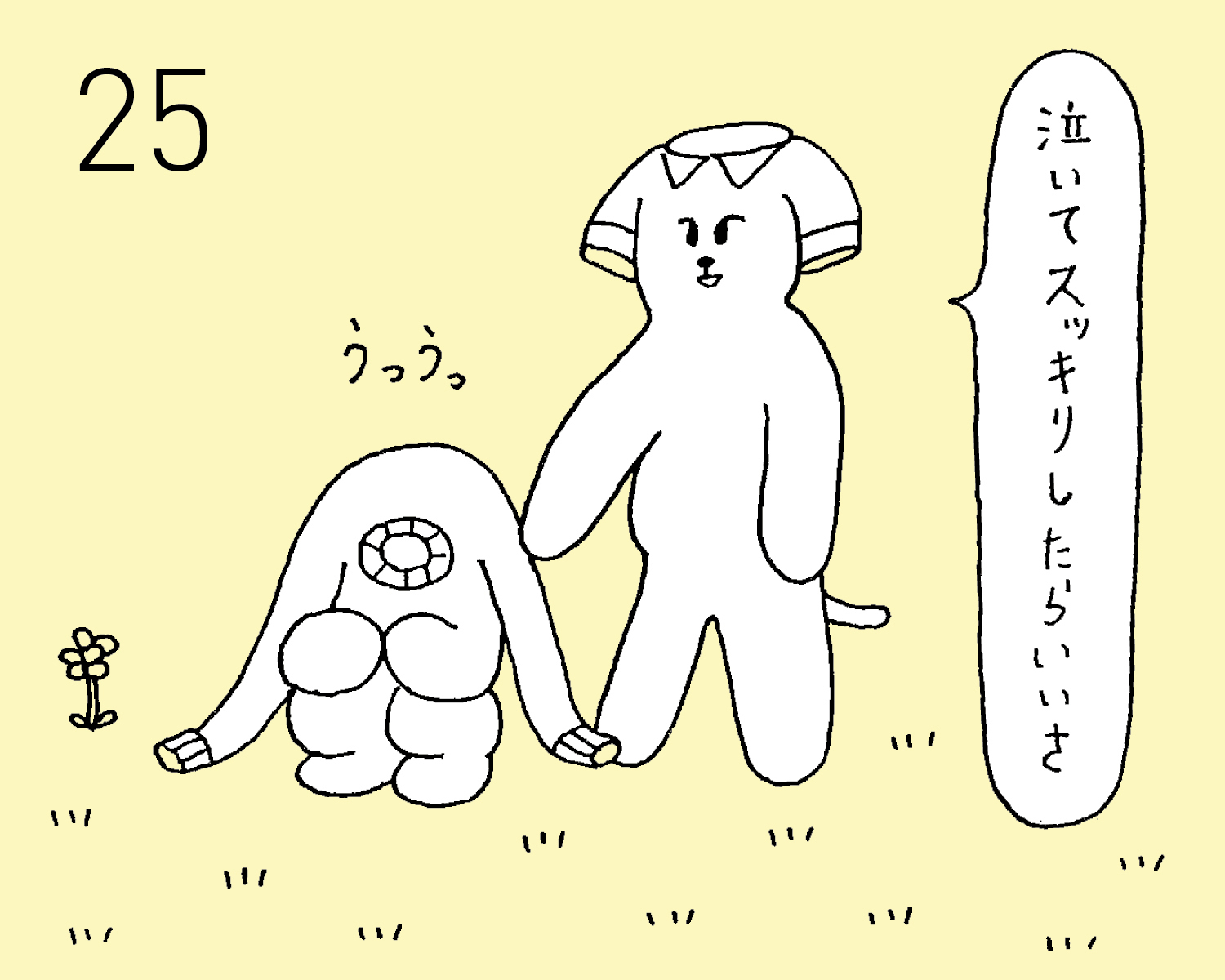70年代後半〜80年代にかけて、パルコにおける名作広告の数々を撮影した 写真家の操上和美さんに、撮影時のお話や、 当時流れていた時代の空気を振り返っていただきました。
パルコの広告を支えた 写真家・操上和美さんにインタビュー!撮影時の話や当時流れていた空気を振り返って「アイデアは現場で生まれてくるもの」
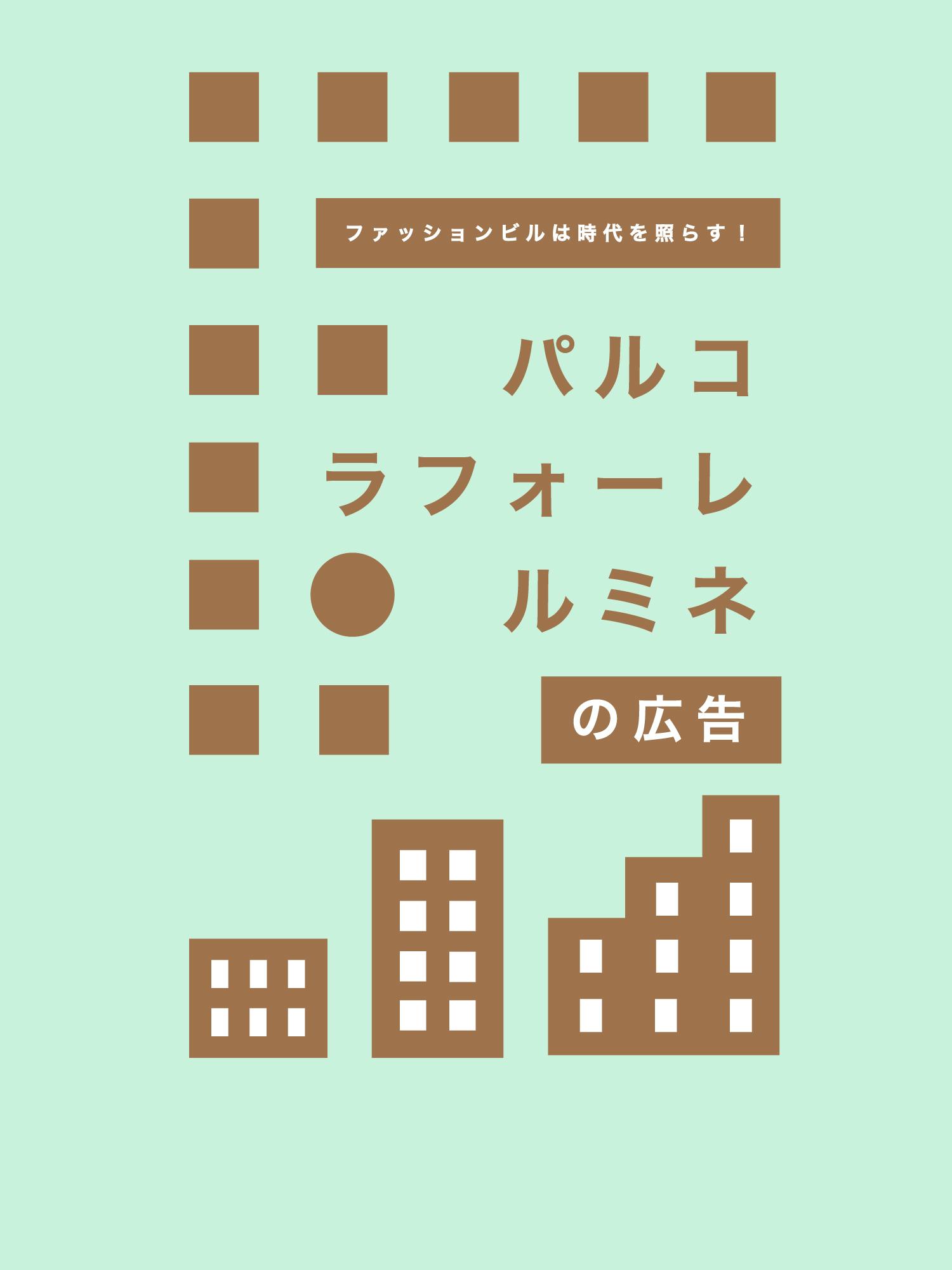
パルコの広告には驚きと 新しさが求められた
僕がパルコの広告を撮影していた70年代後半〜80年代は、音楽であれ、映画であれ、面白いカルチャーをどんどん広告に取り込んでいこう、というムードでした。写真やコピーを通して、若者の心に浸透するもの、驚きやメッセージをいかに強く残せるかが、我々クリエイターの使命だったように思えます。パルコのポスターに裸のジュリー(沢田研二氏)が登場したときは、ものすごいインパクトでした。僕が撮影したもので、女優のドミニク・サンダが涙を流しながら煙草を吸っている写真もあります。現代の広告では考えられないことですよね。 当時の社長だった増田通二さんは、とりわけそういった新しい表現を面白がって受け入れてくれる方でした。パルコはファッションビルでしたが、時代感に対する想いがしっかりとある企業で、いわゆる商品を綺麗に見せるような、商業的な広告とは対極なものを求めていた。最近街にあふれるファッションの広告は、モデルに服を着せたカタログ的な表現が増えてきている気がしますが、70〜80年代の広告には、もっと作り手側が明確なメッセージを持っていたように感じます。
予定調和ではない、 実験的な当時の撮影現場
石岡瑛子さんがADだった時代は特に、力強く、進歩的な女性を描き続けていました。その根底には「自分を解放する」というメッセージが色濃くあったはずです。たとえば、79年に石岡さんと僕が一緒につくった「西洋は東洋を着こなせるか」(P.63)という広告。当時アメリカで一番尖っていた女優のフェイ・ダナウェイと、東洋の少女が出会ったときに、一体何が生まれるのか、という挑戦でした。三宅一生さんの美しい衣装も、いくつかデザイン画が上がってきたものから、石岡さんが選んで決めていたと思います。撮影はLAのスタジオで行いました。フェイがカメラの前に立つと、がらりと空気が変わりましたね。さすが大女優です。最初は少女たちをフェイの両脇に立たせていたんだけど、どこか普通になってしまうので、彼女のドレスで包み込むような構図にしました。僕がこの時代に使用していたのは「コダクローム」というポジフィルム。残念ながら今はもうなくなってしまったのですが、みっちりとコクのある色調は、ポスターにするとけっこうインパクトが出るんです。
井上嗣也さんと取り組んだ85年の「どうも明日は。」も印象的でした。あれは、けっこうビジュアルショックですよね。RCサクセションが、ミイラになって生き返ってくるんですもん。時間のズレを表現している、糸井さんらしいひねりの効いたコピーもいいです。RCサクセションは、撮影するときに細かいところまで指示しなくても、忌野清志郎さんを筆頭に、本人たちのキャラクターが立っているから自然とそれぞれのポージングが出来上がってくるんです。アイデアは現場で生まれてくるものなので、撮ってみないとわからない。撮影前から、きっちり絵が決まっていることはほとんど無かったです。