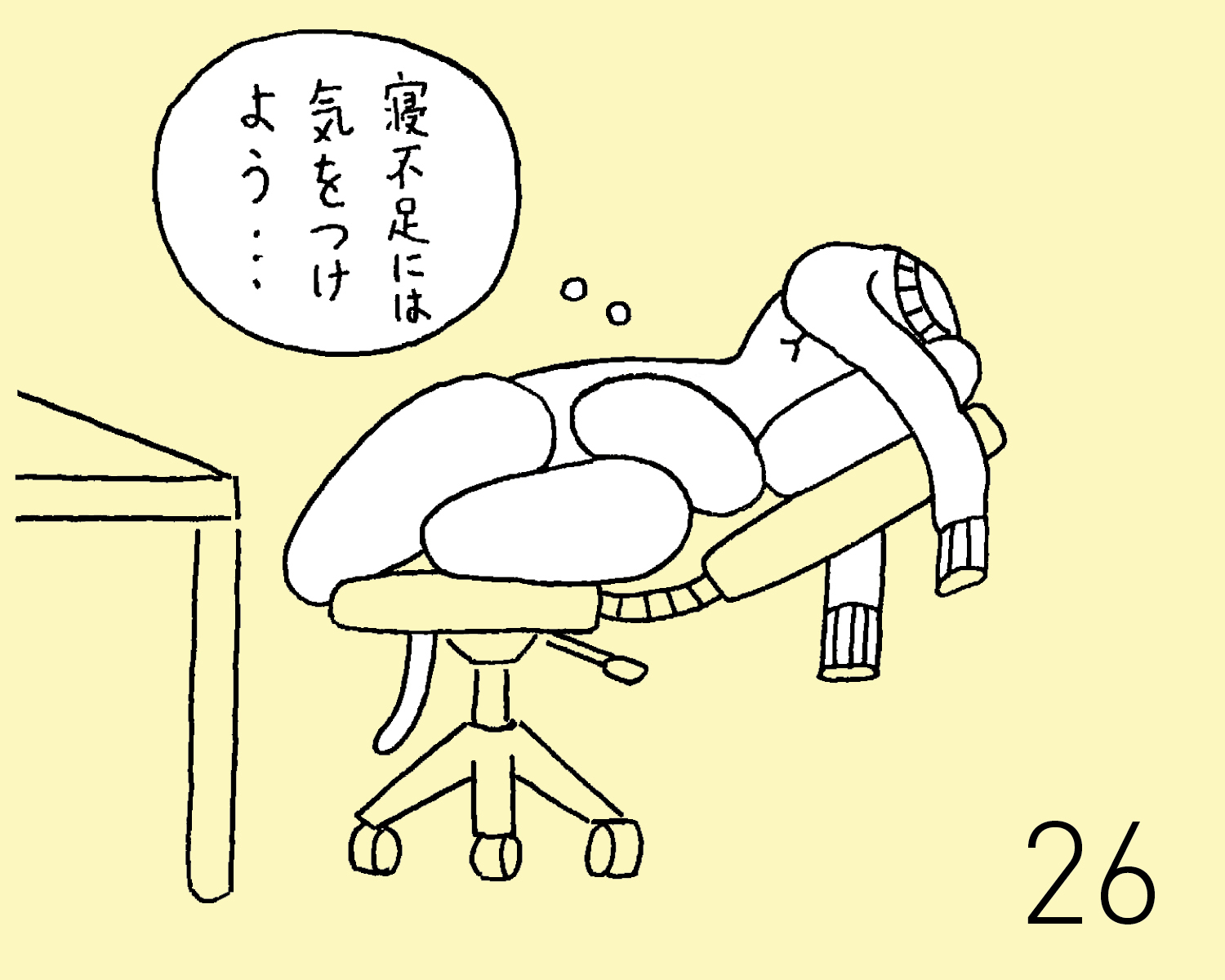そろそろ知っておきたい古典の世界。その嗜み方・楽しみ方のツボはどこにあるの?
はじめまして、ザ・クラシックス〜落語編

落語を楽しめる場所はいろいろあるが、常設の「定席」で行われている寄席は、いつでも気軽に入れる落語のホーム。たくさんの出演者が、短い持ち時間で次々に入れ替わって登場する。だからある意味団体戦で、個々の上手さや完成度だけでなく、観客を含めた場のテンションがどれだけ上がり、グルーヴが生まれるかどうかで、満足度が左右されたりする。大きな会場で長い噺を聴く「ホール落語」と違い、落語に特化した小規模な空間で行われる寄席は、クラブで行われるレギュラーイベントのようなものだ。
寄席は「昼席」「夜席」の入れ替え制で、それぞれの番組(プログラム)で落語家が10名程と5組程度の色物(漫才・奇術・紙切りなど)が出演する。番組の最後=トリを務めるのは、その寄席の「主任」と呼ばれる真打。必ずしも一番のベテランとは限らないが、その席の顔をなって宣伝の中心になる。親しみやすく美声の桃月庵白酒(とうげつあんはくしゅ)や、古典の名手・入船亭扇遊(いりふねていせんゆう)など、人気も実力もある人が主任だと、間違いない席が期待できる。出演者と出演順は、主任を軸に決められる。主任が人気噺家で客足が見込めるときは、若手の出演者は自分を売り込むため、とくに気合が入るらしい。ヒップホップ用語でいう「フックアップ」のような原理だ。
演じるネタは、実はその日の出演直前に決まる。楽屋の「ネタ帳(楽屋帳)」にその日かかったネタを前座が順に書き込んでいき、噺家は出番前に目を通して、重なったりに通ったりしてしまわないように、また場の温まり具合なども考えて、その日の演目を決める。なにしろ寄席は毎日行われるため、全体の流れがずいぶん即興的に、ノリで組み立てられているのだ。落語ファン的には、どの噺がかかるかを予想する楽しみもある。
寄席は長時間で途中入場・退場可なので、出演者をフロアを飽きさせず、反応を見ながら心をつかむ力も試される。場の空気をコントロールするには、導入時に話す「まくら」がだじ。本編に入る前に、気構えずに笑っていいですよと誘ってくれる役割がある。自分にとってまくらが肌に合う噺家は、安心して笑える可能性が高い。まくらといえば、柳家喬太郎が古典落語「時そば」を演じるときのまくらが傑作と名高く、独立して「コロッケそば」と呼ばれるほど。立ち食いそばへの愛を語りながら、全身を使って熱演する、衝撃的な内容だ。
まくらで寄席との一体感を作り出すのが「いじり」のテクニック。名人と言われる落語家は大抵いじりがうまく、特定の客をいじったり、客層を見て語りかけ方を工夫したり、余計なところで客が笑いすぎると抑えるような働きかけもする。若手でも、春風亭一之輔や柳家三三(さんざ)など、人気者はやっぱりうまい。落語の合間にはさまざまな色物も、いじりを使いこなして寄席を巻き込んでいく。
前の演者をいじることも多い。芸人自身をいじることもあれば、前の噺に出てきたものをいじることもある。ついさっき出てきたばかりの特徴的な台詞や仕草を自分なりに真似たり、パロディにして見せたり、うまくはまると寄席はどっと沸く。それはまさに、即興のサンプリングのよう!しかも一度きりで終わらず、たとえば前座の仕草を次の演者がまくらでいじり、主任があえて似た噺をかぶせてその仕草を重ねていく……なんてこともある。大盛り上がりすることは間違いない。何が起こるかわからない、現場ならではの寄席の醍醐味だ。