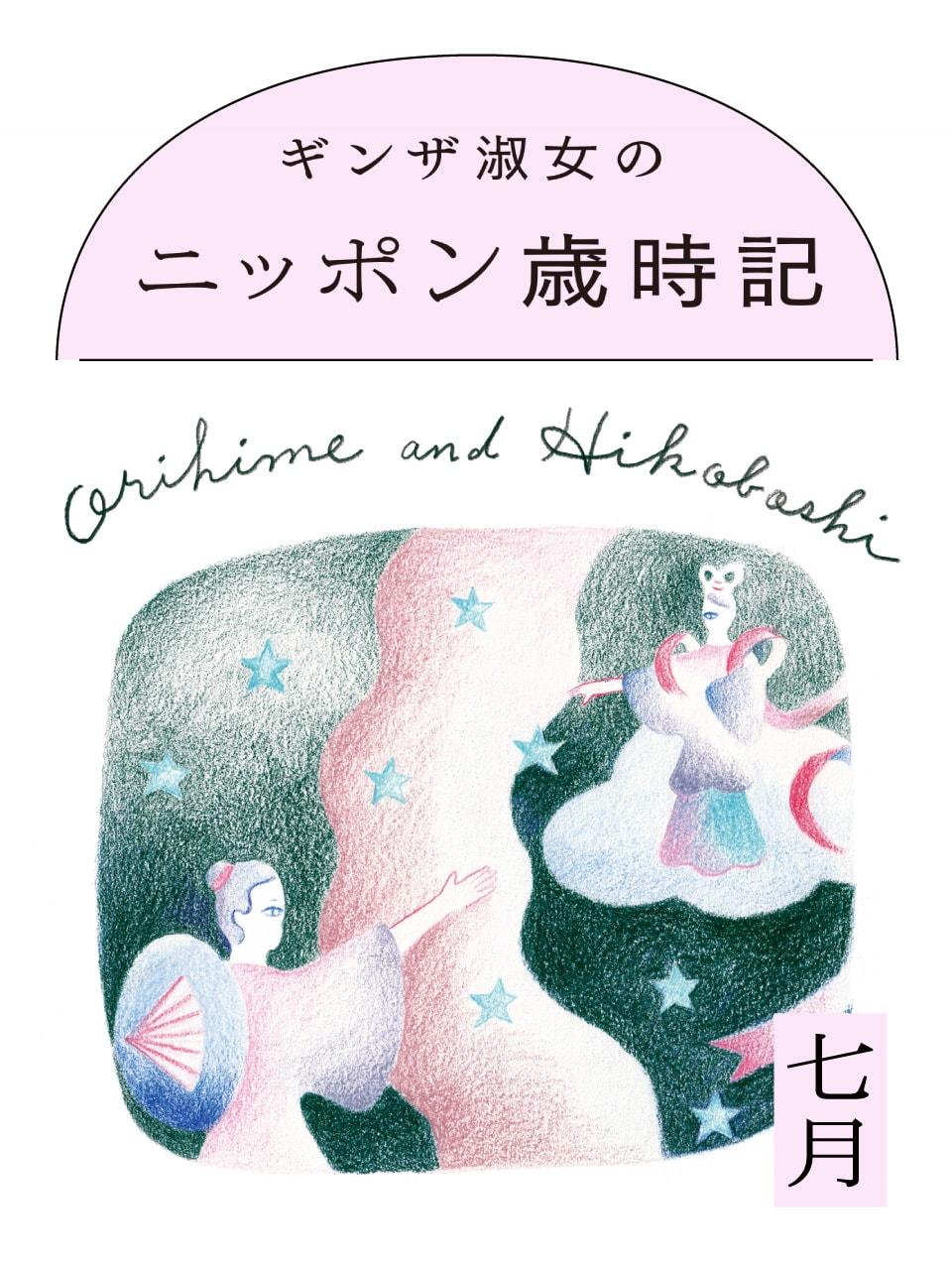知っておきたい日本の言葉、季節のあれこれ。
ギンザ淑女のニッポン歳時記 4月8日はお釈迦様の誕生日「花祭り」です
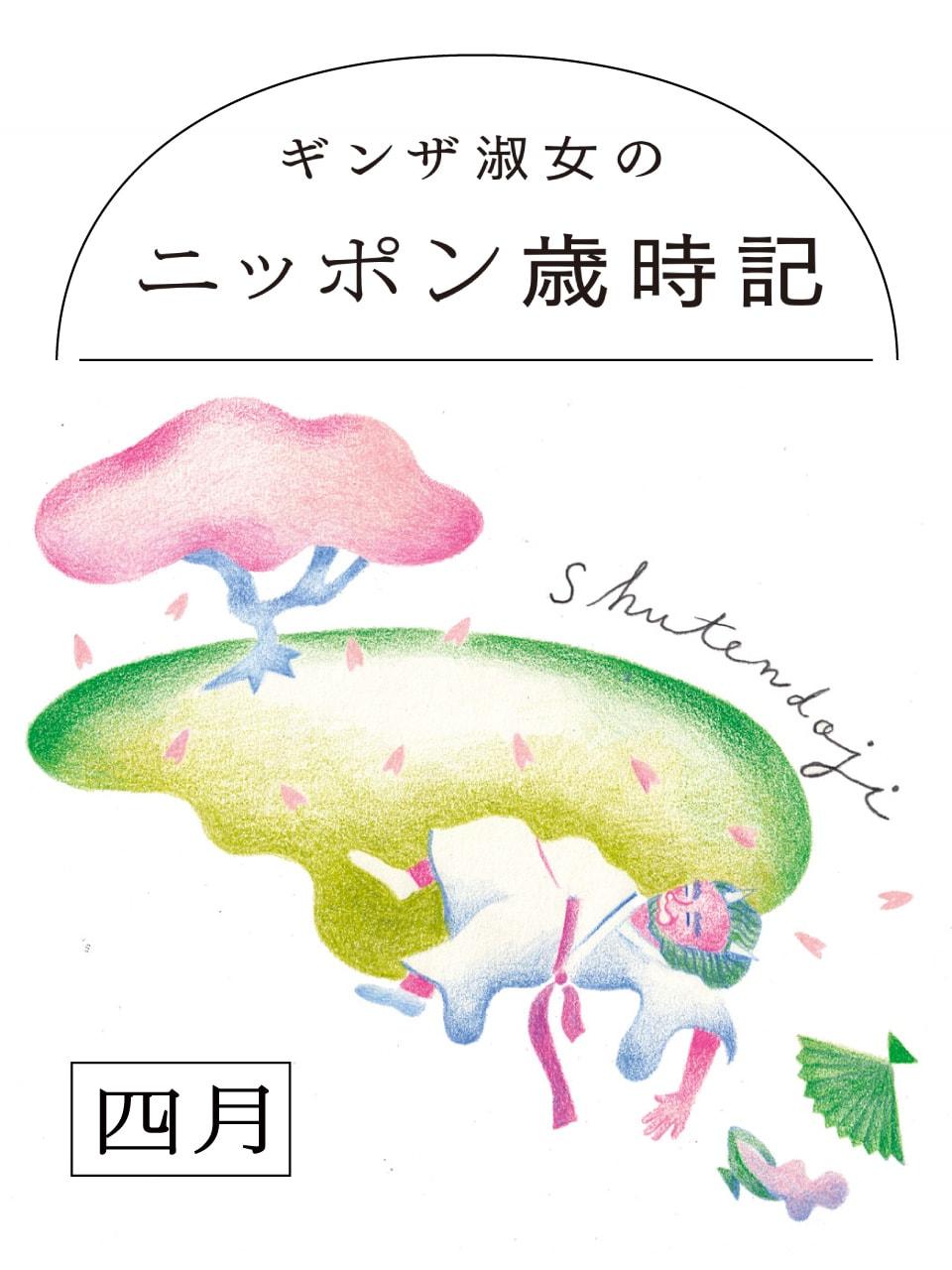
花祭りはなまつり
4月8日はお釈迦様の誕生日。寺院で釈迦誕生を祝う法会のことを灌仏会、仏誕会などと言いますが、花祭りという俗称が近世以降定着しました。お釈迦様は生まれた瞬間にすくっと立ち、右手で天、左手で地を指さし、7歩前に進んで「天上天下唯我独尊」と唱えたと言います。その姿の像を蓮の花をかたどった水盤に安置し、さまざまな花で飾った小さな御堂の内に据え、甘茶をかけて祝います。お寺でふるまわれる甘茶を飲んで無病息災を祈ります。
今月の神様酒呑童子しゅてんどうじ

室町〜江戸時代に成立した御伽草子に書かれた伝説の鬼。京都の大江山に住み、都から人をさらって食ってしまうとして恐れられていました。巨漢の化け物を退治する物語は恐ろしくもどこかユーモラスに絵巻物に描かれています。鬼退治の一行が持参した毒酒を飲み、グウグウといびきをかいて寝た瞬間、首を斬り落として一件落着。大きな首は京都に持ち帰らず、老ノ坂峠に埋葬されました。酒呑童子はそこに首塚大明神として祀られ、首から上の病や怪我に悩む人の守護神となりました。
今月の文様小物扇文の財布おうぎもんのさいふ

風をあおぐ扇という道具は、古代ギリシャ・ローマ、マヤ文明やエジプトでも紀元前から使われていましたが、開いたり閉じたりする形にしたのは日本と言われています。骨を一カ所で留め、そこから大きく開いた様子が末広型であることから、末広がりの繁栄を象徴する吉祥のかたちとして喜ばれました。綴れ織の財布の表に金糸で刺繡された扇文は単純化したモチーフで、幾何学的なモダンさもあります。
財布*小銭入れ付き 扇刺繡 全7色 各¥12,100*税込み(上七軒あだち)
今月の和菓子
卯の花うのはな

陰暦では4月のことを卯月と言いました。卯の花=ウツギの花が咲く頃だから「卯月」と呼ぶようになったと言われます。ウツギの花は真っ白い小さな花をたくさん咲かせます。白い練り切りにところどころ粒あんが見え隠れする上生菓子「卯の花」の姿は、咲き乱れる白い花々の合間に見える梢の影を想像させます。
上生菓子「卯の花」 ¥400*税込み*4月のみ販売(塩野)