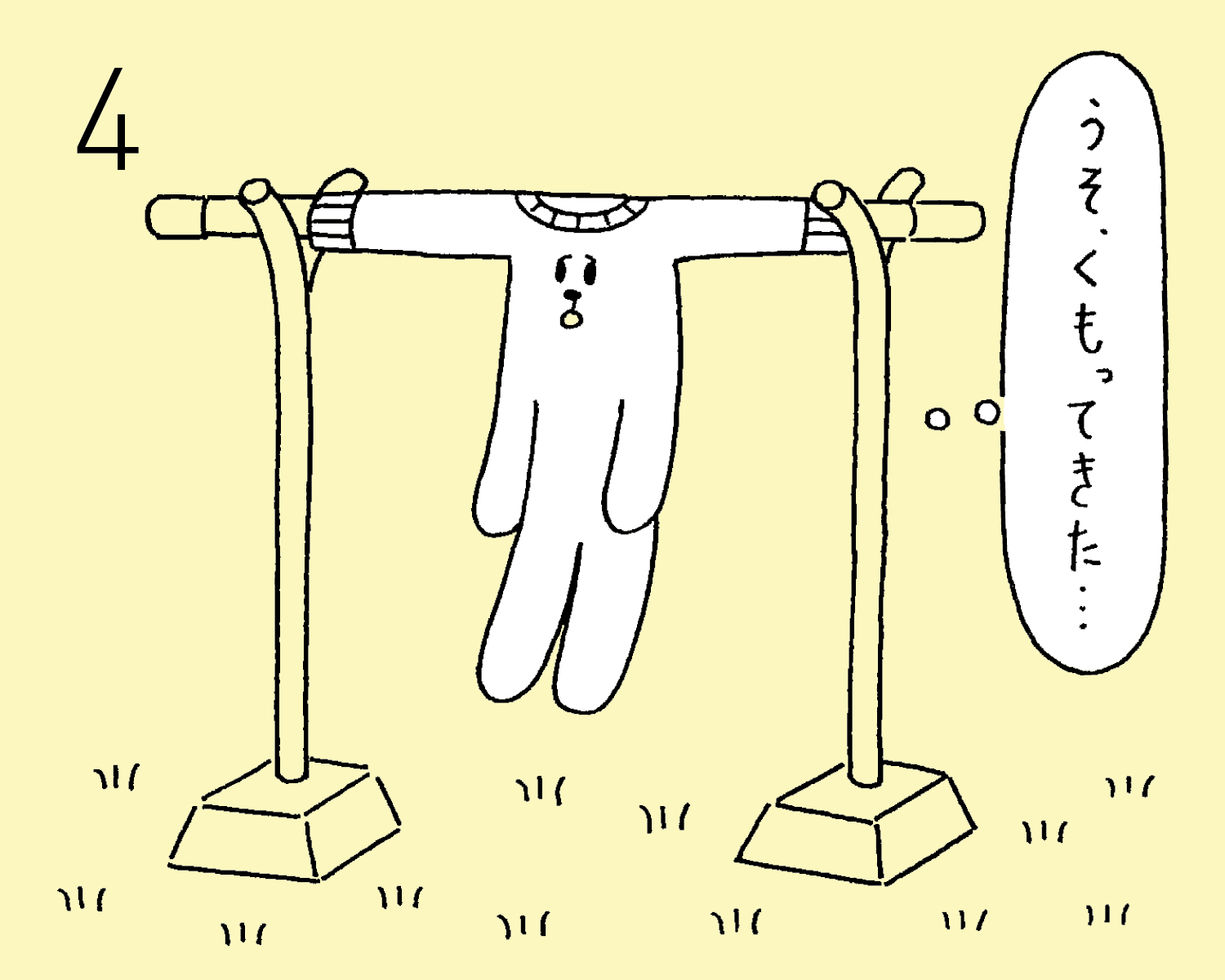TOP: 菅木志雄「通状化 Passing State in Formation」2019, wood, acrylic, h.180.2 x w.135.3 x d.19.9 cm
戦後日本美術を代表するアーティストが提示する「もの派」の世界 菅木志雄展「放たれた景空」

小山登美夫ギャラリーで、菅木志雄展「放たれた景空」が開催されている。菅にとって、同廊で行われる8回目となる個展だ。
菅木志雄(1944-)は、同時代を生きる、戦後日本美術を代表するアーティストのひとり。1968年多摩美術大学絵画科を卒業し、60年代末~70年代にかけて起きた芸術運動「もの派」の主要メンバーとして活動。その後もインド哲学などに共鳴した自身の思考を深化しながら50年以上も精力的に制作を続け、独自の地平を切り開いている。
近年では2017年に第57回ヴェネツィアビエンナーレ国際展やポンピドゥ・センター・メッスで開催された「ジャパノラマ 1970年以降の新しい日本のアート」展に出展。8月24日まで開催されていた国立新美術館「古典×現代2020―時空を超える日本のアート」では、仙厓の「円相図」に呼応した2つの大きなインスタレーション作品を出展し、大きな反響を呼んだ。

菅木志雄「原支 Supporting the Origin」2020, wood, acrylic, stone, rope, h.206.8 x w.122.2 x d.24.4 cm
菅は、普段私たちがよく目にするような木や、石、金属、ロープなどの「もの」を集め、選び取り、融和させたり、対峙させながら、絵画のキャンバスのような木枠、展示空間、屋外などに配置し作品を構成する。そこには、制作に至る前段階として、「もの」に対して「石を、これは石ではないのではと考える」というように、人間がつけたものの役割や機能、イメージを徹底的に取り払い、その本質や存在とは何かを再認識していくものとの対話がある。

菅木志雄「空林空 Gathered Between Spaces」2019, wood, acrylic, h.120.1 x w.93.8 x d.20.3 cm
特徴的なのは、菅が「もの」を人間が意味を与えた「客体」と見るのではなく、むしろ独自の論理と方向性、現在性をもつ主体的な存在として捉えていること。そして、アーティストの役割は「もの」に潜在的に備わっているあるべき姿とそれにふさわしい場を見出すことだ、と考えている。菅は、そんな「もの」たちを切り、曲げ、折り、並べ、重ね、繋げるなど「もの」本来の存在を表出すべく、最低限の行為をほどこしていく。一貫した姿勢は、今私たちが気候や環境の劇的な変化などによってその重要さに気づきつつある、人間以外の存在へのまなざしを先取りしていたようにも思える。

菅木志雄「集点化 Gathering of Points in Formation」2020, wood, acrylic, h.119.8 x w.98.1 x d.20.7 cm
作家はこう語っている。
「(いままでは)つまり作家が主体で、扱うものは客体というわけ。どうして作家がものを支配的に扱わなくてはならないのか?石でも、木でも、それぞれの場所があり、場には個々のリアリティがある。」
(「『もの』をどう見るかは、人それぞれの問題だ」Discovor Japan、2020年3月6日)
そして菅の作品は、ものを単独で存在させるのに限らない。「もの」と「もの」、「もの」と「場」が相互に依存し合う「連関性」や「差異」、「複雑性」や「複合性」を表出させる事で新たな状況を生み出し、ものと場の存在性を一層際立たせていく。

菅木志雄「中縁枝 Internal Edge of Branches」2019, wood, acrylic, h.120.2 x w.90.0 x d.27.2 cm
菅は2015年同廊での個展以降、継続して壁面に展示される立体作品に取り組んでいる。一見すると平面作品とも見えるが、「もの」が立体的に構成されることで、作品内部に空間が抱き込まれるような新たな構造が生まれている。
本展の新作は、木枠の中に格子状の枠組みが更につくられたり、大小異なる木片がリズムよく並んだり、小さい丸太の断面は縦に連なりどこまでも続いていくかのよう。さらに赤、黄、青などのペイントの塗りによる新たな視覚効果も目に鮮やかだ。また、ギャラリーの奥の部屋では、空間全体を使ったインスタレーション作品も展開する。

菅木志雄「空輪行 Empty Circles in Parallel」2020, wood, acrylic, ink, h.90.0 x w.60.2 x d.13.1 cm
菅の作品によって、私たちは、「もの」が今まで知っていたものとは異なる姿や情景を表しているのを見る。そして、それらが相互に関係し、連続していくことも。この気づきは、私たちをとりまく世界の、また別の側面を知ることにつながるはずだ。
従来の価値観の更新が迫られている今、お互いに支えあいながらも、それぞれの存在や自律を認め合う菅の「もの」観は、ものと人、人と人の関係に対しても多くの示唆を含んでいる。菅の作品世界の向こうに見えるものは何だろうか。きっと、自分の心への問いかけが生まれるだろう。
以上画像すべて:Photo by Kenji Takahashi, © Kishio Suga, Courtesy of Tomio Koyama Gallery