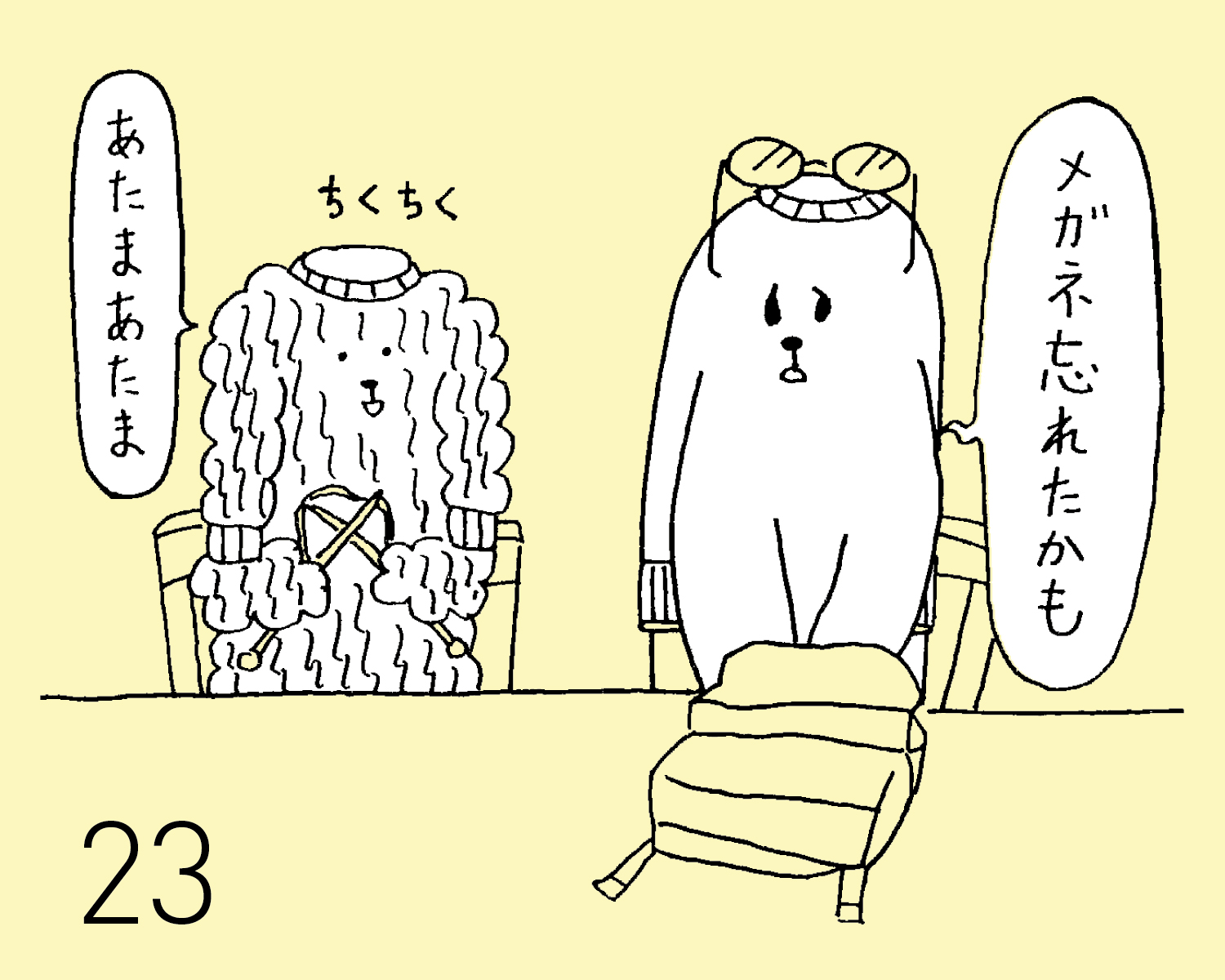ロックバンド・クリープハイプのほとんどの作詞・作曲を手がけるだけでなく、作家としても人の記憶に残る文章を書き続ける。彼の「言葉と音」を覗いて見えたものとは。
尾崎世界観“作詞の限界”のその先へ
「歌詞をつくる人」に聞く

自分が感じたことを
世の中に問う
クリープハイプのソングライターとして、愛と哀の間にある複雑な色彩や社会で抑圧される感情などをインパクトあるワードで表し、多くの人の心を揺さぶってきた。2016年には小説家デビュー。20年に発表した『母影』は第164回芥川賞の候補作に選出。さらに『NHK短歌』(NHK Eテレ)のMCも務めるなど、さまざまな角度から「言葉」と向き合い続けている。
「特技は何かと聞かれたら、作詞と答えます。自分の表現で唯一、精度の高いもの。本当にキャッチーな曲は『何回に1回しか出ない』という感覚があるのですが、歌詞に関してはある程度同じものを出せる確信がありますね」
クリープハイプの楽曲は自身の主張やメッセージをストレートに歌うのではなく、物語調に綴られるものが多い。そういった手法をとるのはなぜか。
「そのことを最近ちょうど考えていました。自分の感情そのままではなく、登場人物を立てたり何かを嚙ませたりして伝える手法は昔から変わらない。ヒットする曲には、誰かを応援するものが多いじゃないですか。でも自分は誰かを応援するために生きているわけじゃない。自分のために生きているし、自分のことがわからないので、その中で感じていることを世の中に問いたいんですよね。まだ形になってない感情をどうにかそれに近い言葉に当てはめて、何度も組み替えたりして、『もしかしたらこれは自分だけのものかもしれない』というところまで持っていって作品にする。それを聴いて『好きだ』と言ってもらえることがうれしいし、やっとそこで『考えたことに意味があったのかもしれない』と思えます」
普段は先に曲を作る。歌詞を書く時はベッドやソファに寝転がるのが尾崎さんの癖。スマホのメモアプリを開き、画面から「3Dみたいに浮き上がってくる」言葉をつかんで広げていく。
「クロスワードパズルみたいに音に文字を埋めていく感覚です。形で見ることが大事なんですよね。目にどうひっかかってくるかが気になります。漢字にするのか、ひらがなにするのか、というところまで考えます」
歌詞を追求し見えた
言葉と音の関係
音とともに届ける「歌詞」と、音がない中で書き進めていく「文章」。その両方で筆を動かす中で得た気づきを、ユニークに語る。
「歌詞は勝手に音になじんでいくんです。脱臼しても骨は筋肉へ勝手に収まっていくと聞いたことがあるのですが、そういう感じかもしれません。なんとなく歌いたい歌詞があって、それを1文字ずつメロディに合わせにいくわけでもなくそこに置けば勝手に音に収まる。それによってメロディが多少変わったりもするんですけど、そういった最終的なズレも込みで歌が完成する感覚があります。その点、文章はしまえるところがないので難しいんですよね」
歌詞と音がなじんだメロディが完成したあと、「時代に合わせながらも自分が納得できる編曲」を作り上げることにも相当気を遣う。
「20代前半くらいの時、どうしても『自分の歌詞』が書けない中で、コミカルなエロは聴いたことがあるけど、切ない感じのエロは聴いたことがないと気づいたんです。みんなそういう行為をしながら、身体を通して感じているのに、なぜ世の中にそういった歌がないのか。そこから、どうしたら切実なエロが書けるかを考えながら、ある時、『疾走感だ』と思ってテンポを速くしてみたんです。それで出てきたのが『イノチミジカシコイセヨオトメ』。これでやっと自分の作品ができたかもしれないと思いました。そこでもやっぱり音が大事だったんです」
「歌詞」の伝え方とはすなわち「音」の作り方であると、尾崎さんは続ける。
「『歌詞ってものすごい』という幻想があるじゃないですか。でもやっぱり『音』なんですよ。詞がいいと言ってくれる人の8割は音を聴いている。そこに反応してもらった時の感覚として、どれだけ言葉にこだわっても、ある一定のところから上はないとわかったんです。そこからより音にこだわらなければと思うようになったし、言葉だけで勝負するなら小説しかないという気持ちがずっとありました。そもそも歌詞とは感情を音にしたもので、それに人は感動したり怒ったり喜んだりする。だから、突き詰めると歌詞とは音でしかない。それは本気で向き合ったからこそ見えたものです」
彼にとって歌詞や文章、音、そして人間の感性の探求に終着点はない。
「言葉も、音楽も、お客さんも、疑っているんですよね。だから『ほとんど音を聴いている』なんて言ってしまう。お客さんもこっちを疑っていると思います。曲を出せば『今回はよくない』と言われるし。でもそれが大事なんです。そうやって疑いがあるからこそ、また届けたくなる。ただ音を出すことや歌うことが好きでやっているミュージシャンもいると思いますが、自分はお客さんに聴いてもらえるから続けているという気持ちが強いです。お客さんがいなかったら明日にでもやめていると思います」
Text_Yukako Yajima