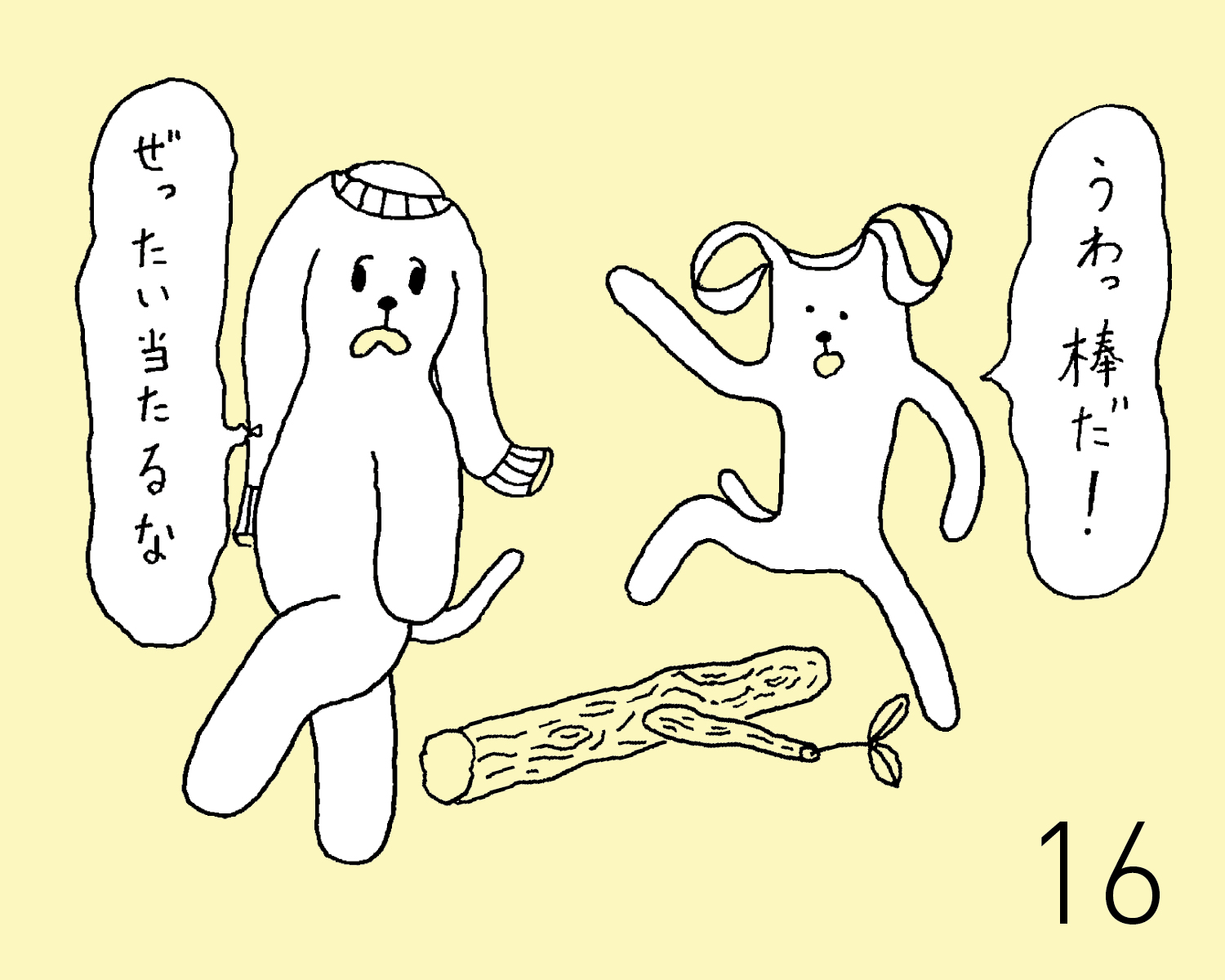光を通してガラスの輪郭を浮かび上がらせ、有機的なフォルムの作品を生み出すアーティストの三嶋りつ惠さん。20代後半にヴェネツィアに移住し、ムラーノ島のガラス工房に通い、職人との共同制作で作品を作り続ける彼女は、現在、ヴェネツィアのアトリエと京都の住まいを往復しながら生活している。そのガラス作品には、個展以外にも、日本橋のCOREDD室町テラス、ザ・リッツ・カールトン京都のロビーなどでも出会うことが出来る。風景に合わせてさまざまな光の表情を見せる作品を手掛ける、三嶋さんの人生哲学とは?
ヴェネチアン・ガラスに魅了されて。アーティスト・三嶋りつ惠さんの人生哲学

──ヴェネツィアへ行ったきっかけはなんだったのですか?
27~28歳の頃に人生のターニングポイントが来ました。いわゆる自分探しですね。それまではスタイリストやインテリア・コーディネーターなど、色々試していました。でも、何か違うと思えてきて。自分が表現する側にシフトしたかったのだと思います。日本以外であればどこでも良かったのですが、その頃文通していたイタリア人がヴェネツィアに住んでいたので、1ヶ月滞在させてもらう事になりました。美術館へ行ったり、お店をのぞいたり、知らない街を歩き回るのは刺激的でした。
──そこで、ヴェネツィアン・ガラスに出合うのですか?
いいえ、そこでイタリアの男性と出会うのです。もともとガラスの勉強をしに行ったわけでもないし、ガラス作家を目指していたわけでもないのです。旅に出て、ヴェネツィアという街と出会って、そこでイタリア人の男性と知り合って、その人と結婚することになって、それがきっかけでヴェネツィアに住むことになりました。
──日本の仕事を全部辞めて、ヴェネツィアに行くというのは大きい決断ですね?
20代だったから、そういうことってあるでしょう?違う世界に飛び込みたかった。知らない世界にワクワクしていたと思います。そこで結婚してこどもを育てていたら、イタリア人の友人に「あなたはセンスが良いからガラスでもやってみたら?」と誘われて。ちょうどそのとき、家に飾る一輪挿しを探していました。街を探しても思っていたものが見つからないから、じゃあ作ろうと。それで、工房に連れて行ってもらって、職人にデザイン画を見せて作り始めるのですが、なかなか思ったようには仕上がらないのです。
わたしは制作する前に簡単なスケッチで職人に説明します。今はデザインしないようにしていますが、その頃は、実寸サイズの細かいデザイン図を描いて職人に指示を出していました。でも、吹きガラスの技術なので、ぴったりデザインしたとおりの形にはできない。そう思いながら、制作を続けていきました。
六本木のシュウゴアーツで2020年1月25日まで開催されていた「光の場 HALL OF LIGHT」展の展示風景
──最初から楽しさを見出せたんですね。
そうね。もちろん楽しかったと思う。イタリアの職人さんたちと作品を作るのは。でも、本当の意味でのものづくりの楽しさは、もう少し後からだったような気がします。第1、第2ときっと段階があって、自分の感覚をガラスというマテリアルで表現できるようになるのは、もう少し後になってからですね。最初の頃に描いていたような実寸サイズのデザイン画は、今はもう描きません。デザインの中にガラスを押し込めるのではなく、流動的なガラスが自然になりたがるような形を目指しています。
頭に浮かぶ形を試行錯誤していたら、いつの間にか20点ほど貯まってきて、そうしたら、また別の友人から「ミラノでサローネがあるから、うちのアトリエをシェアして一緒に展示をやらないか」と声をかけられたのが、作家の道に進む第一歩でした。とにかく、私はイタリア人に助けられています。彼らが私の道へと引っ張ってくれている気がします。ヴェネツィアにも恩恵を受けていると思うし、イタリアに強い縁を感じます。
──当時、ヴェネツィア、ムラーノ島のガラス工房に通う日本人女性というのは、珍しがられましたか?
私は自分が日本人だということをあまり強く意識していないですね。知らない世界に目をキラキラさせて、幼いこどものように職人さんを質問責めにしていたと思います。だから、珍しがられるというよりは、面白がられたのではないでしょうか。
今思うと、私自身が職人さんの中に溶け込むのが得意なタイプでした。慣れない場所に緊張するというよりワクワクしていました。この間、京都で建築家の友人に「三嶋さんは相手の目線の先を読むのが得意ですね」と言われて、自分でも納得しました。その当時から職人たちの目を見つめ、その先にある世界を一緒に見ようと、リスペクトしながら付き合ってきたように思います。
ただ、展示会などで表に出るようになると、ヨーロッパの雑誌社からは、日本人の女性がムラーノ島の閉鎖的な職人の世界で作品を生み出していると、興味を持たれました。
──先ほど、「デザインをしないようにしている」とおっしゃってましたが、職人さんとセッションをするように作られている理由は、自分も驚くようなものが生まれるのを期待しているからですか?
ちょっと矛盾したような言い方になるけれど、デザインしないというよりは、デザインの中に収まらない、前にも話しましたが、デザインを超えて、ガラスのマテリアルが形にとどまった感じです。
私の作品は、職人4人がひとつのグループになって制作します。
彼らの背後で、蜂蜜状のガラスのマテリアルが形をとどめていくプロセスを見つめ、見守りながらオーケストラのディレクターのようにポイントポイントで指示を出しているときもあれば、彼らと一緒にガラスが冷えて亀裂が入らないように剛鉄の先についたガラスを火で炙っている時もあります。
──職人さんとしても、腕を試されますね。
制作の日は朝の6時から始めます。早朝は「今日は何に挑戦しようか」とでも言うような意気込みで職人たちが話しかけてきます。制作の中心にマエストロ(親方)がいて、マエストロの指示を瞬時に読み取る3人のセルベンテ(アシスタント)がガラスに息を吹き入れ、素材を加えていきます。剛鉄の先についた蜂蜜状のガラスが360度ぐるぐる回転しながら形を織りなし、完成に近づくにつれて集中力が増した彼らの呼吸のあった動きは、炎の前で踊る御神楽のようにも見えます。
1000年以上続くヴェネツィアン・ガラスの技術を使って、自分の中に見えてくる形を現代に生み出すガラスの仕事は、何度作っても感動するんです。
──ヴェネツィアン・ガラスはカラフルで繊細というイメージがありましたが、三嶋さんの作品は、生きているような動きがあって、力強い聡明さが印象的です。
透明であることは最初からこだわっていました。透明なガラスは光を通し、回りの風景を映し出します。完成した作品をどのような場所で、どんな風に見せたいか、インスタレーションに重点を置くのも私の特長だと思います。ガラス作品はそれぞれ自立していますが、空間の中に溶け込むように、そして、光を通す窓みたいな存在にしたいなと。とにかく自分の作品をどういうシチュエーションで見せたいか、ずっとトライしてきました。
──COREDO 室町テラスに設置されている「宇宙の雫」は透明な作品に銀加工された作品ですが、「光の帯」はこれまでと違って色を使っていますね。
何の仕事でもそうですが、自分がその場所で作品を展示する意味を考えます。COREDOはかつて江戸の中心地として栄えた日本橋にあります。新しい現代の形でエネルギーが蘇り、人々が行き交う場所になるだろうと想像しました。そして、そこに、朝から夕方までの光の変化を映して上昇する「光の帯」をつくりたいと思いました。
ヴェネツィアを歩いていると、朝の光や夕日、運河に映り込む光の光景にハッとさせられます。朝は、ブルーから始まって夕陽が沈む時はサーモンピンクやゴールド、いろんな色が入っているんですよ。都会を歩いていると、仕事に追われてそうした光景を見失うことがあるけれど、ガラスを通して日々の中にある光の変化を感じてもらいたい。COREDO室町テラスの「光の帯」は、そんな思いを込めて制作しました。
──展示会での作品と、パブリックに設置される作品、置かれる空間や場所のコンセプトから考えるというスタンスは基本的に同じなんですか?
そこがどの場所で、ガラスを通してどんな場を作りたいのかを考えることは同じですね。何度か通って、その場のエネルギーを感じてからアイデアを出す時もあります。当然、いろいろな制限が出てきます。地震の時の揺れや、メンテナンスなど、パブリックスペースでの設置は技術者や建築家の人たちと打ち合わせを重ねて作り上げていくものです。作品はずっとそこに置かれるから、そのガラスたちが場を清めて、見ている人が少しでもリラックスして幸せな気持ちになってもらえたらという思いは、いつも心の中にあります。
──現在は、ヴェネツィアと京都を行き来されていますが、行き来してきたからこそ見えてきたイタリアと日本の違いってどこにあると思いますか?
180度違いますね、正反対。わかりやすく言うと、イタリアは太陽の国で日本は月の国。陽と陰。日本にいると気づかないかもしれないけれど、反射したものを美しいと思うのが日本でしょう?昔の和歌にも歌っているけれど、月自体が太陽の反射で見えているものじゃないですか。全ての美意識にそういうところがあります。やっぱり日本は陰な感じです。でも、イタリアは今日の太陽は美しいから幸せ!みたいな感じですね。
──自分のアイデンティティは、どちらにあるという感じですか?
こうやって行き来して有難いのは、両方の感覚がわかること。ヨーロッパの国のことも日本のことも、両方の気持ちが感覚的にわかるのは、楽しいことです。イタリアやフランスの雑誌の取材で「あなたの作品の中に日本人のアイデンティティは入っていると思うか?」とよく聞かれるんです。その質問に私はいつも「私は自分の作品が日本人的であるとは思っていません。ただ、強いていうならば、見えないものを見るというような物の見方、考え方でしょうか」と答えています。
作品がガラスを通して光となってくれればいいなとか、その作品で場を清め、作品を見ている人や持ってくれる人が少しでも幸せになってくれればという願いが自分の中にある。そういうところは、日本人的なところでしょうか。多くのイタリア人はそんな風には考えないですから。
──最後に、人生の先輩として、20代、30代の読者たちにアドバイスをいただけたらと!
もう2020年、工芸やアート、デザインなどの枠組みは既に溶けている感じがします。これは全ての分野に言えることです。だから自分流を作っていってください。
みなさん、自分はどの枠の中でやるのがいいのかと迷われることが多いですよね。でも、最終的には全部つながっているんです。だから、自分がワクワクして嬉しくなる方を追っていけば、ひとつの形になります。ひとつのことがある程度見えてきたら、表現する場所はアジアでもヨーロッパでも同じ。だから、日本だけを意識して行動しなくてもいいと思う。自分の気持ちに焦点を合わせて行動していけば、情熱とリスペクトを持っていれば、大地はすべてつながり、開かれているんですから。

🗣️
三嶋りつ惠
1962年京都生まれ、1989年からヴェネツィアに移住、1996年よりムラーノ島の硝子工房に通い始め職人とのコラボレーションにより作品を生み出す。2011年から住まいを京都に移し、ヴェネツィアと往復する生活を送る。主な個展に2019年「Lumina」Luhring Augustine (ニューヨーク)、2013年「IN GRIMANI」国立パラッツォ・グリマーニ美術館 (ヴェネツィア)、2011年「あるべきようわ」資生堂ギャラリー (東京)、2010年「Frozen Garden / Fruits of Fire」ボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン 美術館 (ロッテルダム) 。グループ展に2017年「アジア回廊 現代美術展」二条城 (京都)、2014年「ヨコハマトリエンナーレ2014」横浜美術館、2009年「第 53 回ヴェネツィアビエンナーレ 」ヴェネツィア館 など。