モノが主体となる演劇!?つねに新しい演劇の形を提示してきたチェルフィッチュとアーティストの金氏徹平による『消しゴム森』(美術館版)は、モノと人の新しい関係を探るという、ちょっと奇妙なコンセプトをもとに作られている。そこには、最近の気候変動を受けてアートやファッションでもトピックになっている、エコロジーの問題も関係しているらしい。チェルフィッチュ主宰・演劇作家の岡田利規に、本作を作るに至った背景や、込めた思いを聞いた。
演劇作家・岡田利規インタビュー「人間が中心じゃない世界のリアリティ」チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム森』


【グラフィック:金氏徹平】Photo by Yuki Moriya, Courtesy of Kyoto Experiment, Graphic by Teppei Kaneuji
きっかけとなった陸前高田の風景
――モノが主体となる演劇というのは、ほとんど想像がつかないのですが、なぜそのような設定を思いついたんでしょう?
岡田 2016年に、陸前高田で津波の被害を受けた場所を初めて訪れました。そこでの復興工事の様子が、どう受け止めたらいいかわからないという強烈な体験だったんです。そこにあった家や商業施設が再建されたらいいなと願う人たちがいて、そのためにかさ上げ工事が行われている。それは理解できます。ただ、その工事の様子を見て、僕は常軌を逸していると思ったんです。広大な敷地を12メートルかさ上げするわけだから、とんでもない量の土が要る。そのために、山がなくなったりしている。「山がなくなる」ということの意味を僕はつかめなかった。
つまり、復興工事の計画が基にしている尺度が、あまりにも人間のそれなわけです。もちろん、流された家が100年後に再建されても意味はないのだけれども……。でも、人間の都合や尺度をそこまで絶対的な基準にしてあらゆる物事を決めてもいいのかな?ということを素直に疑問に感じた。それで、人間ではないもの、つまりモノの演劇をつくろうと思ったんです。
――ティモシー・モートンの『自然なきエコロジー』を参考にされたとのことですが、それもこの経験があったからですか?
そうです。僕としてはただ流行っている哲学だからというだけじゃ読むモティヴェーションにはならない。高田での経験があって、新しいエコロジーの思想に興味を持ち始めたんですよね。


チェルフィッチュ × 金氏徹平 『消しゴム森』 リハーサル風景 撮影:木奥惠三 写真提供:金沢21世紀美術館
モノと人の新しい関係を作る
――なるほど。モートンによるエコロジーでは、人間以外のものたちを感知することが重要視されています。その意味では、小さい虫とか動物とかも人間ではないと言えますが、今回フォーカスしているのは、いわゆるモノなんですね。
動物とモノの違いはあまりなくて、人間じゃないってことの方が大事です。そもそも演劇は、すごく人間中心的な制度だと思うんですね。人間の役者を人間の観客が見ていて、基本的には人間の問題を扱っている。舞台上にある小道具やセットも、それらは人間の問題を表現するためや奉仕するためにあります。だからこそ、そうじゃないモノと人との関係を演劇でやるのは面白いだろうと。舞台上にたくさんモノがあって、むしろ人間を侵食していくような感じとか、そういう新しい関係を扱えたらと考えました。
――なるほど。モノにフォーカスしていくときに、いわゆるストーリーというか、ナラティブは必要だったんですか?
最低限のものですけどあります。モノとの新しい関係といっても、旧来的なそれから変化していくプロセスは提示しないとならない。そうでないとあまりにも人間の観客を突き放したものになっちゃいますから。

チェルフィッチュ × 金氏徹平『消しゴム山』、ロームシアター京都、KYOTO EXPERIMENT 2019 Photo by Yuki Moriya, Courtesy of Kyoto Experiment
美術館で見せる演劇
――京都で上演された『消しゴム山』は、いわゆる舞台で行われていて、時間も2時間ほどです。一方、今度の『消しゴム森』の方は、一日7時間と、すごく長いですよね。
7時間というのは展覧会がオープンしている時間です。7時間の上演時間ずっと見ていないといけないというわけではありません。『消しゴム森』の中をだいたい3時間くらい彷徨ってもらったら十分じゃないかな。
――美術館でやろうと思ったのはなぜですか?
美術館での体験は劇場でのそれとまったく変わるはずだからです。とくに、時間に対してどう感じるかという点においてまず、演劇は上演時間が決まっていて、始まりと終わりも決まっている。でも、美術館の時間はそうではない。だから、このシーンはもっと長くなったら面白いだろうというのを実際に長くしてみるとか、劇場ではできなかったことをやろうと思っています。あと、美術館って、基本的にモノが展示されている場ですよね。だから、劇場でモノを見るより、観る側も受け入れやすいのではないかと期待しています。
――美術館の方が、人間中心的ではないと?
人間中心と言う言葉に、現在中心というニュアンスを含んでいいとしたらなおさらそう思います。演劇は今を生きている役者が演じるのだし、たとえ古い時代の戯曲をやるのであっても、現在中心主義的な形式ですよね。

チェルフィッチュ × 金氏徹平 『消しゴム森』 リハーサル風景 撮影:木奥惠三 写真提供:金沢21世紀美術館
作品の中だけじゃない、生活からモードを変えていく
――これまでのチェルフィッチュの作品との違いはどんなところですか?
これまで作ってきた作品は、人間の観客の想像をどれだけ喚起させるかに力を入れて、すごく頑張っていました。なかなかいい感じでできるようになってきたけれども、この方向性でやり続けても、だから?ってなっちゃうだろうなあと。まったく違う何かをやらないといけない、そういう危機感がありました。
それで『消しゴム山』を作って、僕自身はすごく手ごたえを感じた。当たり前ですが、観客はみんな人間、つまり中心にいる人たちですから、中心から外されるのは愉快じゃないことかもしれない。でも、僕はそれが大事な気がしているんです。
――そのような意識のもと、ご自身の生活が変わったこととかありますか?
それがほんとうに大変で、課題でもあります。『消しゴム山』を作っている時は、明らかに自分の体質というか、モードの質が変わっている感じがあったんです。でも、10月に初演を迎えて、それからいわゆる通常の演劇の形をした別の仕事をやっていると、その感覚はだんだんと薄れていってしまう。それはすごく残念だし、モードの質をどう維持するかが課題です。体質改善みたいなものですかね。
――モードというのは?
世界のとらえ方の問題です。この水筒を、僕がコーヒーを飲むためのものと捉えるか、そうじゃないものとして捉えるか。場所もそうですよね。ここをリハーサルをしている空間としているは我々の勝手であって、蛾が飛んできてもいいわけですよ。蛾にとって、ここはリハーサルの場ではない。そういうことなんだけど、それが難しい。でも、そちらに行けた方が絶対に面白いはずです。

チェルフィッチュ × 金氏徹平 『消しゴム森』 リハーサル風景 撮影:木奥惠三 写真提供:金沢21世紀美術館
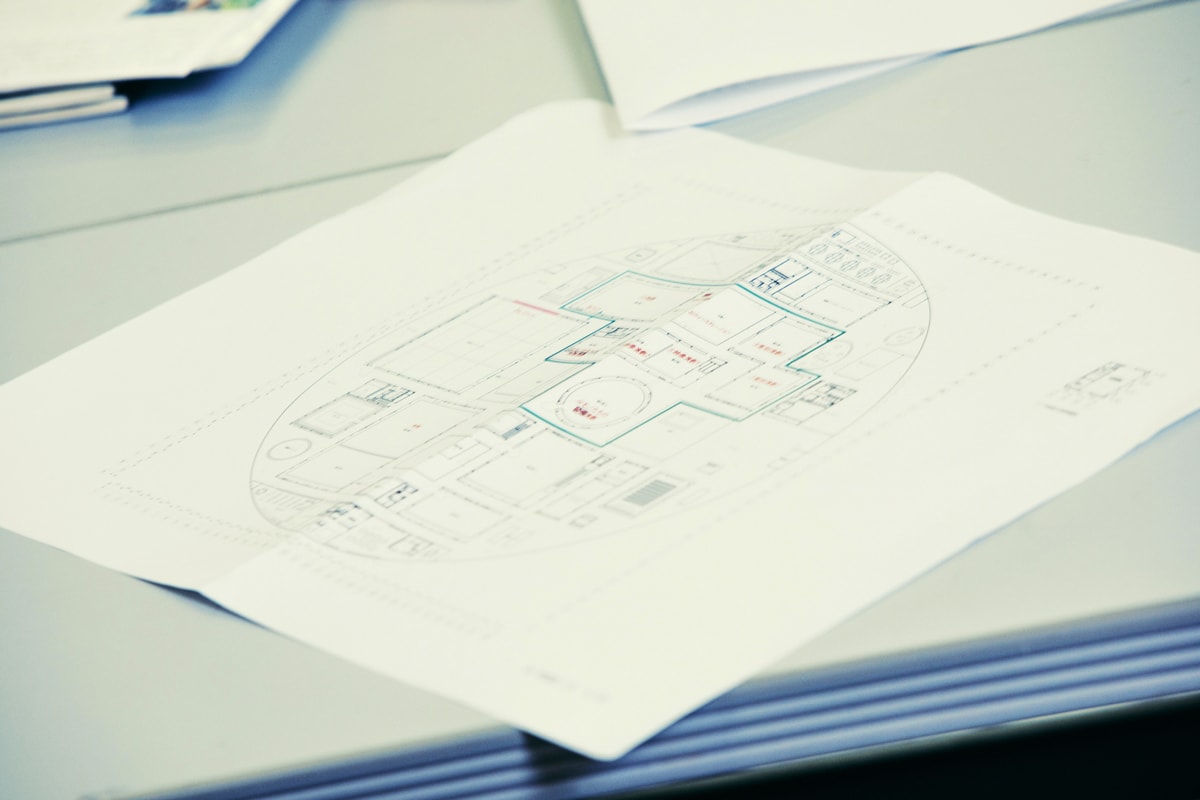
人間中心的な世界からずらしていくために
――モノを主体にした演劇の面白さを追求する一方で、いわゆる人が主体となる演劇も今後手掛けていかれますよね。
そうです。人間中心的な演劇は、今後も作り続けるでしょう。そのことを否定はしませんが、自分自身のモードの質を変えていきたい時に、ちょっと問題になる。やっぱり作っているものには集中しますから、それが人間の問題を扱っていたらそちらの方向に流れてしまう。せっかくモードを変えたのにリバウンドしちゃった、みたいなことはあるかもしれない(笑)。でも、そこを頑張らないと、陸前高田で見た衝撃的な風景は解決されない。
――観客となる私たちにとっても、人間中心的な考え方は慣れているぶん強固です。
この考え方は、一番従いやすい価値観なんですよね。この言葉はすごくエゴイスティックに聞こえますが、実はそんなことなくて、ヒューマンという言葉のニュアンスもあります。例えばある人が家を失って、その人が同じ場所にまた住みたいと感じるのは、きわめて理解しやすい気持ちです。それも含めて人間中心なんです。
ただ、そのためにはとんでもない規模のかさ上げをしたり、すごく高い防潮堤を建てないとならない。しかし、それを必要とする人が100年後にどれだけいるか?を考えると…。やはり我々の思考をずらしていく段階に来ているんじゃないですかね。

チェルフィッチュ × 金氏徹平 『消しゴム森』 リハーサル風景 撮影:木奥惠三 写真提供:金沢21世紀美術館
地球には人間だけが棲んでいるわけではないこと、日々使っているモノは人のためだけにあるのではないこと。これからのエコロジーを考えるには、大きな気候や自然にどう対処すべきかよりも、まず私たち自身の意識から変えていかないとならないのだろう。エコとして推奨されるライフスタイルを実践するのもいいけれど、なぜそうしなければならないのかに目を向けること。考え方をシフトすることが生活に与える影響は少なくない。ラディカルな思考の転換へと誘う『消しゴム森』は、その一歩を後押ししてくれるはずだ。
🗣️

岡田 利規
1973 年横浜生まれ、熊本在住。演劇作家/小説家/チェルフィッチュ主宰。活動は従来の演劇の概念を覆すとみなされ国内外で注目される。2005 年『三月の5日間』で第49 回岸田國士戯曲賞を受賞。同年7月『クーラー』でTOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2005―次代を担う振付家の発掘―」最終選考会に出場。2007 年デビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』を新潮社より発表、翌年第2回大江健三郎賞受賞。2012 年より岸田國士戯曲賞の審査員を務める。2013 年には初の演劇論集『遡行 変形していくための演劇論』、2014 年には戯曲集『現在地』を河出書房新社より刊行。2016 年よりドイツ有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレのレパートリー作品演出を4シーズンにわたって務める。2018 年8 月にはタイの小説家、ウティット・へーマムーンの原作を舞台化し、塚原悠也とコラボレーションした『プラータナー:憑依のポートレート』をバンコクにて発表、12 月にフェスティバル・ドートンヌ/ジャポニスム2018(パリ)、2019年に響きあうアジア2019(東京)にて上演。