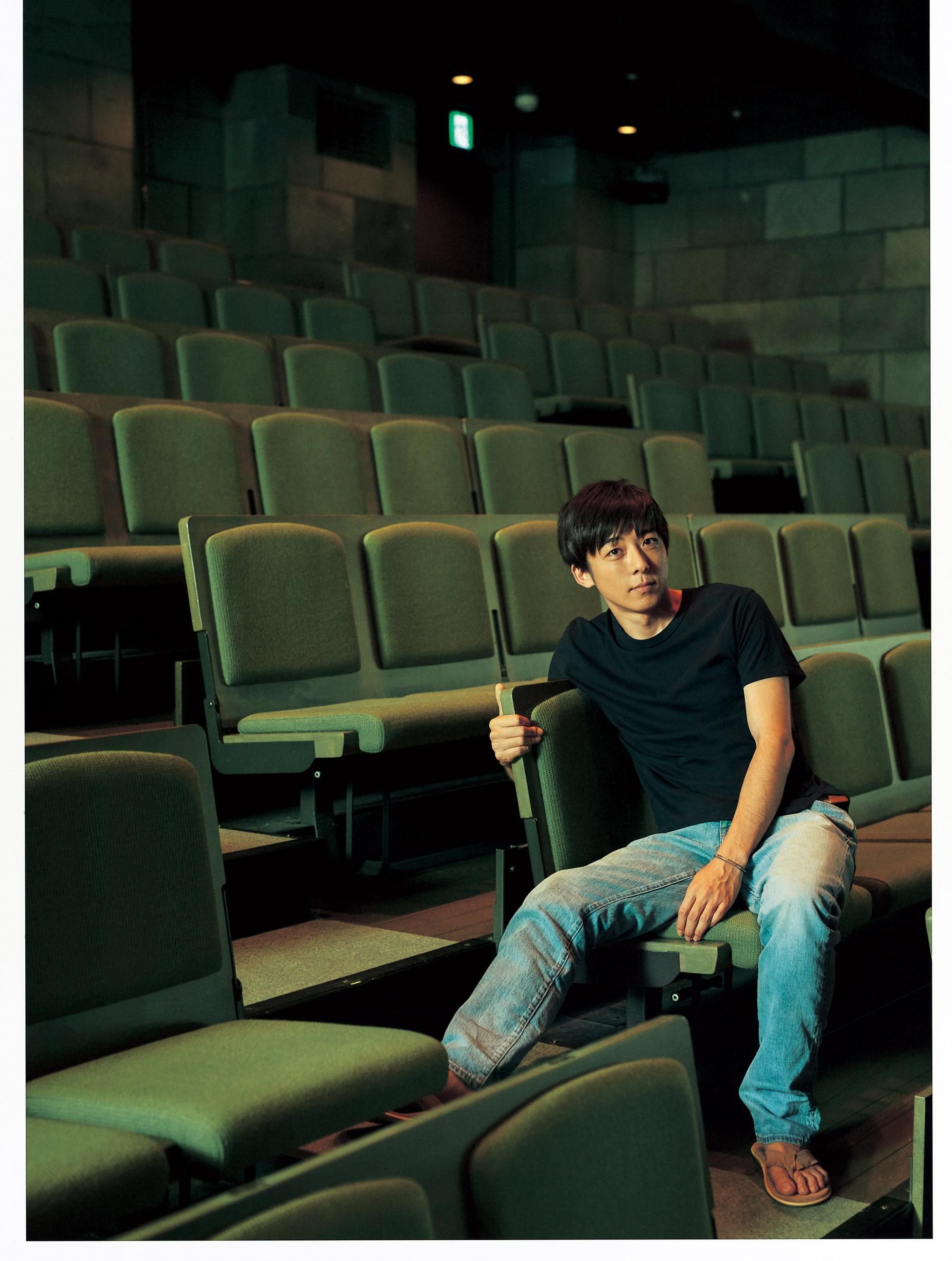9歳ながら並外れた歌唱力とリズム感で当時の音楽シーンに衝撃を残した、あの「Folder」のセンターで知られる三浦大知さんが、日本が誇るエンターテイナーとして世間を騒がせている。ハイレベルすぎるそのパフォーマンスに、セカンド・インパクトを受ける人々が続出中。
「昔を知っている方から声をかけていただく機会は、圧倒的に多いですよね。『大きくなったね』とか(笑)。『アナログ盤持ってるよ』とか『フロアでかけてたよ』とか、大人になってから直接言っていただくことが増えたのはうれしいことですね」
3年間の芸能活動を経て、12歳で変声期を理由に普通の男の子に戻ることになった三浦さん。「じゃあやめます」と、すんなり納得いったのかは気になるところ。
「歌とダンスをやめるという考えは最初からなかったんです。でも、歌い続けると喉をつぶすかもしれない。これからずっと歌っていくためのお休みということで、ネガティブには捉えてなかったですね。むしろ、事務所の社長が自分のことを考えてくれてるんだなとうれしかった記憶があります」
レッスンや芸能活動で小学校へあまり行けなかった彼は、その時期を取り戻すように中学校生活を満喫。2年後、ソロデビューに向け本格的にレッスンを再開する。当時17歳、デビュー前に行われたミニ・ライヴで、ある覚悟が生まれたそう。
「『おかえり』と声をかけていただいて、僕の歌を待っていてくれた人たちがいるんだと。彼らに恩返しできるように、これからも歌っていかなきゃ! と思いました」
好奇心旺盛で工夫好きな性格は、ずっと変わらない。できるできないは置いておいて、とりあえずやってみる。限られた状況の中で自分がやりたいことをどう表現できるかを考えるのが楽しい。たとえピアノが弾けなくても、「弾き語りをしたい」と思ったら、キーボーディストの手を写真に撮って型を覚え、一週間後にはライヴで弾き語りを披露してしまう。その強靭なメンタル、どこで育まれたんですか?
「中学でバレーボール部だったからですかね(笑)。セッターをやっていたんですが、先生や先輩にすごく鍛えられまして。そのときの基礎体力や厳しい練習に耐えた経験は、今に生きてるなと思います」
壁にぶつかることももちろんある。そんなときは、「振り返ったり立ち止まる」のではなく、「前を向いて考えている」とポジティブに変換するタイプだ。
「自分の歌やダンスを定期的に嫌いになることはあっても、どっかで乗り越えられると思ってます。たとえばライヴを演出したり、曲や歌詞を作ったり。あんまりだなと思いながらも振り付けをしてみることもある。でも、それを見たり聴いたりしてくれた人が、『よかったよ』と言ってくれると、救われた気持ちになるんです。そういうゴールがどこかにはある、ということを経験してきたので」
そんな三浦さん、作曲は鼻歌から、ダンスは街で見かけた子どもの変な動きを参考にしたりもするという感覚派。それ故かもっとも苦しむのが、作詞だとか。
「言葉って強いというか、発したことに責任を感じてしまうんですよ。日本語は複雑な感情を絶妙なバランスで表現できるからこそ、慎重になる。正解か不正解かわからず書いているところはあります。僕の場合、歌詞が降ってくるとかはないので、絞った最後の一滴って感じ(笑)」
デビュー20周年を迎える三浦さんの最新アルバム『HIT』は、収録曲でもある、厳しい状況のときに送る声援を意味する「Hang In There」の頭文字から成る。「常に面白いこと、楽しんでもらえることを考え、歌い踊り続ける」という10代から変わらない努力とそのポジティヴな姿勢が、成功へとつながった自身のことを示唆しているかのようだ。
「うまくいかないことを乗り越えるとき、音楽が希望や救いになるといいなと思っていて、そんなアルバムでありたいなと。自分にはない価値観と出合えたり、視野を広げてくれるのが音楽だから」