蜷川実花の鮮やかな写真に、思い切り刺さるインティメイトなコピー。 このタッグは今年で11年目。女心を代弁してくれているようなハッとする 言葉を次々と繰り出すコピーライターの尾形真理子さんは、ルミネの 仕事を「明らかに他の広告業務と違う仕事」という。その意味とは?
言葉を次々と繰り出すルミネのコピーライター、尾形真理子さんにインタビュー!「ルミネらしさってなんだ?」
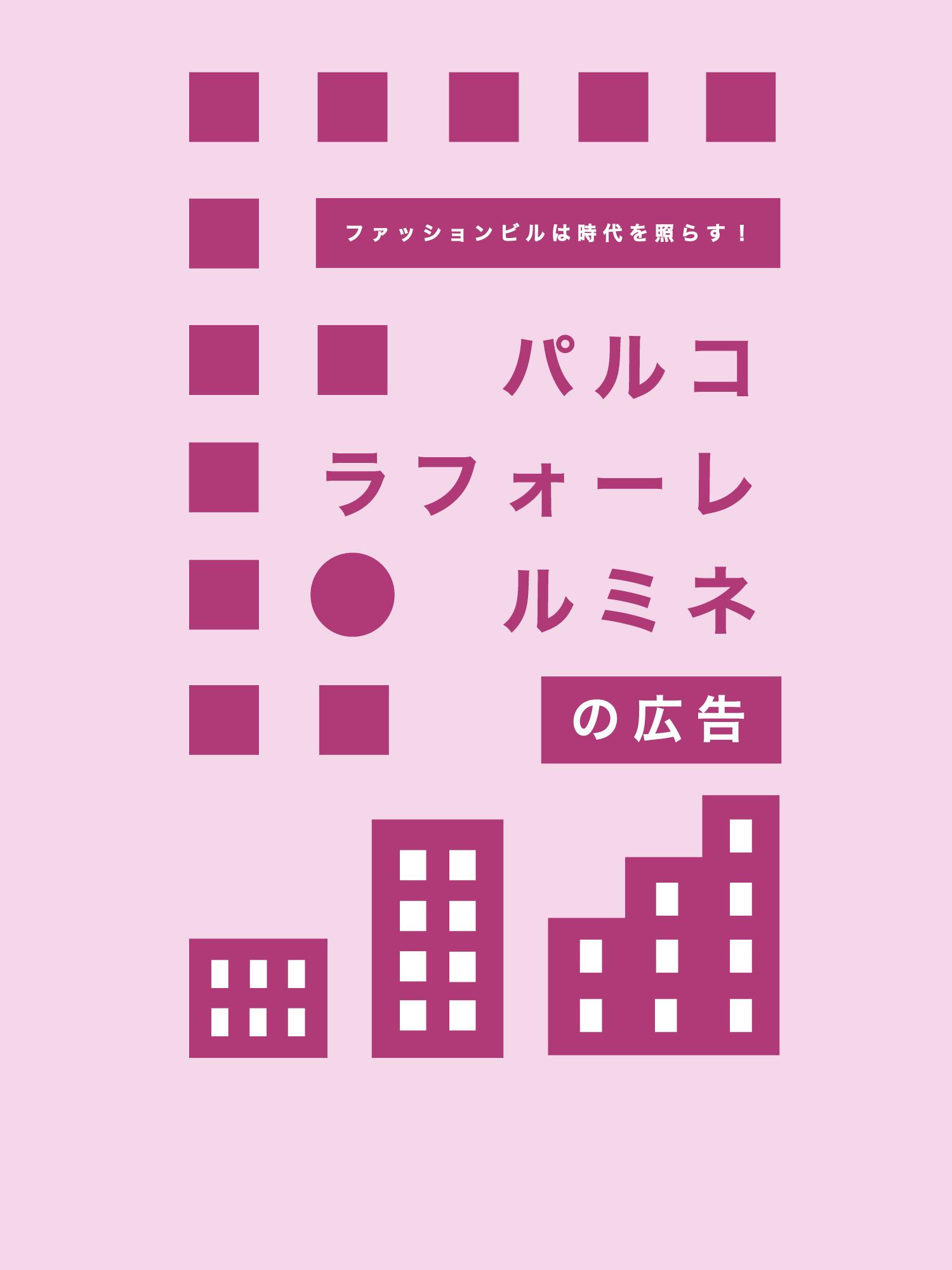
ルミネらしさってなんだ?
わたしが子どもの頃は、ルミネは食品も売っているし、生活雑貨も多くて、雑居ビルみたいな印象が強かったんです。そこからファッションビルに方向転換し始めたのが2000年頃だったと思います。この広告シリーズをやることになった時点で、すでにルミネの方針として「わたしらしくをあたらしく」というスローガンは書いてました。等身大の女性を意識する感覚があったと思います。
ルミネは駅と直結している恵まれた立地なので、本当にいろいろなお客様がいらっしゃいます。ファッションターゲット層以外のお客様もとても多いので、それまでのファッションビルのように、確固たるコンセプトやイメージが打ち出しづらいという難点がありました。そういう状況のなか、当時から女性たちに絶大な人気を得ていた蜷川実花さんの写真に合わせてコピーをつけて、1年を通してルミネのシーズナル広告を出すことになったわけです。だから、最初はすごく悩みました。蜷川さんの写真はそれだけでメッセージ性が強いし、他のファッションビルやファッション広告でも成り立ってしまうんですね。そこで「ルミネらしさ」ってなんだろうって。そのとき、女性たちを集合体で捉えずに、思い切りパーソナルにしたらどうかと考えました。誰でも一瞬でわかるパブリックイメージをひとつに集約するよりも、一人ひとり、個別につながれたらいいんじゃないかと。
パーソナルな表現が共振するところ
その方向性が決まって、口にも出さずに胸の内にしまっておくであろう思いを、あえてコピーにすることにしたんです。人に伝えるため以前の言葉ですから、つたないはずです。その生の感じとか、不完全な感じは大事にしてみようと思いました。写真も色の調整すらしなかったですし、デザインも作り込まないように注意しました。そういうねらいはありましたが、最初は、やっている私たちも、クライアントも、世間も、「わからない」感じがあったと思います。明らかに異質なんだけれど、どう異質なのかもわからないし、正解もわからない。広告のプロからすればどう見ても不思議なクォリティだし、周りがざわざわしていた記憶があります。そんななか、最初に反応してくれたのは広告を見てくれた女の子たちでした。毎月続けていくうちに「ルミネのポスター好き」とか反応してくれる人が増えていって、それがすごく大きなムーブメントになっていった感じです。それぞれ刺さってるものはちょっとずつ違うのも面白いところで、「なんで私のことがわかるんですか」というお便りをもらう一方で、まったくピンとこない人もいたり。いい意味で「フツーの心情」だったからこそ、〝自分ごと化〟してくれた人が多かったんだと思います。
女の自意識に歳は関係ない
女性の感情って、実はそんなに世代差がないような気がするんです。先日出た村上春樹さんの小説(『騎士団長殺し』)に〝すべての女性にとってすべての年齢は、とりもなおさず微妙な年齢なのだ〟っていう面白い一節があって。たしかに、思春期もそうだし、結婚するのかしないのかとか、子どもはどうするとか、老いにどう向き合うかとか、ずーっと微妙なお年頃ですよね。そういう状況のなかで迷ったりしながら、自分の道を進んでいる。だから、ルミネのコピーも、すごくパーソナルな言葉であるぶん、同時にとても普遍的、どの世代にも当てはまることなのかもしれません。そういう、歳に関係ない女性の自意識があるんだってことを、このシリーズをやってて気づかされました。
今ではルミネ=ファッションビルもだいぶ定着しました。最近はファストファッションをハイブランドと混ぜることが当たり前になったり、女の子が自分なりのスタイルを作る才能がどんどん上がっていて、女性たちの感性が成熟してきたように感じます。だからこちらもデザインの完成度を上げたり、言葉遣いをちょっとだけチューニングしたりして、洗練した方向にシフトしています。
ルミネは今もいろんな世代のあらゆる人が来る場所です。しかも、今はどの世代の女性たちも自分の個性とセンスを持っているから、一方的にトレンドを打ち出す必要もない。だから、ルミネの広告は今も揺れています。永遠にはっきりこれという答えが見つからないもやもやが、ルミネらしいのかもしれません。答えを探し続けて、表現が変わり続ける。その意味で、やっぱりルミネはちょっと異質な仕事なんです。





























