トレンドや人気はどのようにして生まれるのだろう。いや、そもそも今の時代、何をもって流行と呼ぶの?マーケティングアナリストで、若者文化にも詳しい原田曜平さんにお話を聞いた。
【生物学、マーケティング、エンタメ視点で分析!特集 #流行と人気の正体 より】
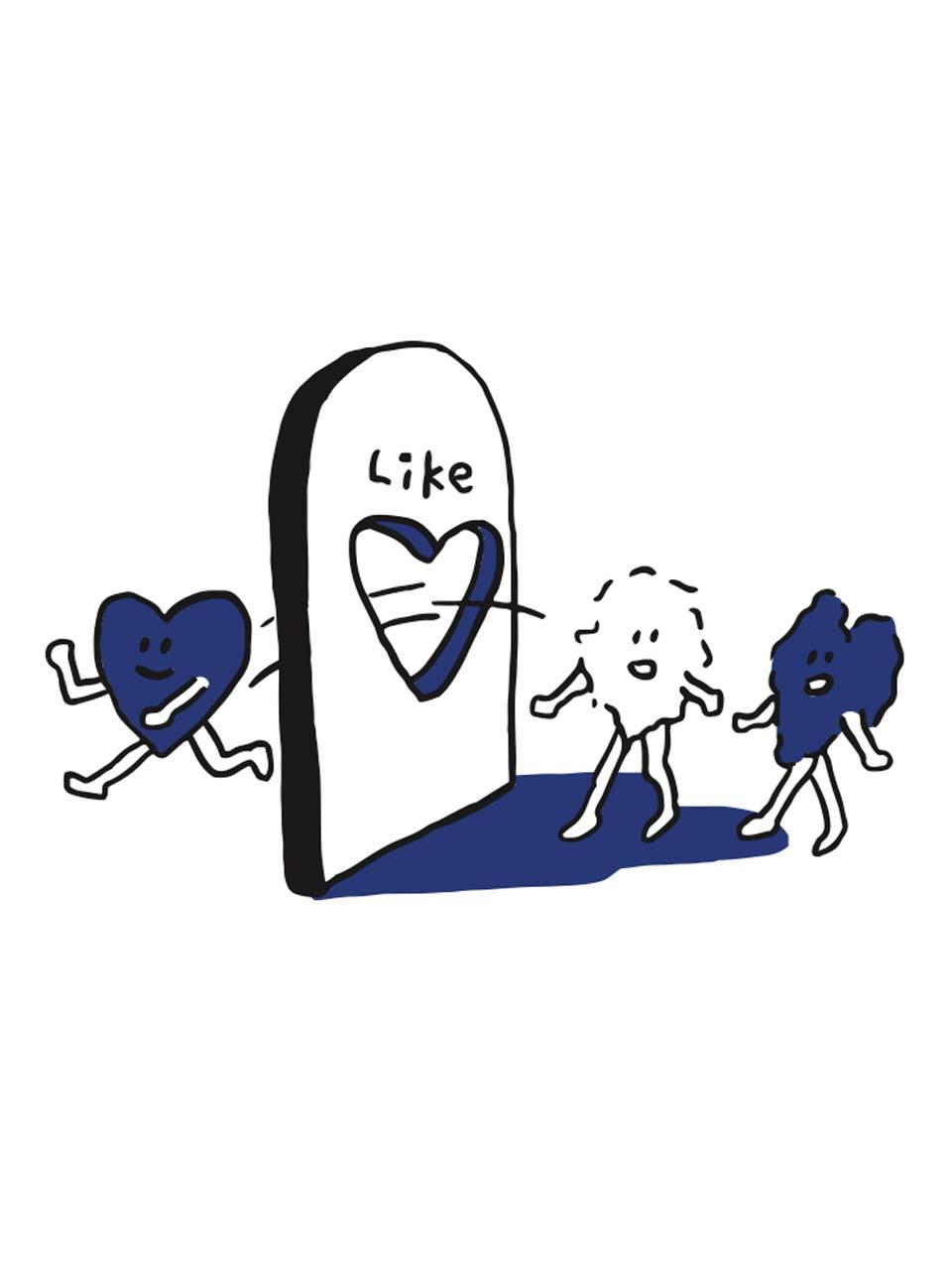
トレンドや人気はどのようにして生まれるのだろう。いや、そもそも今の時代、何をもって流行と呼ぶの?マーケティングアナリストで、若者文化にも詳しい原田曜平さんにお話を聞いた。
【生物学、マーケティング、エンタメ視点で分析!特集 #流行と人気の正体 より】
情報源の違いによる認知度の差
大人世代と若者世代の断絶
「出端をくじくようですが、今は流行不在の時代になっているのが大前提です。たとえば『2022年ジェネレーションギャップランキング』には『美味しいヤミー感謝感謝』『純欲メイク』『水グミ』など、大人世代にはあまりなじみのない言葉ばかり。世の中のブームに対する認知の度合いが世代間で分断しているのです。平成、もっと前の昭和時代は特にマスメディアの影響が強く、年齢が違っても共通項を持つことができた。もちろん、夢中になる対象は違うけれど、若者は深夜ラジオでいち早く新しい情報をキャッチして、その後、家族がそろう茶の間のテレビ番組などを通じて徐々に大人にも知られていくという基本的な流れがあった。だから情報が行き渡るのが早いか遅いかの違いはあるものの、複数の世代が同じモノやコトに飛びついていたので、大流行がおきました。その状況をガラリと変えたのがスマホやSNSで、特にTikTokの影響が大きかったです」
TikTokの利用率は10〜20代では約3割。それが30〜50代だと8%とかなり低い(22年)。その他のSNSでも同様だ。 「スマホを使うのが当たり前の世代と、いまだにマスメディアを頼りにしている大人世代の違いです。子どもの側からしてみれば、家族のいるリビングに行って、受像機の前に座って、リモコン探して、親父からチャンネル変えろとか文句言われたり、テレビってすごく使いにくいツール。それより外出先でも寝転がっていても、誰にも邪魔されずに観られるスマホのほうがいいに決まっている。だから彼らがTikTokを情報源とするのは当然です」
誰でも数十秒の短尺動画を投稿したりシェアしたりできる気軽さ、ひと目でわかる簡単さ。雑誌が企画決定から発刊まで2〜3カ月かかるのに対して、こちらは毎日投稿される。そのスピードの差は歴然だ。あっという間に受容され、伝播されて流行となるが、移り変わりも加速度的に速い。 「SNSを通じて若者の間だけの小さなムーブメントは生まれているのですが、それが大人にはまったく伝わってない。だから見えにくくなっているというのがひとつあると思います。今後はますます変化のサイクルが異様に速くなるでしょうね。今の子たちはYouTubeの10分間動画でさえ長い、かったるいと感じて離れていっているそうです。下手すると数秒の動画だけで理解したい。情報の鮮度について『それって3日も前のことだよね?』なんて言われかねない時代がやって来るかもしれません」
世代間をまたいで起こった旋風
『鬼滅の刃』の軌跡を読み解く
ところが、だ。この流行不在の時代に稀に大ヒットが生まれることがある。その代表例が『鬼滅の刃』だろう。
「世代間の断絶によって流行の分断・分散化が起きていますが、マスの流行が完全になくなったわけではありません。なぜ『鬼滅の刃』が映画興行収入の歴代最高額を叩き出したのか、要因を分析してみましょう。この物語は2016年から『少年ジャンプ』で連載されていましたが、当初は世間的知名度がさほど高くなかった。それが後にアニメ化され火がついたんです。その背景では、若い女の子の間でイケメンの登場人物に対する『推し活』文化が盛んになっていた。自分の推しの柱の画像を切り抜いてTikTokに載せるのが流行り、同世代の男子へも広がりました。そしてもうひとつの要因は、コロナ禍で巣篭もり生活となり、親子の距離が近くなったこと。もともとZ世代には、親と友達みたいに仲が良い傾向があるので、親子で一緒にアニメを観る。そうすると、お父さんは『少年ジャンプ』の夢と冒険のストーリーに慣れ親しんだ世代ですから、懐かしいし、共感してのめり込んでしまう。こうした複合的なファクターによって、世代をまたいだ大成功につながったのです。だから上と下の世代をつなぐ導線を設計することがマス・マーケティングに重要です。放っておいたら世代ごとに分断されたまま。それだとマスの流行になりません」
大当たりを生むためのメソッド
「インサイト」と「橋渡し」
「もうひとつマーケティングに大事なのは『インサイト』という概念です。ニーズは顕在化しているもので、インサイトは潜在化している欲望。つまり、まだ消費者自身が気づいていない自分の欲求のことを指します。流行したものや売れたものには必ず『そう、それ!』と思わず声に出てしまう何かが内在している。そこにいち早く気づいて商品化できたら爆発的ヒットになる可能性はある。そのために必要なのは耳障りのいいコピーなどではなく、ターゲットに関する徹底した実態調査なのです。少なくとも世代ごとのインサイトを見極めつつ、それぞれの世代の間の『橋渡し』をしてあげる。この二つの作業を、地道な分析を通じて徹底することで、現代においても大きなブームやミラクルヒットが生まれる可能性が大いにあると思います」

輪郭がくっきりする前の、“なんとなく好きかも”。それが「インサイト」。
1977年東京都生まれ。博報堂を経て現在はマーケティングアナリスト、芝浦工業大学教授。「さとり世代」などのキーワードを世に広めた。最新刊に『Z世代に学ぶ超バズテク図鑑』(PHP研究所)。