知っておきたい日本の言葉、季節のあれこれ。
ギンザ淑女のニッポン歳時記 大晦日に狐が提灯を下げて集まる伝説「狐火」

狐火(きつねび)
火の気のない里山に、ぽつぽつと松明の灯のようなものが飛んで見える怪現象を、まるで狐が提灯行列をしているようだとして「狐火」と言いました。狐が馬や人間の骨を掘り起こして咥え、骨の燐(りん)が空気と反応して燃えるとの俗説もありましたが、今では光の屈折が原因かと言われています。春から秋にかけて見られますが、大晦日に東京の王子稲荷神社に全国の狐が提灯を下げて集まるという伝説から、狐火は冬の季語になりました。
今月の神様
付喪神(つくもがみ)
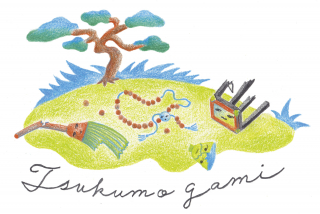
立春前の煤払いの時に捨てられた古道具たち。「長年人々の暮らしに尽くしてきたのにこの仕打ちはひどい」と言って、人間への復讐を企てます。妖怪に化けて悪さをしますが最後には改心して成仏するという物語が『付喪神絵巻』に描かれています。割れた茶釜や数珠などが擬人化されて登場して愉快です。物にも魂があると考えた、古来の日本人の感覚。断捨離全盛の今、なんだか気になります。
今月の文様小物
結び文の皿(むすびもんのさら)
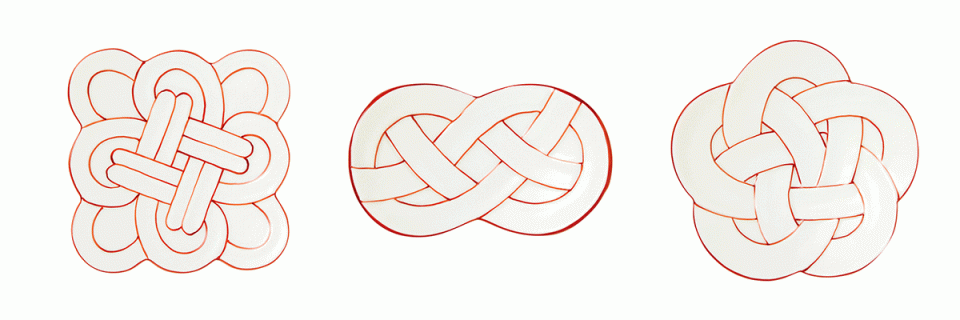
紐を結ぶという行為は、中のものを封じて鍵をかけることが目的でした。その後、特に茶道具をしまう袋=仕覆(しふく)の結び目が蝶や花を表す複雑で美的なものへと発展していったのです。のし袋にかけられた水引の結び目にもさまざまな種類があり、それぞれに意味が込められています。固く結ばれ解けないご縁や長寿の意味合いが込められた結び文の皿は和洋の境を越えていて、コンテンポラリーなデザインに見えます。
左から 小皿 吉祥結び/あわじ結び /梅結び *赤 各¥2,000(田清窯)
今月の和菓子
顔見世(かおみせ)
![]()
![]()

江戸時代、歌舞伎役者は劇場と年間契約を結び、1年ごとにその顔ぶれが変わりました。新しい役者の発表は11月で、これを「顔見世」と呼んだのです。今でも11月の歌舞伎座、12月の京都南座の「顔見世興行」は特に有名です。市川團十郎や海老蔵などの屋号である成田屋の紋「三升」を型押しした、着物の袖を思わせる和菓子から、年の瀬の歌舞伎の華やぎを想像します。
二重にしたういろうで白小豆粒餡を挟んだ生菓子。〈顔見世〉¥400 *12月販売(お菓子調進所 一幸庵)
Photo: Kaori Oouchi (wagashi), Natsumi Kakuto (sara) Illustration: Hisae Maeda Text&Edit: Mari Matsubara
































