オランダの首都、アムステルダム。2017年にミレニアル世代が住みやすい世界の街ランキングで1位に選ばれるなど、近年人気が高まっている街だ。デザイン都市としても知られ、クリエイティブな人々が各国から集まる。そんなアムステルダムで活躍する日本人たちには、どんな街との物語があるんだろう。この街で見せた笑顔や流した涙を知りたくて、彼女たちに会いに行ってみた。
オランダ国立バレエ団のダンサー坂本莉穂/私のアムステルダム物語vol.2
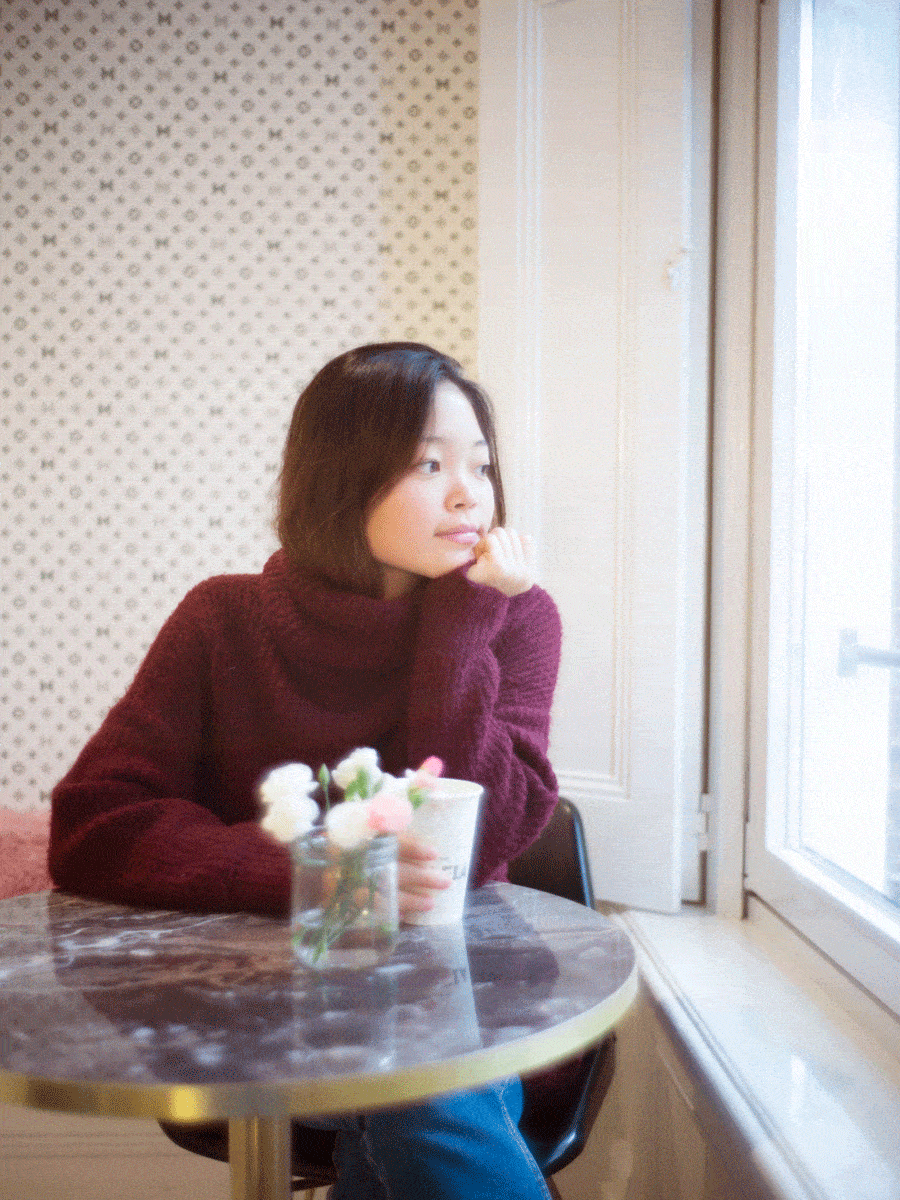
自転車通勤の人々がジャケットやコートを着るようになって久しい9月のアムステルダム。曇り空の肌寒いこの日、若者で賑わう「De Pijp(デパイプ)地区」にやってきた。シックなレストランやカフェがひしめく一方、国内最大のマルシェが開かれたり、ゴッホ美術館や市立美術館などもあったりする。食事や買いもので楽しめるだけでなく、文化的にも豊かなエリアなのだ。
そんなデパイプ地区の路地裏にある小さなカフェ「Matcha Mafia(マッチャ・マフィア)」で今回お話を聞いたのは、オランダ国立バレエ団で活躍するバレエダンサーの坂本莉穂(さかもと・りほ)さんだ。
「日本のテイストが恋しくて…」と恥ずかしそうに笑う彼女は、化粧気がなく素朴な印象。大人びた表情を見せる舞台上と比べると、びっくりするほど若く見える。聞けば、まだ21歳だという。「Matcha」という名のとおり抹茶ドリンクが飲めるこのカフェは、近くのおにぎり屋さんからハシゴをして行き着く、坂本さんの休日の定番コースらしい。
カフェのスタンプカードをいそいそ貯めているのも微笑ましく、その姿は“ごく普通の女の子”。一見、名高い「オランダ国立バレエ団」でソリスト(主要な役を与えられ、ソロを踊ることができるダンサー)を務めている強者には思えない。でも話を聞いてその印象は一転、彼女の持つ圧倒的なエネルギーやメンタルの強さに感銘を覚えることになる。

坂本さんがバレエを始めたのは、たった4歳の頃。祖母から「姿勢が悪い!」と言われたのがきっかけだった。その言葉を素直に受け止め、姿勢をよくするためにバレエを始めた彼女は、周囲が驚くほどその魅力にハマっていくこととなる。
今でも覚えているのは初めての発表会で、ステージに立ち、何か月も練習した踊りをステージで踊りきったときの達成感たるや。どんどんバレエにのめり込んでいく彼女を、母は全力でサポートした。毎日のように、地元から車で片道1時間以上をかけ、大阪市内のスタジオへと送り迎えしてくれたという。
そのバレエ人生が決定的に動き出したのは2008年、彼女が10歳のとき。夏休みを利用して単身アメリカに飛び、ワシントンにあるバレエアカデミー主催の夏季合宿に参加していたタイミングで、日本にいる母から一本の国際電話が入った。
「そのままアメリカに残りなさい」
衝撃だった。バレエアカデミーでのスカラシップ(奨学金)が認められたため、そのまま残ってバレエをやりなさいと言われたのだ。まだ幼かった彼女に、母はどんな気持ちでその言葉を放ったのだろう。「もし私に小学生の娘がいたら、きっとそんなこと言えないですね…」と言う坂本さんは、このとき母が背中を押してくれたことに心から感謝しているそう。
むしろ、10歳という若さだったからこそ、海外に飛び出す勇気を持てたのかもしれないとも振り返る。こうして彼女は、言葉が通じない、友だちもいない、文字どおり、右も左も分からないアメリカに、たった一人で残る決心をした。

晴れて全寮制のアカデミーに入学したが、最初はとにかく大変だった。慣れない環境に慣れない食事、さっぱり分からない英語を必死で勉強しながらの、厳しいバレエ練習の日々…それでも弱音を一切吐かなかったという彼女は、当時アカデミーで最年少ということもあり、目立っていたのだろう。彼女をよく思わない寮のルームメイトの女の子たちから、心ないイジメを受けることもあった。
全寮制なため逃げ場はなく、かつ守ってくれるはずの両親もはるか海の向こう。普通ならこの辺りで心が折れるところだが、彼女は「弱いところを見せたら相手がつけあがると思っていたので、徹底的に無視しました。そうしてたらいつの間にかなくなりましたね」と、やはり強かった。
数々の困難にもめげず、12歳のときにはアメリカのバレエコンクール「ユース・アメリカ・グランプリ」で見事金賞を受賞、またアカデミーでも授業料が全額免除になるスカラシップを6年間、毎年欠かさず勝ち取ってきた努力家の彼女。
“親に一切負担をかけたくない”、“スカラシップがもらえなかったら日本に帰らなきゃいけない”という当時のプレッシャーは、プロになった今以上のものだったという。ごく当たり前の青春を手放して、彼女はバレエの道で食べていく夢のために死ぬ気で頑張った。
そして2014年、16歳という異例の若さでプロのダンサーになった。入団先は、ずっと志望していたオランダ国立バレエ団。世界屈指のバレエ団であり、そのステージ映像を観たときに感動し、「ここに行きたい!」と強く思ったそう。
基本的にどのバレエ団も18歳以上のダンサーしか雇わないのが普通だが、それまでの坂本さんの功績や、すでに高校卒業資格を取得していたこと、そして、当時そのバレエ団でプリンシパル(トップダンサー)を務めていたマイヤ・マッカテリさんの父親がバレエの先生だったことも後押ししてくれたという。
6年間を過ごしたアメリカ・ワシントンを離れ、知り合いがいないオランダ・アムステルダムにまたもや一人で渡った。移住当時、不安はなかったのだろうか。
「不安というより、自由すぎてどうしようって思いました」と坂本さん。というのも、アメリカ時代は寝ても覚めてもバレエ一色、アムステルダムに来て初めて“外の世界”に出たからだ。
初めてのアパート暮らしに初めての自炊…アメリカでは治安の悪さから、学校の敷地外への外出もままならなかったため、好きなときに好きな所に行ける自由を心底楽しんだという。不安だったオランダ語も、ふたを開ければ、大部分の住民が英語を話せたので拍子抜けした。

アムステルダムという街自体も、彼女は気に入った。こじんまりとしていて、自転車一つでどこにでも行ける上、街中に美しい運河が流れている。休みの日は運河沿いに座って、ひたすらボーっと過ごすのが好きだという。アメリカ人お得意のSmall Talk(世間話)をするのが苦手だった彼女は、無駄な話を一切しないアムステルダマーをありがたく思う一方で「お店の店員さんはもう少しフレンドリーでもいいんですけどね」と笑う。
ただ、プロになってから最初の一年は、体力的にも金銭的にも相当苦労した。メインのバレエ団に入団するまで、ジュニアバレエ団で一日8時間、ほぼ休憩なく踊り続ける日々が1年続いた。休みは週1回、給料は月にたったの360ユーロ(約43,000円)。家賃はバレエ団が負担してくれたものの、アメリカや日本に比べ、物価が高いアムステルダムで過ごすのは大変だったはず。
それでも「外食は一切せず、安いスーパーで一番安い野菜とか買って自炊するんですよ。そうやってたら案外大丈夫でした!」と言う彼女は結局、一度も親を金銭面で頼っていないという。

2016年、18歳でメインのバレエ団に入団した後、ついに2019年、念願のソリストに就任。21歳にして世界トップレベルのバレエ団でソロを踊るようになった。
就任がわかると真っ先に、母に電話をかけたという。4歳でバレエを始めてからずっと変わらず応援してくれている母に、誰よりも先に伝えたかったのだ。母に自分のソロを生で観てもらうために、飛行機のチケット代をコツコツ貯めているという。そんな彼女に今後の目標を聞いてみると、はっきりとした答えが返ってきた。
「それはやっぱり、このバレエ団のプリンシパルになることですね。トップになりたいです」
彼女なら絶対に叶えるだろうな、と思った。将来的には日本を含め、世界で公演したいと話す坂本さんの目は、とてもキラキラしている。
最後に「恋の方は?」と聞いてみた。すると少し照れながら、同じバレエ団にいるオランダ系カナダ人男性と付き合って1年半だと教えてくれた。16歳で入団した当時からの仲間であり、親友でもあった彼の存在には、辛いとき本当に助けられたという。本番で一緒に踊ることもある彼は、公私ともにかけがえのない存在だ。人に恵まれているという彼女、しかしそれは自身の魅力もあってのことだろう。
インタビューの後、今晩の食材を買いにマルシェに行く彼女について行った。最近ようやく、バレエ団が拠点を置く劇場の近所に引っ越し、念願の一人暮らしを始めたらしい。たくさんの魚を前に「どれにしようか」と悩む彼女、その姿だけを切り取ると、本当に“ごく普通の21歳”だ。彼女を特別にしているのはきっと、夢に向かってのひたむきな強い想いなのかもしれない。

🗣️
坂本莉穂
奈良県出身。2008年よりアメリカ・ワシントンにあるキーロフ・アカデミー・オブ・バレエにてスカラシップを得て学ぶ。2014年 にプレジデント賞を得て卒業。2008年の全国バレエコンクールin Nagoyaにて第1位、バレエコンペティションin奈良にて第2位、2010年のユース・アメリカ・グランプリ・ニューヨークファイナルにてゴールドメダルなど、様々な賞を受賞。2014年にオランダ国立ジュニアバレエ団に入り、翌年にはオランダ国立バレエ団にエレフとして入団。2019年にソリスト就任。
@riho_sakamoto
Photo & Text: Sakie Miura Edit: Milli Kawaguchi