夢に向かって努力する自分と、大人として社会に適応しなければいけない自分。あわただしい日々の中で「あの頃夢見ていたのは、こんな自分ではなかった」と、理想と現実の狭間で揺れる主人公を描いた漫画『パーフェクトシンドローム』の連載が〈ginzamag.com〉でスタートする。就職、転職、結婚など、人生の転機で多くの人が経験するであろうこの葛藤を描くのは、イラストレーターで漫画家の日向山葵さん。どうやってこの物語が生まれたのか、その道程について話を聞いた。
連載漫画『パーフェクトシンドローム』の著者・日向山葵インタビュー


ふんわりとした佇まいの中に、ピリッとスパイスも効いている、日向山葵さんの絵。これまでロックバンドのシャムキャッツをはじめ、さまざまなミュージシャンのグッズやCDジャケットなど、イラストの仕事を中心に活動をしてきた日向さんだが、大学時代に自費出版した短編漫画集など、自分の制作のすぐ近くには、いつも漫画の存在があったそう。
日向さんと漫画の物語を伺うべく、仕事場でもあるご自宅に向かった。老舗のたいやき屋さんや理容室などが並ぶ、どこか懐かしい住宅街の中に、その仕事場はある。多肉植物や観葉植物がぐるりと囲む室内には、行きつけの居酒屋さんが閉店した時にもらったという、大きな魚拓とメニュー札など、日向さんの思い入れがつまった愛らしいものたちが並んでいた。
「家にこもって絵を描くことが多いので、部屋をわくわくする空間にしたいんです」。室内で何よりも目を引くのは、大きな本棚に隙間なくぎっしりと詰まった漫画の数々。そのほとんどは、子どもの頃から読んでいた大切なものだという。
「私の母が大の漫画好きで、いわゆる“オタク第一世代”なんです。家の本棚には、あらゆるジャンルの漫画がたくさん並んでいて、萩尾望都さんの名作『半神』を少し怖いなと思いながら読んだり、棚の高いところに隠されていたエッチな『東京大学物語』をこっそり見つけ出したりしていました。
高校に入ってからも、周りの友だちはアイドルや芸能人に夢中になっていたけど、私はラジオを聴いていたことから大槻ケンヂさんが大好きになって。そこから自分が生まれる前に流行ったカルチャーに興味を持つようになり、ますます母と漫画の趣味が合うようになっていきました。今でも実家に帰ると、“あの漫画の続き買ったけど読む?”とお互いに貸し借りをします」
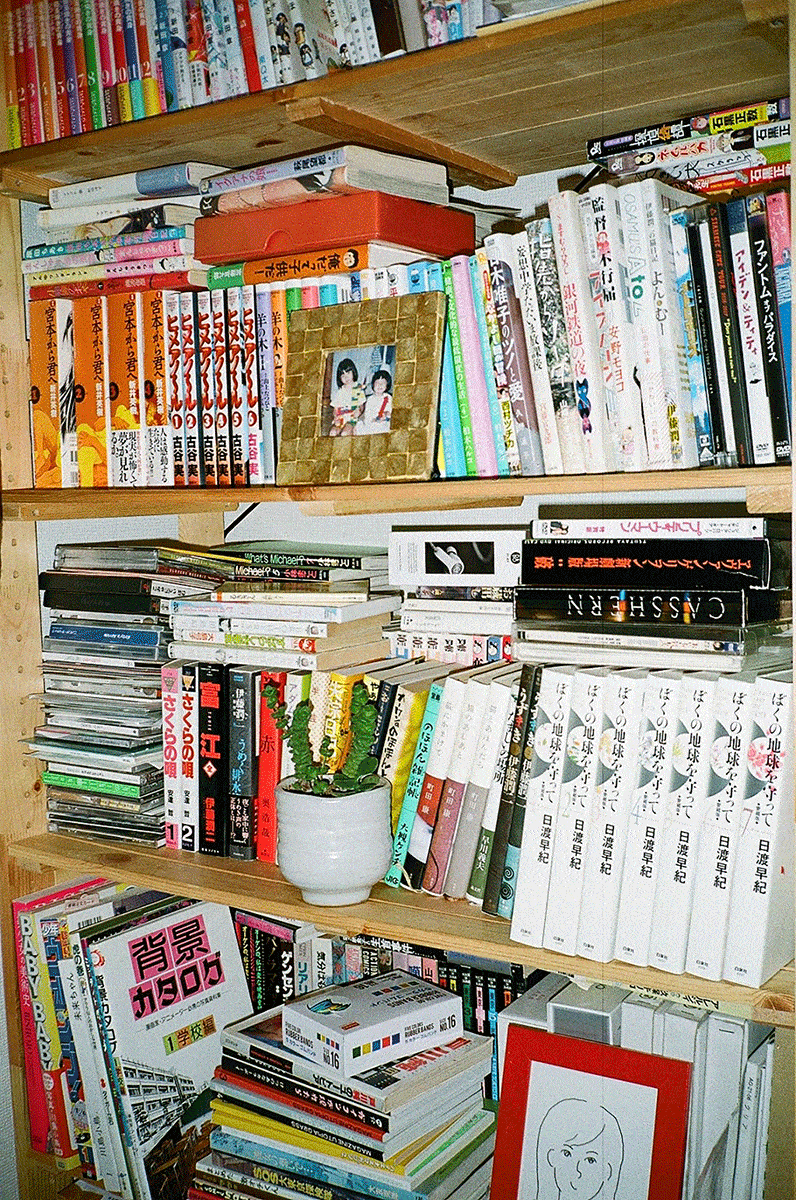
小さい頃からずっと、母の影響を受けながら幅広く漫画を読んできたという日向さんだが、「漫画を読むのが好き」という読者側から、「絵を描きたい・漫画家になりたい」という描き手側に気持ちが動いたのは、いつ頃からなのだろう。
「小学校の時から、クラスでも絵が上手く描ける方で、漫画好きの友だちと3人で手作りでの漫画雑誌を作っていたんです。子どもらしいクオリティーでしたけど、いっちょまえに『スイーツ☆』っていう雑誌名まで考えて(笑)。漫画誌『ちゃお』の作りをまねて、PP貼り加工のつもりでセロハンテープで表紙をツルツルにしたりしてました。
今思い返すと、小学生の時から美大に行くまで、自分のベースには“いつか漫画家になるんだろうな”という気持ちがいつもあったような気がします。実は、私の母も絵が得意で、漫画家になりたいという夢があったらしく、昔から家の中には、“漫画家になりたい”という気持ちが充満していたのかもしれないですね」
大学在学中には、漫画史の授業の課題として描いた短編をブラッシュアップした作品などを収録した、オリジナル短編漫画集『アントン』を自費出版。一方で、当時から好きだったシャムキャッツのライブに、バンドメンバーの姿を描き込んだ自作のポスターを持参し、彼らに直接自身の仕事を売り込んだことも。
自ら積極的に行動を起こし、音楽関係を中心にイラストの仕事が広がっていった。当時を振り返りながら、「音楽って、本や映画や漫画などのカルチャーよりも親しみやすくキャッチーな印象があります。音楽業界の人だけでなく幅広い業種の人が聴いているから、その人たちにも自分の絵を知ってもらえるかなと思いました」と話す日向さん。“冷静な戦略家”という一面も垣間見えた。
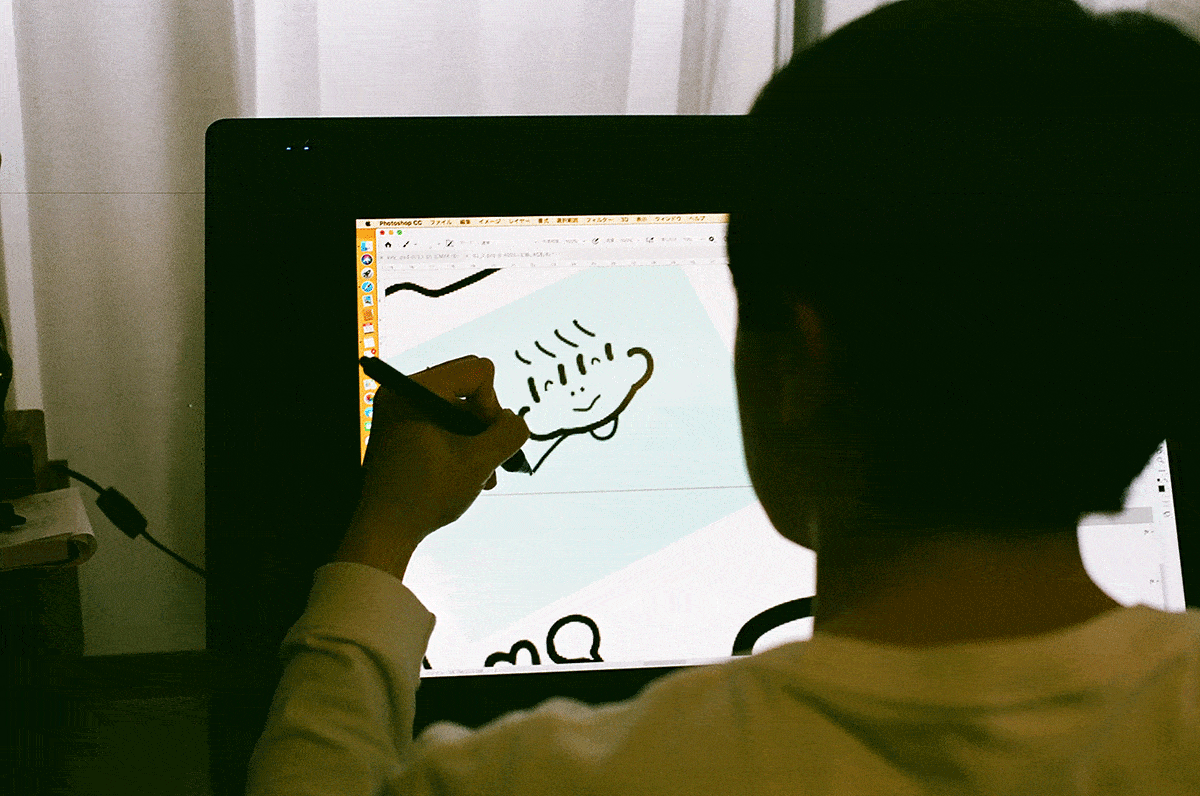
卒業後、WEBデザインの会社に就職した日向さんは、会社員生活を送りながら、自身のイラスト制作も続ける道を選ぶことに。
「これは母にも言われたことですが、私はあまり不自由なく育ってきたこともあって、自分の生活が安定してハッピーな状態でないと制作に集中しにくい性格なんです。だから、まずは金銭的に生活を安定させたいと思って就職しました。奨学金も返済しないといけないですし。
WEBデザインの仕事を選んだのは、フォトショップなど、イラストの仕事に役立つデジタルスキルを身につけるため。でも実際に働き始めたら、目の前の仕事に集中しすぎて、絵の方がどんどん置き去りになってしまって。
その頃、漫画誌を多く発行している出版社の編集さんが『アントン』を読んで、漫画連載を依頼してくださったんです。でもラフを出しても出しても全部ボツになったりと、なかなか形にならなくて、毎日焦っていました。そんな時、当時付き合っていた彼に“どんどんつまらない会社人間になっていくね”って言われて…すごくムカついたし悔しい気持ちになりました。でも実際そんな自分のことも嫌いになり始めていたので、会社を辞めて自分の制作に集中して向き合う決断をしました」

人と自分を比べて自己嫌悪に陥ったり、SNSに投稿される知人の姿が眩しく見えて嫉妬したり。そんな日向さんの実体験は、今回連載がスタートする『パーフェクトシンドローム』にも多く反映されている。
「漫画やイラストって、表には出ない水面下での作業が多くて。だからよく、自分ではすごく努力しているのに、人からは何もできていない人に見えているんじゃないかなと感じていました。すごい勝手なんですが、”音楽ってずるいなー”って。悔しいくらい格好いいし、ダイレクトに輝けるじゃないですか。
でも4年ぶりにアルバムを出した人が“ずっと暮らしを立てるのに忙しくて、音楽に向き合えなかった”と話しているのを聞いて、みんな口には出さないだけで、理想と現実の間で苦しんでるんだなと思ったんです」
タイトルの「パーフェクトシンドローム」は、なれそうでなれない”理想の自分”に苦しめられている精神状態を、病気症状にたとえたオリジナルの造語だそう。
「主人公の柄藤(えとう)は、理想に全然届かない自分を、どうにか何かで補完しようとしてもがいています。かつての私もそうでしたが、きっと同じように焦っている人は世の中にたくさんいるだろうから、そういう人にぜひこの作品を読んでもらいたい。”焦らなくていいよ”と励ましたいし、背中をちょっとでも押すことができたら嬉しいです」

これからもイラストと並行しながら、日々体験したり考えたりしたことを伝える場として漫画を描いていきたいと話す日向さん。最後に、今後挑戦してみたい漫画のテーマや作風についてたずねてみると、「ほのぼのしつつピリリとアクセント」という由来のペンネームを体現しているような、日向さんらしい、まっすぐで芯の強い答えが返ってきた。
「たとえば壮大なファンタジー漫画も、読むのは楽しいです。でも自分の漫画なら、実際に体験したことの中でしか描けないと思っていて。私にとって一番大切なのは日常だし、目の前の毎日を楽しく生きたいと思っているから。昔から好きな漫画も、玖保キリコさんの『シニカル・ヒステリー・アワー』や、けらえいこさんの『あたしンち』のような、日常に視点を置いたものが多いんです。
あとは、ホラー漫画だけど不思議なおかしみもある諸星大二郎さんの『栞と紙魚子』シリーズとか、波乱万丈な日々をポップに描いた吾妻ひでおさんの『失踪日記』とか…。この2作には、日常が描かれている中に、どこか反骨精神のようなものも感じられます。
私も自分の穏やかな暮らしを大切にしたいし、それを失いたくないと思っているからこそ、ただほのぼのしているだけじゃなくて、その向こう側にある現実社会の問題や危機感とかも垣間見えるような、多面的な作品を目指したいです」

🗣️
日向山葵
イラストレーター・漫画家。1991年生まれ、東京都出身。多摩美術大学絵画学科版画専攻卒。2年半の会社員生活の後、2018年よりフリーランスとして制作活動をスタート。独特な曲線で描かれる人物イラストからタイポグラフィーまで、その作品はシンプルながらもポップで親しみやすい。近年ではシャムキャッツやTHE FULL TEENZ、1983など、バンドのグッズやジャケットも手がける。ペンネーム・日向山葵は「ほのぼのしつつピリリとアクセント」の意。
hinata-wasabi.com
@wasabi_hnt
▷連載漫画『パーフェクトシンドローム』はこちらから。
Photo: Sorami Yanagi Text: Tomoe Adachi Edit: Milli Kawaguchi