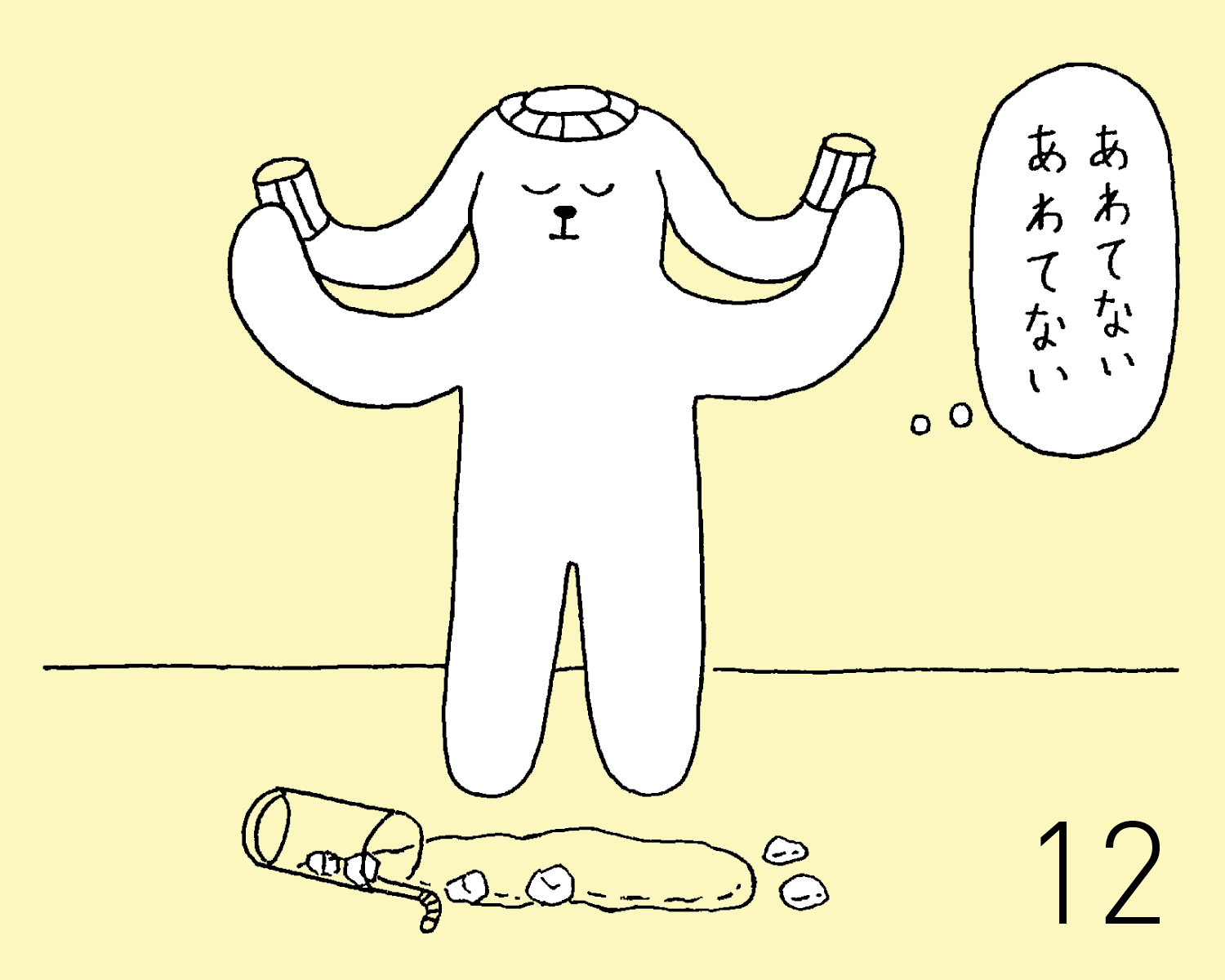小説、建築、パティスリーやグラフィック…さまざまな分野でいま、脚光を浴びているキーパーソンにじっくり話を聞きました。あなたの創造のタネ、情熱の源はいったいどこにあるの?
建築家・工藤桃子が語る、創造のタネと情熱の源|あのフィールドの旬な人 vol.1

architect
工藤桃子
コントロールも予想もできないだから建築は面白いんです
〈SIRI SIRI〉の店舗デザインや「横浜トリエンナーレ」の会場設計など話題の空間を手がけ、ファッションからアートまで、幅広い分野からのオファーがひっきりなし。そんな工藤桃子さんに、この仕事を志したきっかけを聞いたところ、
「オタク気質の蛇行人生を続けていたら、建築にたどり着いたんですよね……」
と、ユニークな答えが返ってきた。
「小学生のころスイスに住んでいて、母とよく観に行ったのがバレエやオーケストラ。舞台上と観客が一体となって盛り上がる世界に、ワクワクしたのを覚えてます。東京に戻ってからの中高時代は完璧なサブカルオタク。太宰と『スタジオ・ボイス』とテレビ番組『ファッション通信』がバイブルでした」
やがて哲学と物理学にハマって物理学者を目指したものの、突如方向転換して美大生に。工芸や映像制作に没頭し、舞台美術や演出も経験した。あれこれのめり込んだ末の大学3年目、本気で面白いと思えたのが建築だった。
「建築は〝文化の総合体〟。ひとつ紐解くと枝葉が無限にわかれていくんです。たとえばル・コルビュジエ。膨大な作品のひとつひとつに、時代の香りや土地の歴史があり、個々の物語や美学があり、同時代の絵や本や音楽の影響が見え隠れする。それらのルーツをさかのぼるとさらに昔の建築家につながったりもして、いくら深掘りしても終点がないし、枝葉が多いほど面白い。あちこち蛇行したオタクには、たまらなく魅力的でした」
卒業後は公共建築も手がける大手設計事務所で建築の本質をとことん学んだ。
「分厚い石、無垢の木など本物の素材に触れ、厚みや重みを身体で覚えさせてもらいました。コンマ2ミリの銅板がどう曲がるかは、実際に手を動かしてみて初めてわかる。建築は空間。体感するものです。現場を知って建物に昇華させた経験は、PCや映像上の勉強では決して得られない。いざとなったら本物を扱えるという自信は、大きな財産になりました」
建築には必ず人が表れる。工藤さん自身がどんな建築家でいたいかと言えば、
「圧倒的な力を放つ、太く強く毛深い表現ができる人。それから、ともにものづくりをする仲間の面白いところをきちんと拾える人でありたい。建築物を作るということは、まだどこにも存在しない、誰にも見えてないものに向かって思考や発想を重ねること。できれば多くの人とそのプロセスを共有したくて、そのために……とにかくいっぱい話をします!」。
と、再びユニークなひとこと。
「コンクリートの色を決める時も、職人さんと雑談をする。私が思い描く〝赤みがかったグレー〟を伝えるのに、まずファッションの話や小説の話、心理学や江戸工芸まで、たくさん話をして私を理解してもらうんです。こちらも雑談の中で相手との共通言語を見つけ出す。〝この人には食べ物の例えが伝わりやすいな〟って。そこで初めて色の話に入ります」
今どきのプレゼンテーションは3DやVRが主流だし、工藤さんだって本当は絵も巧いし映像もお手のもの。なのに言葉を使うのはなぜなのか。
「自分ではコントロールできない部分を残したいのかな。CGや写真で伝えると、日本の職人さんは腕がいいからその通りに仕上げてくれる。でもそれは私が考えたものの再現でしかないんです。反対に、言葉という曖昧な手段で伝えることで、相手が違うイメージを汲み取って、何倍も面白いものを作り出してくれるかもしれない。その偶然にも期待してるんです」
完成し世に送り出した作品が、誰かによって新たな解釈をされるのもまた楽し。
「設計を手がけたレストランが、いつの間にか〝エドワード・ホッパーの絵みたい〟とSNSで話題になっていたんです。作り手にその意図はまったく無かったのだけど、なんだかうれしい。これもまた、私たちには予想も制御もできなかった展開。だから建築は面白いんですよね」
🗣️
工藤桃子
東京都生まれ、スイス育ち。多摩美術大学環境デザイン学科卒業。松田平田設計勤務後、工学院大学大学院藤森研究室修士課程修了。2016年MOMOKO KUDO ARCHITECTS(現MMA Inc.)設立。