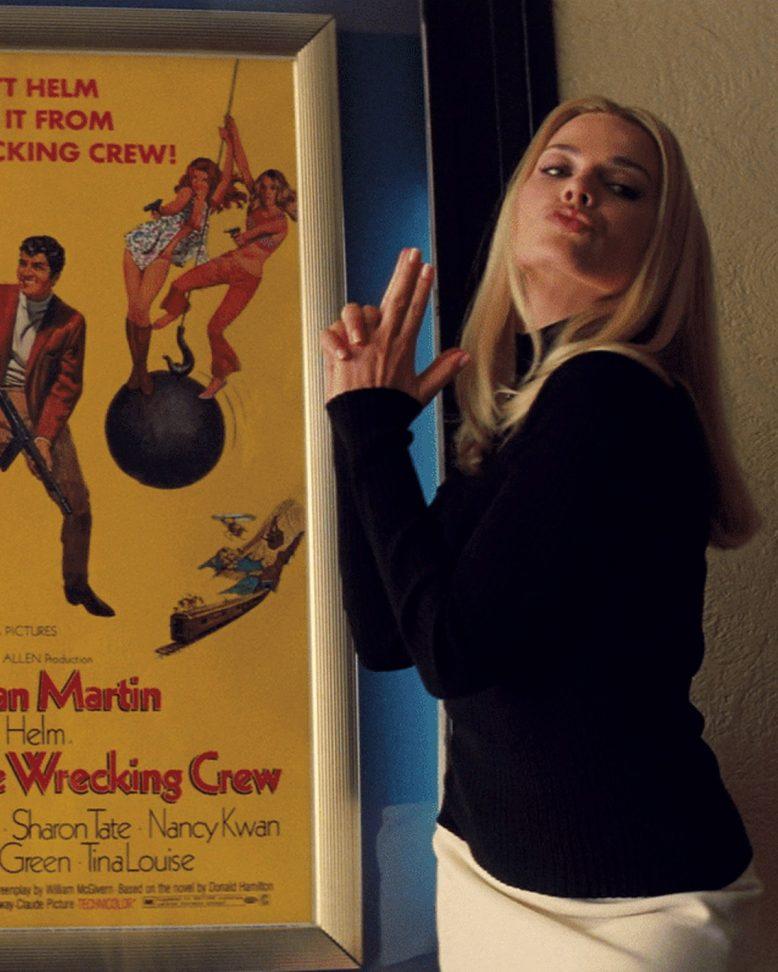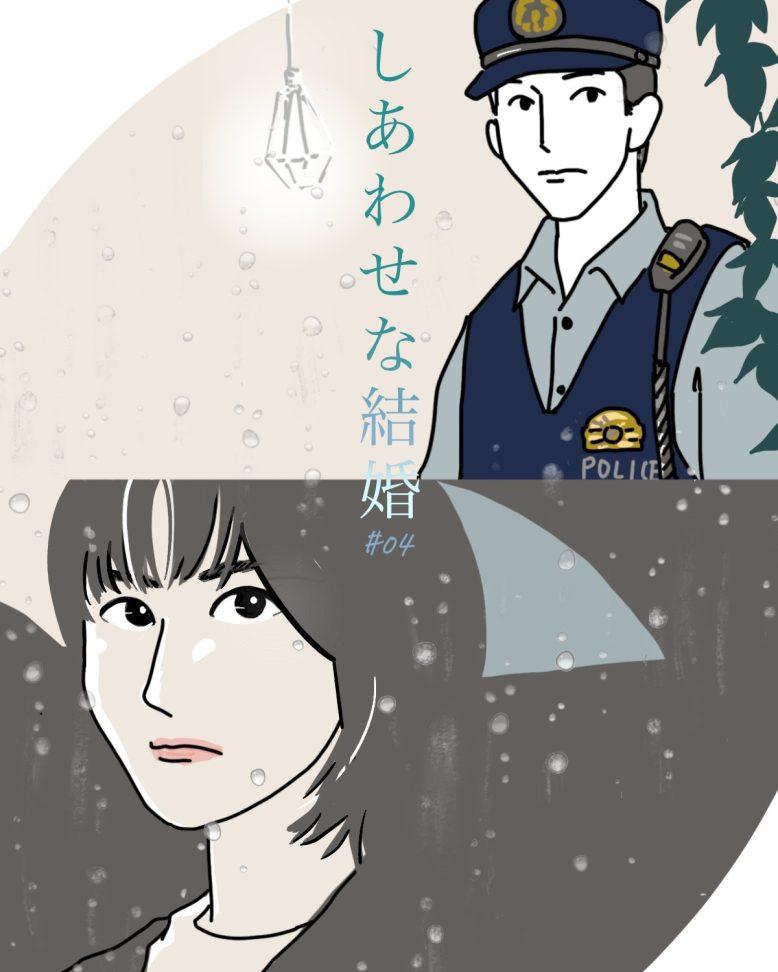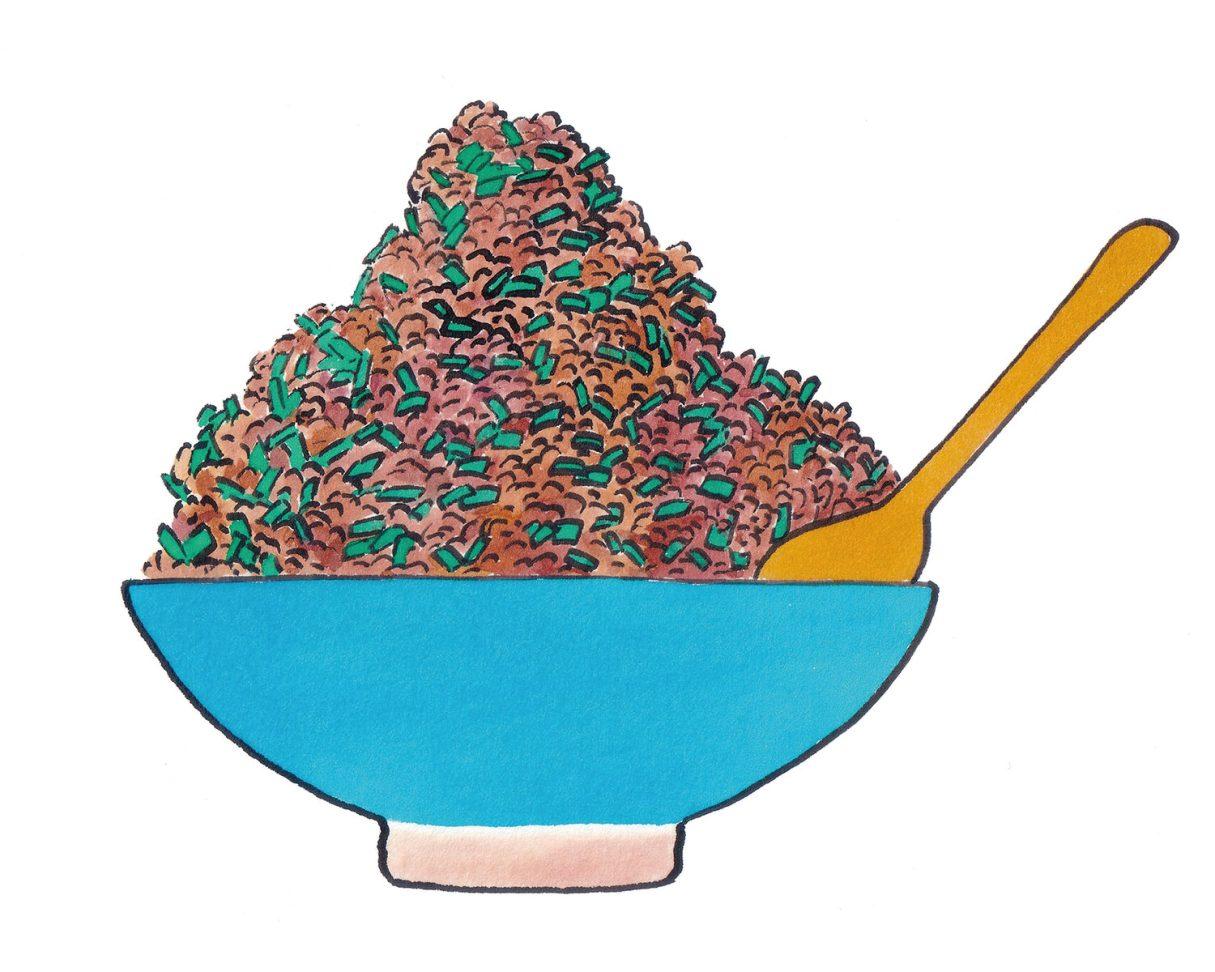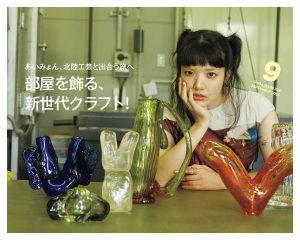主観と客観のあいだにある目線──それが映画に感じられたなら、作り手を信頼できるように思うのだが、クレール・ドゥニはその筆頭だ。グレタ・ガーウィグ、バリー・ジェンキンスをはじめ後続世代も敬愛してやまない、今世紀の重要作家の一人といえる。5月31日、1999年公開の監督作『美しき仕事』の4Kレストア版が公開を迎えた。幼少期を過ごしたフランスの植民地、ジブチでの記憶。敬愛するハーマン・メルヴィルの小説。90年代当時のアフリカの実情。すべてが混じり合い成立した幻の名作の知られざる背景について、みっちりと濃密に語ってくれた。
フランスの映画作家、クレール・ドゥニにインタビュー
名作『美しき仕事』をかたちづくる「私の記憶」について

──『白鯨』で知られるアメリカの作家ハーマン・メルヴィルの遺作小説『ビリー・バッド』。本作を原案として1999年に発表されたのが、映画『美しき仕事』(99)です。ドゥニ監督は以前、メルヴィルの小説に「ノスタルジー」や「何かを失ったという感覚」を見出し、共鳴すると話していました。
……それよりどうしても気になるのですが、(取材場所であるレストランのテーブル上に飾られた植物を指して)この鉢植え、面白いですね。料理に使うハーブを数種類植えて、デコレーションにしているのね。ガーデニングの参考にしたいので、写真を撮っておきましょう。
──(言動の自由さに少し虚をつかれ)……!! 話を戻しますが、今もメルヴィルは監督にとって特別な存在ですか?
もちろんです。でも私だけじゃなく、きっと誰にとっても特別な作家ですよね。『美しき仕事』を軸に話すなら、この物語はメルヴィルから始まったわけではありません。そもそもはテレビ局アルテで映画部門を立ち上げたプロデューサーのピエール・シュヴァリエから、“外国人であること”をテーマに映画を撮らないかと誘われたんです。
私は7歳の頃、父の仕事の都合で、ジブチ共和国の首都ジブチに住んでいました(*監督の父は当時、植民地の行政官だった)。そこでは劇中で描いたように、フランス外人部隊の兵士たちが肉体訓練をおこなっていました(*外人部隊は当時、北アフリカの植民地支配・権益維持をおもな任務としていた)。戦時中ではなかったにせよ、とにかく暑くて乾いた、非常に過酷な環境でした。
子ども心に、なぜフランス軍なのに「外人部隊」と呼ばれているのかがわからなくて。そんな私に父は、ナポレオンの時代にフランス軍が足りず、外国人の傭兵を雇ったのが始まりだと説明してくれました。異国から来た男たち、犯罪歴のある男たち、名前を変えて違う人生を歩みたい男たちのために創設された部隊なのだと。そういった記憶から、ピエールに「外人部隊についての映画を撮りたい」と伝えました。
──外人部隊を撮ることが出発点だったんですね?
ええ。加えてジブチにも思いを馳せていました。とても小さな砂漠の国で、非常に若くて活動が活発な火山があります。常に地殻変動が起きていて、アイスランドに少し似ているかもしれません。国土のほとんどが砂漠で、中には塩や硫黄に覆われた砂漠もあります。草木は生えておらず、農業もおこなわれていません。ラクダを連れたキャラバンや、家畜のヤギがいるだけです。村もありません。お店が立ち並んでいるのは海の近くだけ。この土地は、古くはシルクロードの時代から、エジプトからアフリカに入ったキャラバンがスパイスや香料を探しに、海を越えてアラビアへ渡るための通り道でした。
それから、メルヴィルの『ビリー・バッド』を思い出しました。というのも、この小説に出てくる船乗りたちは、外人部隊がジブチで共同生活していたのと同じように、船という小さなテリトリーで暮らしているから。ある日、イギリス海軍の軍艦に、容姿も人柄も優れたビリー・バッドが強制徴募されます。船長は即座にビリーを気に入り、船乗りたちを取り仕切る先任衛兵長は嫉妬します。そういった物語の骨子を映画に取り入れました。
あと『ビリー・バッド』の冒頭には、メルヴィルの思い出が書かれていて。彼自身が船乗りだった頃、ある暑い7月の真昼にイギリスのリバプールで見た、首に華やかな色の絹スカーフを巻いた黒人の水兵が、取り巻きの仲間たちとはしゃいでいる様子が忘れられない、というふうに綴っているんです。だから劇中にも夜明けごろ、一晩中飲み明かした水兵たちが、赤いスカーフを首に巻いた黒人の仲間を担いでいるシークェンスを入れました。
──以前のインタビューで、「男性を描くのが好き。それは支配したいのではなく、観察したいから」と話していました。この映画でも外人部隊の面々への、ジャッジメントのない、観察する視線を感じますが、なぜそれができたのでしょう?
この映画の前に、私はマルセイユで『ネネットとボニ』(96)という作品を撮影していました。フランス国内における外人部隊の拠点で、海沿いに軍人のための大きな病院があります。
夜間の撮影が終わるのは早朝の5時か6時でしたが、ホテルの隣にある小さなカフェがまだ開いていて、寝る前のコーヒーを飲みに通っていました。そのカフェにはいつも軍病院から2、3人、入院中の兵士が来ていて。怪我を負っていたのか、それともマラリアの治療中だったのか。片足を切断したポーランド人の兵士に会ったこともあります。自然に会話を交わすようになり、私は彼らの悲しみやノスタルジー、メランコリーに気づきました。外人部隊を懐かしみ、北アフリカに戻りたがると同時に、病気や負傷のためにもう戻れないのではないかと恐れていたんです。
外人部隊には厳密なルールがあります。まず基本的に最低5年の任期を過ごさなければならない。そのまま5年経てば、フランス国籍の取得を申請できます(*現在は3年)。15年以上勤務して初めて、軍人年金の受給資格を得られます。(年齢制限があるため、)若くしてフランスのパスポートを得られるし、望むならフランス風の名前を名乗れるし、毎月少しずつお金ももらえるし、難なく市民生活を送ることもできる。私は外人部隊を恐ろしいと思っていましたが、でもそうではなく、実際の彼らは悲しげでした。それで自然と、優しく愛情深いまなざしを向けるようになったんだと思います。
──外人部隊役の俳優たちの姿を捉える上で、長年組んできた撮影監督のアニエス・ゴダールさんとはどんなことを大事にしましたか?
当時はちょうどデジタルカメラが主流になってきた頃。アニエスとは最初、予算の関係もあり、デジタルで撮ろうと話していたんです。ただ驚くべきことに、ジブチが暑すぎて機材がダメになってしまった。それでアニエスと再度相談し、フィルムで撮影することになりました。
こだわりとしては、外人部隊が過酷な環境に疲れきったさまを見せるため、人物と景色を同時に映したいと考えていました。それで、被写界深度が深い35ミリフィルムを採用することに。16ミリだと人物と風景のカットを割らなければならないところ、35ミリならワンカットで全体を俯瞰できるからです。本編で人物が映っていないのは、おそらくほんの数カット。それも戦車を捉えるなど、必ず人間の痕跡を残すようにしました。

Photo_Yuka Uesawa Text& Edit_Milli Kawaguchi