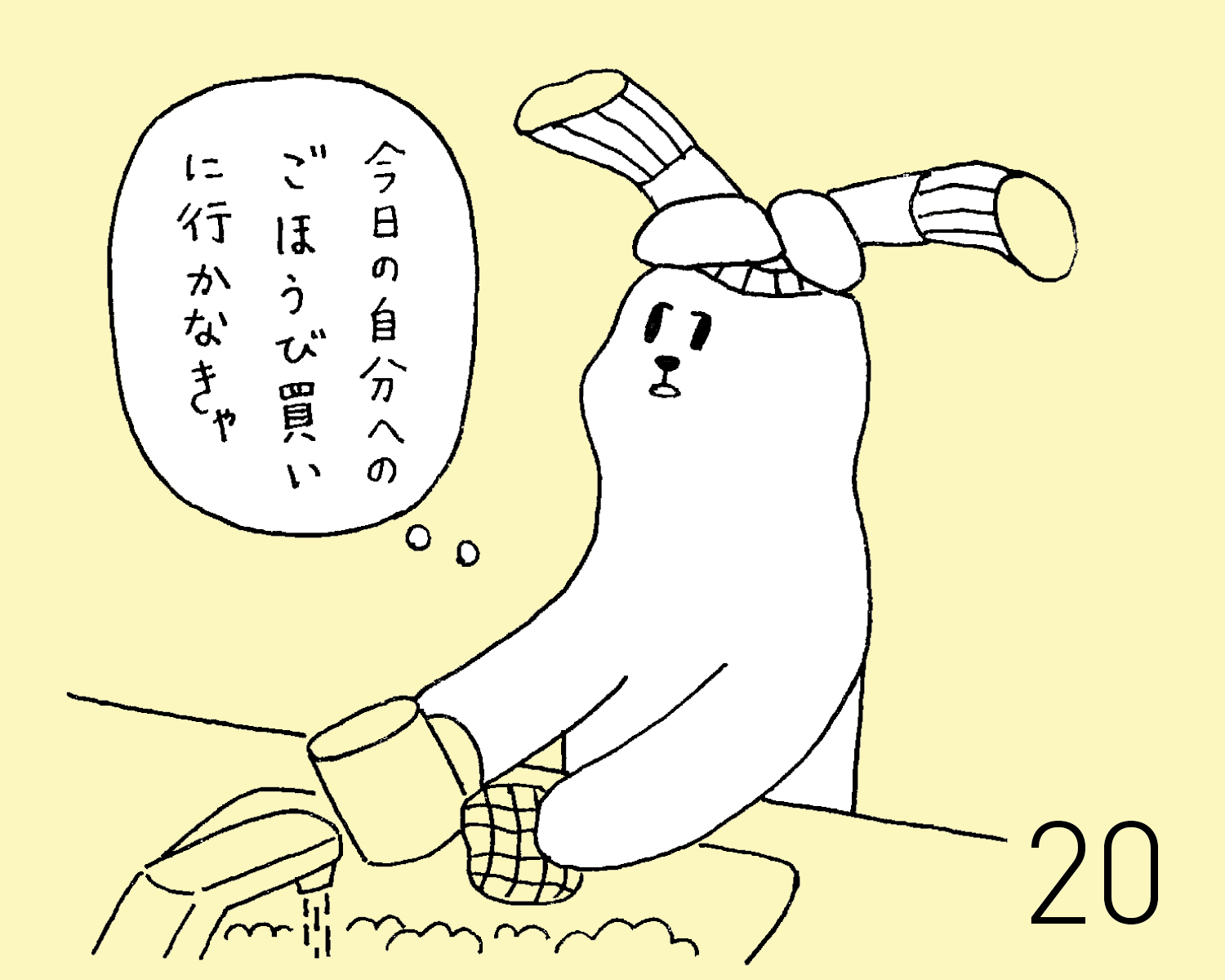最愛の父の誕生日に、病気で療養中の父の元を訪れた7歳の少女が体験する1日をみずみずしく描く『夏の終わりに願うこと』(8月9日公開)。第73回ベルリン国際映画祭でエキュメニカル審査員賞を受賞し、第96回アカデミー賞国際長編映画賞ショートリストに選出された本作を手掛けるのは、メキシコの新鋭として注目を集めるリラ・アビレス。 今年3月には、国際女性デーに合わせ、マテル社が“ロールモデル”として世界で活躍する女性らをモデルにしたオリジナルのバービー人形を贈呈するプログラムの一人に、ヘレン・ミレン、ヴィオラ・デイヴィス、カイリー・ミノーグらと共に選ばれた。アルフォンソ・キュアロンといった監督らも絶賛する、彼女のまなざしと独自性のあるストーリーテリングの秘訣について聞いた。
映画『夏の終わりに願うこと』監督リラ・アビレスにインタビュー
「自分にとって映画は、心臓の鼓動のようなもの」

──7歳の少女ソルが中心になりながら、一つの家族や友人たちが小宇宙のように映し出される本作ですが、脚本はどのように生まれたのですか?
長編一作目『The Chambermaid』(日本未公開/18)を監督した後に、娘のことを考えて、この作品をつくりたいと思っていました。パーティーの日もそうじゃないときも、彼女と一緒に過ごしてきた日々は私にとって旅であり、冒険でもあったんですね。悲しいことに彼女は早くに父親を亡くしているので、彼女の思い出のために何か深くて美しい物語をつくりたいと考えていたんです。芸術のおもしろさは、とてもパーソナルなところから始まったものが、いろいろな場所へと広がっていくところですよね。
──本作は、世界70以上の映画祭で上映され、30以上の賞を受賞されていますしね。原題である「Tótem」は、どんなときに思いついたんですか?
自分が娘を肩車して撮った写真を見たときに、パッと思い浮かびました。ほかに選択肢はありませんでしたし、この言葉から全ての芽が出てきたと言っても過言ではないですね。観ている方に解釈を押し付けたくはないので、それぞれにその意味を想像してもらえたら一番嬉しいですが。
──ソルの心情がすごくリアルに伝わってきて、自分の幼少期の好奇心、そして心細さや不安感といった感情が蘇るようでした。ソルというキャラクターには、ご自身の少女だったときの感覚も入っているのでしょうか?
私自身の要素もかなり強く入っていると思います。私の娘は、7歳当時、そこまでいろんなことを表現するところまで至ってはいなかったので。
Photo_Raita Yabushita Text&Edit_Tomoko Ogawa