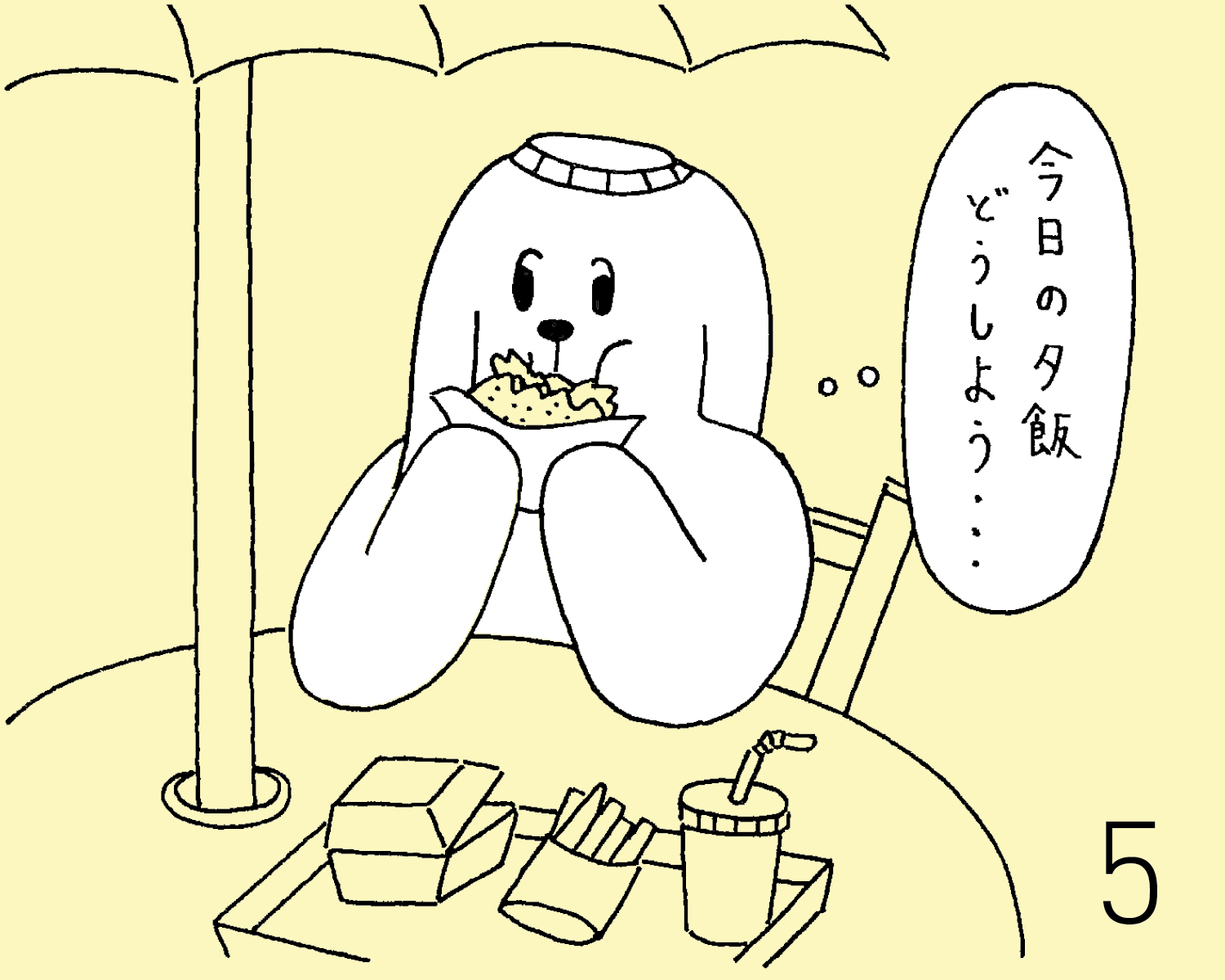初監督作『リヴァイアサン』(04)で圧倒的な映像体験を発明した、ルーシァン・キャステーヌ=テイラーとヴェレナ・パラベル。ハーバード大学感覚人類学研究所の人類学者監督コンビだ。2人のコラボレーションから生まれた4作目は、最も身近ながら、私たちが知らない「人体」のドキュメンタリー、『人体の構造について』(11月22日公開)。パリ北部近郊にある5つの病院のオペ室を舞台に、医師視点のカメラや内視鏡を使い、脳や大腸、眼球、男性器など様々な外科手術の模様を医師の視点から見つめる。知っているはずなのに見たことのない身体をつまびらかにする本作を手がけた監督のひとり、ルーシァン・キャステーヌ=テイラーに話を聞いた。
タブー視される人体を、内側から見つめる
『人体の構造について』人類学者監督ルーシァン・キャステーヌ=テイラーにインタビュー

──今まで観たことのないような映像体験で、とても美しく、ときに恐ろしく、でも感動的でもありました。病院が、映画になるような演劇的であり、ドラマチックな空間であることに気づいた具体的な瞬間はあったのでしょうか?
いい質問ですが、答えられるかはわかりません。私たちは常にアイデアがありますが、最初のアイデアから脚本化された映画をつくることはないからです。私たちは人類学者なので、今回の場合は、本当に待つことが重要でした。6、7年を映画づくりに費やしたので、私たちが目撃したものの中で、最も新しいもの、独創的なもの、興味深いもの、私たちが共有したと思えるものを見つけるために、何が起こるかを待っていたんです。それについての映画をつくるために。ただ、最初の構想は今のものとは少し違いました。解剖学の創始書のひとつに、16世紀半ばにベルギー人の外科医、アンドレアス・ヴェサリウスが書いた『ファブリカ』(De Humani Corporis Fabrica)という本があるんです。映画の原題とも同じタイトルのこの本には、7つの章があり、それぞれが彼の人体解剖学の概念に対応しているんですね。なので、世界の7つの地域、国での7つの異なる手術を撮影し、医療視覚化装置を使用し、人体の内部のみを撮影した7つの章からなる映画を制作しようとしていました。
──病院の手術室は開かずの間のようなイメージが勝手にあるので、なぜそんなところにカメラが入れて、医師たちの等身大の会話がここまで聞けるのかが不思議でなりませんでした。
最初はボストンにいたので、アメリカの病院の医者や患者たちはとても寛大に受け入れてくれましたが、管理部門との許諾交渉が地獄のように大変で。アメリカでは病院が民営化されているので、病院側は何かミスが起きたときの映像が公になり訴訟を起こされることを恐れていて、アクセスするのがとても難しかった。そんなとき、当時パリ北部にある5つの公立病院のディレクターをしていたフランソワ・クレミューと出会い、ラッキーなことに彼がいわゆる「Carte blanche」をくれたんです。無制限にアクセスしていいという素晴らしい機会を。それで、当初の構想はなかったことにし、パリの病院がこの映画の舞台になりました。彼は病院のディレクター、院長でありながらも、映画好きなんです。クリス・マルケル(1921-2012)というフランスの重要な映画作家ともかつて映画でコラボレートしていました。だから、私たちが望むものを何でも撮る自由を与えてくれたのだと思います。
──体内のみを撮影するプランからなぜ変わっていったのでしょう?
最初は医師が使っている画像機器の映像をダウンロードしたり、音を録音したりしていましたが、ちょっと飽きてきて(笑)。だから、自分たちの撮影も始めたんです。スイスのチューリッヒにエンジニアの友人がいて、医療用レンズに非常に近い、自由に動き回れるような超小型の特別なカメラをつくってもらいました。細胞鏡や内視鏡カメラのようなもので、体外で撮影することができる。この映画で使われているほとんどの映像は、本物の医療用カメラで撮影された体内のものから、私たちが特注したカメラで撮影された体外のものにつながるようになっています。
──身体の内側に広がる風景の神秘には驚きました。
内側から見た身体の美しさを追求するのは、とても面白いことだと気づいたんです。もちろん、私たちが見ているものはかなり拡大されていて、現実にはごくごく小さな5ミリ程度のパーツですが、それが、ある意味、宇宙のように感じる。でも、内部と外部の間を行ったり来たりすること自体が全宇宙なのだと思います。しばしば肉体に外にカメラが出ることが面白い緊張感をもたらすのは、突然、扱われているのは本物の人間であることにハッとさせられるからですよね。どういうわけか、私たちは彼らの内側にあるこの世界を覗いているけれど、彼らもまた、病気になるかもしれない、死を免れない人間であり、私たちみんなと同じように、あらゆることに怯えているのだと気づかされる。

Text&Edit_Tomoko Ogawa