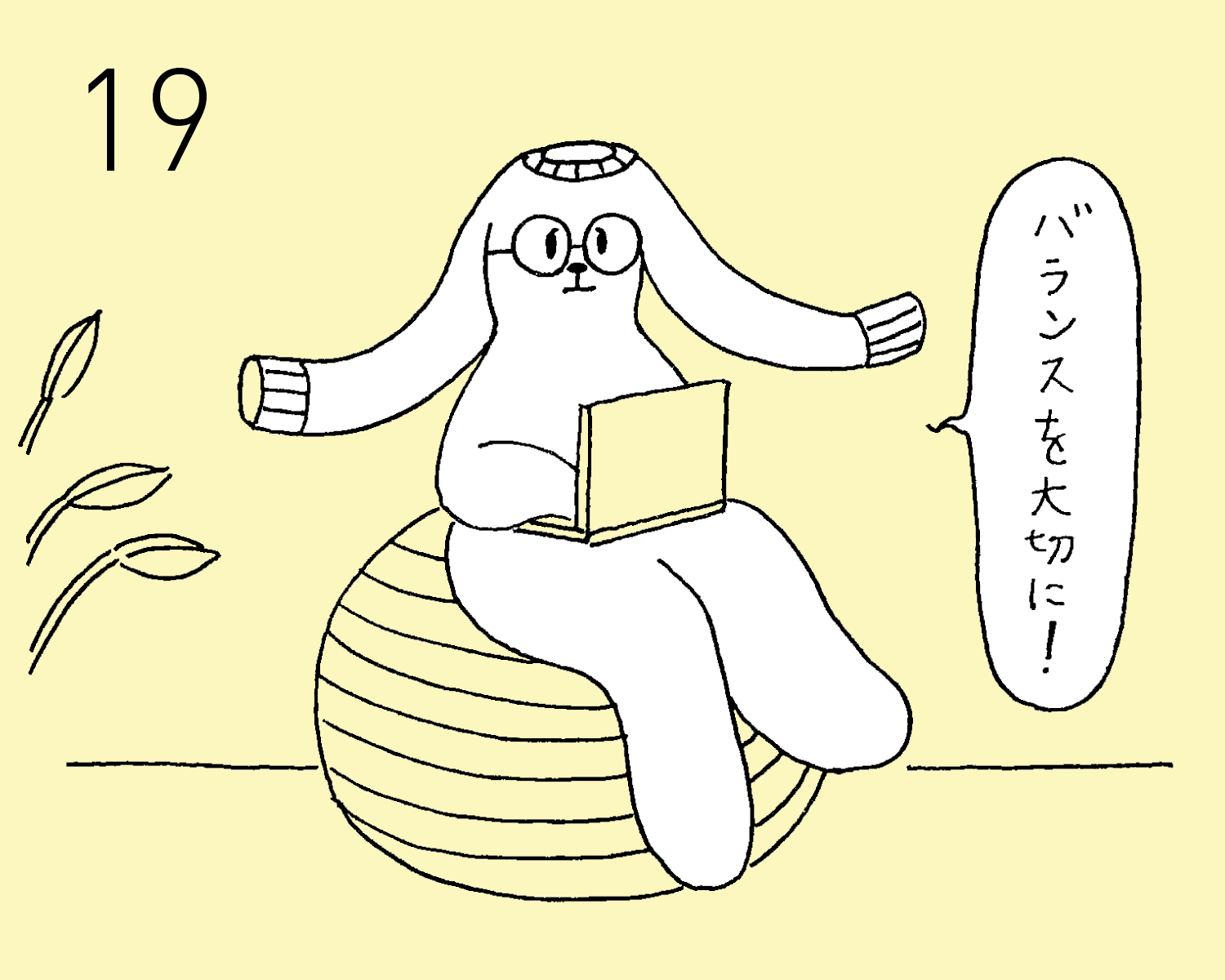国内外のアーティストへの取材を通じて世界を見つめてきた林央子さん。彼らとの親密でプライベートな対話やその作品からの気づきをまとめたこの連載からはきっと自分の中にユニークな感覚を発見できるはず!今回は、ベルリンでの長い滞在生活を経て広島→東京に拠点を移したアーティスト、小金沢健人さんが見た「上海」という街を覆うアートの勢いについて。
林央子の「アーティスト・リーディング」〜小金沢健人が見た上海アートシーン前編

11月の半ば、Facebookを開いてみたら、アーティスト小金沢健人さんの書き込みをみつけた。ながくベルリンに滞在されていて、その土地で家族をつくられて、昨年お子さん2人をつれて帰国。帰国の折には大都市をさけて広島県の尾道に住まわれていたが、最近は東京に移られた。そんなことを耳にしていた小金沢さんは2009年から『here and there』にも執筆いただいき、いろいろなプロ ジェクトを御一緒させていただいた関係だ。
独特のユーモア感覚と、「つくる」行為に正面から向き合う姿勢(ときにその結果として迂回する道のりもふくめて)に感動することの多い小金沢さんの、 Facebookでの書き込みは、最近アートフェアに参加するため立ち寄られた上海で目にしたものの印象をビビットに伝えられていて、とても印象に残った。普段はSNS上では寡黙な印象の小金沢さんであるからこそ。
その小金沢さんが立ち寄られた11月の上海は、大きな会場でのアートフェアが2つ同時開催されて、オープニングに内外のコレクターが集まってきており、また非常に広大なスペースを占める、新興の美術館やギャラリーが急増しているなかで、たくさんの現代アートを一度に目にすることができる場だったそうだ。雑誌『BT』の10月号も、上海の現代美術の活況を特集しており、Facebook にはその時期上海に行かれた美術関係者の相次ぐポストを覗くことができた。 その時期、その街にいた人に伝染しているなにかの空気が、あきらかにあるようだった。私はその場にいなかったけれど、小金沢さんが感じた熱気を、覗いてみたい。そう思ってアポイントをとり、話を聞きに行ってきた。

「魔都」とは上海の別名

どこもかしこもキラキラ
スマホで撮った写真を見せてくれながら小金沢さんが話してくれたことは、いまの上海の街の風景の断片的な印象で、老若男女みんな手にはスマホ、足には真新しい(日本ならある特定の年代の層しかはかないような?)ブランドもののスニーカーで全員がいる、という様子やら、地下鉄に人がものすごい混雑している様子やらで、それをきくだけで変化に前のめりな街の人々のイメージが具体的になるなぁ。というエピソードばかり。とくに、「日本はソバで、上海はウドン」という比喩が面白かった。日本は素材の比率や食べ方にやかましくいろいろ言うソバみたいだけど、上海はふっといウドンがそこにある、というイメージ(注:現地の食べ物がウドンのようなものだ、ということではありません)。

上海の街並み
東京をはなれてベルリンに長く住んでいた小金沢さんが、尾道経由でまた東京にかえり、そして上海へ。こうした経験からくる複眼的な視点をもっとつっこんで聞いてみたいと思って、メールのやりとりがはじまった。
小金沢さんとの対話を、「上海街歩き編」と「上海アート編」の2回にわけて、小金沢さん撮影の写真とともにお伝えしたい。
上海街歩き編
林 小金沢さんのお話をきいて考えたことがあります。私はこの秋、エレン・フライスの「Disappering」という展覧会に携わったのですが、パリを離れて南西仏の村に住んでいるフランス人の彼女は「消えていくものに美しさを感じる」といい、COSMIC WONDERの前田征紀さんとコラボレーションをして、古着の服を墨で染めて作品としました。一方でこの秋、小金沢さんは上海のアートシーンで突然その場にあらわれつつある何かの熱気にふれて、それを好意的にうけとめられたんだと思います。DisapperingもEmergingもこの世界には両方あるものですね。
小金沢 そうですね、dissapearing/emerging というのは面白い対立項だと思います。消えつつあるものに”だからこそ美しい”、というのは老いてゆくものの感覚で、消えつつある”けど面白い”というのは若者が古着とか古民家とかに感じる感覚ですね。前者は保存へ、後者は容赦ない改造へ傾きがちですが、そこで古着を染めるという道をとったエレンは面白いなと思います。
平田オリザの『下り坂をそろそろと下る』という新書を以前読んだのですが、なるほどもっともだと思う反面、寂しさに向き合うとか、成長を諦めるという言葉が頻出して息苦しいというか。こんなこと子供たちに言いたくないなぁという感じ。

新しさと古さが隣接する
欧米の諸都市ではそういったサイクルがもう何周目なのかずっと回っていて、 批判的に歴史を検証してアップデートするやり方は洗練されているがゆえにパワー不足、と思いますが上海や(おそらく)アジアの諸都市はそのサイクルの端緒についたばかりの勢いがあるんだろうと。
今回の上海でのキーワードは「太い」ですね。何がどう太いのか、を考えなければいけないれども、第一印象がそうだし、帰国後に思い出すのもやっぱりその太さです。「大きい」というと空間に拡散してしまうし、「厚い」というほど中味を知らない。
「太さ」は街なかに、大通りに垂れ下がるような、または立ち上がるような形態をしています。どこから始まってどこで終わるのかわからないけれども、巨大なうどんなのか、はんぺんなのか、かまぼこなのか、そういった白くて柔らかくてつるつるしたものが、ぬーっと存在しているのです。その、白いビルみたいな物体の、前にも、後ろにも、中にも大勢の人たちがいて、忙しげに歩いているのですが、そこに灰色の群衆みたいな印象は受けない。むしろ、カラフルな人たちが勝手にそれぞれの生を生きている、という感じがあるのです。

路肩で賭け事に興じる姿もこの街の日常

上海のクラブALL
例えば東京のことを考えてみる。東京の通勤風景と江戸の街のにぎわいを描いた絵では、群衆の与える印象がまるで違いませんか。記録映像を見ると、昭和の頃までは銀座の、新宿の、原宿のにぎわいというものがあったように思います。それがだんだんコミケの、ライブの、イベントごとのにぎわいになっていくように思えます。なんだろう、街でぶらぶらしなくなったのだろうか。

スクーターにはかならずこの布団みたいなのが

こういう店は5元(約80円)くらいから食べられる
林 『甘えの構造』を書いた土居健郎さんに『「いじめ」の構造』という本があって、そこには「ねたみ」が聖書にも登場する、人間にとっての原初的な感情であると語られています。その本は1995年の初版本が2008年に新書で復刊されたものなので、アジアの中で日本は文句なしにNo1であるという視点も垣間見えたりして、今とは違う感覚なのは否めないのですが、そういう感覚のある時代もたしかにあったのでしょう。都市それ自体も、それがもつイメージも、時代 によってどんどん塗り替えられて行く。小金沢さんのような現代アートの作家は過去を振り返りながらもつねに今も射程において世界にふれ、見たり感じたりされるのだろう、と思います。
小金沢 街にアウラという言葉を使ってみれば、それは成長したり死んだり生まれ変わったり日々刻々と形を変えているものだろうと思いますが、上海のそれは格段にデカくて、自信に満ちていて、無表情です。でももし街がなんらかの理由で根こそぎ破壊されたとしたら、それでもロンドンやパリやローマにはそれらしい面影が残るような気がしますが、上海は葦の生い茂る漁村に戻るかもしれない、とは思いました。海側から船に乗ってタワーのあった辺りまで行き、上陸してそこに立ってもかつてのよすがは消えているのではないかと。そしてそれは東京にも言えることかもしれません。(でも京都は、、何か残りそうです)
「上海アート編」に続く(後編公開時にリンク挿入)
※写真は、小金沢健人氏の撮影による。

🗣️
林央子
資生堂で『花椿』の編集に携わったあと、退社してフリーランスに。2002年3月に、個人出版プロジェクト「here and there」をスタート。2011年『拡張するファッション』を上梓。2014年、同名の展覧会が水戸芸術館現代アートセンター「丸亀市猪熊弦一郎 現代美術館」で開催になる。アート欄をGINZAで長く執筆。似顔絵は小林エリカさんによるもの。