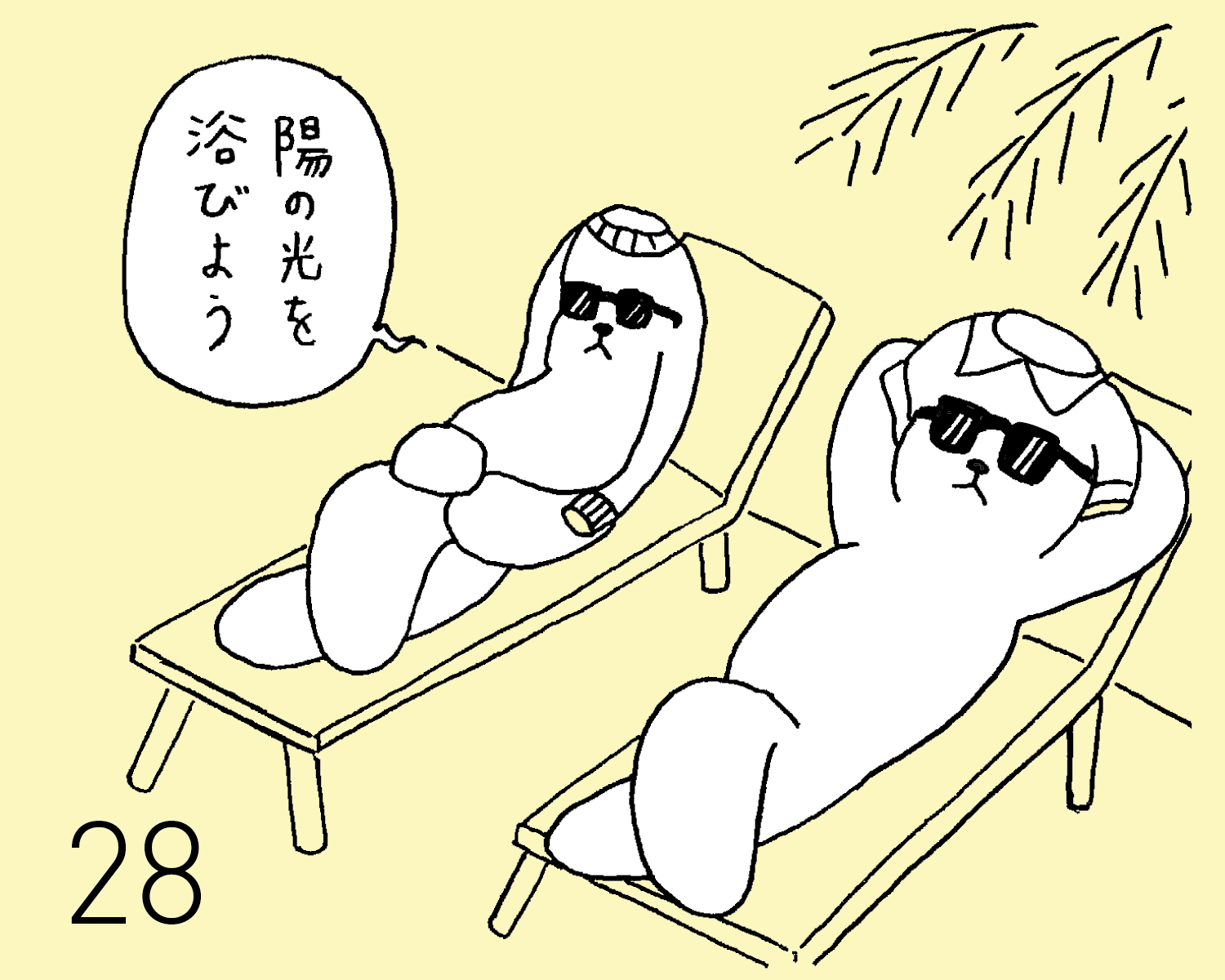今度の週末観たいもの、行きたい場所

●歳時/都内の花火大会
●展覧会/デザインあ展 in TOKYO
●イベント/日本橋周遊クルーズ
●映画/グッバイ・ゴダール!
打ち上げ花火、どこから見るか?
文=柴原聡子
てくてく歩いて見え隠れ。 都会の花火見物のススメ。東京の下町は、花火大会ラッシュ。7月21日に「足立の花火」、その3日後に「葛飾納涼花火大会」、28日には真打「隅田川花火大会」と、乱れ打ちのように続く。
花火大会の元祖は隅田川花火大会である。この名称は1978年からと意外と新しく、以前は1961年まで「両国の川開き」という名で行われていた。その始まりは享保17年(1732年)。江戸が大きな飢餓と疫病に襲われたため、8代将軍吉宗は慰霊と悪病退散のために「水神祭」を行う。この祭にあわせて両国橋周辺の料理屋が花火を上げたのが由来とされる。江戸で人気に火がついた花火大会は、灯篭流しのように火を使うお盆の風習も相まって全国に広まり、夏の風物詩となった。
日本最古の花火大会ならば、ますます見たい。ただ、都心の花火大会をちゃんと見るには、ぎゅうぎゅうの人混みに耐えながら、待ち並ぶ気合と体力が必要。想像してやや怯む。
開き直って、立ち止まらないという選択はどうだろう。歩きながら花火を見るのだ。
だったら深川の馬肉料理「みの家」から始めよう。創業は明治30年。築60年を超える和風建物のお座敷で、まだ明るいうちから馬刺と甘辛い桜なべをつつく。奥には小さな箱庭があって下町風情もたっぷり。ここらはかつて隅田川から木を運んだ木場だった。馬肉はそこで働く屈強な男たちのスタミナ食。これから歩く体力もばっちりだ。
店を出たらほんのり暮れていた。穴場スポットと言われる浜町公園を目指す。ここから両国橋までの遊歩道は花火が楽しめる上、隅田川に浮かぶ屋形船も風流だという。缶ビールを買って、いざ散歩しながら花火を堪能する。猛烈な音のあられにまみれて、街路樹の合間から、ビルとビルの谷間に、首都高の向こうに、花火を見つける。「あ、見えた!」
これこそ、都会の花火の醍醐味。
東京の一番乗り「足立の花火」は7月21日(土)、「葛飾納涼花火大会」は7月24日(火)に開催。どちらも打上数は約1・3万発。約2万発が上がる「隅田川花火大会」は、墨田区・台東区の河川敷で7月28日(土)開催。例年約90万人の観客で賑わう。
さぁ夏休み。 オトナも自由研究しなきゃ。
文=柴原聡子
子どもの頃、自由研究のネタ探しに出かけた思い出がある人も多いのでは?企画展『デザインあ展 in TOKYO』は、第一線のクリエイターによる、”オトナの自由研究”的展覧会。
これは、NHK Eテレの人気番組『デザインあ』が元となっている。身近なモノをデザインの視点から徹底的に見つめ直し、斬新な映像手法と音楽で表現するこの番組は、スタイリッシュなのにユーモアあふれる絵作りや、そうきたか!と唸るアプローチから、大人のファンも多い。
そこから生まれたこの展覧会にも、目からウロコな驚きを「体感」できるしかけがいっぱいだ。まず「観察のへや」で、身の回りのモノ・コトから、「みる」「考える」「つくる」ステップを知る。そのひとつ「つめられたもの」はお弁当とその食材のつめられ方を観察する、真剣さが可笑しい作品。続く「体感のへや」は、音楽とぴったりシンクロした映像が四方の壁いっぱいに映し出されるダイナミックなインスタレーション。最後の「概念のへや」には、座ったときの人とのちょうどいい距離を探るなんていう面白そうな作品も。他にも、「はやい『あ』」と「おそい『あ』」、「しくみ寿司」など、気になるものがたくさん。
デザイナーといえば、何もないところにシャッと線を引いて魅力的なかたちを生む人と想像する人もいるだろう。けれど、駅のサインとかコンビニ袋みたいな些細なものから、政治や社会といった目に見えない仕組みまで、あらゆるところにデザインはある。デザインとは物事をじーっと観察して本質を見出し、工夫を加えてより良くするわりと地味な行為なのだ。それには、子どものような、「なぜ?なに?」が大切。忙しい日々に追われて、「そもそも」考えることを休んじゃっている大人たちにこそこの展覧会は必要なのかもしれない。
NHK Eテレの人気番組『デザインあ』の世界を、デザイナーの佐藤卓、映像ディレクターの中村勇吾、小山田圭吾といった豪華顔ぶれによる約40作品で体感できる。 ≫ 7月19日(木)〜10月18日(木)/日本科学未来館
日本橋から舟に乗って お江戸気分の夕涼み。
文=柴原聡子
暑い夏の日は、水の傍に行くに限る。その入口が、東京のおへそのような日本橋にある。たもとの階段を降りると、そこには小さな船着き場。2011年に作られたこの場所からは何種類ものクルーズが出ていて、お気軽な水辺散歩が楽しめる。
出発地を流れる川はその名も日本橋川。耳慣れないかもしれないが、ここは徳川家康の江戸入り直後に掘られら運河で、江戸初期から舟運の中心となった重要な水路だ。両岸には河岸(かわぎしに立つ市場)が並び)、日本橋のたもと近くには大きな魚河岸、京橋には通称・大根河岸と呼ばれる青物市場、その隣には竹問屋が並ぶ竹河岸があったという。ここから荷揚げされた食料や生活用品が、江戸中に運ばれていったのだ。人とモノが行き交う江戸随一の繁華街、日本橋と京橋は、まさに水の都だった。
江戸っ子気質のガイドさんの話を聞きつつ、舟はゆっくりと進む。真上は高速道路。東京の川の上をなぞる首都高が建設された話はよく知られる。巨大な天井がなくなり隅田川に合流すると、海がぐっと近づき、波を受けて舟がたゆたう。水辺に生える葦がそよそよと風になびき、川岸には夏の花ノウゼンカズラが見える。目の前を真っ白いシラサギが通り過ぎる。この解放感といったら!
クルーズは45分程度の短いコースから、月島や豊洲の方まで回るもの、神田川を進む90分くらいのコースまで行き方も時間もさまざま。夏限定のサンセットクルーズも。友達を誘って舟ごと貸切るのもおすすめだ。フードやドリンクも持ち込み可で、水辺のピクニックが楽しめる。かつて優雅な遊びといえば舟遊びだった。舟に揺られて、移り変わる風景をつまみに酒と会話に興じる。現代の江戸東京で楽しむ、納涼遊び。これもまたなかなか風流じゃない?
【日本橋周遊クルーズ】
日本橋のたもとにある「日本橋船着場」から発着するクルーズは「東京水辺ライン」「東京湾クルージング」「舟遊び みづは」の3種類。それぞれ趣向を凝らしたコースが用意されている。連日運航。コース詳細やスケジュールは各社HPにて確認を。
天才との結婚は 散々?
文=小野寺 系
伝説的映画監督、ジャン=リュック・ゴダール。フランスの革命的な映画運動「ヌーヴェルヴァーグ」の申し子であり、いまも世界でもっとも崇められているアーティストのひとりである。
1967年、20歳を迎えようとしていたアンヌ・ヴィアゼムスキーは、30代で天才監督の名をほしいままにしていたゴダールの新しい恋人として、彼の新作『中国女』の主演を務めるなど、刺激的な毎日を送っていた。だがプロポーズを受け結婚生活が始まると、予想もしていなかった事態が次々に起きることになる。本作『グッバイ・ゴダール!』は、アンヌ自身による自伝的な著書によって明かされた、ゴダールとの結婚生活の内情を、フランスのミシェル・アザナヴィシウス監督が映画化した作品だ。アカデミー作品賞に輝いた『アーティスト』(11)がアメリカの無声映画を再現していたように、ここではおしゃれなゴダール映画の演出を模倣しているところが楽しい。
アンヌを演じるのは、俳優やファッションモデルとして活躍、ミュウミュウ フレグランスの広告塔にもなったステイシー・マーティン。『中国女』でも登場する人民帽をイメージしたキャスケットや、ボーダーのトップなど、本作ではポップなフレンチファッションを可愛らしく着こなし、街を歩くだけでうきうきとさせてくれる。避暑地カンヌのバカンスで見せるビキニ姿の脚線美や、きれいに整えられていたストレートボブをくしゃくしゃにして、アパルトマンのベランダに佇むアンニュイさも魅力的だ。
時代はベトナム戦争のさなか。ゴダールはその頃、政治的に先鋭化しており、政治テーマを押し出した実験的な『中国女』は、娯楽作を求める観客はもとより、批評家にも不評を買ってしまう。さらには、商業主義に背を向け、いままでの仲間たちと距離をとってまで学生運動に参加するも、学生たちにはブルジョアとなじられ孤立する始末。自身もゴダールの信奉者だという俳優ルイ・ガレルは、そんな散々な目に遭うゴダールをユーモアたっぷりに演じる。
ゴダールとの結婚は、最高級車の助手席に座るかのように、アンヌを幸せへと猛スピードで運んでくれるはずだった。しかしそれだけに、彼の調子が下降すると、アンヌも立ち往生してしまう。次第に険悪になる結婚生活のなかで、ゴダールから「凡庸な女優だ」とののしられようとも、アンヌはひとりの俳優として商業映画の世界に歩み出そうとする。自分が信じてもいない政治メッセージを読み上げる人形のような役から脱皮するために。それは、高級な車から自転車に乗り換えるようなことなのかもしれない。でも自分がハンドルを握れるのだ。『グッバイ・ゴダール!』は、そんな自分らしい生き方を選び取ることを教えてくれる映画だ。
『グッバイ・ゴダール!』(2017)
映画監督ジャン=リュック・ゴダールと、2番目の妻となったアンヌ・ヴィアゼムスキーの結婚生活を描く。ステイシー・マーティンの可愛らしさ、ルイ・ガレルのコミカルな演技が見どころ。7月13日(金)より新宿ピカデリー、シネスイッチ銀座他にて公開。全国順次ロードショー。
■『グッバイ・ゴダール!』に出演しているステイシー・マーティンへの10の質問はこちら
小野寺 系
Kei Onodera
ワールドカップが決勝を迎えるのに、家にTVが無いので観戦することができない、悲しみの映画評論家。
Twitter: @kmovie Web: k-onodera.net