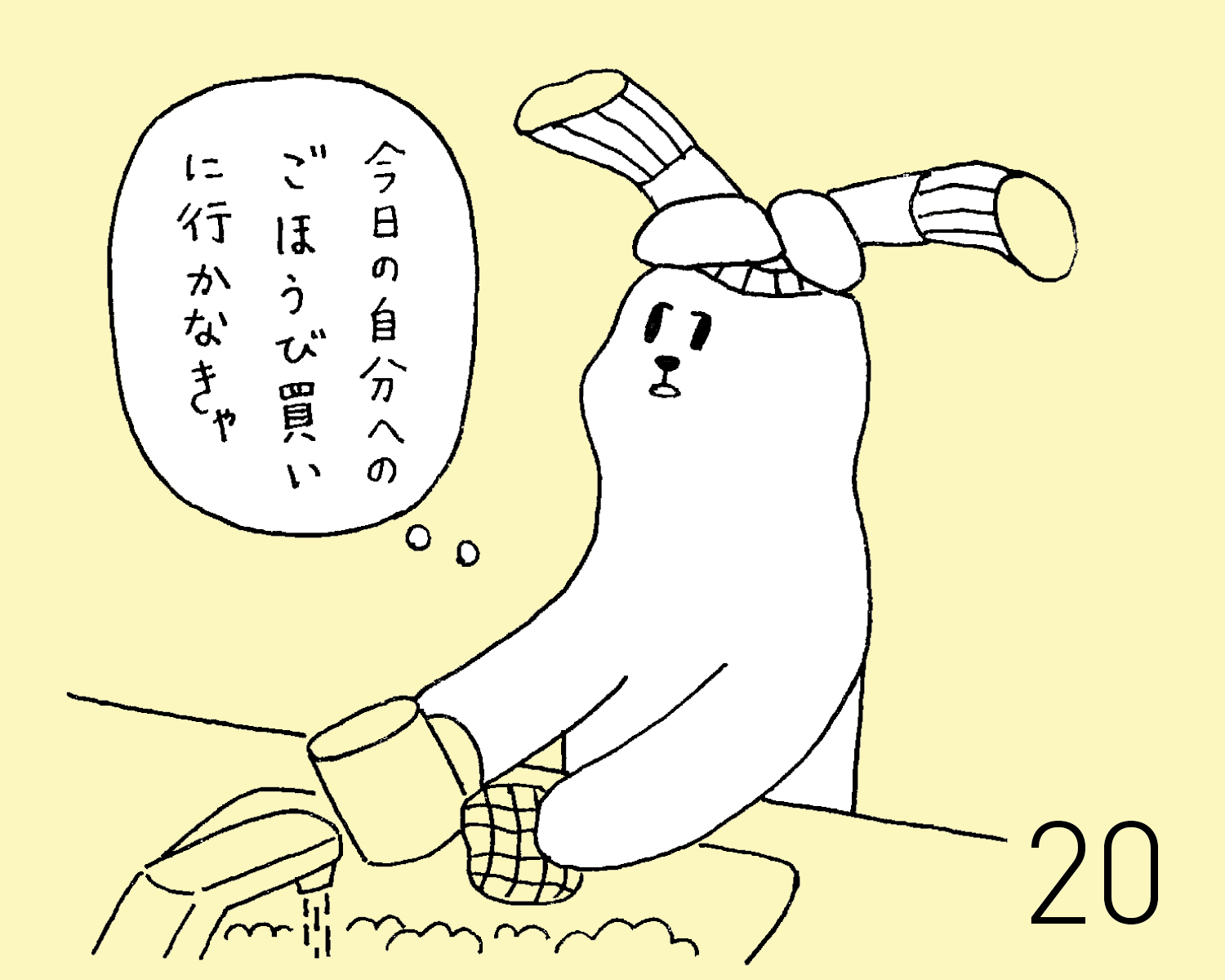そろそろ知っておきたい古典の世界。その嗜み方・楽しみ方のツボはどこにあるの?
はじめまして、ザ・クラシックス〜大相撲編

近年ちょっとしたブームが起こり、良くも悪くも話題になりやすい大相撲(=プロ相撲)。せっかくNHKの中継があり、AbemaTVでも観ることができるわけだし、お茶の間桟敷で観戦するなら「まわし」に注目してみてほしい。
土俵上の力士は規定に従って髷を結い、まわしだけを身につける。皆が同じ格好なので、初心者には「どのお相撲さんも同じに見える」問題が起こりがちだが、まわしの色の違いはわかりやすい。本来「紺、紫色系統」と決められているが、実際にはカラーバリエーション豊富だ。
たとえば横綱・稀勢の里は、まず臙脂(えんじ)色という部屋の慣習があり、10年使用してから横道の茄子紺に変えた。大関に昇進した栃ノ心は銀鼠(ぎんねずみ)色。実は師匠が現役時代に使っていたもの(!)という噂で、褪せた感じがシブい。まわしの色はその力士の象徴にもなるので、強い力士にあやかることも。たとえば昭和の横綱・輪島は金まわしがトレードマークで、縁戚の若手力士・輝や、同じ石川県出身の人気力士・遠藤も同じ色だ。上位陣は落ち着いた色を選ぶ傾向があるように思う。一方、上を目指す段階では、ピンクやオレンジなど派手な色で自己主張する力士も多い。ビッグマウスで期待も大きい阿炎は、四股名に通ずる赤が印象的だ。
負けが込むと別の色に変えたり、出世すると心機一転で新たにしたり、まわしからはその力士の状況もわかる。昨年、大関から陥落して引退の可能性もささやかれた琴奨菊が、それまでと同じ鮮やかな青のまわしを「新調」したのも、相撲ファン的にグッときた。現役を続けるぞという無言の決意が、まわしから読み取れたのだ。
大相撲は階級社会。十両という地位に上がると「関取」という一人前の力士となり、給料が出て付け人がつく。関取は「締込(しめこみ)」と呼ばれる繻子(しゅす)のまわしで自分の色が選べるようになり、前に垂らす「下がり」という紐を同色でそろえる。稽古用の木綿のまわしも、関取は白、その下は黒系と区別される。さらに関取は土俵入りで使う高価で華やかな「化粧まわし」が後援会などから贈られる。まわし自体が地位を表す、文字通りのステータスアイテムなのだ。
まわしのように、大相撲には一見すると競技とは関係ない装飾や不文律が多い。神事・祭礼と結びついた儀式的な意味合いもあるが、近世の勧進相撲に連なる興行の側面、エンタメ性を意識して整えられてきた部分も大きい。そうした成り立ちはともかく、民藝運動の柳宗悦は「相撲の美は工芸美」と言った。四股の踏み方、決まり手の形、呼出の声、行司の言葉使いなど、一切の性質が工芸的だというのだ。
器や布など、手づくりの工芸品にひとつひとつの繊細な違いがあるように、同じ格好で同じ所作を身につけた力士たちにもそれぞれ個性があって、一点物のアート作品でも規格通りの工業製品でもない。伝統や型で縛られた世界のようでいて、実はおおらかなのも相撲の魅力。すっきりしないイメージの人もいるかもしれないけれど、コンプライアンスで固めるのではなく(もう少しちゃんとしてほしいところもありますが……)、いろいろなスタンスの人がいたり、盛り上げるために新しいものを取り入れたりして、長い歴史で少しずつ変わってきたのが大相撲の世界。「品格」の問題だって、明確な定義がないところに観客の入り込む余地があり、アーダコーダと言い合えることが面白いのだと思う。
とはいえ観る側には知識などなくても、相撲はすぐに決着がつくから、その場で贔屓を決められる。まわしの色が好きな方を応援するうちに、あっという間に最後の一番だ。そして、いつかは国技館で、あるいは地方場所で、鍛え上げた身体がぶつかり合う迫力を体感してほしい。