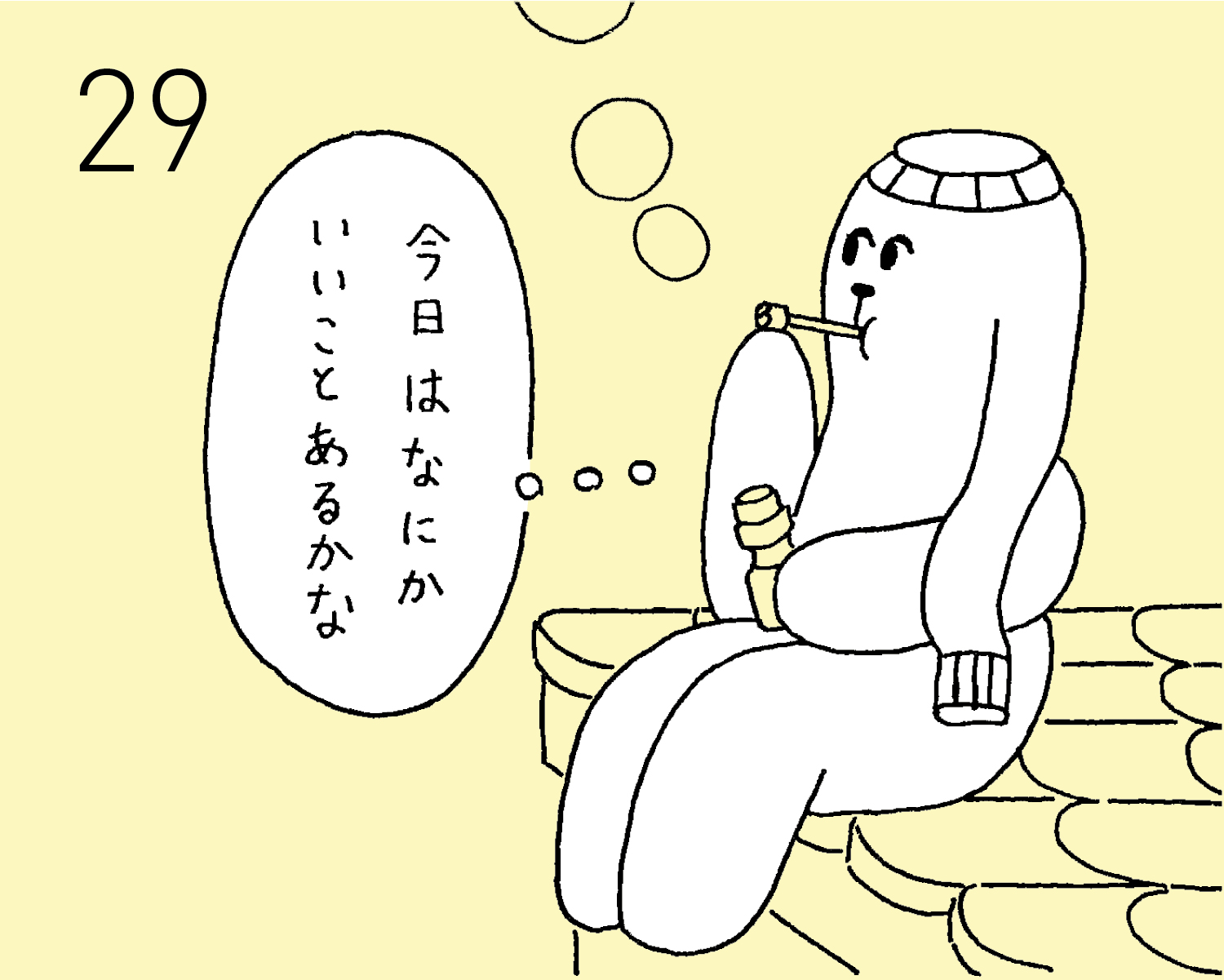知っておきたい日本の言葉、季節のあれこれ。
ギンザ淑女のニッポン歳時記 お正月のしめ飾りや鏡餅に使われるシダの葉をあらわす言葉「裏白・楪」

裏白・楪(うらじろ・ゆずりは)
お正月のしめ飾りや鏡餅に必ず使われるシダの葉。裏側が真っ白なので「うらじろ」と呼ばれます。日本の植物分類上でもウラジロ科ウラジロ属に属します。シダは伐り取った後もなかなかしおれず青々としており、必ず2枚の葉が対になって生えるので、仲のいい夫婦の象徴と見られました。楪もお飾りに使われることがあります。新芽が出ると古い葉が垂れ下がることから、親から子へ座を譲る世代交代を表しているそうです。
今月の神様
天照大神(アマテラスオオカミ)

古今東西の文化において太陽神は崇拝されてきましたが、日本ではアマテラスが太陽を司ります。イザナギ・イザナミの間に生まれたこの女神は、弟スサノオの乱暴に怒り、天岩戸(あめのいわと)に引きこもってしまいます。世の中は真っ暗闇に。アメノウズメが桶を踏み鳴らし、半裸で踊って神々が大騒ぎすると、様子が気になるアマテラスは岩戸を少しだけ開いた。その瞬間外へ引きずり出され、世界は再び明るくなりました。
今月の文様小物
宝尽くし紋(たからづくしもん)のタンブラー

打ち出の小槌(=振れば宝が出る)、丁子(=貴重な薬や香料)、宝巻(=お経の巻物)、天狗の隠れ蓑(=魔物から身を守る)、分銅(=お金をはかる)など、ラッキーチャームがちりばめられた文様。古くから着物や調度品の柄として使われてきました。伝統的な意匠が現代のプロダクトにも生きています。
〈サーモマグ〉とのコラボ商品で、二重構造のステンレスタンブラーの表面に天然漆で絵付け。〈URUSHI MOBILE TUMBLER〉¥6,500(土直漆器)
今月の和菓子
福徳(ふくとく)せんべい
![]()
![]()

金を表す黄色と銀を表す白色の餅種を焼き、色違いを合わせたモナカ。その形は福俵や打ち出の小槌などをかたどっています。中には、金花糖や土人形でできた縁起のいいモチーフが入っています。何が入っているかはモナカを割ってからのお楽しみ。江戸時代にはお城の落成祝い菓子として、明治以降はお正月菓子として親しまれてきた金沢銘菓です。
中の人形はほかに招き猫や大黒天、巾着など。〈福徳せんべい〉1個 ¥270〜*12月〜1月初旬販売(落雁 諸江屋)
Photo: Chihiro Oshima (wagashi), Hiromi Kurokawa (komono) Illustration: Hisae Maeda Text&Edit: Mari Matsubara