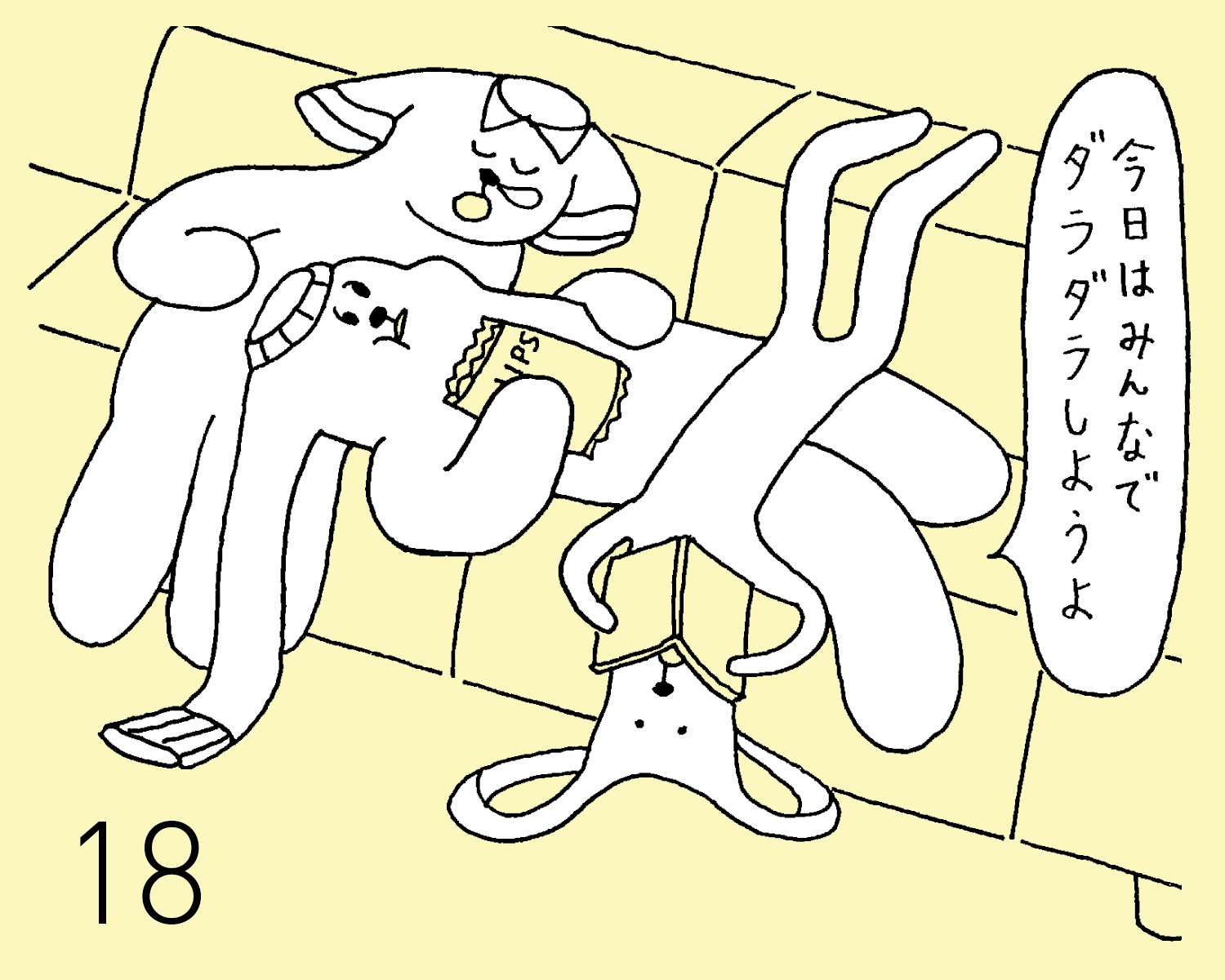映画界の“異端児”とされる俳優シャイア・ラブーフの物語を映画化したのは、ポン・ジュノ監督が「2020年代に注目すべき気鋭監督20人」のひとりとして名前を挙げるイスラエル系アメリカ人監督アルマ・ハレル。シャイアは彼女が手がけたシガー・ロスの楽曲「フョーグル・ピアノ」(12)のミュージック・ビデオに出演しており、前作『ラブ・トゥルー』(16)では、エグゼクティブ・プロデューサーとして参加する仲だ。息子が父からもらった痛みと向き合い、役者ではない現実の人生を歩き出す物語を、繊細且つ力強い映像として作り上げた彼女に話を聞いた。
映画界の“異端児”シャイア・ラブーフの物語を映画化『ハニーボーイ』監督 アルマ・ハレルのインタビュー

今作『ハニーボーイ』は、『トランスフォーマー』シリーズなどで知られるシャイア・ラブーフが、長編映画で初めて脚本を務めた作品。タイトルは、人気子役だった当時のシャイアのニックネームに由来している。
少年オーティス(=シャイアのこと)が、父ジェームズへの誤解やトラウマを乗り越えて成長していくさまを描いた本編では、幼少期を、『ワンダー 君は太陽』(17)、『フォードvsフェラーリ』(19)のノア・ジュプが、10年後の彼を『マンチェスター・バイ・ザ・シー』(16)でアカデミー賞にノミネートされたルーカス・ヘッジズが、そしてシャイア自身は前科者で無職の“ステージパパ“ジェームズを演じ、三世代の勢いのある役者が顔を揃える。
──俳優シャイア・ラブーフは、あなたにとってどんな存在なんでしょうか。
アートにおけるソウルメイトですね。私の作品『Bombay Beach』(11)を観た彼がメールをくれて、実際に会って話したときに、分かり合える部分が多いなと思いました。それ以降一緒に仕事を続けてきて、お互いを高め合ってきた仲ですね。いつも何かやろう!と私に声をかけてきてくれるんです。彼は私が知るなかでも、最も情熱的で心が広い。と同時に、恐らく残りの人生をかけて自身の傷と格闘し続けなくてはいけない人でもあると思います。
──“傷”とは、彼が父親との関係で苦しんだことですか?
それによるPTSD(心的外傷後ストレス障害)だったり、アルコール依存症だったり、精神的なさまざまな問題を抱えていて、毎日葛藤しているので。
──この映画は彼にとってセラピー効果があると最初から考えていたんでしょうか?それとも結果的にそうなったと思いますか?
どんな種類のアートでも、深いところで心に触れたり、変化が生まれたりしますよね。それが希望なんじゃないかと思う。私はセラピストではないし。何かが誰かに与える影響をわかってはいるけれど、誰のことも責められないです。この映画を作ってから2年近く経ちますが、これきっかけで彼が人生で初めて断酒しているとは言えないし、推測したくもない。ただ、彼が今しらふでい続けているという事実が凄いことだと思っています。
──シャイアに若き自身ではなく、父親役を演じさせた理由をお伺いできますか?
この映画の始まりは、彼が乱闘騒ぎを起こして逮捕されてリハビリ施設に入ったときに、PTSDの原因かもしれない子役時代のトラウマについて書いてみるようにセラピストに薦められたこときっかけでした。映画づくりをサポートしてくれたセラピストは、シャイアが父親役を演じることは効果的かもしれないと考えていました。私も彼女の意見に賛成で、暴力によって記憶から消してしまった父親像を芸術的な視点からより理解することで、断酒への道が開けるかもしれないと思ったので。役を演じることで、役と友達になることができるから。
──父親を演じることで、彼が傷つくかれもしれないとは思いましたか?
最も危険なのは、おそらく飲み続けることと、物事を破壊してしまうことだったから。それに、傷つくかもしれないから、と問題から友人であるシャイアを遠ざけるほうが危ないですよね。
──確かにそうですね。多くの男性が、弱さや内情を特に同性に打ち明けられないことも一因かもしれませんが、父と息子の関係は父と娘のそれに比べて、複雑化しやすいものだと思いました。
役割が関係上のバリアになることはありますよね。男性の方が父親との関係に難しさを感じる人が多いのは、特に上の世代は「男らしさ」への期待が強かったから。30代のシャイア、20代のルーカス・ヘッジズ、10代のノア・ジュプという俳優はそれぞれにシンクロしていたけれど、彼らの「男らしさ」への期待度は異なっていたし、父親像が変化したことで男性としての関係性も変わってきたというか。
──若い世代の方が、父親から受ける「男らしさ」のプレッシャーは少なそうですよね。
若い世代のほうが、お互いに果たしているジェンダーの役割やパフォーマンスに対する意識は高いし、それについて深く考えているかもしれませんね。一方、女性は「女らしさ」への期待という大きな重荷を背負って、母親や父親との対話においても一生かけてその問題と対峙してきたから、同じとは言えないかもしれないけれど、少しずつ変化している。
ジェンダーってめちゃくちゃ複雑で、数十年ごとに変動するスペクトラム(分布範囲)のどこかに存在しているものだと思うんです。外見が性別を反映しているときもあれば、そうじゃないときもある。たとえば私は少年についてばかりの映画を撮っているなと自覚してるんですが、私は中身がほぼ少年なのでそうなってしまうんです(笑)。
──確かに、これまでの作品でも少年と父の記憶は通じて描かれていますね。
継続して作品をつくっていると、前の作品が教訓となって気づかぬうちにメタなつながりが生まれたりするのが自分でも面白いんですよね。

──フィクションとドキュメンタリーとの境があまりないような作風ですけれど、つくる上で取り組み方に違いはあるんでしょうか?
私は物事を二項対立的に考えないようにしているので、「これはドキュメンタリーだ!」と言われても、「へー、これが? そう?」という感じ(笑)。取り組み方はどちらも同じだけれど、ドキュメンタリー制作はすごく好きですね。内側にある生活、誰かの想像力、夢や希望、それら全てをドキュメンタリーとして、典型的なものとしてではなく捉えることが好き。多くの人は演技や表現方法に着目しますが、私は映っている本人の行動に興味があって。そのアクティブなものに突き動かされて、人は映画のなかで自分が何者であるかに直面し、それを表現する。だから、ドキュメンタリーもフィクションも対立せずに共存できると思っています。

──イスラエル、テルアビブ出身の移民としてアメリカで映画を撮ることは、あなたにとってどんな価値があると思いますか?
外からの視点を持っているから、内側からは見えていないものが見えることは多いですよね。移住してきて20年以上経つけれど、今も見えなかったものをイスラエルに見ることがある。もし私がイスラエルに帰って映画を作ったら、現地の生活とは全く違うものになるはず。だから、移民はアウトサイダー的な視点を与えてくれると思います。
あとは、移民として生きるって、自分の居場所と自分のために闘わなきゃいけないことが多いから、チャンスを得たら、もう大きく声をあげなきゃいけないんですよね。
──アルマさんは、ジェンダー・バイアスがいまだ残る広告業界で、女性への平等な機会を求める非営利団体 「Free the bid」も立ち上げていらっしゃいます。日本社会で生きる女性にどんな印象がありますか?
実は、今取り組んでいるコマーシャルプロジェクトが、日本の女性についての短編映画なんです。日本社会における女性の居場所や期待、彼女たちの選択について日本人作家と一緒につくっていて、とても面白いプロジェクトになると思うし、今からワクワクしています。来年くらいには動き出せることを願っています。
──最後に、いつも素敵なコーディネートをされているアルマさんですが、好きなスタイルやこだわりはありますか?
あえて言うなら、エクレクティックでボヘミアンですかね。私をある特定の気持ちにさせてくれるものを好んで着ています。たとえば、自分らしいと思わせてくれる着心地がいいもの。ファッションって多くの場合、何が似合うか、何を着るべきかを強制的に、よく言えば親切に売りつけられているようなところがあるけれど、特定の形や色、スタイルを自分で決める必要はないと思うんです。ただ、ちょっとワイルドでよりパーソナルであればいいんじゃないかな。
『ハニーボーイ』

原題: Honey Boy
出演: ノア・ジュプ 、ルーカス・ヘッジズ 、シャイア・ラブーフ、FKAツイッグズ
監督: アルマ・ハレル
脚本: シャイア・ラブーフ
配給: ギャガ 2019 年/アメリカ/95 分/シネスコ/5.1ch デジタル/PG12
2020年8月7日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国公開
🗣️
Alma Har'el
監督・プロデューサー。1976 年イスラエル・テルアビブ生まれ。イスラエル系アメリカ人の映像作家。2011 年に発表したドキュメンタリー作品『Bombay Beach』は第15 回トライベッカ映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞を、2016 年の『ラブ・トゥルー』はカルロヴィ・ヴァリ国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞をそれぞれ受賞。。Filmmaker Magazine 誌は「いま最も革新的で輝いている若手監督」として評し、「映画界のニューフェイス 25 人」にも選出。また、コマーシャルディレクターでもあり、冬季オリンピックのコマーシャル「Love Over Bias」は、2018年全米監督協会賞にノミネートを果たす。本作では、サンダンス映画祭で審査員特別賞を受賞するほか、世界各国の映画祭・賞レースに多数ノミネートをするなど、次世代を担う新しい才能として注目が集まる。