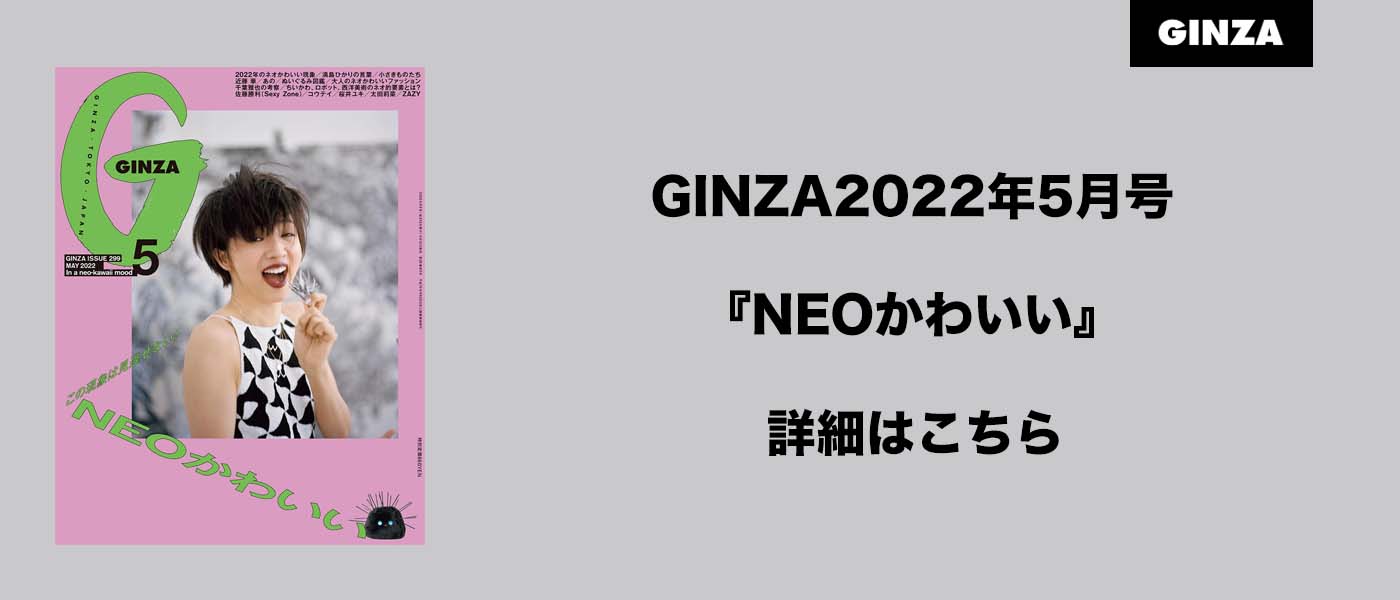サンリオ、キモカワ、ゆるかわ、そして海を越えたkawaiiブームと、いろんな変遷を経た今、私たちの「かわいい」はどこにある?さまざまな分野の識者たちに聞きました。
千葉雅也さんに聞く「かわいい」概念の現在地。【哲学編】

お話を聞いた人
千葉雅也さん(哲学者、作家)
厳しい現実に「かわいい」のインフレで蓋をしてきた日本のこれから
ドゥルーズなどフランス哲学を専門としながら、サブカルチャーにも詳しい千葉雅也さん。若者の文化現象に対する考証が冴え渡る気鋭の哲学者に、日本の「かわいい」はどう映っているのだろう?
「戦後が今も実質上続いている日本の大きな特徴は、軍隊を持たない国であるということです。それがいろんな面に影響を及ぼしているのではないでしょうか。〝戦後日本〟そのものが、かわいい存在なんですよ。
そうした国家のあり方が、若い女性の感覚にも関係しているのは、当然といえば当然です。たとえば、欧米の男性アイドルは力強さや野性味がよしとされる一方、日本ではフェミニンな男の子が〝カッコかわいい〟と受け止められ、評価された時代がずっと続いてきました。
しかし、ここ10年ほどの間に、ある種の保守派の動き、つまり積極的に戦後体制の見直しをしたいというムーブメントが一部に起きています。それに呼応するように、国内でも、男性アイドルに男っぽさの再導入が図られました。肉体派のダンスグループなどが人気を得たのも、その証だと言えるでしょう。
僕自身は、90年代のギャル男に象徴されるような脱力系のカッコよさのほうが好きでした。キメキメじゃない、ちょっとダメなところも含めてゆるい感じを評価するメンタリティは、日本独自の『かわいい』にもつながっていたと思います」
「適度なかわいさ」を持続できるか?
「しかし、地球環境問題への関心の高まりや資本主義への懐疑、ジェンダーや格差の案件など、あらゆる意味でシビアな世の中になってきている今、世界標準では『もうかわいいだけじゃやっていられない』という価値観が強く出てきているように思います。『かわいい』に安住していられないという認識が、少しずつ芽生えてきているのではないか。その一端に、昨今グローバルに発生している強いフェミニズムの訴えもあるのでしょう。
だからといって、世界に追いつけとばかりに『脱かわいい』に向かうというのはちょっと違う、と僕は思っています。他国のシリアスな動向に対して、日本は白けていると言われますよね。ですが、その一歩引いたところで成立していた『かわいい』って、案外大事だったのではないでしょうか。日本が育んだ『かわいい』文化は、アメリカ的な成果主義へのアンチでもあったし、西洋社会のマッチョイズムに疎外感を感じる人たちが、日本のアニメや漫画といったサブカルチャーに共感してきたわけです。日本がグローバルスタンダード一色になってほしくない、というのが僕の気持ちです。
ところが、同時に、公共や行政の領域にまで『かわいい』がはびこる日本の状況は行き過ぎだとも感じています。昔を知る僕の感覚としては、今日の社会は、アニメ的なイメージがあふれすぎていると思います。しかし、大人の真面目な世界は、そういう『かわいさ』とはある程度、一線を引くべきではないでしょうか。
なんでも『かわいい!』の一言で済ませようとする日本は、深刻な事態に蓋をしようとしているかのよう。見たくない現実や不快なものに対し、過剰な『かわいい』でカバーしているのです。世界状況が人々にある種のマッチョさを強いる時代に、日本はかわいさのインフレでなんとかやり過ごし、事の重大さを隠蔽しようとする。そこに欠けているのは『適度なかわいさ』だと思います。現実逃避のための度が過ぎる『かわいさ』ではなく、ほどほどを保持していけるのでしょうか?個人的には、日本独自のかわいい文化をうまく活かしていければと願っていますが、現実はなかなか難しいところに置かれていると思います」

バリアに守られて独自の「かわいい」を形成してきた日本。そのゆるさは案外貴重なものなのかも。
🗣️
千葉雅也
哲学者、作家。1978年生まれ。フランス現代哲学、表象文化論の分野での著作のほか、「マジックミラー」で川端康成文学賞を受賞するなど作家としても活躍中。著書に『現代思想入門』(講談社現代新書)など。