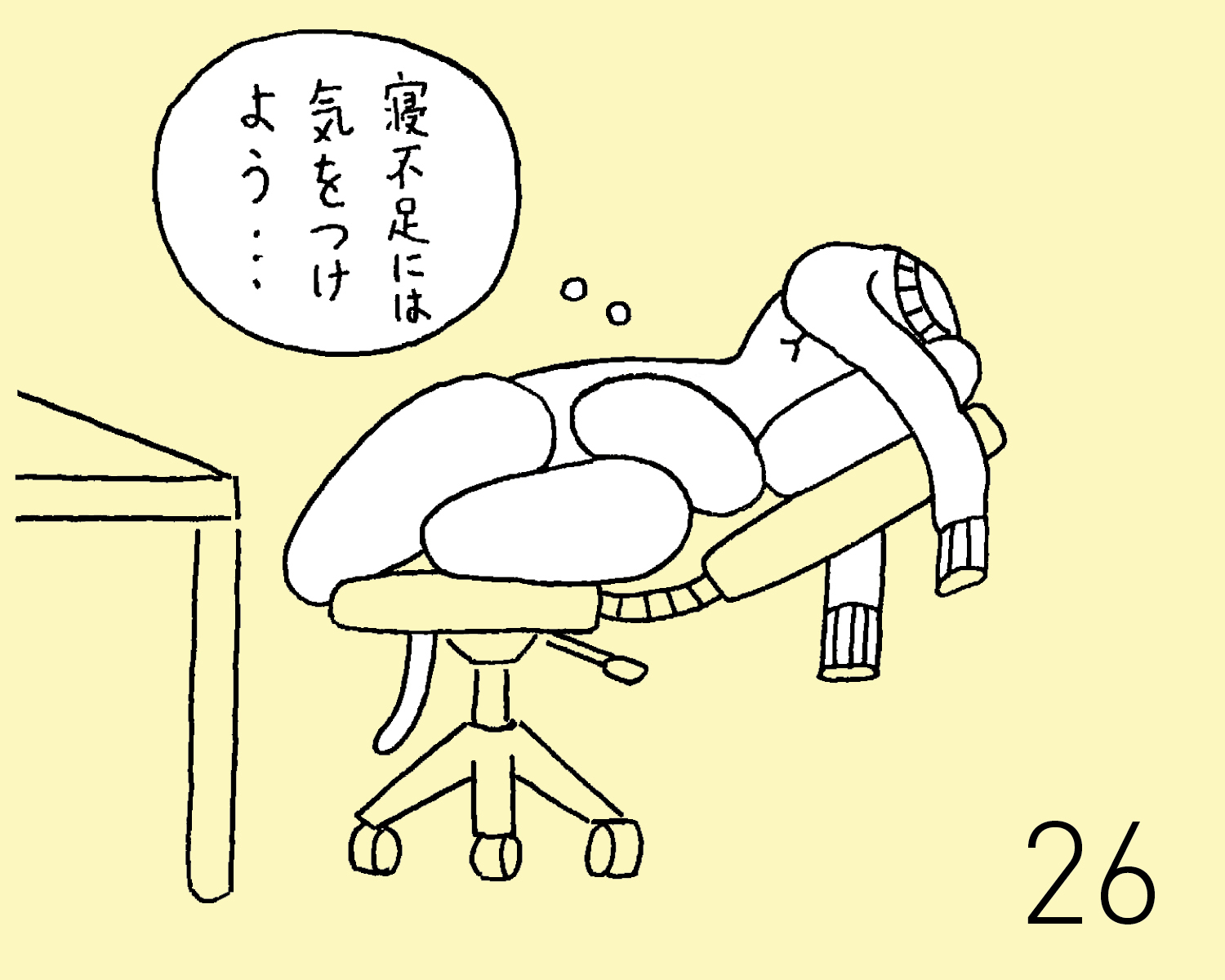興味が赴くまま、クリエイティブな脳内を紹介していく連載企画『Liberty Circus』の第三回目。BiSH解散後「新学期の春を迎えたよう」と話すMISATO ANDO。6月に訪れた『マティス展』(東京都美術館/会期終了)からインスパイアされたこと。そして新しく描いた作品について話を聞きました。
MISATO ANDOのLiberty Circus vol.3
マティス展と私:自分を主題とした作品づくり

マティス展を訪れて
『マティス展』に行き、たくさんの刺激をもらいました。日本では約20年ぶりの大規模な回顧展とのことで、絵画をはじめ、彫刻、ドローイング、版画、切り紙絵などが揃う圧巻の内容。豊かな色彩が優しく調和するアンリ・マティスの作品。私もカラフルな絵を描くのが好きなので、赤の使い方や、複数色あっても“チカチカ”しない色合わせなど、とても勉強になりました。美術館で鑑賞する時は音声ガイドがマスト。ふむふむと思った情報や作家の言葉は巻き戻して何度も聞き、必ずメモをとるようにしています。マティスは女性の肖像画も身体の柔らかい描き方が印象に残ります。緻密なデッサンと比べて、油絵で実践される実験的な構図に驚かされました。
展示のなかでも特にひかれたのは『コリウールのフランス窓(1914年/油彩)』。カラフルな色彩にあふれる作品群の一方、黒を多用しているところに目が吸い込まれました。第一次世界大戦中、まわりの人間が徴兵される中、ひとり自宅に残されたマティスが描いた作品だそう。よく見ると、真っ黒に塗りつぶされた部分をよく見ると、ベランダの手すりのようなモチーフがあるように感じて、真っ暗な世界の先に続く、べつの風景があるのかなと、この絵に対する興味がさらに膨らんだ気がします。
MISATO ANDOが描く“自分”の物語
女性の肖像画と並び、自画像もたくさん描いていたマティス。さまざまなタッチで描かれた自画像にインスパイアされて、私も自分を題材とした作品に挑戦してみよう!とアイデアが湧いてきました。そこで作ったのがこの木版画。

どんなメイク、キャラクターにでもなりきれるように、まずは自分のすっぴんを木版画に! 和紙に刷り、目元には最近ハマっているシルバーアイシャドウ、羽根の頭飾りにターコイズのピアスと大好きなインディアンの要素も入れてみました。和紙のサラサラした質感と、羽根に塗ったパールのきらめきがマッチするという発見もあったり。顔の部分だけを版画として彫り、刷っているため、そこに重ねるメイクや着させる服、描く背景次第で、いろんな自分になれる。そんな自画像をシリーズ化していきたいと考えています。

『まだかね』は“かわいいな”って思う絨毯を描くことからはじまり、レトロな家を描き込んでいくうちに、自然と幼い頃に住んでいた家に近づいていきました。その家には大きな柱がどんと室内にあり、二匹の犬と暮らしていました。両親は共働きだったから、学校から帰ってくると犬と一緒にお留守番。和装店で母が働いていたので、そこで教わったお裁縫をしたり、おもちゃで遊んだり。そうして、真っ赤な車に乗り帰ってくる母を待っていたんです。帰宅予定の時刻を過ぎても現れないと“まだかな”ってそわそわしたり。そんな懐かしい時間を思い出しながら、常に窓から見えていた地元・静岡の富士山の景色と、小さな赤い車も描いてみました。観た人にあたたかい気持ちになってもらえるような、やわらかい色使いを意識しています。

BiSHの解散と共にすべてがリセットされ、今、ひとり新学期の春を迎えたような気持ちでいます。これからアート活動をしていく中で、会ったことがない人たちと “はじめまして”をする毎日。誰かにやさしく拾われたいという気持ちがある半面、自分でひとつひとつしっかり決断していきたいと身が引き締まる気持ちです。そんな私の春の葛藤を描いた作品です。
解散してはじめて手がけた一枚で、初の油絵に挑戦しました。油絵は絵具が乾燥するのに時間がかかるため、これまでなかなか手を出せなかったんです。でもこの作品も結局乾くのを待てず、一気に描き上げました。今抱えている緊張感に通ずる“スリル”と、救世主にさらわれたいような思い、そして自分を取り巻くいろんなもの=いくつもの赤い掏摸の手をかけあわせています。
最後に、『マティス展』の音声ガイドに流れてきた『マティス 画家のノート』から引用された言葉ですごく響いた一節があり、あらためて自分でも本を読んでみました。
「私が夢見るのは心配や気がかりの種のない、均衡と純粋さと静穏の芸術であり、すべての頭脳労働者、たとえば文筆家にとっても、ビジネスマンにとっても、鎮痛剤、精神安定剤、つまり、肉体の疲れをいやすよい肘掛け椅子に匹敵する何かであるような芸術である」
(『マティス 画家のノート』より)
観た人の心にゆとりをもたらしてくれる、そんなマティスの作品。彼のメッセージを胸に、私もアートと向き合っていけたらと思っています。
Art Work&Direction: MISATO ANDO Text&Edit: Sakiko Fukuhara