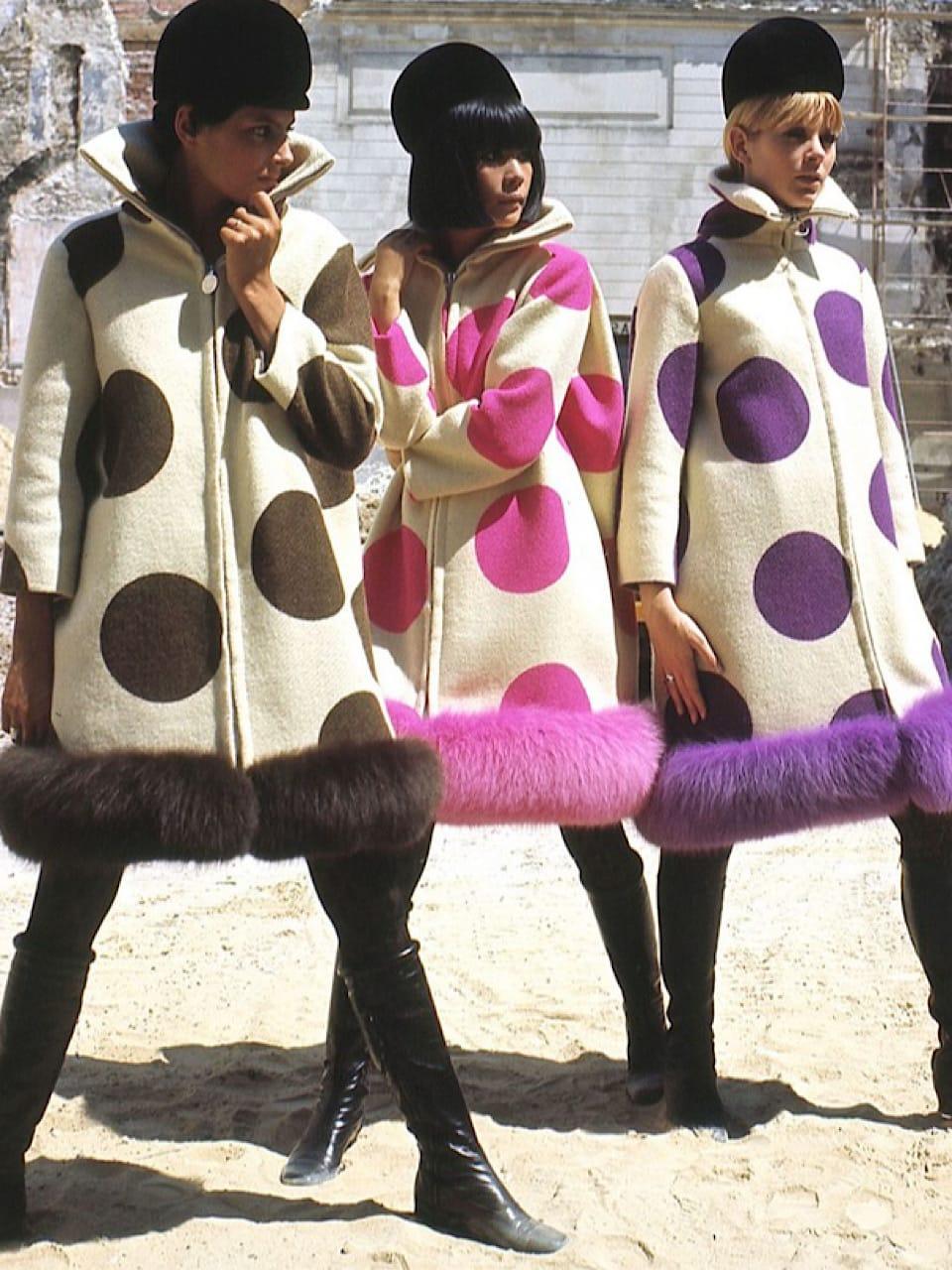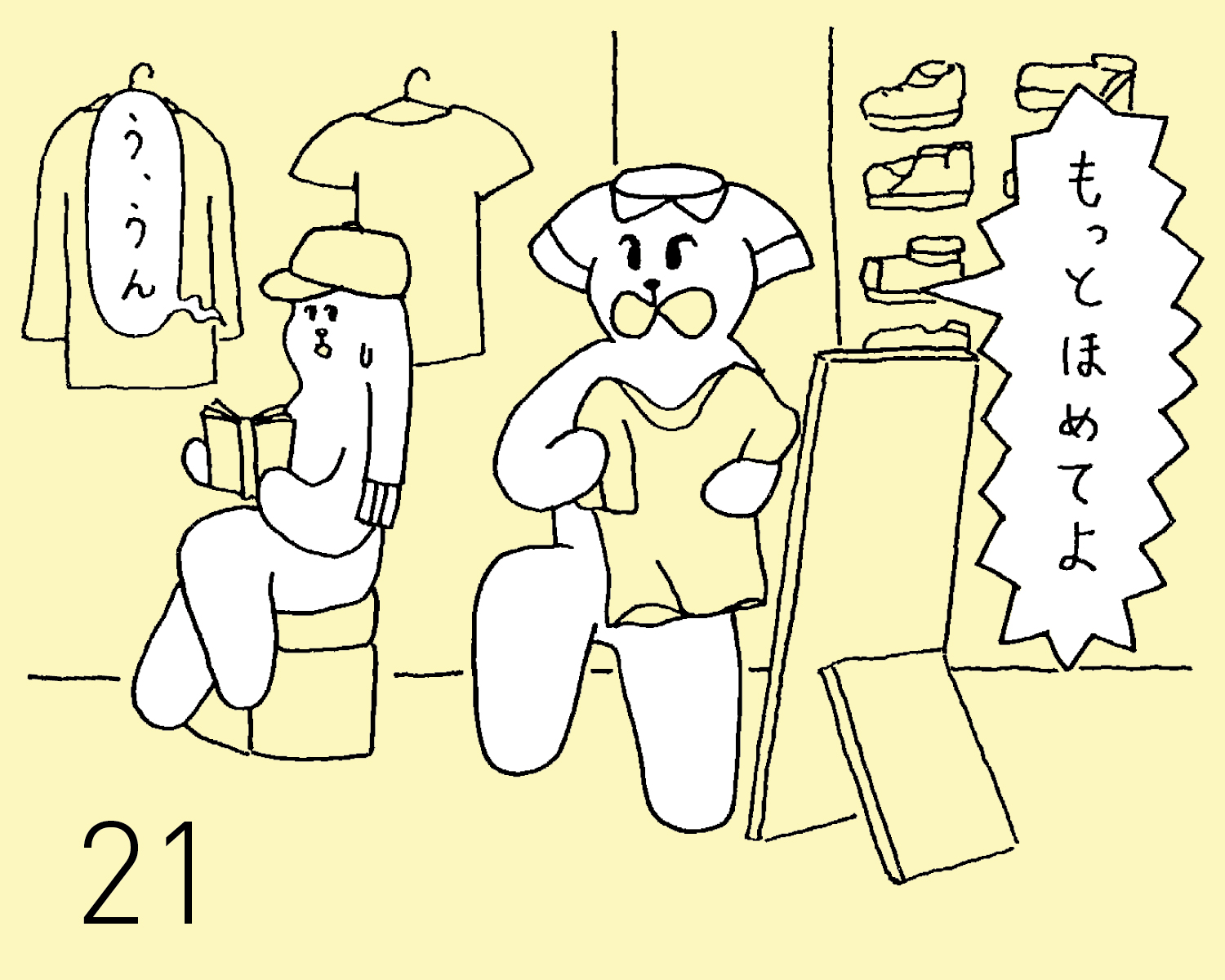Netflixオリジナル映画『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(21)でアカデミー賞®監督賞に輝いた、ジェーン・カンピオンによる不朽の名作『ピアノ・レッスン』が、日本公開から30周年を記念し、4Kデジタルリマスター版として上映される。19世紀半ば、言葉ではなくピアノで感情を表現してきたエイダが娘フロラと共に、ニュージーランドへ嫁ぐところから始まる物語だ。女性たちがいかに男性中心の社会のシステムに支配され、ときに自らの可能性や人生を閉じてしまう危険性があるのか。常に、人間の弱さの中にある強さを描き、ソフィア・コッポラ、マギー・ギレンホール、グレタ・ガーウィグなど後に続くクリエイターをエンパワーする存在である彼女が、「女性」監督として呼ばれてきた道のりと、MeToo運動以後の変化について振り返る。
映画『ピアノ・レッスン 4Kデジタルリマスター』ジェーン・カンピオン監督インタビュー
「パワーを独占することは支配であり、愛じゃない」

──日本で初めて公開されてから30年が経ちましたが、4K映像で本作を振り返ってどんな気持ちになりました?自分の中の変化など気づいたことはありましたか?
久しぶりだったのですが、目に見えて改善された映像を観ることができたのはうれしかったですね。俳優たちのパフォーマンスが最高でしたし、最近のものにはあまり見ないような、複雑で力強い女性の作品だと思いました。ただ正直、まるで自分ではない誰かが撮った映画を観ている感覚で(笑)。あまりに遠くに感じたのは、今は当時と全く違うことを考えているからだと思います。若い頃、この映画に救われたのは確かですし、年は取りましたけど、私自身は何も変わっていません。自分を特定したり、捉えたりはしないようにしてるので、そう思うのかもしれません。わかっているのは、ベストを尽くすことだけなので。
──世界的に注目される女性の監督が少なかった時代に、カンヌ映画祭史上、女性監督としては初のパルム・ドールを受賞され、「女性」という冠が常に肩書きについてまわることにはどのように感じていました?
本当にイライラさせられました(笑)。なぜなら、監督という職業にとって、性別は関係ないんですよ。自分が何をやっているかをわかっていて、技術があって、情熱を持ってさえいればいい。つまり、仕事の内容としては、完全に男女平等なので。
──とはいえ、この作品が「女性のまなざし」として男性中心社会だった映画界に風穴を開け、後に続く多くの女性のフィルム・メーカーを勇気づけたのも事実です。
私自身は、70年代のフェミニズム運動の最初の波が起きたところから来ている、という意識があります。物事を変えていこうと思っていたし、脚の毛も脇の下も剃ることはなかった。私たちはとても強く、当時、男女の平等に対して大きな後押しもあった。女性に関することは全て退屈で愚かだという考えを払拭する、それが私たちの意思でした。単純なことですが、権力がすべてという世の中では、権力を持つ者は誰でも面白く、重要に見えるものです。そして、権力はしばしばお金として表されます。つまり、世界中の女性たちが十分なお金を望み、自分たちのことを映してほしいと主張するようになった。それが2017年の後半のMeToo運動につながったと思います。最初はテレビで、次いで映画業界で起こりましたが、MeTooは、社会にも私自身にも本当に大きな変化をもたらした、とても重要な出来事でした。正直言って、それ以前は、女性たち自身がフェミニストであることを恥じていたから。おかしな話ですが、女性がフェミニストに対して、「耳障りだし、泣き言みたいに聞こえる」と言っているのを耳にしたことがあります。でも、それは無知から来るものだったと思います。
──フェミニストの定義は、時代や人によって本当に異なりますよね。
そうですね。私にとって、フェミニズムとは常に平等を求め、健全化していくことです。だから、特別なものは何も必要ないと思っています。でも、突然、周りがオリンピックか何かのように、「最優秀女性映画賞を設けるべきだ!」と言い始めたときは、「それは要らない」と強く反対しました。必要なのは、お金と機会だけなんですよ。私が学生だった頃は、学校がキャリアを暗示するとても重要な場所のように感じたものですが、卒業すると全てが変わりました。女性であるだけで、信頼されなかった。とはいえ、私は本当によくしてもらった方ですし、初期の頃から支援してくれる方たちもいたので、あまり文句は言えないんですけどね。
──でも、そのために努力もされたわけですもんね。
それは間違いなく。今は状況が変わって、女性が手に届く機会がとても増えたと思います。Me Too以前の映像業界は、アパルトヘイトの終焉やベルリンの壁崩壊のようにまさに危機的状況にありました。何年もの間、公平でないという感情に対して自分で指一本触れることができなかった。だからこそ、女性への虐待の酷さと機会のなさを如実に示すものになった。もちろん、バックラッシュはあったけれど、グレタ・ガーウィグ監督が『バービー』(23)で大ヒットを飛ばしたように、繰り返しベストを尽くしてきたから、今、女性たちは卓越しているという強力なエビデンスが世界中にある。女性たちが生み出した作品がこうして評価されるのは、素晴らしいことだと思います。特に最近は、女性というテーマがより関心を集めていると感じますし、複雑でパーソナルな人生が、映像作品の題材として、興味深く受け入れられるようになってきている。これまでは、ひどい状況や戦争に巻き込まれた男性がサバイブしたり、成功するような英雄的な物語が多かったわけですが、基本的に、英雄神話が何度も何度も繰り返されることで、アメリカは深く沈んでいったと思うんです。そして、そのメソッドの中には、もちろん女性も存在していました。だからこそ、今、女性たちが自分たちの言葉で語り直している。私は女性たちが一緒になって、暗闇に明かりを灯すようなムーブメントを見る準備ができているし、日本もきっとそうなっているのではないでしょうか?
──まだ牛歩ではありつつも、変化はしてはいると思います。ちなみに、映画業界で権力を持つ男性たちも変わってきたと感じますか?
女性へのサポートが遅れていた時代に、もう戻ることはないとは言えますよね。またあんな時代が来るなんて、考えたくもない(笑)。Me Too運動は、女性だけでなく男性からも多くの力とサポートが必要だったと思いますし、明らかにひとつの時代が終わりました。しばらくの間、女性監督に需要が集まったのには、彼らが自分たちを良く見せたいからじゃないかという懸念がありましたよね。男性が享受し続けた優位性を手放すのは、難しいと思います。精神的に変化が必要になる。権力を共有するという考えは、彼らにとってどこか怖いものなのかもしれない。人々に愛される理由が、自分の権力にあると信じているのだとすれば余計に。でも、彼らがパワーをわかち合いたいと思うように変わらなくてはいけない。権力を独占することは、支配であり、決して愛じゃないですから。
Photo_Grant Matthews courtesy of Netflix Inc. Text&Edit_Tomoko Ogawa