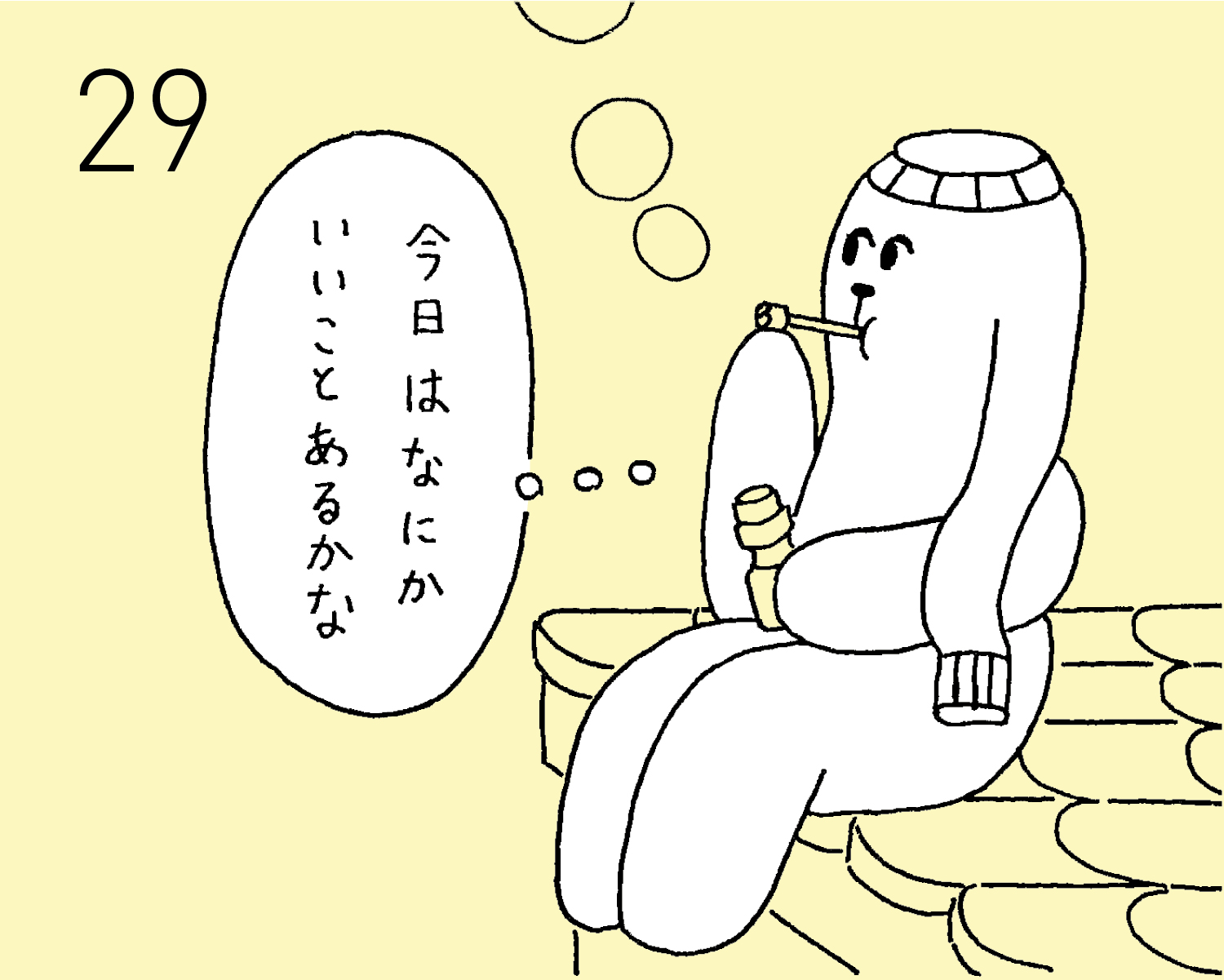明るく雄大なサウンドの
爽やかな失恋ソング。

『ハートのイアリング』1984年11月1日発売。作曲のペンネームは、佐野元春のラジオ番組のリスナーが、ホール&オーツをHolland Roseと聴き間違えたことにちなむ。ラジオ好きな佐野さんらしいエピソード。イアリングは「ヤ」ではなく「ア」。「ダイアモンド」「ブラッサム」などと同じ若松さんのこだわり。「長調的な響きが聖子っぽいからね」。揺れ動く乙女心をスクリューの不調に例えたB面の『スピード・ボート』も秀逸。
M 佐野さんにオファーされた理由は?
W メロディメーカーで、新しい音楽を取り入れて人気も実力もありましたから。しかも他のアーティストへの楽曲提供はほとんどなかった。で、ダメもとで事務所にオファーしたんです。するとすぐに当時青山にあったエピック・ソニーでお会いすることができて、15分くらい話したのかな。もしかしたら立ち話だったかも(笑)。そしたら「OK、もちろん書くよー」ってその場でね。
M えっ、そんな短い打ち合わせだったんですか?
W そう。打ち合わせ、あまり長くしすぎない方がいいんですよ。長く話すとあれこれイメージを限定しちゃうから曲がつまんなくなる。
M この曲は少し佐野さんの『Someday』の香りもします。
W やっぱり佐野さんと大村雅朗さんのコンビだから自然と似るけど、音楽は娯楽だから境界線を作らずに楽しむことが大切ですから。
M このアルバムは歌詞の当て書き感もすごいです。聖子さん自身も当時のインタビューで『銀色のオートバイ』の歌詞の気持ちがよくわかると。『Star』も歌手の歌ですよね。少しちあきなおみさんの『喝采』にも通じるような私的な世界観が新鮮で。
W 松本隆さんがマンネリ化しないように、その都度いろんなボールを投げてくださっていたからね。
M 若松さんは当時聖子さんがマスコミで話題になったときは、どんなことを思っていたんですか?
W 聖子は竹を割ったような男っぽい性格のところがあるから、ある面、不器用なんです。だから、ぶつかるときは、ぶつかっちゃう。真っ直ぐに進めば、向かい風ですから。逆に言えばサバサバした性格だから、ここまで前向きにやってこれたとも言えるよね。引きずる性格だとこの世界は難しいから。
M 何かアドバイスしたり?
W いやいや、何も言わない。会っても「最近どう?」って言って雑談するだけ。遠くからそっと見守ってました。元気なら何事も前向きに乗り切っていく強さを持ってる子だから。もちろん具体的な相談があれば、ちゃんと話しますよ。だから、きっと歌の世界の中で気持ちを発散させていたんじゃないかな。
M 聖子さんって、子育てもして夢も実現して、80年代以降の女性の自立もリードしたと言われていますが。
W 聖子自身は無我夢中で一生懸命生きていただけで、本人の中にそういう意識はあまりなかったんじゃないかな。深く考え込まずに突き進んで、思うがままにね。それが歌からも発散されていたよね。
M このアルバムでは矢野顕子さんが『そよ風のフェイント』で初めて曲提供されていますね。
W 矢野さんの独特の世界が大好きでね。1985年の『The 9th Wave』の中の『両手のなかの海』や2000年に出したシングル『上海ラヴソング』でもそれぞれ曲や詞を書いてくださっている。『上海ラヴソング』はライブでもすごく人気があると、あの頃聖子自身が言ってましたね。聖子は矢野さんの世界も自分のものにしちゃうからすごいよね。
M 『MAUI』でのNOBODYの起用も意表をつかれました。
W 大村くんがその頃よく一緒に仕事していて、それで紹介があったと記憶しています。旬でしたからね。いいなと思ったらどんどん参加していただいて。ロックな要素もプラスされました。
M 『ピンクのモーツァルト』にはどんな思い出がありますか?
W モーツァルトは私が大好きだから。一日中聴いていても飽きない。日本人に合うし、繊細で品もある。人間が生きているなかで命の真ん中に突き刺さるような感じさえします。それで当時「今度の聖子はモーツァルトかなぁ」と思っていて。西麻布のカフェで細野晴臣さんと松本隆さんと打ち合わせをしたんです。でも当時ケータイがないから、1時間位待たせちゃったんだけど、お二人とものんびり待ってくださっていた。そのときに「モーツァルトってタイトルに入れたくて」とお話ししたら、細野さんが「じゃあ、ピンクのモーツァルトはどう?」と。
M アリスの次はモーツァルト?
W いやいや。そこは全然意識してない。脈絡はないの。いつも一陣の風のような思いつき(笑)。何がそのときの聖子に合うかなーと。