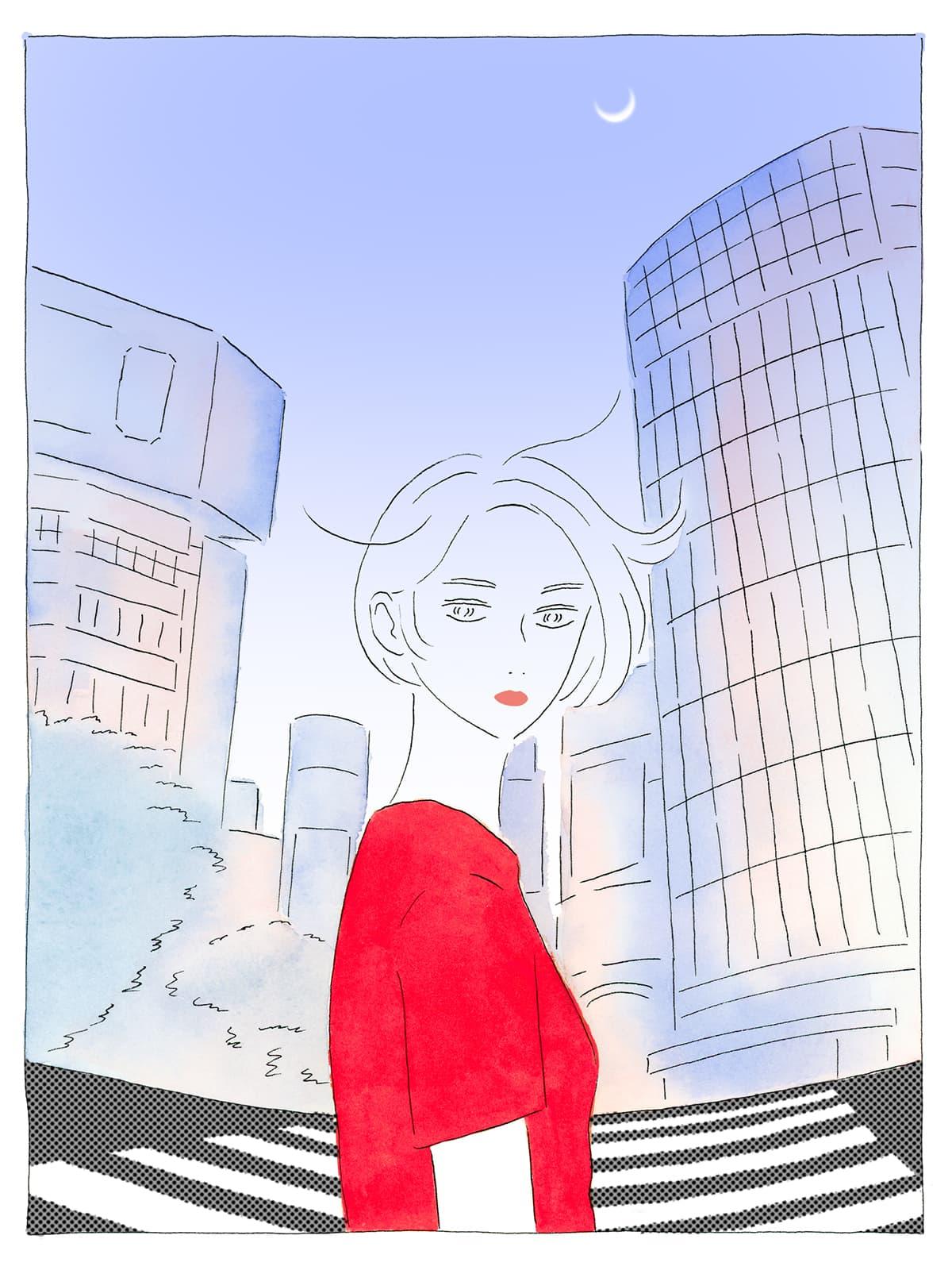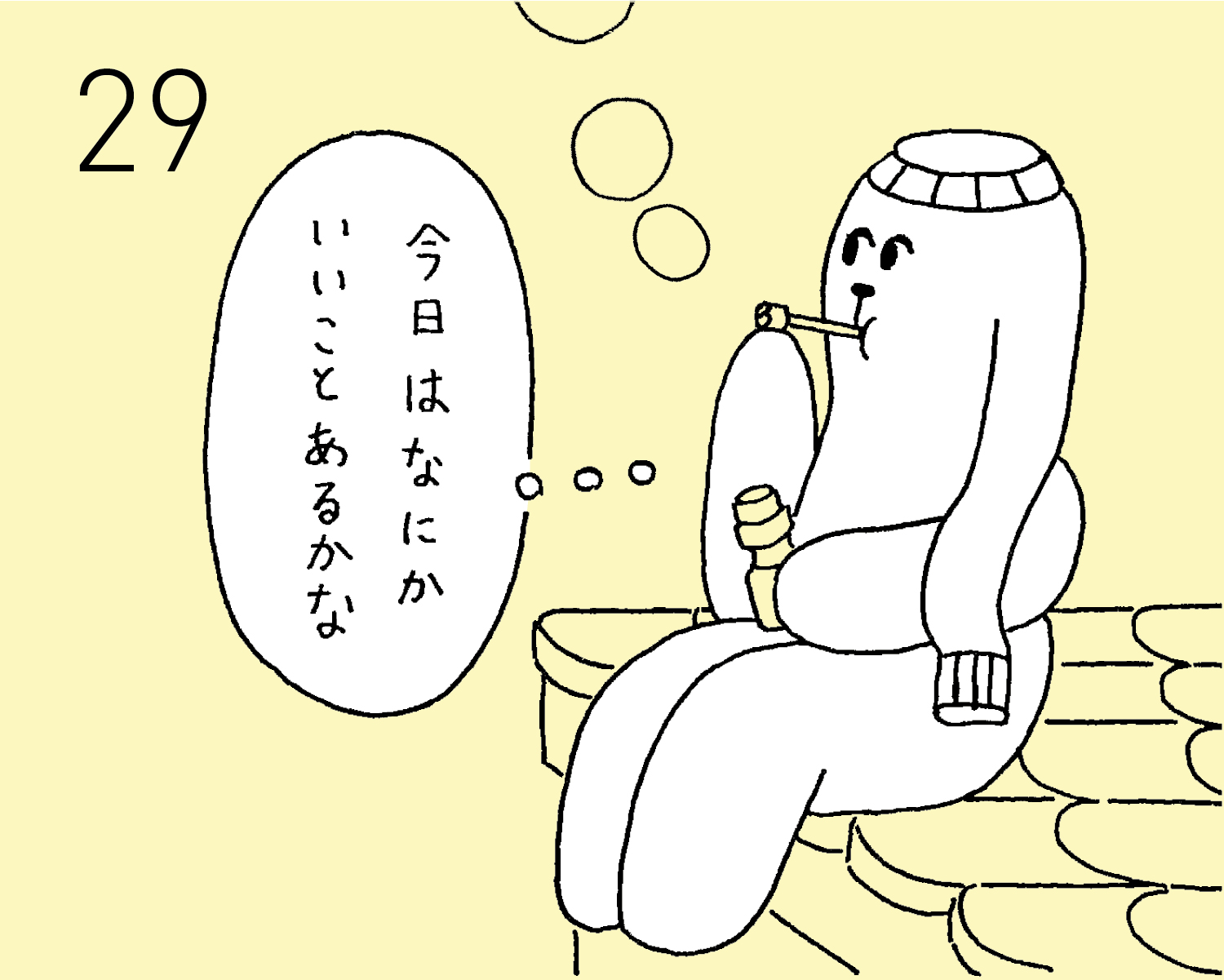上京して7年目、 高層ビルも満員電車もいつしか当たり前になった。 日々変わりゆく東京の街で感じたことを書き綴るエッセイ。
前回記事:『Vol.14──四谷三丁目』
シティガール未満 vol.15──高円寺

雪が降るたびに思い出す恋がある。
と書いてみるものの、あの日降っていたものを雪と呼んでいいのか、あの時の気持ちを恋と呼んでいいのか、未だに少し迷っている。
彼と出会ったのは19歳の冬だった。その頃の私はTwitter上で同じ大学の知らない人たちと交流することが日課で、その日は学食で何人かとオフ会をしていた。そこへ、ダッフルコートにベレー帽をかぶった、おそらくフリッパーズ・ギターなどの渋谷系を意識しているであろう出で立ちの青年が現れた。私たちがいるのを聞きつけて休み時間に寄ってみたという彼は、私と同じ1年の同じ学部で相互フォローではあったが、あまりツイートをしないタイプで交流もほとんどなかったため、特に印象に残っていなかった。
彼は私の隣に座り、授業や音楽の話で一通り盛り上がった後、真顔で「てかLINEやってる?」と出会い厨のテンプレみたいな聞き方をしてきてギョッとしたが、緊張感が伝わってきて私も真顔で「やってるよ」と答えるしかなかった。LINEを交換するなり彼は授業があるからとそそくさと去っていった。
翌日さっそく彼からLINEが来た。スクショを撮っていたため、当時の痛々しいやり取りの一部が残されている。
「東京で好きな街は?」
「1番好きなのは高円寺かな」
「高円寺かー。サブカルの好みそうな街だよね笑」
「よくサブカルって言われる笑」
「そうかな? なんか終電ちゃんはあんまり既存のジャンルに当てはまる感じじゃない気がする。そういうところがかっこよくてずっとファンだったんだ。だから実際に会えて嬉しかったよ」
「そうなんだ、ありがとう」
「ルックスもクールだし、ファッションとかも大学ではあんまり見ない感じで、僕は好きだよ」
カテゴライズできないような特別な存在でありたいという若さゆえの欲求を刺激され、直球な口説き文句に、私もすぐにその気になった。話せば話すほど、趣味も価値観も性格も驚くほど似ていることがわかった。これはもう付き合うものだと思い、ちょうど住んでいた寮の契約満了が近かったので、彼の家の近くに引っ越そうかと密かに考えていたほどだ。
「せっかく仲良くなったし、今度暇なとき遊ばない?」
大学の試験期間が終わった頃、ついにデートの誘いが来た。お互い忙しかったこともあり、初めて会ってから2ヶ月が経っていた。
「いいよ!」
「やったー!」
彼が「吉祥寺に行ってみたい」ということで吉祥寺に行くことになったのだが、約束の日が近づくにつれて死ぬほど億劫になってきてしまった。付き合う前のデートというものが、とにかく苦手なのだ。慣れていない人と映画を見たり買い物をしたり食事をしたりと、半日ほど行動を共にするのは、友達のいない修学旅行の自由行動のような苦痛を感じる。最初は食事や軽い散歩だけにして欲しい。
今思えば正直に相談して代案を出すべきだったのだが、その時の私は悩んだ末に、精一杯かわいこぶって「明日行きたくなくなっちゃった>_<」とだけ送って丸投げするのが限界だった。幸いにも彼の返事は「実は僕もそうなんだよね笑 まあ、話したいってだけだから、わざわざ吉祥寺に行く必要はないかな」とのことで、こんなところまで似ているのかと嬉しくなったのだった。
相談の結果、お互いの家の中間地点だった高円寺で食事をするだけになった。待ち合わせ場所は純情商店街。まさに私の理想的なシチュエーションだった。
銀杏BOYZの前身バンドであるGOING STEADYの名曲、『佳代』に
「あなたを乗せて自転車こいだ 真夜中の純情商店街」
という一節がある。
曲名の『佳代』はボーカル・峯田和伸の初めての彼女の名前で、その彼女が高円寺に住んでいたというのはファンの間では有名な話だ。今やこうして毎回東京の固有名詞が出てくるエッセイの連載をしている私だが、「純情商店街」は上京前から知っていた数少ない東京の固有名詞の一つだった。
そして自分も大学生になって東京に行けば、真夜中の純情商店街で二人乗りするような恋愛ができるのだと、信じて疑っていなかったのだ。
しかも彼も銀杏BOYZとGOING STEADYが好きだったのだから、もう完璧としか言いようがなかった。
その日の東京は朝から雪が降っていた。
マフラーをいつもより上まで巻き、傘で顔の上半分を隠して、純情商店街のアスファルトに次々と消えていく雪を見つめるしかなかったのは、寒さではなく緊張のせいだった。
「久しぶり」という声に、少しだけ傘を上げる。
久々に会った彼を一目見て、私は内心、何かが違う気がした。LINEだけで盛り上がっている間に美化してしまっていたのかもしれない。
私たちは傘と傘が触れるくらいの距離で、純情商店街を歩き始めた。
沈黙が流れ、何を話そうかと考えていると、「雨だね」と彼が静かに呟いた。耳を疑った。
「え、雪だよね?」
「雨だよ」
「いや雪でしょ」
絶対に負けたくなかった。どう見ても雪と呼ぶべき白い粒が、初めて彼と並んで歩く靴のつま先で解けて染み込んで、痛かった。
「積もってなければ雨だよ」
「積もってなくても降ってれば雪でしょ」
「俺にとっては雨だよ」
「雪でしょ」
彼は諦めた様子で黙りこみ、私もそれ以上は何も言わないことにした。
適当に通りかかった洋食屋に入ってからは、何事も無かったかのようにいつものLINEの続きのような話で盛り上がった。音楽の話、古着の話、大学の話、地元の話。そしてLINEではしなかった恋愛の話に、彼が切り込む。
「恋人とかいないの?」
「いないよ」
「そういうの興味ないの?」
「あんまりないかも」
人並みに興味はあったはずなのに、なんとなく恥ずかしくて咄嗟に嘘をついてしまったのだった。
店を出る頃には、雪は雨に変わっていた。別れ際に「ありがとう。寂しさが紛れたよ。じゃあまた」とだけ言った彼の背中を見て、もう二度と会うことはないような気がした。
話している間も、間違いなく気は合うのだが、恋愛対象としては違うと感じていた。それは直感的なもので、彼が雪を雨だと言わなくても同じだったと思う。彼がどう思ったかはわからないが、実際にその後一切連絡はなかった。
あれから6年が経とうとしているが、毎年雪を見ると彼の「俺にとっては雨だよ」という言葉を思い出す。そして今でも考える。
もし論争にならなかったら、その後の私たちの関係は違ったのだろうか。意地を張らずに適当に流した方がよかったのではないか。子供のように雨だ雪だと言い張るのではなく、気象庁の定義を調べたりしてせめてもっと建設的な議論をすべきだったのではないか。誰が何と言おうと「俺にとっては雨」、そういう解釈もあっていいのではないか。
今年ももうすぐ雪の季節が来る。あの日降っていたのは、雪だったのだろうか。それとも雨だったのだろうか。でもやっぱり、私にとっては雪だったのだ。
(初出:「失恋手帖」vol.2収録「雪の定義」を加筆修正して転載)
🗣️
絶対に終電を逃さない女
1995年生まれ、都内一人暮らし。ひょんなことから新卒でフリーライターになってしまう。Webを中心にコラム、エッセイ、取材記事などを書いている。
Twitter: @YPFiGtH
note: https://note.mu/syudengirl