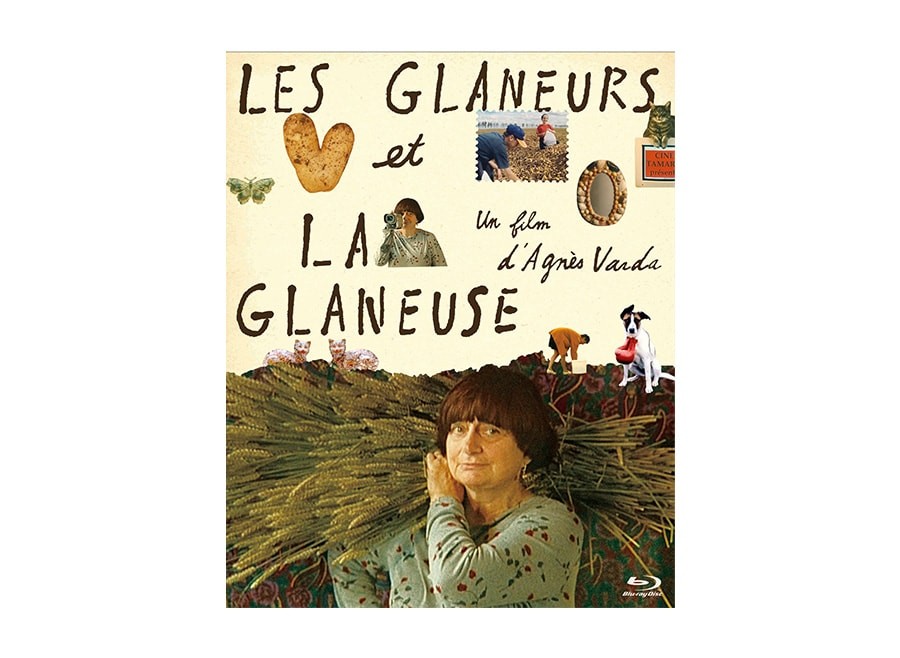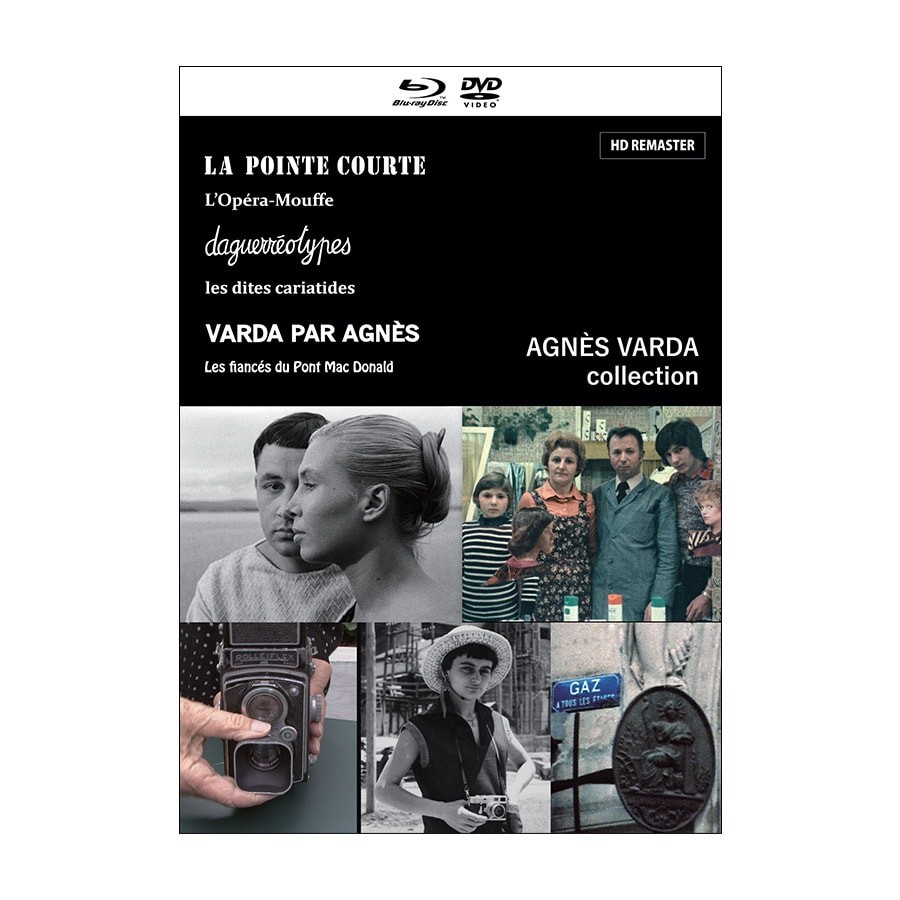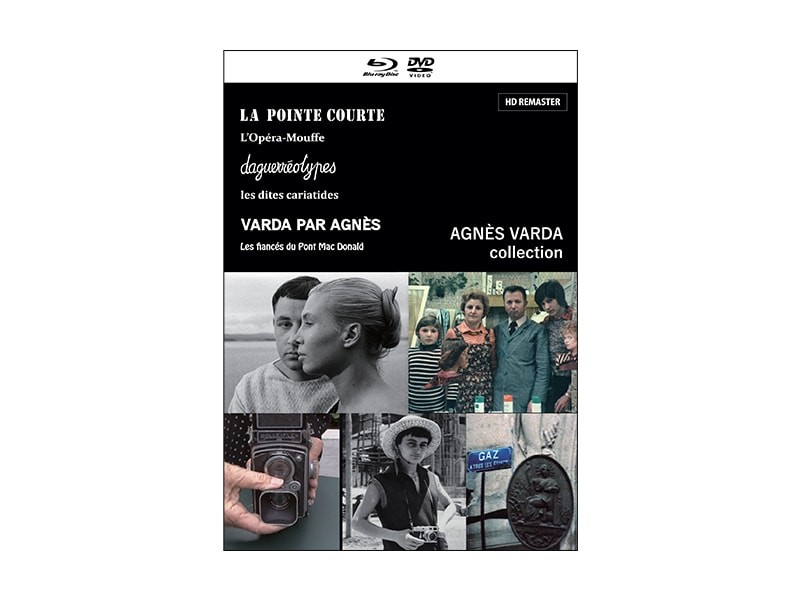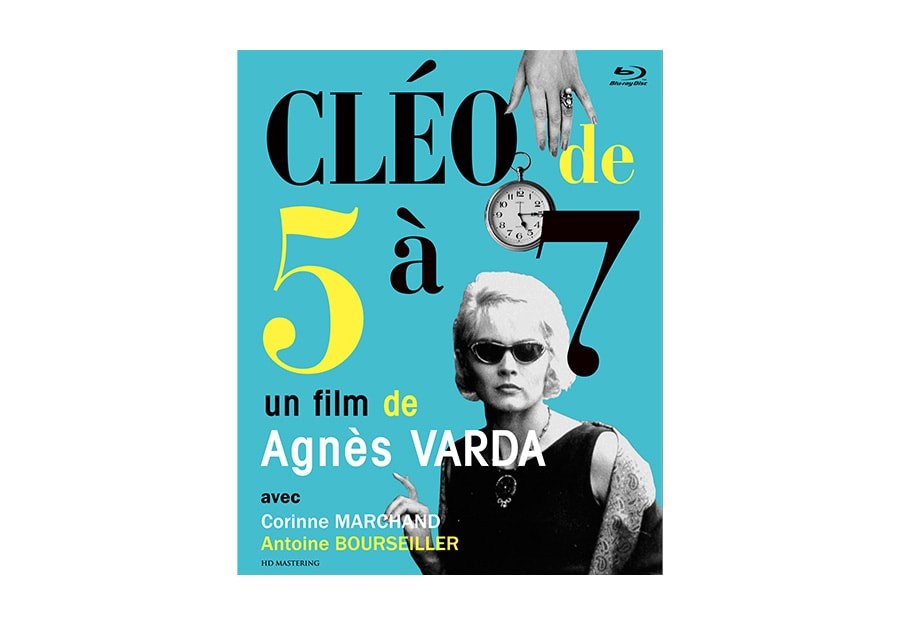2019年3月、生涯現役を貫いて90歳で亡くなった、映画監督アニエス・ヴァルダ。ヌーヴェル・ヴァーグの先駆者として彗星のごとくフランス映画界に現れ、フィクションとノンフィクションを行き来して多くの作品を残したヴァルダの、劇映画における最高傑作とされるのが『冬の旅』だ。
1985年、ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞するも、日本では興行も批評も振るわなかった。それが2022年3月、国立映画アーカイブでの一度限りの上映が大盛況に。やっと時代が作品に追いつき、現在、劇場公開中。再評価の機運が高まっている。
寒々しい冬の南フランスを放浪する、孤独な18歳の女性モナの旅を描いたこのミステリアスな映画を、ヴァルダのフィルモグラフィーをおさらいしながら、4つのフレーズからひもとく。
アニエス・ヴァルダの映画『冬の旅』を知るための4の事柄。漂流する女性・モナは幸福なのか?

アニエス・ヴァルダは1979年に来日したときのインタビューで、こんな言葉を残している。
「幸せとは、慎重に扱うべき言葉です。自分に満足していると感じるとき、環境に調和していると感じるとき、それが幸せといえる」。
だとしたら、1985年にヴァルダが発表し、ヴェネチア国際映画祭金獅子賞に輝いた『冬の旅』の主人公である18歳の不良少女、モナの場合はどうなんだろう? モナを演じた撮影当時17歳のサンドリーヌ・ボネールは、ヴァルダの自宅キッチンで初めて顔を合わせたとき、役について「ありがとうを言わず、誰に対しても突っかかる、悪臭のするキャラクター」と説明されたそう。
映画の冒頭、南フランスの片田舎の、ブドウ畑の側溝で、モナの凍死体が発見される。カメラは、モナが死に至るまでの数週間の足取りを、その旅の様子だけでなく、彼女に路上で出会った人々の証言を通して辿っていく。
モナは生前、寝袋とリュックを背負い、野宿をしながら徒歩とヒッチハイクの旅を続けていた。「大学を出て秘書をしてたけど、人に使われるのはまっぴら」と言うシーンがあるが、まさにこの映画の原題『Sans Toit Ni Loi(屋根も法もない)』のとおりの、住所不定無職のその日暮らし。
ヴァルダによれば、この映画のテーマは「自由」と「汚さ」で、こう語っている。「私たちの時代は汚さに対してひどく排他的だと思います。(…)貧しい労働力は必要とするけれども清潔でなければならないというわけです」。
髪も身体もろくに洗わないモナ。あるとき、プラタナスの樹の研究をしている、さっぱりとした性格のランディエ教授(マーシャ・メリル)の車にヒッチハイクで乗せてもらうが、ふとアップで映る、教授のきれいな赤いネイルと、モナの黒く汚れた爪の対比にはハッとさせられる。
思いのままに生きるモナは、幸せな自由主義者なのか? それとも不幸な社会の犠牲者なのか? この問いが、映画を観ている私たちに突きつけられる。無口なモナは答えをくれないので、観客は自分なりに見つけだすしかない。
ドキュメンタリーの手法
『冬の旅』は、ヴァルダの映画作りのカギがよく分かる1作だ。まず、ドキュメンタリーの手法を取り入れていること。ヴァルダはドキュメンタリー作家でもあり、パリ14区ダゲール通りの住人たちの暮らしを映しだす『ダゲール街の人々』(75)や、貧困を背景にあらゆる「もの拾う人々」を追いかける『落穂拾い』(00)など、数々のドキュメンタリー作品を発表してきた。
デビュー作の劇映画『ラ・ポワント・クールト』(54)でも、セットを組むのが当たり前だった当時としては異例のロケ撮影を行い、また職業俳優のほか、ロケ地である漁村の住人を出演させていた。
『冬の旅』では、モナに出会った人々が思い思いに印象を語る、インタビュー風のシーンが全編に散りばめられている。それに『ラ・ポワント・クールト』と同様、演じているのは職業俳優だけでなく、現地住人の場合もある。
本人役の羊飼いがモナについて「目的がなく仕事をやる気もない。あれは放浪じゃない。怠け者さ」と言えば、ヨランド・モロー演じる女中のヨランダが「独りだと寂しい。二人でも満たされないわ。(…)彼の誘いを待つだけの私。私は涙もろいからあの娘が忘れられない」と話す。ほとんどのキャラクターはアウトサイダーのモナを見下すか、哀れむか、とにかく色めがねでしか見ておらず、理解しようという気がない。
この映画を作ったきっかけは、ヴァルダが憲兵から、リンゴの樹の下で凍死した放浪者の青年の話を聞いたことだったそう。やがて自身が10代を過ごした南フランスの、イトスギの樹がある風景が思い浮かび、ヴァルダは駆り立てられるように一人で、パリから車で南フランスへ。放浪者の取材とロケハンに着手した。その最中にヒッチハイクで拾ったのが、セティナという若い女性。この出会いによってモナというキャラクターがより豊かになり、最終的に製作会社はセティナのアイデアを買い取ったという。
のちに、ヴァルダはプロデューサーや共同編集者らを伴い、2度目のロケハンにも出かけた。こうした綿密なリサーチこそ、他者を理解しようという誠実さの表れだ。なおセティナは終盤の駅のシーンで、不良少女の一人を演じている。
シネクリチュール
準備に余念がなかったヴァルダだけれど、実はラッシュ試写(未編集素材を確認するための試写)の後、制作方針を方向転換させたそう。ラッシュではモナが「人々に出会う合間に、ちょっと歩いている」ふうに見えてしまい、「これは絶対に違う!」と思ったヴァルダ。むしろ真逆で「一人で歩き続けている合間に、人々に出会う」ように見せたい。どうしたら孤独な徒歩旅を印象づけられるか。
そこで加えたのが、13のドリーショット(カメラをドリー〈台車〉に乗せて動かしながら撮影する方法)。ジョアンナ・ブルゾヴィッチによるサスペンスフルな音楽が流れる中、モナが画面の右から現れ、左に歩き去るまでを、カメラが1分間ほど並走して撮る。
自作を振り返るドキュメンタリー『アニエスによるヴァルダ』(19)で、ヴァルダはこれらのドリーショットを「毎回ショットの最後に現場にあるものや道具を撮ってモナと消える。10分後に登場する次のドリーショットには必ず同じものや道具を入れて撮り始めて前のショットとリンクさせる。自分にしか分からない謎を映像に残したの」と解説している。
シナリオの内容で思考停止せず、各段階でのあらゆるチョイスを通して作品を紡いでいく姿勢は、ヴァルダがフランス語の「映画」と「書くこと」をかけ合わせた造語「Cinécriture(シネクリチュール)」が意味する映画哲学そのもの。この映画のシナリオはあってなかったようなもので、各シーンのセリフは撮影当日の朝に書いていたそうだが、この「作りながら考えるスタイル」には、ドキュメンタリー畑での経験も大いに影響しているはず。
女性としてのディスクール
ヴァルダとほぼ同世代のフランスのフェミニストに、女優のデルフィーヌ・セイリグがいる。セイリグは1976年、国務長官のフランソワーズ・ジルーがテレビ番組で発した、自身も女性でありながら女性の地位を軽視した発言の数々を皮肉たっぷりにこき下ろすドキュメンタリー『マゾとミゾは舟でゆく』を初監督した。
ヴァルダはセイリグほど戦闘的ではないとはいえ、映画を作る上で「女性としてのディスクール(言説)しか私にはない」と話し、まさにジルーのように男性的なものの見方をすることで成り上がる女性の権力者を批判してもいる。本来は女性同士、手を取り合うべきなのだと。
ウーマンリブ全盛期に撮った『歌う女・歌わない女』(77)は、当時フランスでは禁止されていた中絶や、シングルマザーとしての経験を通して、タイプの違う女性同士の友情を描いていたし、そういえば『5時から7時までのクレオ』(62)でも、ガンの疑いにおびえながらパリの街をさまよう主人公が一瞬ほっと笑えたのは、女友だちとの時間だった。
『冬の旅』でモナが犠牲者に見えうるのは、若い女性だからだろう。ジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード』の影響もあり、多くの若者が放浪していた時代。なぜ女性だからって、放浪の自由を制限されなきゃならないの?という怒りが、モナの仏頂面ににじむ。
ヴァルダは以前、「女性と有色人種は同じ(マイノリティとしての)問題を抱えている」と話した。だからこそ、モナがいっとき親密になる何人かの男性のうちで最も心を許すのは、ブドウ畑で働いているチュニジア人労働者のアスーンだ。なおこの役も本人が演じている。
『冬の旅』は、映画史に残る名作『市民ケーン』(41)と、関係者の証言で構成されているところが共通している。ヴァルダは『市民ケーン』を例に挙げ、映画は本来男性の仕事だったために、本作もほかの多くの名作と同じように女性蔑視的な映画で、文句なしの傑作であるだけに余計自分を傷つけると話したことがある。ケーンは裕福な男性で、モナは何も持たない女性だ。ヴァルダ自身が関連性を明言したわけではないが、このカウンターには彼女の鋭い視線が感じられる。
サンドリーヌ・ボネール
ブーツを修理する、カチカチのバゲットをかち割る、オイルサーディンを缶から指ですくって食べる……。『冬の旅』はモナの内面を言葉で説明する代わりに、その無骨な動作を一つ一つ見せる。主演のボネールは、動作の大切さを理解し、火を起こしたりテントを張ったりの練習を重ねたそう。
ボネールは1983年にモーリス・ピアラ監督作『愛の記念に』でデビューし、『冬の旅』は2作目。ヴァルダはボネールの反抗心を引き出すためにあえてそっけなく接していたそうで、『アニエスによるヴァルダ』収録の対談で、ボネールは冗談混じりに「役作りで土を掘って手にマメができたとき、あなたに見せたら邪険にされた。ムカついたわ」と話した。
二人はその後しばらく会わなかったというが、10年後に映画発明100年を記念して作られた『百一夜』(95)では、ヴァルダがボネールに再びモナ役をオファーするというサプライズが。
2007年、ボネールがドキュメンタリー『彼女の名はサビーヌ』を初監督すると、ヴァルダから感想を書いた手紙が届き、それからもよく「うちのキッチンでお茶しにおいで」と電話があったそう。出会いの場所である、キッチン。2019年にヴァルダが亡くなる2日前、ボネールがお別れの挨拶に行ったとき、ヴァルダは開催直前だった写真展の話をしながら、「Osons être sentimentales(あえてセンチメンタルでいよう)」と言ったそう。
このそっけない社会で、いかに感傷的でいられるか。それを、ヴァルダは描き続けてきたように思う。『冬の旅』でほろっとさせられるのは、モナとランディエ教授の友情だ。二人で揚げ菓子をおいしそうにほおばるシーンの屈託のなさ。モナは自ら孤独を選び、教授はその孤独を尊重する。二人がいっとき結ぶ友情の背景にはきっと、ヴァルダとセティナがいて、ヴァルダとボネールがいる。
モナは幸せか、不幸か? はっきりした答えはないが、教授とのシスターフッドに、幸福のかけらはあった気がした。

『冬の旅』

冬の寒い日、フランス片田舎の畑の側溝で、凍死体が発見される。遺体はモナ(サンドリーヌ・ボネール)という18歳の女性。モナは寝袋とリュックだけを背負い、徒歩とヒッチハイクで放浪する日々を送っていて、道中では同じく放浪中の青年や、お屋敷の女中、牧場を営む元学生運動のリーダー、そしてプラタナスの樹を研究する教授などに出会っていた。警察はモナのことを、誤って転落した自然死として身元不明のまま葬ってしまうが、カメラは、モナが死に至るまでの数週間の足取りを、彼女が路上で出会った人々の語りから辿っていく。人々はモナの死を知らぬまま、思い思いに彼女について語りだす。
1985年、ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞。しかし当時の日本ではテーマの骨太さゆえか、1991年にようやく公開されるも、興行も批評も振るわなかった。30年以上経った今、時代が作品に追いつき、再評価の機運が高まっている。クロエ・ジャオの『ノマドランド』(21)や、ケリー・ライカートの『ウェンディ&ルーシー』(10)、シャンタル・アケルマンの『私、あなた、彼、彼女』(74)などに通じる、「漂流する女性」を描いた傑作。
監督・脚本・共同編集: アニエス・ヴァルダ
撮影: パトリック・ブロシェ
音楽: ジョアンナ・ブルゾヴィッチ
出演: サンドリーヌ・ボネール、マーシャ・メリル、ステファン・フレイス、ヨランド・モロー
配給: ザジフィルムズ
1985年/フランス/ヨーロッパ・ビスタ/カラー/105分/原題:Sans Toit Ni Loi (英題:Vagabond)
シアター・イメージフォーラムほか全国公開中
© 1985 Ciné-Tamaris / films A2
Text: Milli Kawaguchi