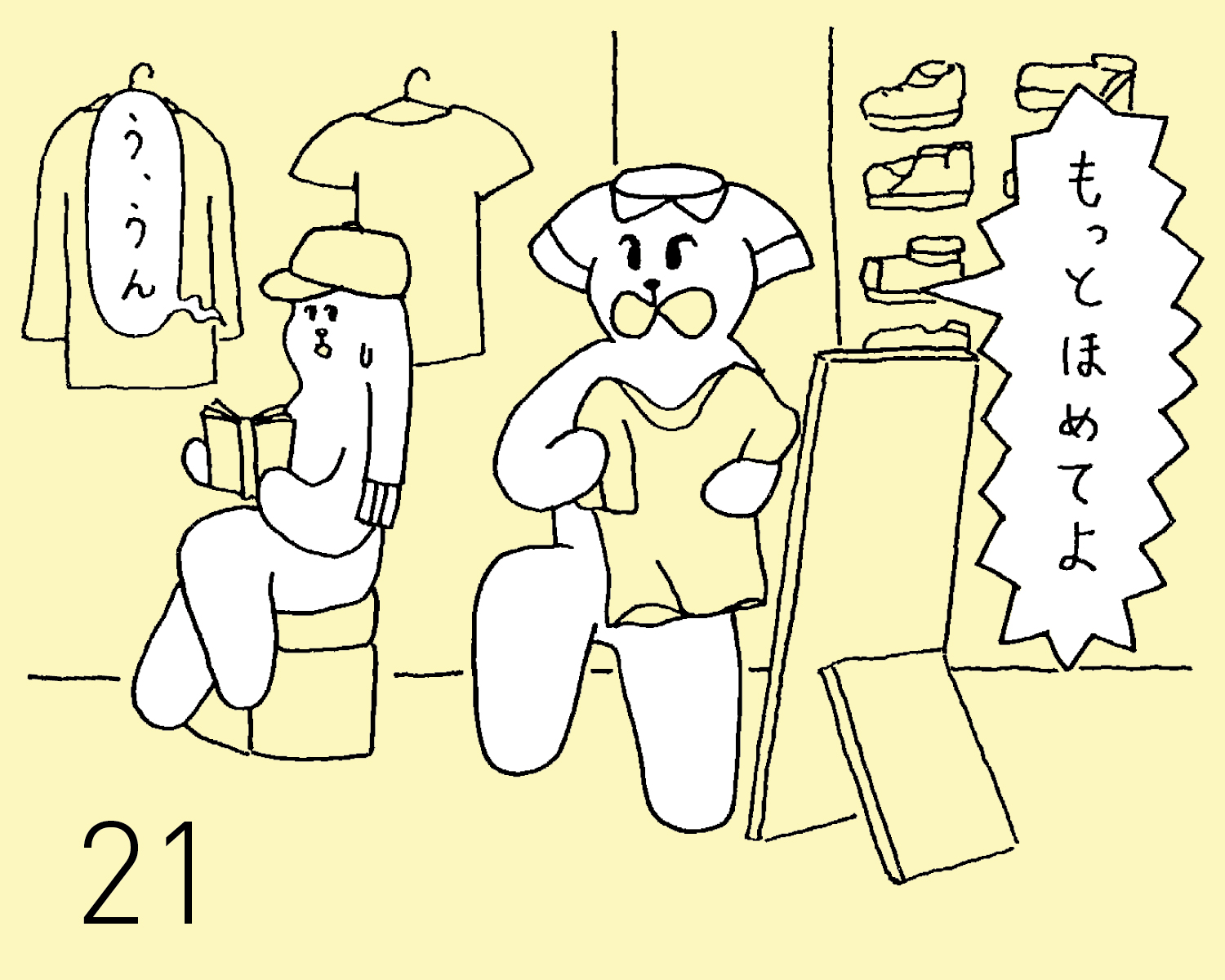アイスランド映画界で20年以上、特殊効果などを担当し、活躍してきたヴァルディミール・ヨハンソン監督による初の長編映画『LAMB/ラム』。羊飼いの夫婦が羊から生まれた、羊ではない“何か”を育てる……そんな不気味かつキャッチーな物語のイメージがつい先行しますが、監督に話を聞けば、人生で誰もが味わう喪失感をテーマに、アイスランド特有の動物との暮らし、白夜や天候、民話などをふまえ、民俗学的なアプローチで紡いだ作品なのだそうです。
『LAMB/ラム』でヴァルディミール・ヨハンソン監督が描くアイスランド。「民話ではクリスマスの夜に“何か”が起きる」

──監督は映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(16)などで特殊効果を担当してきたんですよね?
ええ。僕が生まれ育ったアイスランドでは、独自の風景を求めて、海外の映画の撮影がよく行われています。『ローグ・ワン』をはじめ、そうした多くの作品に、特殊効果などの部門で参加してきました。壮大な特殊効果を必要とする作品といえば、基本的には大作です。だから、クルーが300人くらいいることもあるんですよね。でも、僕の初の長編監督作『LAMB/ラム』のクルーは、30人くらいしかいなくて。仕事のやり方はそれぞれ根本的に違いますが、どんなプロジェクトにも必ず学びがあります。おかげで、作品ごとにベストなやり方を選べばいいんだなとフラットに思えるようになりました。
──2013〜2015年にかけては、唯一無二の作家性で知られるハンガリーの映画作家、タル・ベーラ監督に師事していたそうですね(※タル・ベーラ監督が2012〜2016年の間、ボスニア・ヘルツェゴヴィナのサラエヴォ科学技術大学で開講した、3年間の映画製作の博士課程「film.factory」に参加)。『LAMB/ラム』の制作総指揮の一人としてクレジットされてもいますが、彼からはどんな影響を?
「人に好かれることをしようとするのではなく、自分の心のままに、やりたいことをやりなさい」と勇気付けられました。つまり、“Be yourself !”ってことですね。
──上映時間が7時間を超える映画『サタンタンゴ』(94)を撮るような方ですから(笑)。
そうなんですよね(笑)。
──タル・ベーラ監督の“Be yourself !”という教えと、特殊効果部門における経験が混じり合い結実したのが、今回の『LAMB/ラム』だと思います。アイスランドの山間部で暮らす羊飼いの夫婦、マリア(ノオミ・ラパス)とイングヴァル(ヒルミル・スナイル・グズナソン)は、ある日羊から生まれた“何か”に、かつて亡くした我が子と同じ「アダ」という名前を付けて育て始めます。
この映画は、第一に壮絶な喪失感を描いた映像詩です。誰の人生にも当てはまる普遍的な物語だと自負しています。僕の祖父母がまさに長いこと羊牧場を営んでいて、主人公マリアの強さや決意は、つい最近亡くなった祖母に触発されたものです。マリアは喜びや幸福感を取り戻すためならどんなことでもする。決して折れることなく、人生を諦めようとはしないんです。
──夫婦の新たな生きがいとなるアダを作り出すために、以前のインタビューによれば、10人の子どもと、2人の人形使いと、4匹の子羊を集めたそうですね?
そのとおりです。ただ、子羊と人形を組み合わせて撮影したショットは数えるほどで、ほとんどのシーンでは、子羊と子どもを別々に撮影してCGで溶け合わせています。
──監督の技術をもってすれば、アダを全面的にCGで作り上げることもできた気がするのですが。
子羊や子どもは、ときに予想外の効果を与えてくれるんです。アダにより生命力が感じられるし、信憑性が高まるというか。クランクインしてからまず2週間撮影した後、子羊の成長を待つために2カ月間の休みを取ってから、撮影を再開しました。それくらい、できる限りカメラで撮影するということが重要でした。
──子羊や子どもがいることで生まれる、予想外の効果とは?
子羊で言えば、撮影中に眠ってしまったりするんです(笑)。テイクごとに動きが変わるので、より子どもらしく見えるテイクがいいのか、何をしているのか分かりやすいテイクがいいのかと、映像素材に豊富な選択肢が出来たのがよかったなと思います。もしアダの造型がうまくいかなければ、この映画は大失敗で、悲惨なコメディになると分かっていましたから。最終的な仕上がりには満足しています。
──羊以外にも、猫、犬、馬といった、さまざまな動物を起用していました。動物との撮影は思いどおりにならなくて大変だと聞きますが、どうでしたか?
もっと難しいかと思っていたんですが、どうにかうまくいきました。優秀な家畜の世話役の人がクルーに入ってくれたんです。僕自身も小さい頃から祖父母の羊牧場で、動物と一緒に多くの時間を過ごしていましたし、スタッフの多くも、動物との距離が近い田舎で生活しています。撮影の早い段階で学んだのは、動物が安心していれば、大抵望むとおりに動いてくれるということでした。
──たとえば、何者かが吹雪の夜、羊小屋に侵入するというオープニングシーン。羊は怯えたり逃げたり、迫真の演技を見せていました。
そうなんです。でも、猫にだけはまったく歯が立たずで(笑)。あの猫は本当に気まぐれで、たとえばあるシーンで窓際に座っていてほしいと思っていても、ぷいといなくなってしまう。でも翌日は、前日に座っていてほしかった場所にぴったり座っているんですよ。そのシーンはもちろん撮り終わっているので、やり直すわけにもいかないですからね。
──タル・ベーラ監督もよく動物を映画に登場させていましたが、影響は受けています?
そう思います。さっき挙げてくれたオープニングを思い付いて絵コンテを描いたのは、ちょうどタル・ベーラのもとで学んでいたときなんですよ。刷り込みじゃないけど、なんとなく影響されているような気がしますね。
──あと今回は、可能な限り自然光を使ったと聞いています。
夏のアイスランドは、白夜で24時間明るいんです。劇中で、登場人物たちが外は明るいのに寝ているのを観て、なんで日中に眠るのかと不思議に思う観客もいるでしょうね。僕と撮影監督のイーライ(・アレンソン)は、ロケ地に何度も足を運び、農場に泊まり込んでは、最も光が柔らかく美しい時間帯を探したんです。それは、夜中でした。だから、夜中に撮影したり、霧を活かしたり。あとは、曇り空ですね。アイスランドの天候は、急に雨や雪が降ったり、1時間に5回も状況が変わるくらい不安定なんですが、できる限り雲が出て光が柔らいだときに撮影しました。
──霧だとか、オープニングの吹雪だとかは、実際の自然現象で撮ったんでしょうか?
霧は少し足したりしましたけど、吹雪はそうです。あまりの悪天候に、立っているだけでも大変で、カメラがレールの上で動かなくなるほどでした。でも、オープニングはとにかくパワフルでないといけないと思っていたので、あえて吹雪の日を狙いました。
──吹雪の中を進んでいた何者かが、羊小屋に到着したときには、辺りが暗くなっています。劇中で唯一の暗闇ですよね。
あれは、クリスマスの夜なので。アイスランドの民話では、クリスマスの夜に何か不思議なことが起こるのが通例です。動物が喋り出すとか、そういう伝承がたくさん残っています。物語の大半は夏の白夜のアイスランドで展開しますが、あの夜がすべての始まりなんです。一緒に脚本を書き上げた作家のショーンは、民話をよく知っていて。
──ショーンはアイスランドを代表する作家で、同じくアイスランド出身のシンガー、ビョークの盟友としても知られています。ビョーク主演、ラース・フォン・トリアー監督の映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(00)では劇中歌を作詞し、アカデミー賞歌曲賞にノミネートされました。そんな言葉を巧みに扱う作家が参加した脚本ですが、セリフはかなり削ぎ落とされていましたね。
僕らが最初から決めていたことです。不必要なダイアローグは省き、映像で伝えることができればそれでいいのだと。ものを言わない動物が登場すると、観客は動物の心を読み取ろうとしますよね。同じようにセリフが少なければ、観客は俳優のボディランゲージを読み取ろうと集中するんです。俳優にとっては、難しいチャレンジだったはず。見せかけのボディランゲージでは下手な芝居になってしまうので、役を完全に自分自身としてその場にいなければならないから。その点、ノオミ・ラパスをはじめ俳優陣は素晴らしかったですね。
──この作品はホラー映画として紹介されることもありますが、監督自身はそう思ってないそうですね。監督にとって「ジャンル」とはなんでしょう?
この映画がどんなジャンルだとかは最初から考えていなくて、ただ自分たちが観たい、そして観たことがないと感じる作品を作ろうとしていました。でも、誰もがジャンルは何かと聞いてくるので、「ファミリードラマかな」と答えたりして。僕にとってジャンルという概念は重要ではなく、多種多様な映画を、特定の分野にまとめるその行為が奇妙に思えることがあります。もちろん観客が観たい作品を見つけるために必要なものなんでしょうけど、本来は「映画(cinema)以上でも以下でもない」というのが一番的を射ている気がします。そもそも、この映画を何か恐ろしいものとして観る人がいるのはおかしいなと思ってて。個人的にはびっくりです(笑)。
『LAMB/ラム』

山間に住む羊飼いの夫婦マリアとイングヴァル。ある日、二人が羊の出産に立ち会うと、羊ではない何かが生まれてくる。子どもを亡くしていた二人は、その存在に「アダ」と名付け育てることにする。奇跡がもたらしたアダとの家族生活は大きな幸せをもたらすが、やがて彼らを破滅へと導いていく——。
監督: ヴァルディミール・ヨハンソン
脚本: ショーン、ヴァルディミール・ヨハンソン
出演: ノオミ・ラパス、ヒルミル・スナイル・グズナソン、ビョルン・フリーヌル・ハラルドソン
配給: クロックワークス
2021年/アイスランド・スウェーデン・ポーランド/カラー/シネスコ/アイスランド語/106分/R15+/原題:LAMB
9月23日(金・祝)新宿ピカデリーほか全国公開
© 2021 GO TO SHEEP, BLACK SPARK FILM &TV, MADANTS, FILM I VAST, CHIMNEY, RABBIT HOLE ALICJA GRAWON-JAKSIK, HELGI JÓHANNSSON
🗣️
ヴァルディミール・ヨハンソン
1978年生まれ、アイスランド北部出身。『父親たちの星条旗』(06)、『ゲーム・オブ・スローンズ』シーズン2(12)、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(16)、『トゥモロー・ウォー』(21)など、数々の映画やテレビシリーズで美術、特殊効果、技術部門を担当し、20年以上にわたりアイスランド映画界で活躍。2013年から2015年にかけては、ボスニア・ヘルツェゴヴィナのサラエヴォ科学技術大学で開講されたタル・ベーラ監督による映画製作の博士課程「film.factory」に在籍。ティルダ・スウィントン、ガス・ヴァン・サント、カルロス・レイガダス、アピチャッポン・ウィーラセタクンらの指導を受け、在学中に本作の構想に着手した。初の長編監督作『LAMB/ラム』で第74回カンヌ国際映画祭ある視点部門「Prize of Originality」を受賞。その他の監督作としては、短編映画『Harmsaga(原題)』(08)、『Dawn(原題)』(12)などがある。2022年5月に米大手エージェンシーCAAとの契約締結を発表するなど、今後世界での活躍が最も期待される新鋭監督の一人。
Text&Edit: Milli Kawaguchi