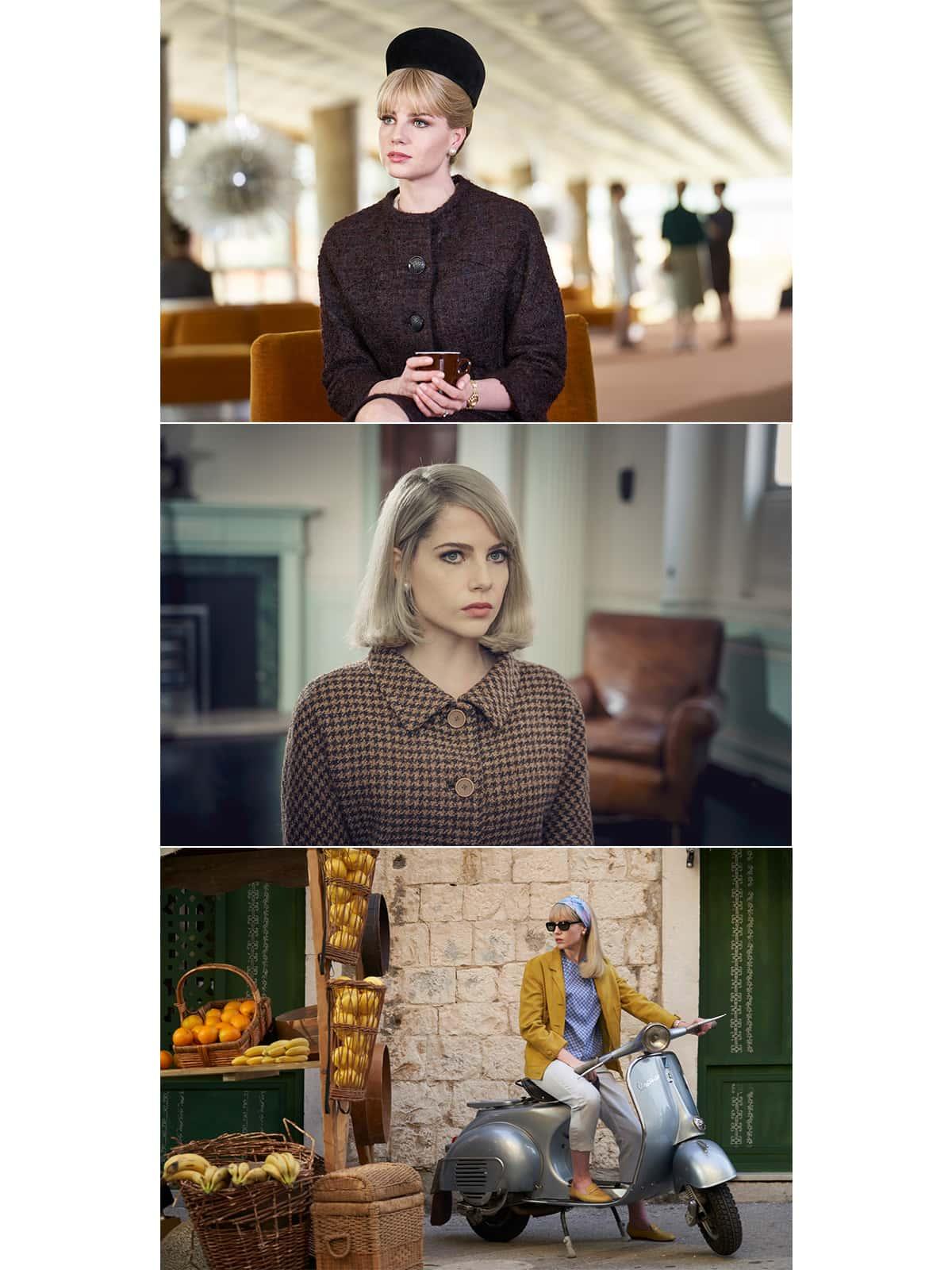34歳で独身、キャリアもないブリジットが、ナニー(子守り)のバイトで6歳のフランシスに出会い、その偏見のないまっさらな友情に支えられていく姿を描いた映画『セイント・フランシス』。コメディのテイストを醸しつつ、生理、妊娠・中絶など、女性の悩みや社会問題に向き合った1作でもあります。脚本・主演を務めたケリー・オサリヴァンさんは、あらゆる実体験を元にこの物語を書き上げていったと話します。
映画『セイント・フランシス』ケリー・オサリヴァンにインタビュー。女性の権利を巡る物語に冠した「Saint=聖人」の意味

──ケリーさんが脚本・主演を務めたこの映画は、34歳で独身のブリジットがナニー(子守り)の短期バイトで、6歳のフランシス(ラモーナ・エディス・ウィリアムズ)に出会い、交流するうちに少しずつ変わっていく一夏の物語です。フランシス役のラモーナさん、自然でキュートな演技が素晴らしいですね。
はい、本当に。オーディションに来てくれた子たちの多くは、まるでディズニー・チャンネルの子役スターみたいに、おませなポーズを取るようにと大人から指導されてきたような感じで。そんな中、ラモーナは当時5歳で最年少でしたが、すごく自然体だったんです。彼女がいてくれたおかげで、私の演技もよくなりました。二人でいると、「そうか、誰かのふりをする必要はないんだ」と思えて。だって、「カット」の声がかかるたび、「この棒でアリをつっついてみようよ!」なんて言うんですから(笑)。
──(笑)。
ラモーナのナニーとして一夏を過ごしたような感じでした。ちなみに今回の脚本は、私自身が以前、実際にナニーをしていた経験も元になっています。
──フランシスは、レズビアンのカップルであるマヤ(チャーリン・アルヴァレス)とアニー(リリー・モジェク)の一人娘。親同士の会話を真似たのか、不意に「女性の体は一人一人違うから、生理用品も合うものを見つけないと」と語り出すところもチャーミングでした。
笑っちゃいますよね!(笑) あのセリフは、私がいつも友だちと「月経カップ使ってる?」「私はタンポンのが合うんだよねー」なんて話している感覚で書きました。
──ブリジットは親子ほど歳の離れた年齢のフランシスとの絆を深める一方で、カジュアルな関係のジェイス(マックス・リプシッツ)との間の予期せぬ妊娠、そして中絶を経験します。中絶を描くにあたり、どういった点に気を付けましたか?
私たちは中絶をあえてライトに描きたかったんです。というのも、これまでの映画やドラマでの中絶の描写は、どれも恐ろしかったから。以前、私も経口薬による中絶を経験したのですが、「クリニックではひどい目に遭うんだろうな」と内心おびえてました。でも実際は、医者から「12時間、気分が悪くなるけど大丈夫?」と言われるくらいで、どうってことなくて。今回はそういった経験をふまえ、「もしパートナーが中絶を経験したらどうすればいいのか」が伝わるように描きたいと思いました。
──たしかにブリジットとジェイスのやりとりは印象的でした。
ジェイスがブリジットのために快適な環境を用意するとか、一緒にテレビを観るとか、背中をさするとか、二人が絆を深める瞬間として、ライトでロマンチックなシーンにしたかったんです。でもそれだけではなくて、ブリジットはトイレで発見した小さな血栓を「これ(が胚)かな?」とジェイスに見せます。この描写も実体験に基づいていますが、罪悪感にさいなまれる瞬間として見せたくはなかった。ただ二人がそれを目にして「なんて奇妙なんだろう」と思い、少し冗談を言い合って、前に進むというふうに描きたかったんです。
──「女性の体は女性のもの」だというメッセージ性がありました。先日アメリカの最高裁は、1973年に「憲法上、中絶は女性の権利である」と認めたロー対ウェイド判決を覆しましたよね。
本当に衝撃的で恐ろしいです。この映画の脚本を書いたのは2018年で、当時はロー対ウェイド判決が覆るなんてありえないと、世界中のお金を賭けてもいいくらいでした。それに2021年、ドナルド・トランプがホワイトハウスを追い出された時点で、そういう日々の不安はなくなるだろうと思っていたんです。だから今回のことはまるで虐待関係から抜け出したのに、「一生君のそばにいるよ」ってストーキングされているような感覚で……!

──この映画でも、ブリジットが昔の同級生の家に行くシーンで、中絶の廃止を訴える「Unborn Lives Matter(胎児の命も大切だ)」と書かれたステッカーが何気なく登場したりします。
それにも実体験が関係しています。少しの間ナニーをしていたある家には、共和党(※トランプが所属している保守政党)の本がずらりと並んでいたので、「今目の前にいるこの子もきっと、私の中絶という選択を認めないんだろうな」と思っていました。自分の生き方を受け入れてくれない人の下で働くのって、本当に気分が悪いです。そういうことは何度もあって、今だってそう。「Anti-Choice, Pro-Life(女性の選択の権利に反対し、胎児の命を支持する)」なんて書かれた看板の前を車で通り過ぎるたび、「ああ、私の選択を本気で批判している人がいるんだ」と思わされます。
──日本でも中絶は、心身への負担が軽い経口薬がまだ承認されておらず、配偶者がいる場合には同意が必要です。この問題において、今なお当事者である女性の思いが無視され続けている中、『セイント・フランシス』を作ったことを振り返ってどう思いますか?
作っておいてよかったと思います。世の中には「中絶は犯罪だ。それを望むあなたには何か問題がある」というメッセージがはびこっていますから。特に今、アメリカで中絶が違法になった州で悩んでいる女性がこの映画を観て、「私の選択は正当だし、実際トラウマになるような恐ろしいことではないんだ」と思ってもらえたらいいなと。
──アメリカにおける中絶の権利の規制には、カトリックや、プロテスタント保守派である福音派の影響が強いといわれています。あえてカトリックの聖人を思わせる『セイント・フランシス』というタイトルを採用した理由を聞きたいです。
私自身はかなり早い段階でこのタイトルに決めていたんです。後に「お堅い宗教映画だと思われてしまうよ」と猛反対されましたが、決して譲りませんでした。というのも、ブリジットに祝福(※神から恵みを授けられること)を与えてくれるのはフランシスその人だから。宗教を信じるより、「人を信じる」ことが大事だと伝える上で、これ以上のタイトルはないということで決まりました。
──ケリーさんにとって「Saint=聖人」という言葉が意味するものとは?
ブリジットは、中絶という選択に自信が持てないだけでなく、何者にもなれずにくすぶっている自分の人生を恥じています。でも子どもという、最も偏見のない存在との友情関係を通じて、自分を受け入れていく。子どもは、あなたが立派な弁護士であろうがなかろうが気にしませんよね。それこそ聖なる態度というか、祝福そのものだと思うんです。

──フランシスのレズビアンの両親の一人、マヤをカトリック教徒という設定にしたのはなぜですか? カトリックは同性愛を認めていませんね。
たとえ宗教に自分の存在を認められていなくても、信仰し続けることができるという、カトリックの別の面を見せたかったからです。「宗教は悪者だ」という単純構造にはしたくありませんでした。マヤを演じてくれたチャーリンもカトリック教徒で、彼女自身の経験も脚本に取り入れています。この映画のQ&Aでは、何度かカトリックの観客が「いつか教会に、LGBTQの権利や同性婚を認めてほしい」という意見を言ってくれました。そういう意見を尊重する描き方ができてよかったなと思います。
──ここまで聞いてきて、この映画の脚本にはケリーさんの実体験や、日々の考えが色濃く反映されているんだとよく分かりました。今回が長編映画での脚本家デビューになりましたが、自分自身について書くって、きっと勇気がいることですよね?
この映画は完全に自伝的な作品というわけではなくて、実体験に少しフィクションを重ねたという感じです。とはいえまあ、最初はこの映画を誰かに観てもらえるなんて思ってなかったので(笑)。脚本を書いている間はすごく自由な気分で、映画が広がるにつれて恥ずかしくなってきました。でも自分の経験を元に書くことで、「心に響いた」と言ってもらえることがよくあるんですよね。想像力だけでは作り出すことができないような、特殊性が生まれるんです。
──以前のインタビューによると、女子高校生が主人公の新作脚本を書いているとのことでした。その企画は今どうなっていますか?
ちょうど今キャスティング中です。撮影は来年の春を予定していて、前回より予算がついたのでワクワクしています。舞台は私の故郷であるアーカンソー州。『セイント・フランシス』みたいに、コメディとドラマが隣り合ったテイストで、私自身についてというよりは、私が出会った人たちについての物語になると思います。(私生活のパートナーで、『セイント・フランシス』の監督でもある)アレックス(・トンプソン)から「このまま自分について書き続けたら、いつか思い出が尽きちゃうよ」と冗談を言われたこともあり(笑)、次は自伝的要素は抑えめで、観察的に書いてみようと思って。
──インスピレーションはどんどん湧いてくるものですか?
ええ。私は常に100の異なるアイデアを持っているような書き手ではなく、数年かけて一つのアイデアを温めていくタイプ。脚本を書くってまだ分からない部分も多いんだけど、直感に従うのがいいのかなって。いつも人への興味からアイデアをスタートさせているせいか、インスピレーションに困ることはない……というか、そう願っています(笑)。
『セイント・フランシス』

うだつがあがらない日々に憂鬱感を抱えながら、レストランの給仕として働くブリジット、34歳、独身。親友は結婚をして今では子どもの話に夢中。それに対して大学も1年で中退し、レストランの給仕として働くブリジットは夏のナニー(子守り)の短期仕事を得るのに必死だ。自分では一生懸命生きているつもりだが、ことあるごとに周囲からは歳相応の生活ができていない自分に向けられる同情的な視線が刺さる。そんなブリジットの人生に、ナニー先の6歳の少女フランシスや彼女の両親であるレズビアンカップルとの出会いにより、少しずつ変化の光が差してくる――。
監督: アレックス・トンプソン
脚本: ケリー・オサリヴァン
出演: ケリー・オサリヴァン、ラモーナ・エディス・ウィリアムズ、チャーリン・アルヴァレス、マックス・リプシッツ、リリー・モジェク
配給: ハーク
2019年/アメリカ/英語/ビスタサイズ/5.1chデジタル/カラー/101分
8月19日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、シネクイントほか全国ロードショー!
© 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED
🗣️

ケリー・オサリヴァン
俳優、脚本家。アメリカ・アーカンソー州ノースリトルロック出身。『セイント・フランシス』が初の長編映画脚本となる。俳優としてはステッペンウルフ・シアター、グッドマン・シアター、ライターズ・シアター、パシフィック・プレイライト・フェスティバル、Ojai Playwrights Conferenceで舞台に立つ。テレビ出演には『Sirens』の2シーズン、映画出演にはインディペンデント映画の『Henry Gamble’s Birthday Party』『Olympia』『Sleep with Me』などがある。ノースウェスタン大学、またステッペンウルフ・シアター・カンパニー付属の演劇学校を卒業。プリンセスグレース財団の劇場向けの奨学金を受け、3Arts Make a Wave(※シカゴを中心にしたアーティスト間の寄付プログラム)の受賞者でもある。
Text&Edit: Milli Kawaguchi




![映画『マイスモールランド』川和田恵真[監督]×嵐莉菜[主演]インタビュー。「いろんなルーツの人を心に思いながら作りました」](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.ginzamag.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F3b56e68912df64e53a52223154c9988c.jpg&w=3840&q=75)