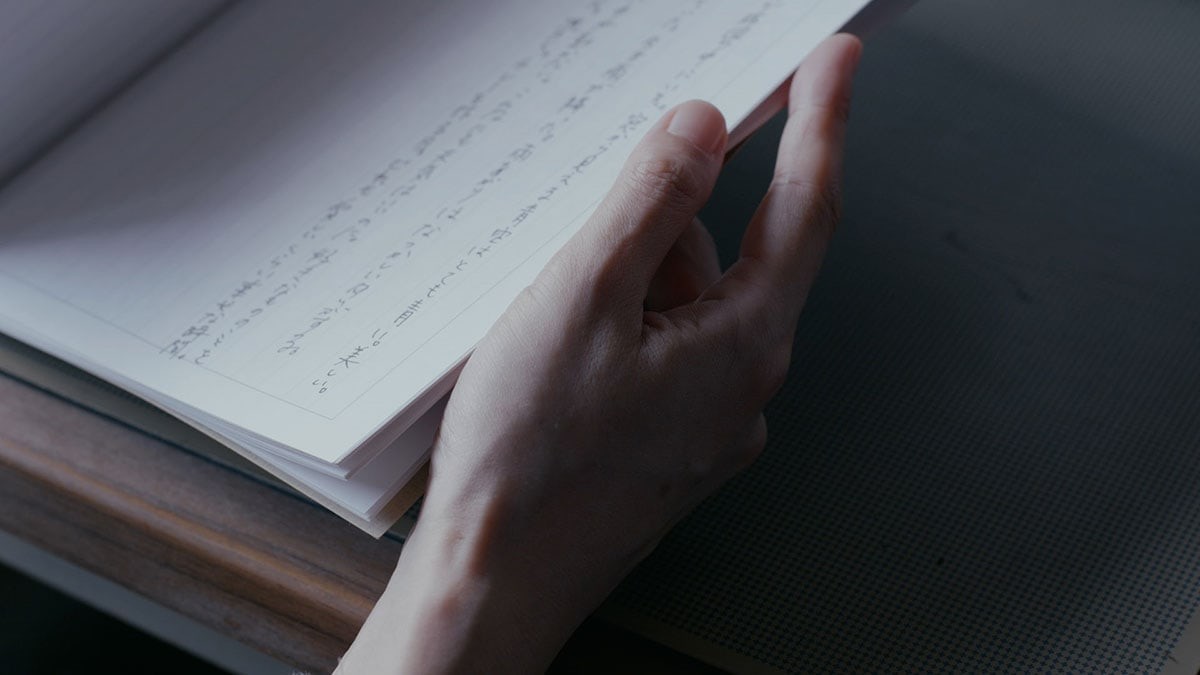青山真治監督が唯一プロデュースした映画『はるねこ』で、2016年に長編デビューした甫木元空監督。バンド・Bialystocksではヴォーカルを務める、多才な30歳の新鋭です。長編第2作『はだかのゆめ』は、高知県四万十町を舞台に、死者と生者が同居する世界をファンタジックに描きます。この詩的な一作は、監督自身の経験が元になっているといいます。
甫木元空監督が語る『はだかのゆめ』。亡き母との時間、移住先の高知の風土…「私」からいかに映画を紡ぐか。

──『はだかのゆめ』の舞台は、甫木元監督が移住し暮らしている高知県四万十町。病気で亡くなったお母さまや、現在も一緒に住んでいるおじいさまと過ごした時間を元に作られた映画です。監督は以前のインタビューで、主演の青木柚さんが撮影現場で少し困惑していたと話していましたが、それはどうしてだったんでしょうか?
柚くんが演じたのは、いつも何事にも間に合わないノロマな幽霊のノロです。困惑していたというのは、この映画にはいわゆる物語がなく、シナリオとして文字化しても分かるような話ではなくて。感情のあり方というか、そこにどう佇んでいればいいのかについて悩んでいたようでした。ただ佇むにしても悲しいのか、それとも別の感情なのか、一人一人のさじ加減で見え方がかなり変わってしまうから。その余白があった分、最初はノロの母役の唯野未歩子さんも、おんちゃん役の前野健太さんも、役者陣はみんな戸惑っていたように思います。
──そういうとき、役者さんたちとはどんなやりとりを?
戸惑うのは普通の生理だし、すべてを理解するのが正解だとも思いませんでした。今回のおもな舞台は高知にある、僕が実際に暮らしている家で、劇中に登場する祖父もそこで生活していて。役者陣が撮影中にその風景を目にする中で、自然と「こういうことかな」という答えを見つけてくれたので、違うときは「違います」と言って微調整するくらいでした。
──唯野さん演じる母は、病気で余命宣告を受けている設定です。そんな彼女が、セミの抜け殻とかカエルとか台風とか、目に入った自然物についてぽつりぽつりと話すのが印象的でした。
僕の母も余命を宣告されてから、ああいう日常的な、ささいなことにいろいろ気がつくようになった気がしたんです。それで、ノロの母には体調が悪そうな人というより、「時間の流れ方や見えているものが周りと少し違う人」でいてほしいなと思いながら、シナリオを書き進めました。だんだん自然と一体になっていく感じというか。
──唯野さんの、聴く人の胸をキュッと締めつけるような、切ない声がまた素晴らしいですよね。
唯野さんの声については、僕も黒沢清監督の『大いなる幻影』(99)などで観ていて感じていたことでした。最後のナレーションも、唯野さんが読み上げることで、この映画のキーになるだろうなと。僕からお願いしたのは、スピードのことだけです。読む速度だったり、歩く速度だったり、ゆったりと生きている人だとは伝えましたが、それ以外はほぼ唯野さん自身が考えてくれました。
──全体としてゆったりと優しい世界観ながら、冒頭の「夜、お盆に遅れたノロがあわてて現世に帰る」シーンは、音の使い方を含め、少し不穏にも感じられたんです。どんな意図があったんでしょうか?
まず木が映り、画面が暗転すると、蝉の音が聴こえてきて、それを消し去るように波の音が響く。そこから抜け出すように、列車の音がだんだん人の吐息の音に変わり、柚くんが走るショットにつながっていく。その後の物語をいかようにも広げられるよう、あえて謎の残る始まり方を選びました。不穏に感じるのは、言われたらそうだなと思います。ちょっと死の香りがするというか。音響の菊池信之さんとは、「虫の音だけはにぎやかに鳴っている映画にしよう」と話しました。自然の音が生き生きと鳴ることが、死者に対する弔いになるんじゃないかと。

──一方で、この映画には懐中電灯や電車の灯りなど、闇夜に浮かぶ光がよく登場します。何か意図はありましたか?
高知に移住して驚いたのが、街灯がほとんどないことでした。夜は本当の闇が訪れるので、出かけるなら懐中電灯は欠かせませんし、電車が走ってくるとちょっと本当に浮いているようにさえ見える。光の一つ一つが気になるし、自然と求めてしまうというか。それは、いろんな心情にも当てはまるなと思いました。
高知では水害が多く、ノロの母が夜、川に向けて懐中電灯を振るのは、ノロが川に流されて亡くなったからです。僕は海のない埼玉県で生まれ育ち、高知に来るまで、灯台の光が360度回転するとは知りませんでした。旅立つ側の海だけに向かって、180度しか行き来しないと思っていたのに、実際は見送る側の陸も照らす感じが面白いなと。移住して感じたそういうことが、各ショットに散りばめられているんだと思います。
──光と似て非なるものですが、火も目を引きました。ノロの母が懐中電灯を振る川を行き交う、漁船の上の火だったり、祖父がカツオを藁焼きにするための火だったり。
灯籠流しをはじめとする、日本の伝統的な弔いの文脈において、火は必ず取り入れたくて。あの漁は「火振り漁」といって、水面上で松明の火を振ることでアユを追い込む伝統的な漁です。最近はほとんど松明からLEDに置き換わっているらしいんですけど、あの区間ではまだ昔ながらの方法が現存していて。映画って、そういう風景を記録する側面もありますよね。それが、自分が母と暮らした家を撮った理由の一つでもあります。
──民俗学的なアプローチですね。
そうですね。以前、青山真治監督(※青山監督は甫木元監督の大学時代からの恩師で、甫木元監督の初長編作『はるねこ』(16)をプロデュースした)から「高知に行くなら読め」と勧められ、民俗学者の宮本常一さんの著書『忘れられた日本人』に出てくる、土佐源氏という馬喰の老人の話を読みました。宮本さんが老人の話を聞き書きしたものですが、その影響で今回のシナリオも、祖父から家族や土地の話を聞いて書き留めるところからスタートしたんです。

──以前のインタビューで、「文字化できるなら映画にする必要はない」と話していたのが印象に残っています。今回の作品も当初は小説として書き始めたそうですが、何がきっかけで映画になっていったんですか?
小説を書いているときから、あの家に母がいた気配を再現するのではなく、どうしたら残せるんだろうと思っていて。文章でも母の人柄と言葉は残せるんですが、まあ音ですよね。音としてどう残せるんだろうなと。そのうちになんとなく、ノロマな幽霊が家の周りを徘徊するという話を考えつき、それは映画じゃないとできないんじゃないかと思いました。
──映画は小説よりも関わる人数が多いですし、パーソナルな出来事をより大きな視野で見つめ直そうとする今回の試みには、きっと合っていたんでしょうね。
たしかに、一個人の悲しい吐露になるのだけは避けたくて。完成までに年数がかかり、思い入れも強い分、作品と距離感を保ちたい気持ちはかなりあったと思います。自分にしか見えていない思いは、映像にはまったく映らない。つまり、映画ってそういうことじゃない。この作品を撮ったり編集したりする中で、改めて学んだことなんですけど。
それと今回は、初めて組むスタッフがほとんどで。僕のパーソナリティを知っている人よりも、よく知らないで高知に来たくらいの人の方が、僕が原案の小説を書いていた頃の「訪問者」の状態に近い。死生観は人によってバラバラですし、どうしたら普遍的な作品になるんだろうと考えたときに、訪問者の視点を取り入れた方がいいと思ったんです。演出面でもこれまでの作品同様、今回も事前に決め込んではいたんですが、現場ですごく変わっていったんです。
──どう変わったんでしょうか?
単純に動きだったり、即興性が強くなるというか。たとえば、風が強くて花や葉っぱが落ちるとか、陽がかげるとか、自然に抗えない部分が多くて。できるだけエゴを通さず、その場で何が一番いいかを考えるようにしました。そういえば、高知の四万十川の本流にはダムがなく、雨が降ると増水するので、「沈下橋」といって、橋が水面の下に沈んでもさしつかえのないように元々造られていて。いろんな災害を経て、自然に抗わずどう共存するかを考えている土地柄なんです。そこから映画作りに影響を受けたのかもしれません。
──今後について考えていることはありますか?
まったく知らない街を舞台に、自分とはかけ離れた人の物語を伝える映画をやってみたいです。『はるねこ』で父の死、今回の『はだかのゆめ』で母の死と、主人公の設定自体は僕自身と変えているとはいえ、自分の経験を出発点にした作品がたまたま続いたので。まだざっくりアバウトですけど、いくつかぼんやり考え始めているところです。
『はだかのゆめ』

四国山脈に囲まれた高知県、四万十川のほとりに暮らす一家の人々。祖父の住む家で余命を送る決意をした母、それに寄り添う息子ノロ。嘘が真で闊歩する現世を憂うノロマなノロは、近づく母の死を受け入れられず徘徊している――。土地に刻まれた時間の痕跡と、幽かな生と確かな死。これは若くして両親を亡くし、高知県で祖父と暮らす監督自身の現在を半ば投影した、親子3代にわたる時間と、その時間の境界線を飛び越えた触れ合いの、そしてそれでも触れることのできない残酷な距離の物語である。
監督・脚本・編集: 甫木元空
出演: 青木柚、唯野未歩子、前野健太、甫木元尊英
音楽: Bialystocks
配給: boid、VOICE OF GHOST
11月25日(金)より渋谷シネクイントほか全国順次公開
©️PONY CANYON
🗣️
甫木元空
1992年生まれ、埼玉県出身。多摩美術大学映像演劇学科卒業。2016年に青山真治・仙頭武則共同プロデュース、監督・脚本・音楽を務めた『はるねこ』で長編映画デビュー。第46回ロッテルダム国際映画祭コンペティション部門出品、ほかイタリア、ニューヨークなどの複数の映画祭に招待された。2019年にはバンド「Bialystocks」を結成。2022年11月30日、アルバム『Quicksand』でメジャーデビュー。映画による表現をベースに、音楽制作などジャンルにとらわれない横断的な活動を続ける。現在、高知県四万十町在住。
Photo: Tomohiro Takeshita Hair&Makeup: Chiaki Saga Text&Edit: Milli Kawaguchi