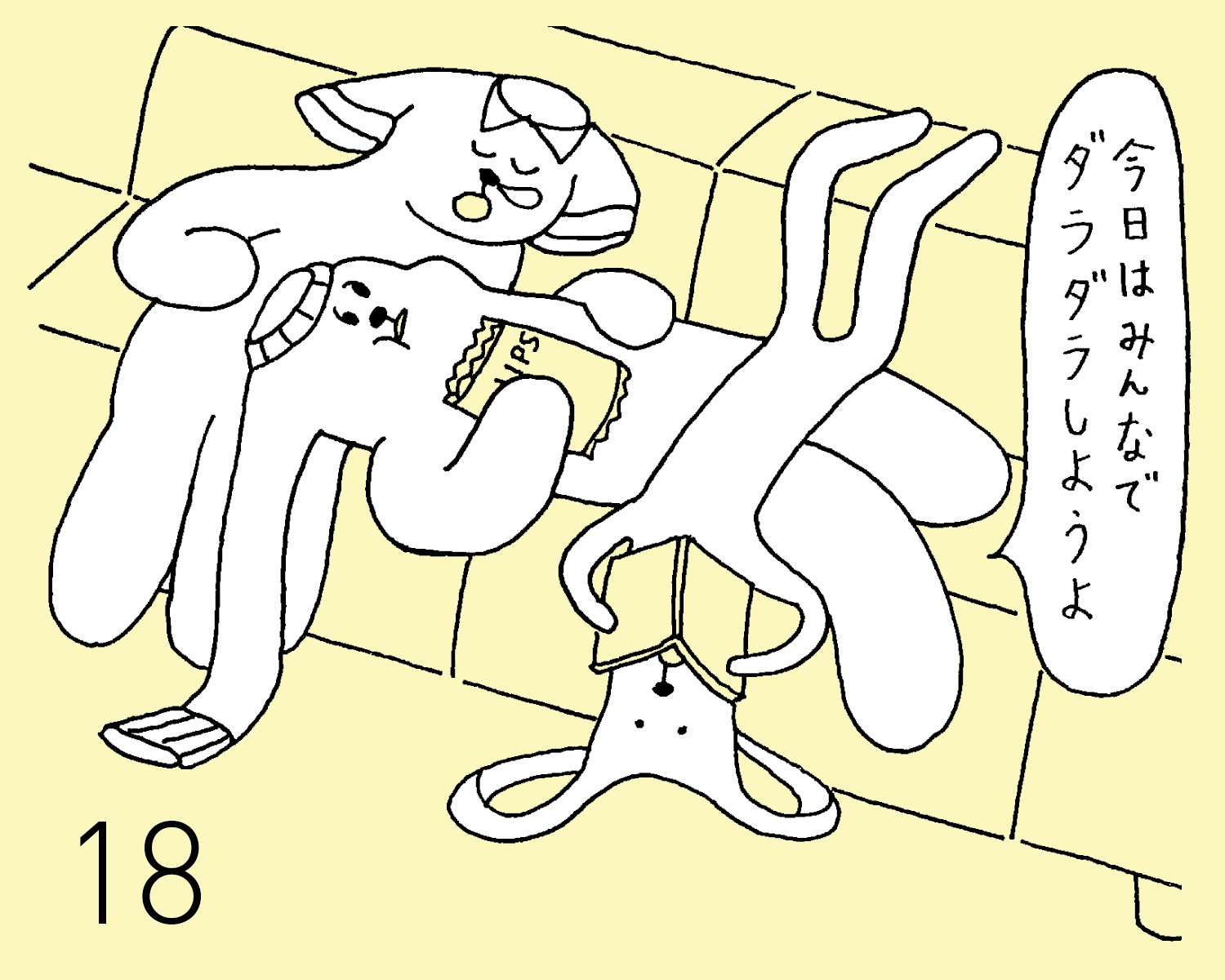6歳のときに両親をHIVで亡くし、叔父夫婦に引き取られた自身の幼少期の体験をもとにした『悲しみに、こんにちは』で長編監督デビューしたカルラ・シモン。彼女の長編2作目となる『太陽と桃の歌』(公開中)は、かつてはシモンの祖父が、現在は父の兄弟らが桃農家を営むスペイン、カタルーニャの奥地にある、アルカラスが舞台。3世代にわたって大家族で桃農園を守ってきたソレ家が、地主から夏の終わりに土地を明け渡すよう迫られ、最後の収穫を迎えることになる。演じるのは、妹役を引き受けたベルタ・ピポをのぞき、オーディションで選ばれた演技未経験のキャストたちだ。それぞれの考えで居場所を守ろうとすることで亀裂が生まれていく大家族の様子が、他人事とは思えない圧倒的なリアリティで映し出される。変わりゆく農家、そして、家族の物語を生き生きと描き、2022年のベルリン国際映画祭で最高賞・金熊賞を受賞したカルラ・シモンが、彼女の映画づくりについて語る。
その土地の人と生活しながら書き、自然な関係を映画にする
『太陽と桃の歌』監督カルラ・シモンにインタビュー

——ロンドンの大学で映画を学ばれていた際、自分たちが実際に経験したことを題材にしたほうがいい、それがまず自分が一番知っている分野であり、自信があるところだからと先生から教えられたそうですが、今回はどういう経験がインスピレーションソースになっていて、脚本にしていく際にどのようなプロセスを経ているのか教えていただけますか?
本作は、自分の直接的な経験を映画にした『悲しみに、こんにちは』とは違って、私の家族が桃農家を営んでいたというベースはありつつも、登場人物に関しては、私の家族とは重ならない部分も多かったんですね。また、私自身も、撮影をしたカタルーニャの奥地にある小さな村では育っていません。夏休みやクリスマス休みのときに家族で集まって過ごしたことはあるんですけど。そういう背景から、脚本を書くにあたり、共同脚本家のアルナウ・ヴィラロと、父親の兄弟の家に住みながら、ふた夏を過ごし、共同生活をするなかで観察をしました。そこでものを書くと同時に、叔父の家族だけではなく、その地域で働いている人たちとも会話をしたり、見守ったりしました。例えば一つエピソードをあげるとしたら、外で騒ぎ声がして、駆けつけてみたら、トラックから大きな木箱が落ちて、収穫した桃が転がってしまっていたり。そういった出来事は映画のシーンにも盛り込みました。自分にとって一番大切にしていたのは、そこの村の人たちが、実際に映画を観たときに、本当に自分の村にいると思えるようなシーンをつくりたいという思いでした。2年間で二度の夏を過ごすのはかなり長いリサーチ期間ではありますが、その時間なしにはこの脚本は書けなかったですね。
——家族の葛藤する姿や関係性が本当の家族にしか思えず、ドキュメンタリーを観ているかのようでした。どうやってそういう環境をつくっていったのでしょうか。
実際、家族単位で人選することをまず試みたのですが、なかなか難しくて、今回の演者さんたちは同じ地域のそれぞれ違う村から集まってきた人たちなんですね。どういうふうに関係をつくっていったかというと、撮影の3、4ヵ月前頃からみんなが一斉に集まれるような大きな家を借りました。みなさんプロの俳優ではないので、それぞれ学校や仕事を終えてから午後に集まってもらって、私もそこへ行って、即興でいろんなワークをしました。まずは、それぞれの共通するエピソードや自分の思い出を話してもらったり、たとえば、今回の映画の筋書きのように、土地の契約書もなく、弁護士もいない状況で、地主から土地を明け渡すように言われたらどうしようか、という具体的なシチュエーションを与えて即興をやってみたり。ただ映画に沿った練習をするだけではなく、普通に一緒に買い物に行ったり、子どもだったら学校の宿題を一緒にやったり、お菓子を焼いたり、普通の生活を一緒に過ごして、徐々に本当の家族でいられるような関係性が生まれていきました。撮影の段階までには、「お父さん」「お母さん」といった二人称が自然に出てくるようになっていました。お互いのパーソナルな部分を知ることができて家族のようになっていたため、もちろん脚本を覚えてはもらうのですが、少し自由度を与えながら撮影に挑みました。
Text&Edit_Tomoko Ogawa