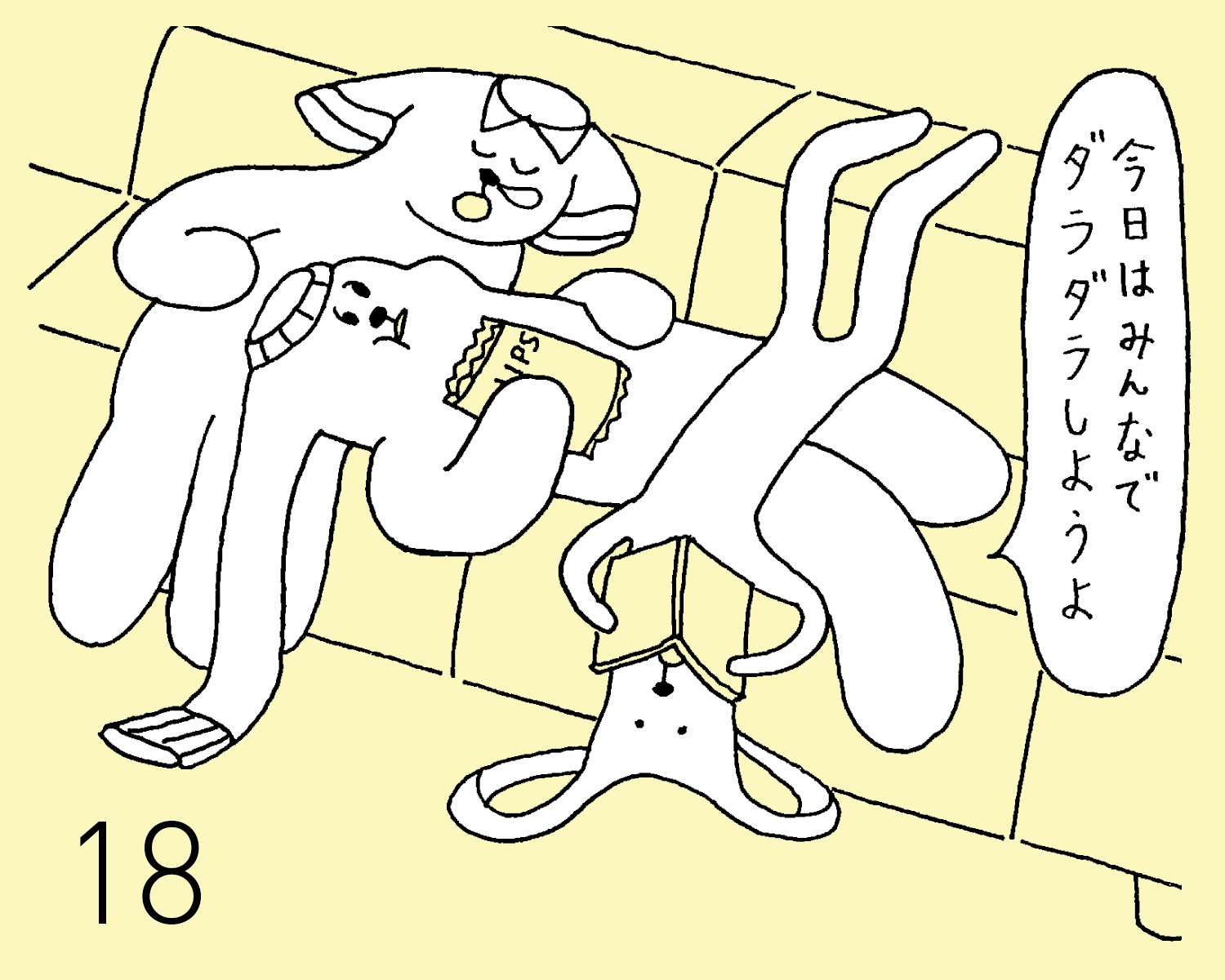前作『あのこと』では、法律で中絶が禁止されていた1960年代フランスで、望まぬ妊娠をした大学生のたった一人の闘いを圧倒的没入感で描いたオードレイ・ディヴァン。彼女が1974年に『エマニエル夫人』として映画化された官能小説を新解釈したのが、『燃ゆる女の肖像』や『TAR/ター』で知られる俳優ノエミ・メルランを主演に迎えた『エマニュエル』(1月10日公開)だ。舞台は現代、ホテルの品質調査の仕事をするエマニュエルが、香港の高級ホテルに滞在し、査察をするなか、自身の内なる欲望を自覚する。第37回東京国際映画祭で来日していた彼女に、観る者をエマニュエルの感覚世界に導く映像制作の秘訣について聞いた。
性的同意と興奮は共存できることを示したかった
『エマニュエル』監督オードレイ・ディヴァンにインタビュー

——1974年に映画化された『エマニエル夫人』は、女性の性や欲望の解放を象徴する一方で、現代の視点から観ると、女性の客体化やポストコロニアリズム的な問題を内包していて、楽しめる内容ではありませんでしたが、本作はエマニュエルという人物について新たな解釈を与えてくれるものでした。
もちろん、それは私も感じたことです。
——日本の公開時のタイトルは『エマニエル夫人』となっているのは知っていました?
知りませんでした。(「マダム・エマニュエル」と訳され)それは変ですね、若い女性という設定なのに。
——誰かの妻という意味の夫人だと思います。当時はその方が魅力的に響いたということなのかもしれないです。
それはもっと最悪ですね(笑)。
——そういう意味でも偏見がありましたが、本作でキャリアや自分の欲求を追い求める自身として登場するエマニュエルを観て、すごくしっくりきました。あなたの映画は、映像とサウンドを通して、主人公のまなざしを観る者と深く共鳴させる力があると思いますが、どうやって主人公の経験を自分もしているように映画を構築させているのでしょうか?
各部門と正確に話し合いをしますが、香港に到着したとき、エマニュエルの感覚についてとても長いミーティングをしました。それぞれの視点を持って、撮影のロラン・タニーや音響担当やみんなでどのようにするかを一緒に考えました。一方がサウンドでその後にイメージと切り離すのではなく、クルーとしてどれだけ一緒にそれを実現できるかが重要で。例えば、エマニュエルが布に触れているとき、ドアを開けたときに、観ているみなさんがエマニュエルになりきって、彼女の表情、香港の街の音や音楽を感じてもらいたいんです。
——スタッフとの信頼関係があるからこそできるという部分も大きいですか?
ほとんどのクルーのスタッフとは既に一緒に仕事をしていますし、10年以上の付き合いになるので、例えば私がどのようにサウンドに取り組むのが好きなのか、ときに感覚を呼び覚ますためにノイズを誇張することもあることを知っているんですよね。お互いのことをよく知っているので、本当に助けられています。回数を重ねることで、オーケストラとしてコラボレーションする方法をもっと知ることができる。もうひとつに、私たちはオーケストラのように仕事をしているので。撮影が終わるたびに、俳優や技術者のみんなにモニターの前に来てもらって、「これ、変えていいよ」と言うんですよ。むしろいいアイディアがほしいので、すぐ取り入れます。

Photo_Mayumi Hosokura Text&Edit_Tomoko Ogawa