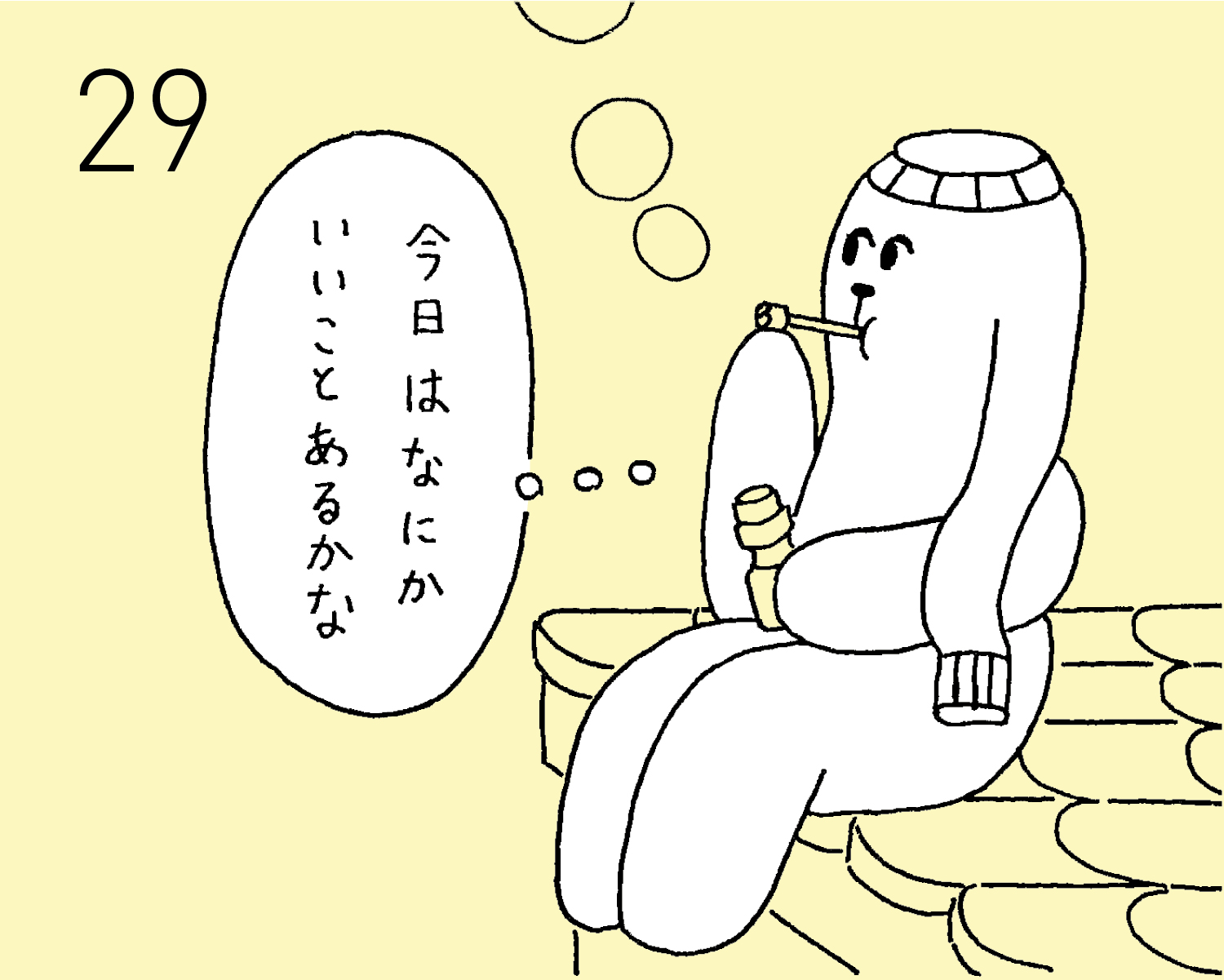世界的な観光地であり、女子の永遠の憧れ、京都。この街にお引越ししたライターYが、ストリートから神社仏閣まで、初心者目線で見つけた気になるモノやスポット、イケてる人たちなどなど、フリースタイルでご紹介します。前回は〈HOSOO LOUNGE〉。
ライターYの京都通信 チャリで回って見つけた素敵なモノ Vol.17
京焼の奥深き世界 その1_〈森里陶楽〉の器たち

京都に住みはじめて早くも3年半。大好きな場所や、お気に入りのモノも増えました。それでも、街を歩くと新たなインスピレーションが絶えないのが、この街の懐の深さ。例えば、清水焼で知られる“京焼”が、私の目下気になる存在。最近は海外からのゲストをアテンドする機会も増えたのですが、古都ならではのモノ作りには彼らも興味津々で、「京都のCeramicを見たい」とリクエストされることもしばしば。仕事も兼ねて、もっと勉強したい欲がムクムクと!
そこで今回は数ある窯元の中でも特に素敵だなと思っている〈森里陶楽〉を深堀り。工房にお邪魔して、アレコレ教えてもらいました。

私の〈森里陶楽〉との出会いは、毎年8月に開かれる「五条若宮陶器祭」でした。フォーシーズンズホテルに通訳をしたゲストをお送りしてからの帰り道、五条通の若宮八幡宮の境内にずらりとストールが並んでいるのを発見。なんとなく入ってみたところ、まんまと一目惚れ。京都の焼物というと茶席で使う抹茶碗のような、シックなデザインのイメージが強かったのですが、〈森里陶楽〉の器は、その固定概念を覆すデザインなのです。例えば、ほんのりとヨーロッパを感じさせる繊細な柄使いと、使い込んだような風合いが感じられるパープルがかった色合い、ところどころに彩色された緑や黄色のアクセントといった具合。結局お祭りに3日間通って、お皿やカップなど諸々お買い上げしたという次第でして。

熱が冷めやらぬまま後日、工房を訪問させていただくことに。お話を伺ったのは「陶楽」こと森里秀夫さん。森里さんによると、京焼の歴史は異文化との交流と共にあるのだといいます。日本では茶道が広がった江戸時代初期、茶器の需要の高まりから陶器や磁器が広く作られるようになりましたが、茶の湯の中心地といえば京都。ですがその生産地は備前や瀬戸、薩摩など全国各地に分散していたため、発注や運搬など煩雑なやりとりが必要でした。そこで、多くの茶器が実際に使われる場所である京都で生産も!と、この地で盛んに作られるようになったのですって。
さらにいうと、実は京都は意外にも焼き物に使う土の資源が乏しく、近隣エリアから土を取り寄せて作られてきたという背景も。異なるカルチャーが混ざり合い、交差しあって、今日京焼と呼ばれる器が出来上がったのです。

工房の片隅にろくろが置かれていて、ここで森里さんが成形します。一日に50から60もの器を作るのだというからすごい。土は産地の異なる3種類を取り寄せ、ブレンド。歯切れのようにカットした部分も、また捏ねて再利用する。改めて考えると、陶器作りってとてもサステナブルなのですね。
Photo and Text: Hiroko Yabuki