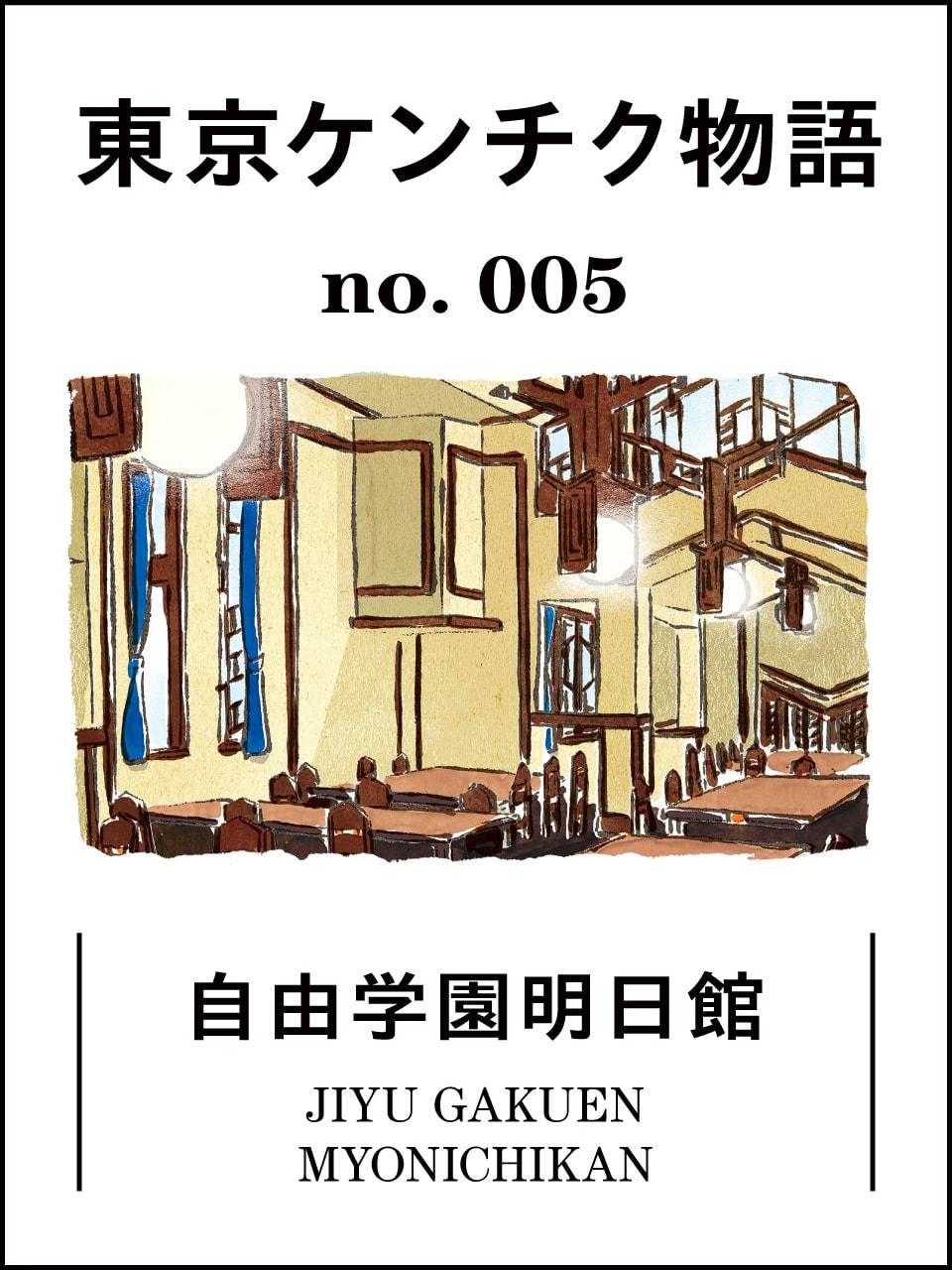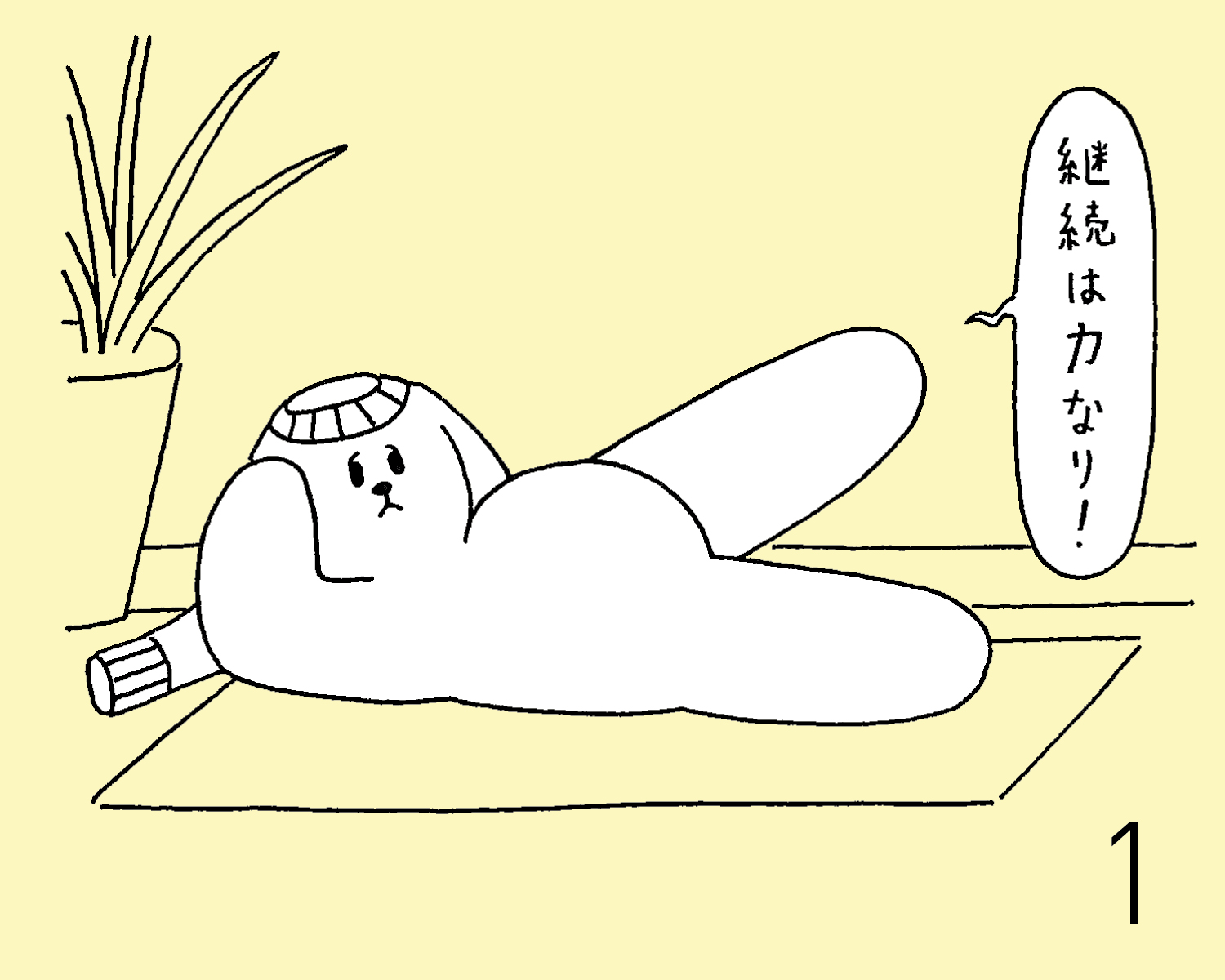世界各国からの見学者も絶えない「中銀カプセルタワービル」が今回の目的地。丸窓のカプセルが積み上がるひときわ変わったこのビル、「50年前につくられた未来」なのです。
過去の未来を目撃せよ!中銀カプセルタワービル:東京ケンチク物語vol.9

NAKAGIN CAPSULE TOWER BUILDING

銀座と汐留のちょうど中ほど。高層ビルが立ち並び、首都高がぐいっとカーブを決めるそのすぐ横に、かなり変わった風貌のその建物はある。丸い窓のついた小ぶりのカプセルを空高くまで積み上げた、その名も「中銀カプセルタワービル」。高度経済成長期から今世紀の初めにわたって長く活躍した建築家・黒川紀章による、1972年完成の怪作だ。
晩年に手がけた六本木の「国立新美術館」も知られる黒川だけど、最大の功績はやはり「メタボリズム」と呼ばれる建築思想を広く世界に知らしめたこと。1950年代から70年代にかけて、時の若手の建築家やデザイナーが意欲的に展開したこの思想、〝新陳代謝(メタボリズム)〟との言葉の通りに、社会の変化に伴って、建物も生物のように新陳代謝し、変化していくべきものだという考えだ。
……え、建物が変化するの?どうやって?と思うでしょう?その答えのひとつがこの「中銀カプセルタワービル」なのだ。遠目からだと積み重なっているように見える各カプセルだが、近くで見ると各カプセルの間には隙間があるのがわかる。実はこれ、中央の鉄筋コンクリートの塔の部分に突き刺すようにして固定してあるのだ。だからカプセルは交換可能。必要に応じて減らすこともできるし、同じようなコンクリートの塔を建てれば増殖も可能。生き物みたいに成長できるというわけだ。カプセルはそれぞれが住居ユニットで、高さ約2・5×幅約2・5×奥行き約4m。片側の壁面いっぱいに棚やラジオが作りつけられ、小さなバストイレがついた最小限の住空間だ。
実際には建物の完成以来ほぼ半世紀、カプセルの交換は実現していないのだが、できていればかなり面白かっただろうことは想像に難くない。カプセルひとつを取り外して、車で引っ張ってグランピングに出かけるとか(黒川自身、同じような構想を持っていたらしい)、いくつかのカプセルをまとめて所有し、ベッドルーム、書斎、リビング、バスルームなど機能もインテリアも変えて使うとか……。「いろんな住み方・使い方ができる」は今でさえ家を建てるときに使われるキーワード。暮らし方や社会の変化に寄り添ってくれる建物ができるとしたら。建築家の描いた未来のかたちが、この建物にはある。