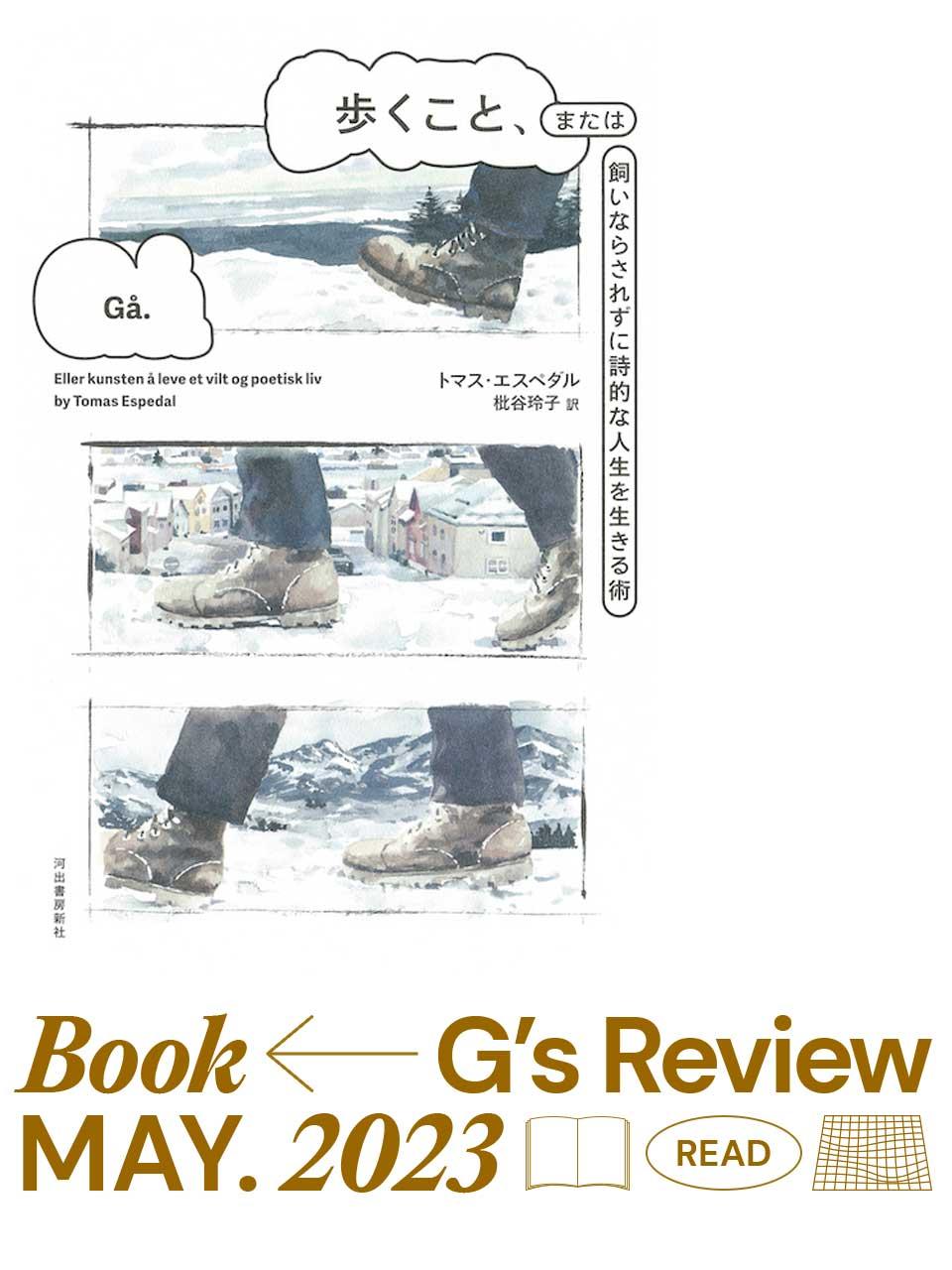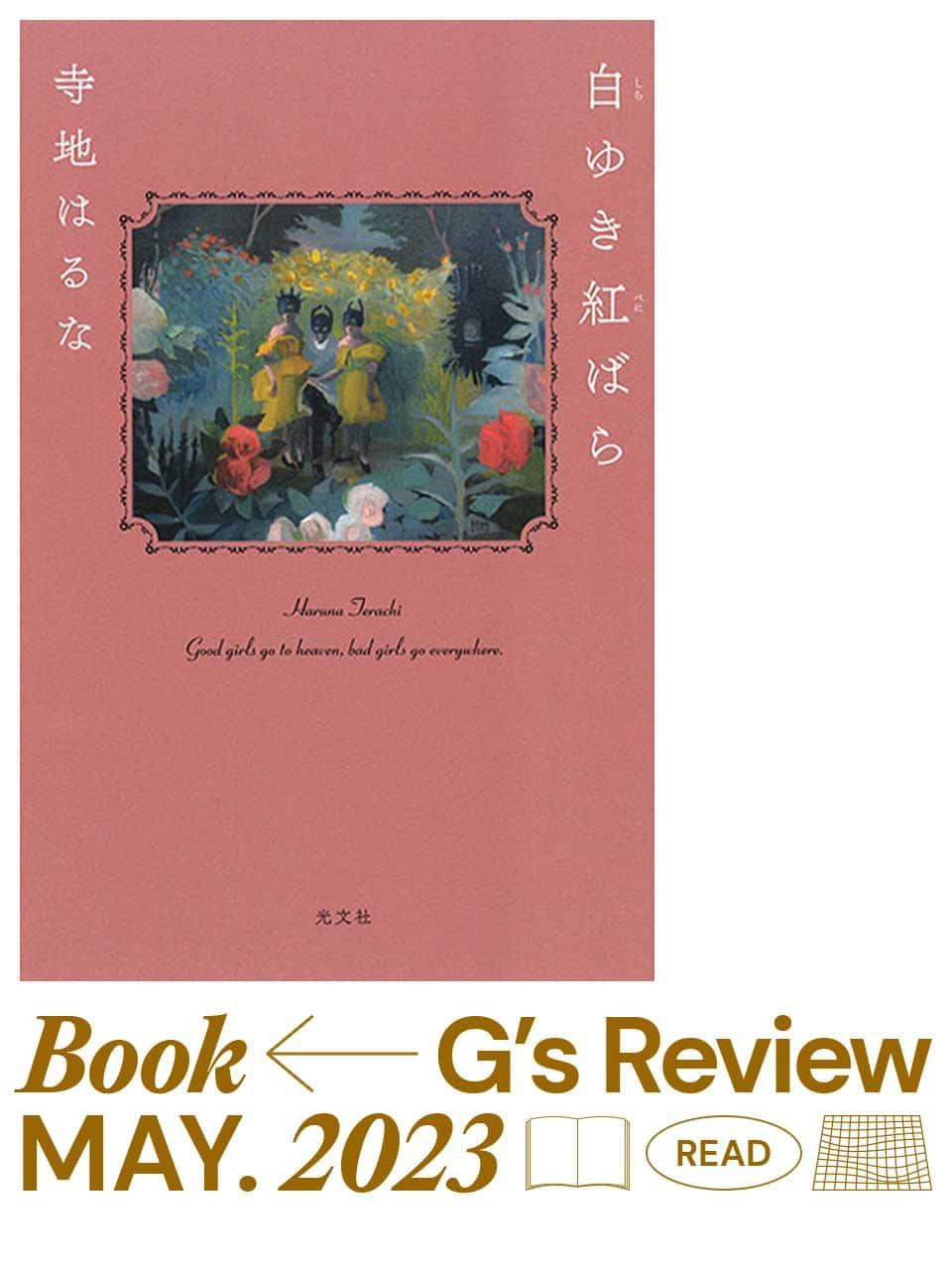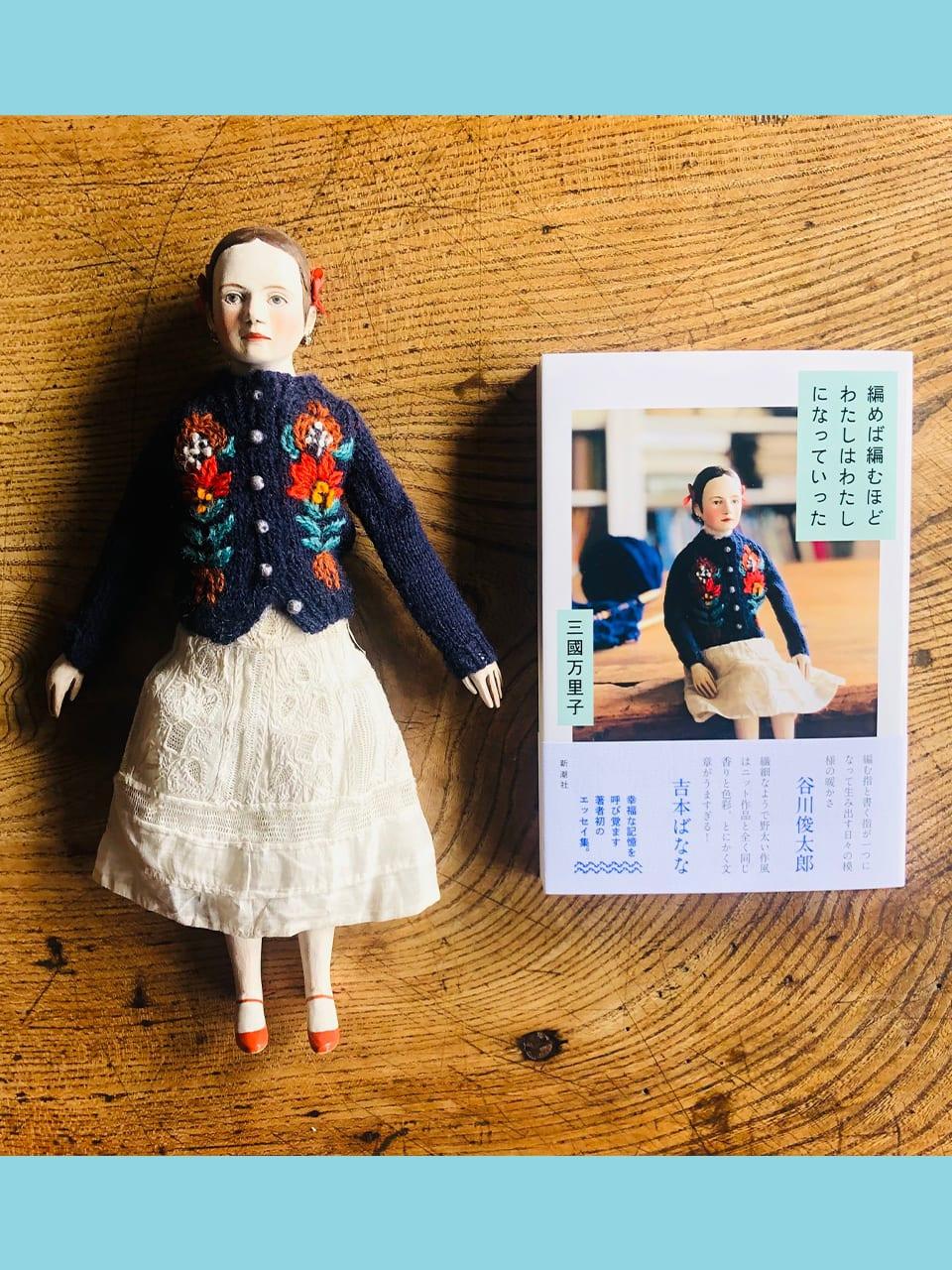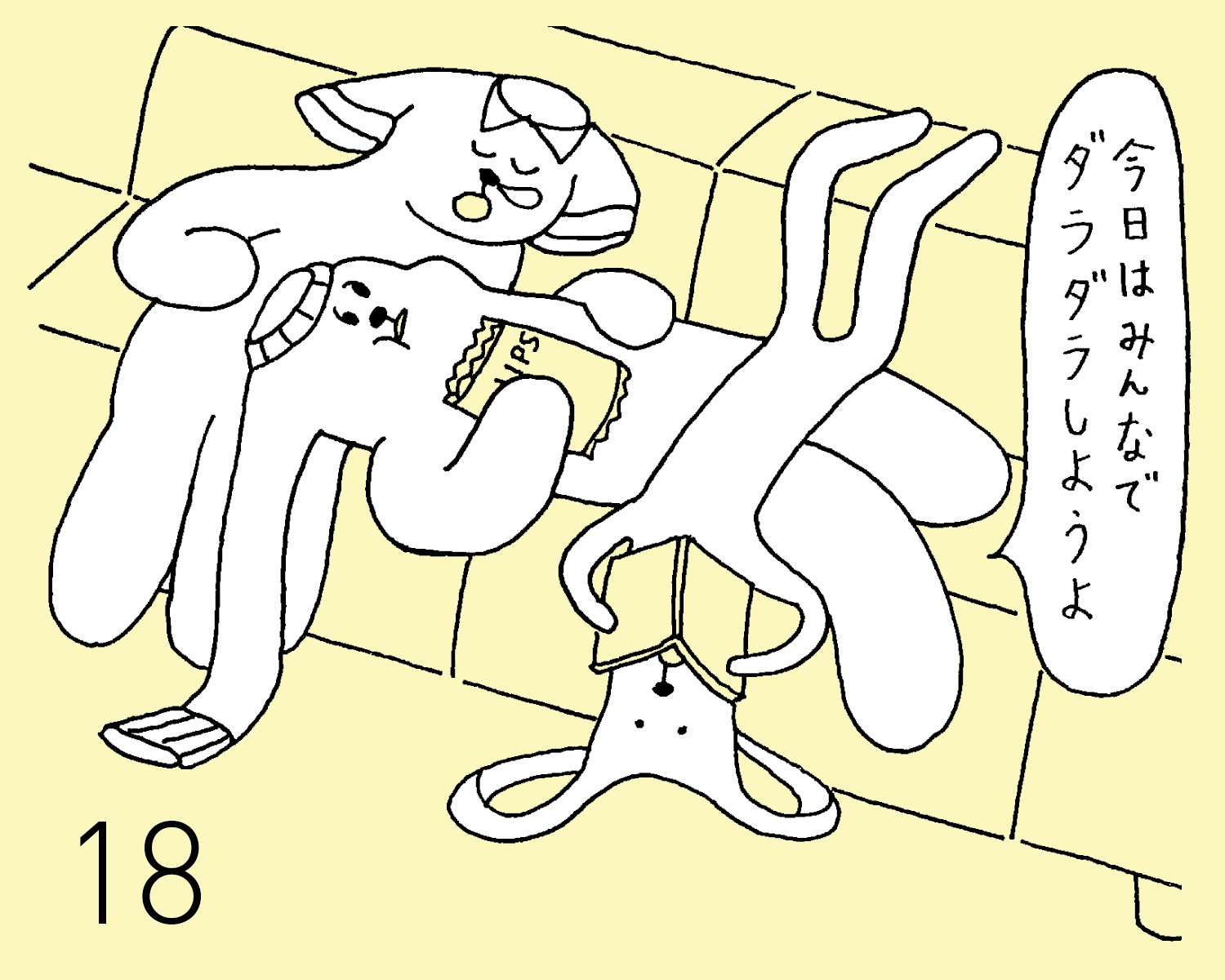幼い日々に喘息の苦しみを分かち合った、亡き弟を思う姉の視点から語り出される小説「息」。三島由紀夫賞にもノミネートされたこの作品は、2020年に作家デビューした小池水音さんの3作目にして、初単行本の表題作だ。世界の繊細さと脆弱さに目を向け、静かな息遣いに耳を傾ける。小池水音という作家は、どのように世界を見つめ、小説を生み出しているのか。
小説家・小池水音が耳を傾ける、世界の息遣い

──『息』の単行本発売、おめでとうございます。デビュー作「わからないままで」、2作目「アンド・ソングス」に続いて、今作も“喪失”を主題に選ばれていますね。
「息」では、自死を選んだ春彦の家族が、弟や息子を失ってからの10年をどう過ごしてきたのか、10年を経たからこそ感じ得るものを書こうとしています。登場人物たちはそれぞれの想像力、それぞれの記憶を持って死者にアクセスし、届こうとするけれど、決して届かない領域もある。大学生のころに姉をなくした私自身にとっても切実なものとして、自分の中にある石をひとつずつどかしていくように、3作かけてようやく「息」を書くことができたという思いがあります。
──「息」には、喘息の苦しみが記憶として、現在のこととしてたびたび描写されます。体の記憶はどのように取り出され、小説の言葉に置き換えられたのでしょうか。
私も小児喘息を患っていたんですが、大人になってからは発作は起きていないので、幼いころの記憶を探り、実際に呼吸を止めて酸素が欠乏していく感覚を鮮明に思い出しながら書いていきました。過去を回想すること自体には懐かしむ感覚のようなものがあるんですが、苦しみは苦しみとして引き出すしかない。小説の他の部分とは成り立ちが違っていたかもしれません。
──苦しみという個人的な体験や感情は、小説の言葉として外に出されることで、形や関係性を変化させるのでしょうか。
たとえば喘息の苦しみにしても、幼いころは「苦しい」としか言いようがなかった。それが、気管支が膨れて狭まっていき、と言葉にしていく過程で、完璧ではないにせよ苦しみに輪郭が与えられて、それを扱えるようになっていったと思います。内発的な動機から自分のことを掘り下げていく過程で、深いところで、社会の、多くの人にアクセスし得る何かが見つかるといいなと願いながら小説を書いています。

──1作目、2作目とは違い、今作では登場人物に春彦や環などの名前がつけられていますね。
この作品では、一人称視点の登場人物の、ある季節を描き切りたいという目標がありました。名前をつけることにはまだ慣れていなくてなんとなく気恥ずかしくもあるんですけど…作品に馴染むいい名前が見つかったので書けました。鍵括弧のセリフも以前より増えて、1作目、2作目よりはリーダビリティが上がっていたらいいなと思います。姉の環がみる春彦の夢の描写を章ごとに挟んだことも、私にとっては新しい挑戦でした。
──走る列車のなかで弟に再会して、隣に座ったり、声をかけたり、抱きしめたり。夢のパートが繰り返し現れて、小説が豊かに奥行きを増していくのを体感しました。
ああいった夢はここ10年ほど繰り返し見ていて、それくらい自分にとって強いイメージなんだろうと思います。いつもは描写を淡々と重ねるようにして小説を書いていくんですが、夢の場面はよりポエティックですね。一人称性にもう一歩踏み込んで、春彦に消えてほしくないと願う環の感情も率直に書くことができました。案外これは、自分にとって新しい文章の鉱脈のようなものかもしれません。
──「息」ではガネットという海鳥が、併録の「わからないままで」では紙飛行機が登場して、文字でしか読んでいない、目にしていないはずの景色が強く印象に残ります。
自分でも気づかないうちに飛ぶものに惹かれているんですかね。「わからないままで」の紙飛行機は、小さいころに父親とよく遊んでいたもので、ガネットは別の話のために調べていたのがふっと小説に入ってきたんです。こういった、人とかかわっているけど人そのものではない、物の動きを通してこそ表現しうる感情を書いていきたいです。

──描写の美しさや文章の端正さにも心を掴まれますが、小説の言葉としては、特にどんなところにこだわられていますか?
整頓された言葉が好きですね。たとえ描く対象が美しくないものであっても、それを文章に仕立てる時には文章的な美が宿り得るでしょうし。重たい文章が来たから次はこう、というリズム、句読点の位置、母音の繋がりなどを小説を書くときの主動力にしているというか、定理として自分のなかにあると思います。それと同時に、整頓された文章を崩していくことで生まれるものももちろんあって、「息」で父親が酩酊した状態で口にする言葉など、そこにしか宿らないリズムも見つけて、書いていきたいです。
──特に大きな影響を受けた本や読書体験は?
新潮クレスト・ブックスがすごく好きなんです。スマトラ沖大地震で家族全員を失ったソナーリ・デラニヤガラの『波』など愛読書がたくさんあります。他言語で書かれたものを、原書を尊重した、整頓された形で伝える翻訳書をまとめて読んできたことが、感性や文章的親切心と言うべきものを磨いてくれたと思っています。小説によって示すべきものがあり、そのために奉仕する言葉があって、時にはそれが遊び始めるというところまでいけるのが理想ですね。もうひとつ、小中学生時代に“整頓された文章”に触れた原体験を挙げるなら『こち亀』も…。
──えっ!? 『こちら葛飾区亀有公園前派出所』ですか!?
はい。本ではなくマンガですけど、2010年代までに起こった流行をヴィヴィッドに、たまごっち、ベーゴマ、VHSとベータマックスなど、それ自体を知らない読者にも伝わるよう整理しつつ描かれているんですよね。小学生のころに『こち亀』100数十巻を繰り返し読んだという、広い意味での言語体験から、人に伝えるための表現をたくさん学んだ気がしています。

──今後の作品について教えてください。
9月1日から公開される、山田洋次監督の映画『こんにちは、母さん』のノベライズ本が7月に発売される予定です。
──山田洋次監督の作品はもともとお好きなんですか?
『男はつらいよ』はもちろん、監督作品は一作残らず観てます! 寅さんシリーズは金字塔と呼ぶべき素晴らしいシリーズだと思うんですが、幸田文さん原作の『おとうと』のような作品でも、人と人との哀しく、やるせない、しかし愛おしい距離について克明かつ面白く表現なさっていて憧れています。もうひとつ、学生時代アルバイトしていた幼稚園を舞台に、これから育っていく子供という存在を書きたくて、いままさに悩みの日々を送っています。どうなるかまだわかりませんが、完成したらよろしくお願いいたします。
Photo:Satoshi Nagare Text:Hikari Torisawa