愛する恋人を突然失い、その悲しみを誰にも共有できないとしたら──。喜びや喪失、葛藤といった若者の揺れる感情をまっすぐ描いた映画『突然、君がいなくなって』(2025年6月公開中)。第77回カンヌ国際映画祭ある視点部門のオープニング作品に選ばれた本作は、アイスランドで繰り広げられるある夏の1日を凝縮した80分の物語だ。16ミリフィルムで捉えた幻想的な光や街並み、観る者の心を揺さぶる映像美の裏側とは。監督を務めるルーナ・ルーナソンに作品への思いを聞いた。
ルーナ・ルーナソンが喪失と再生を描く、映画『突然、君がいなくなって』
アイスランドを舞台に映し出す、夏の儚き美しい1日

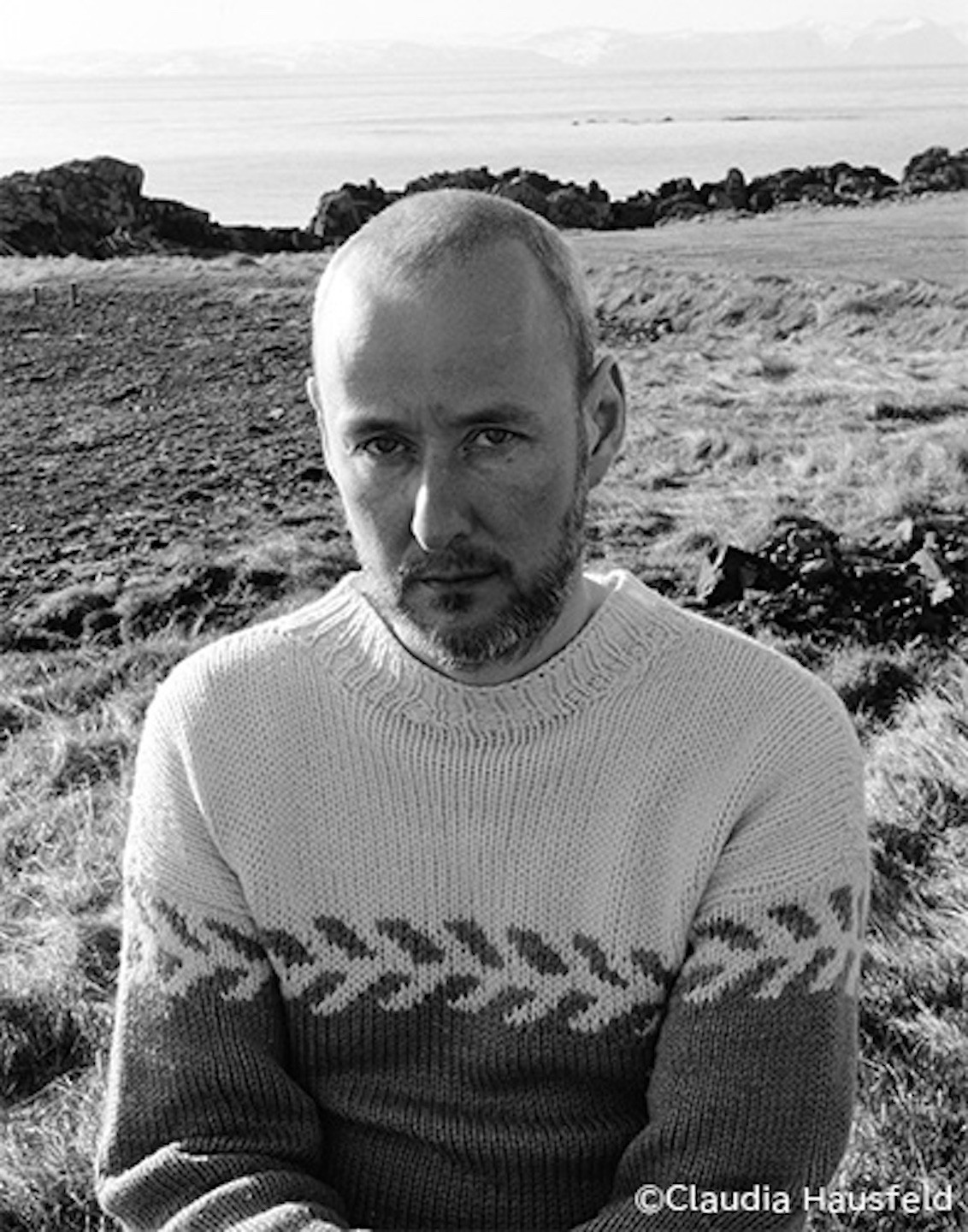
──本作は「喪失」をテーマに描かれ、普遍的なメッセージを持っていると感じました。台詞だけではなく、ただ映像を観ているだけでそのメッセージが伝わってくるということに感動しました。
私は映画には大きく3つの語りの方法があると考えています。ひとつは「感情を伝えること」、次に「物語を伝えること」、そして「音や映像で伝えること」。この3つをバランスよく駆使して、ただ台詞や文字に頼るのではなく、作品そのものの力で観る人に語りかける映画を目指したんです。
──「人生のグレーな領域」に興味があるとお聞きしましたが、その感性はどこからきているのでしょう?たとえば、子ども時代の経験や、読んできた文学などでしょうか?
一番の影響は、やはり「人生そのもの」だと思います。私は3人の姉と母に囲まれて育ち、今は妻と娘と暮らしています。映画制作の現場でも、主要なキャラクターはもちろん、撮影監督、美術、プロデューサーなど、中心にいるのは多くの女性たち。感受性豊かで繊細な人々と一緒に育ち、共に仕事をしてきたことが、自分自身の感性や視点を形作っているのかもしれません。
すべての物語は、ある意味で、すでに語られてきたものです。だからこそ私が大切にしているのは、「その物語をどう語るか」、そして「どこに目を向けるか」。人生はいつも明るいわけでも、ずっと暗いわけでもなく、そのあいだを行ったり来たりしている。日常の中には、はっきりとは言い切れない曖昧で、グレーな領域がたくさんあります。
たとえば、この映画では、若者が人生で初めて大切な人を失い、深い悲しみを経験します。でも、その中で彼女たちは、美しい瞬間に出合い、心を動かされることもある。人生は決して白か黒かで割り切れるものではありません。そのあいだにはたくさんの色がある。グラデーションになって重なり合った色彩のように、人生を豊かにしていると思います。
──本編でもそのニュアンスがアイスランドの夏の光と結びついているように感じました。また、カメラのレンズと主人公ウナとの距離がとても近いのが印象的です。でも、近すぎて侵略的にはなっていない。その距離感はどのように決めたのですか?
シーンによってカメラの視点は変わりますが、大きく分けると2つのスタイルがあります。一つは、ウナと少し距離を取って観察するような視点。もう一つは、彼女にぐっと寄り添い、感情や内面をとらえる視点です。この2つを場面に応じてバランスよく使い分けています。
特にこだわったのは、多くのシーンをワンカット(長回し)で撮影していることです。こうした手法を選んだのは、「時間」をリアルに感じてほしかったからです。編集でカットを細かく入れると、どうしても“作られた物語”であることが際立ってしまう。でも喪失の初期段階というのは、時間が濃密に、ゆっくりと流れるもの。その感覚を観客に体験してほしくて、あえてカットを最小限にとどめ、シーンの中で自然な時間の流れを作るように工夫しました。
──でも、決してウナに対して意地悪じゃないし、敵対的でもないと思いました。
そう感じてもらえて嬉しいです。というのも、普通は自分自身に対して敵意を持つことってあまりないですよね。もちろん、そういうことが起きる場合もあるけれど。私はこの映画に登場する人物たちを、みんな愛しているんです。まあ、1人だけ例外がいて……あるシーンで車を運転している男だけは、ちょっと別ですけど(笑)。
──私も同じように感じました。また、冒頭のトンネルでの事故のシーンと、終盤の夕日のドローンショットに、どこか共通するものを感じました。なぜあのような構図にされたのでしょうか?
冒頭ではカメラが下を向いていて、炎のような火の玉をとらえています。一方でラストは、カメラが上を向いて太陽を写している。火の玉は命を奪うもの、太陽は命を照らすもの。そうやって対比させることで、物語を枠で囲むような「視覚的な並行構造」を作りたかったんです。似ているようでいて本質的には異なる要素を並べることで、物語の意味をより深く伝えられると思いました。
映画全体に、多くのメタファーを仕込んでいますが、それに気づいてもらおうとは思っていません。ただ、たとえば冒頭にしか登場しないけれど、物語に大きな影響を与えるある若者がいます。彼の存在を象徴する色として、夕日のような黄色からオレンジを設定しました。
2人の若い女性がバスルームで会話するシーンでは、窓に黄色のガラスを使っていますし、彼が通る道もオレンジ色に染めています。彼の気配を、視覚的に現前させるための工夫です。
物語が進むにつれて、黄色からオレンジの色味を少しずつ取り入れていくことで、彼の存在を静かににじませていきました。でも、それをあからさまにはしたくなかった。観客が「なぜだかわからないけれど、心に残る」と感じてくれるような、そんな描き方を目指したんです。
──ウナと恋人のディティの服装や髪型が似ていて、どこか双子のようにも感じられました。ヘアメイクや衣装はどのように決定されたのですか?
脚本の初稿では、髪型まで細かく書いていました。でも、それが絶対の正解というわけではありません。俳優の顔立ちや体格によって、似合うスタイルは変わりますから。ウナを演じたエリーン・ハットルはとても小柄で華奢な方。彼女が演じるキャラクターには、パンセクシュアルで性別に縛られないジェンダーフルイドな一面もあります。それは、この映画の舞台であるアイスランドのアートシーンとも重なっています。登場人物たちの服装やスタイルも、実際の美術学校で見かけるようなリアルな雰囲気を意識して決めていきました。
また、エリーンは目元やあごの筋肉の動きで感情を繊細に伝えられる俳優なので、その微細な表現を引き出しつつ、彼女の持つマスキュリンな魅力も活かしたかった。だからこそ、強い赤髪などは避けて、外見はあえてミニマルな印象にしています。こうしたビジュアルの調整は、監督、俳優、衣装デザイナー、ヘアメイク、チーム全員の密な連携で生まれたものなんです。
──ウナ役のエリーン・ハットルと、クララ役のカトラ・ニャルスドッティルは顔立ちがよく似ていると感じました。キャスティングの際に、そうした点を意識されたのでしょうか?
たしかに、肌の色や髪のトーンが似ているので、外見が重なって見えるのかもしれません。でも実のところ、キャスティングの時点では特に意識していませんでした。脚本を書いていた段階では、2人はまったく異なる外見のキャラクターとして描いていたんです。
一般的には、登場人物の見た目ははっきり違っていた方が観客にとって識別しやすい、というのがセオリーですよね。でも私はそれよりも、「その役に本当にふさわしい俳優かどうか」を重視しています。髪の色や身長、体格といった外見よりも、その人がどれだけキャラクターの感情を体現できるか。もし必要であれば、脚本の方を変えることも厭いません。
映画制作って、まずは脚本という“宇宙”を作るところから始まるんですが、実際に撮影が始まると、そこからまた別の“宇宙”が生まれていくんです。だから私は、常に変化し続ける映画というものに対して、自分のビジョンも柔軟でありたい。あまりに固定観念にとらわれてしまうと、作品の成長の可能性を奪ってしまうかもしれませんから。
──「ハットルグリムス教会」「ハルパ」など、たくさんの“ガラスの建築”が登場しますよね。あれにはどんな意図があったのでしょうか?
アイスランドには本当に多くのガラス建築があるんです。私自身も日本に行ったことがありますが、日本にもガラスを使った建物がたくさんありますよね。ロケーションを選ぶ際には、ただ美しいというだけでなく、その場所が物語の中で自然に存在できるかどうかも大切にしています。というのも、アイスランドはとても小さな国なので、「あの建物だ」とすぐに特定されてしまう。だからこそ、その建築が物語の中に違和感なくなじむかどうかは、慎重に見極めるようにしています。
この映画では、ガラスを“語りのツール”として使っています。ガラスは別々の空間をつなぐ“橋”のような存在。たとえば、カメラが直接写していない世界を、ガラス越しに見せることができる。また、2つの世界をゆるやかに融合させたり、登場人物が気づいていない真実をほのめかす、そんな演出も可能になります。
もちろん、撮影面ではガラスへのライトの反射や、マイクが映り込んでしまうなど技術的な課題も多いのですが、それを乗り越える価値があると思っています。ガラスには、美的な魅力だけでなく、語りの可能性がたくさん詰まっているんです。
──たとえば、ウナとクララの顔がガラスに反射して重なるシーン、とても美しかったです。それと、歴史的に見ても、アイスランド映画は自然をエキゾチックに描いてきた印象がありますが、この映画の風景はもっと日常的で、観光的ではないですよね。それは意識されていたのですか?
物語ごとに描き方は異なります。私はきれいだからという理由だけでは風景を映しません。すべての映像には物語との結びつきが必要だと思っています。今回は舞台がレイキャビクという小さな都市で、生活の中の出来事を描いているため、自然の風景は控えめです。ただし、初夏のアイスランド特有の“光の質感”は重要で、もし「自然が印象的だった」と言われるなら、それは風景ではなく“光”の存在を指しているのかもしれません。アイスランド映画というだけで自然を期待される傾向があるのかもしれませんが(笑)。
──これまでに影響を受けた映画監督や芸術はありますか?
たくさんありますが、日本の映画には大きな影響を受けてきましたね。特に日本の小津安二郎監督の作品には深く感動しました。彼が描く世代間ドラマは繊細で、人間への優しさが感じられ、本当に美しいと思います。
また、アンドレイ・タルコフスキーの「時間」の描き方には強い影響を受けましたし、イングマール・ベルイマンとスヴェン・ニクヴィストによる映画『叫びとささやき』は傑作だと感じます。あとクシシュトフ・キェシロフスキの作品で、撮影監督を務めたスワヴォミル・イジャックのコンビも印象的でした。イジャックがビジュアル面でキェシロフスキに挑戦を促し、世界観をより深く豊かにしていると思います。自分に影響を与えた人はもう数え切れないほどいるんです……(笑)。
Interview_Milli Kawaguchi








