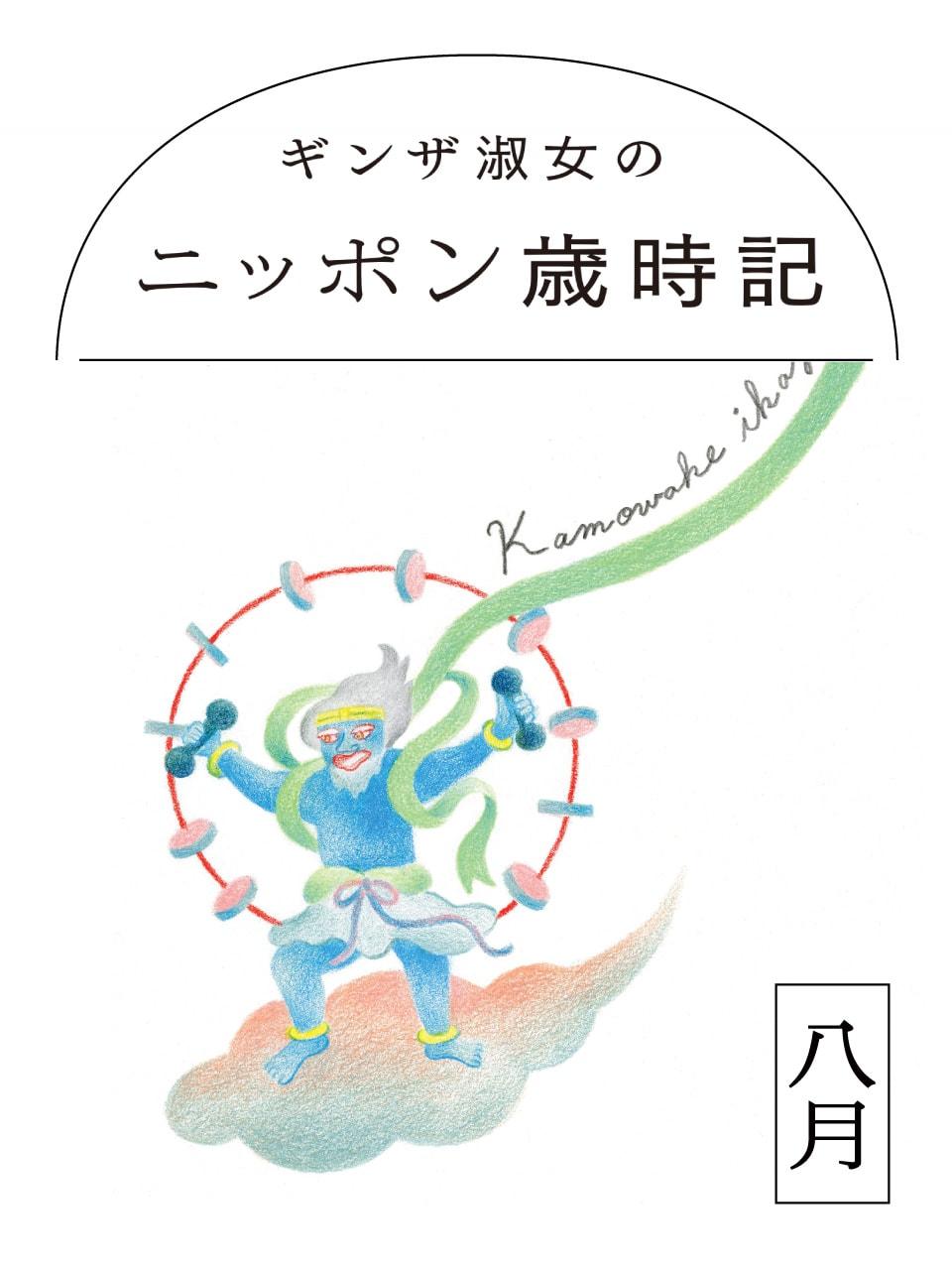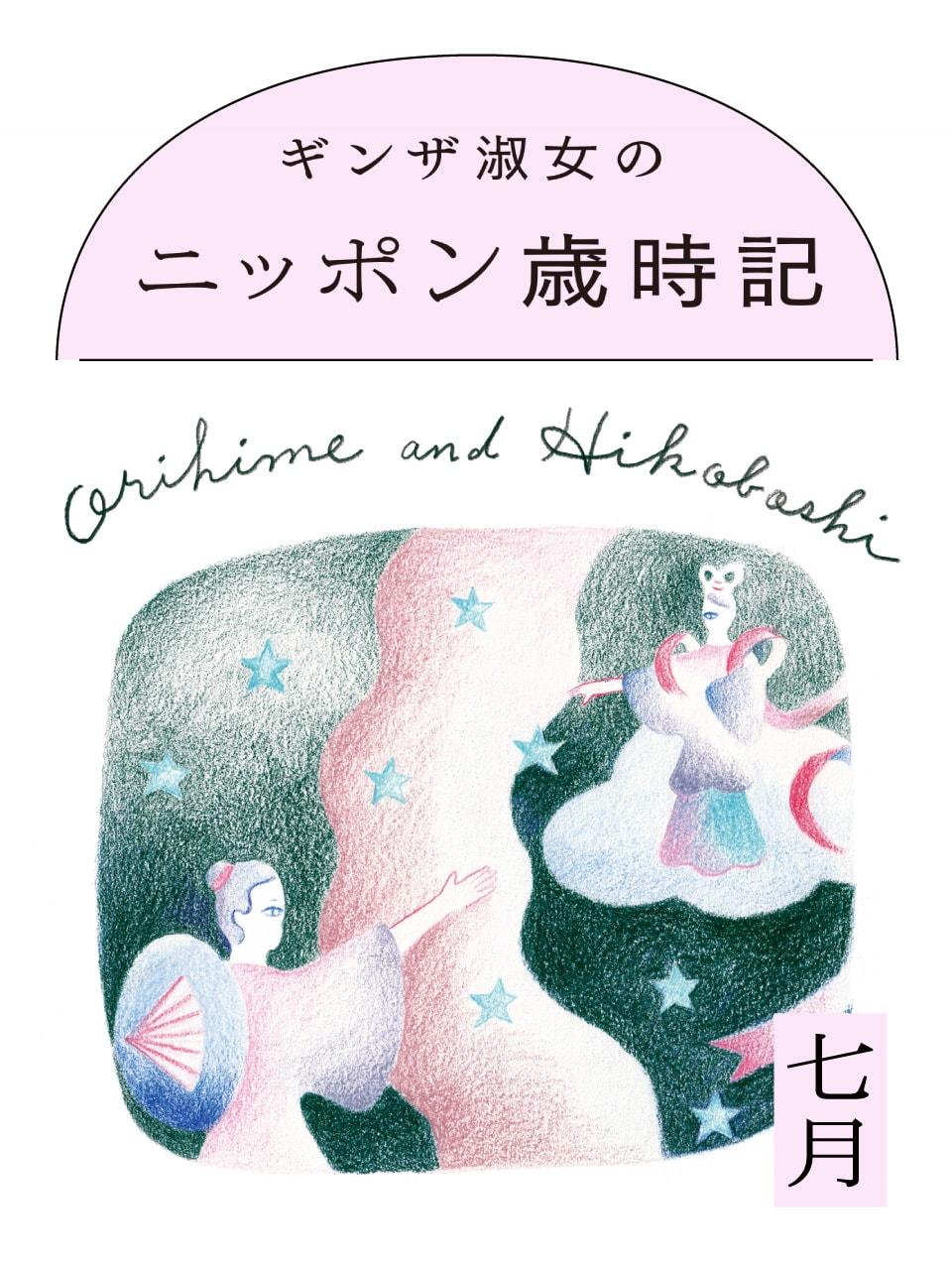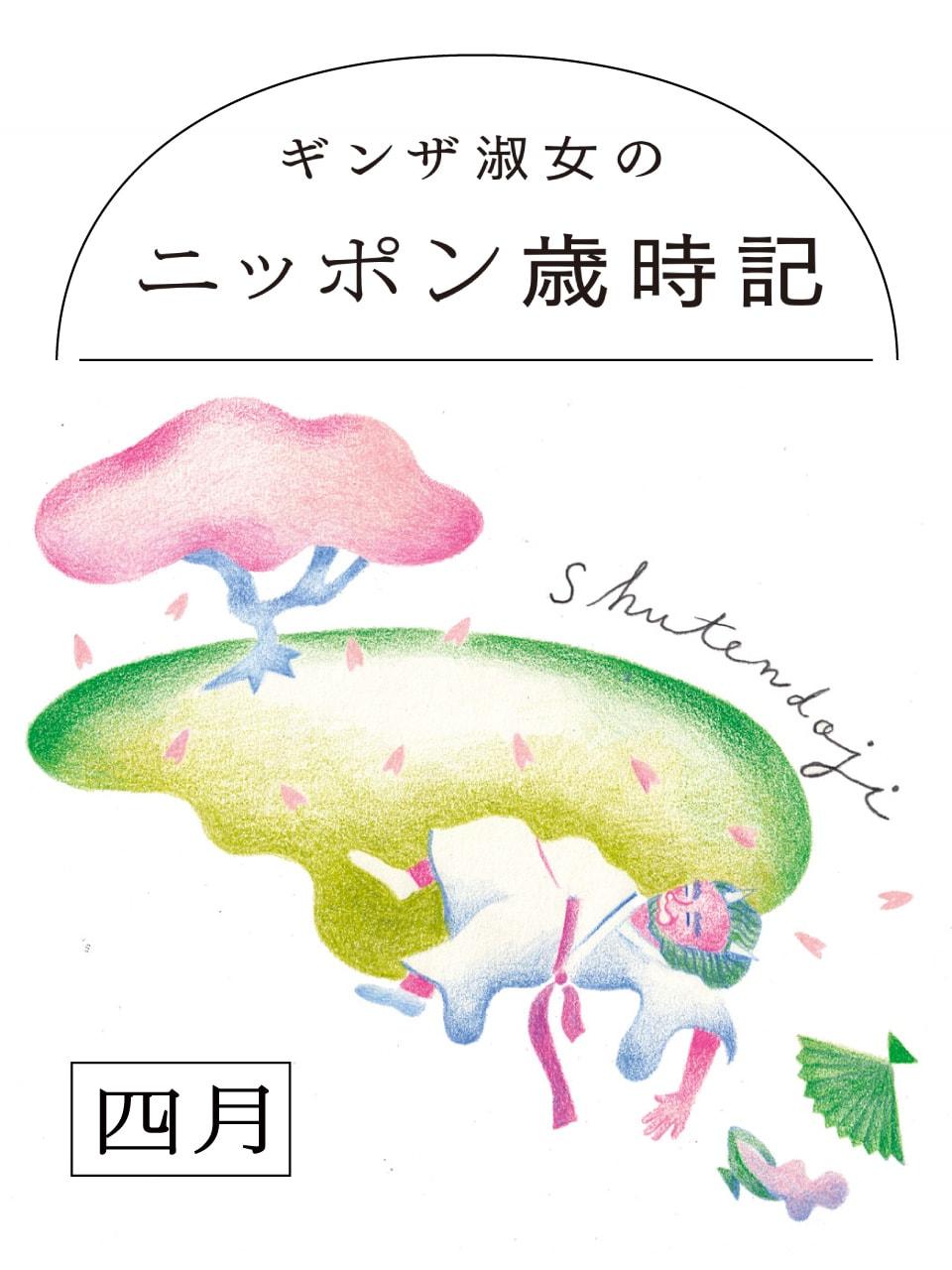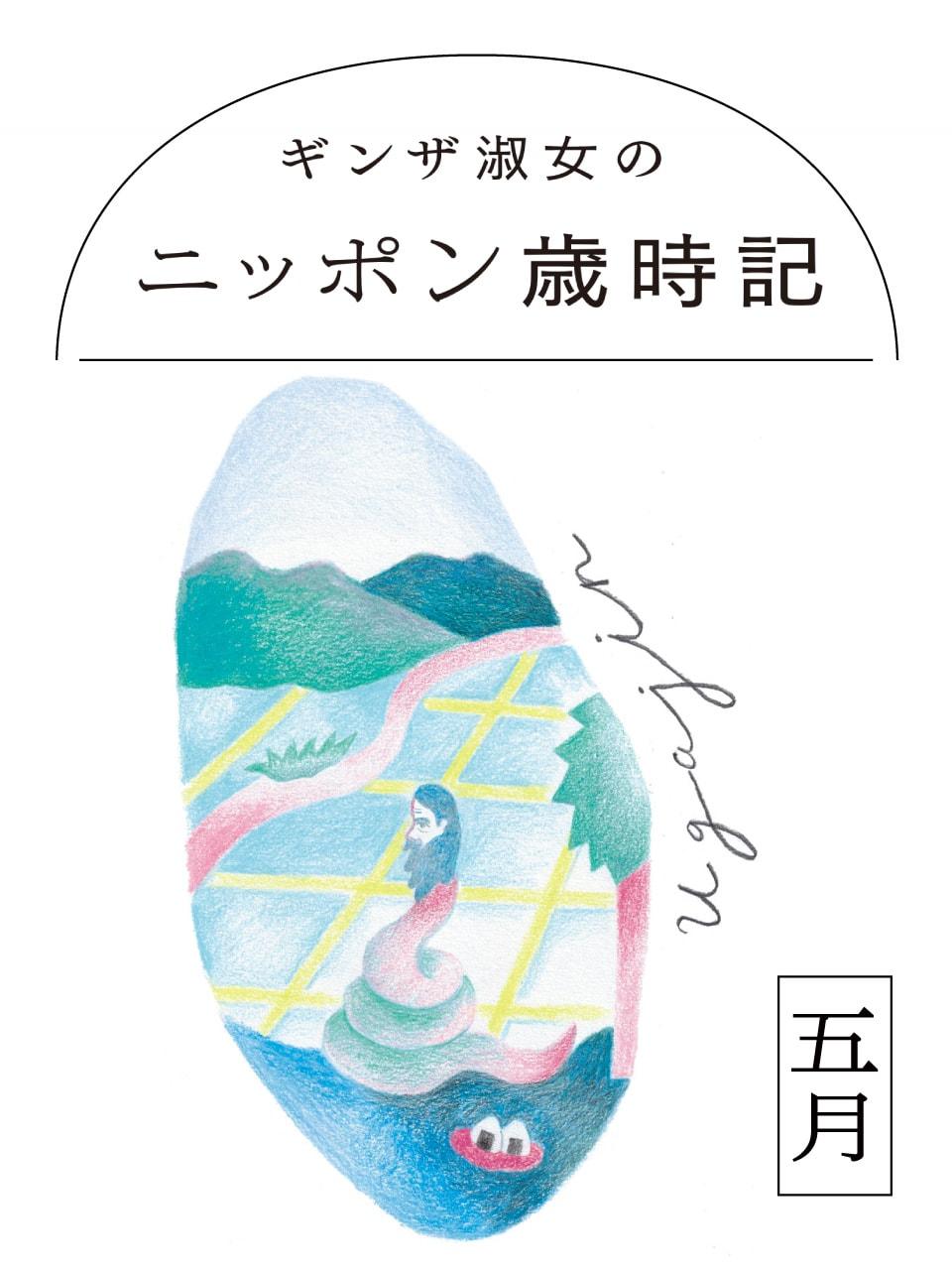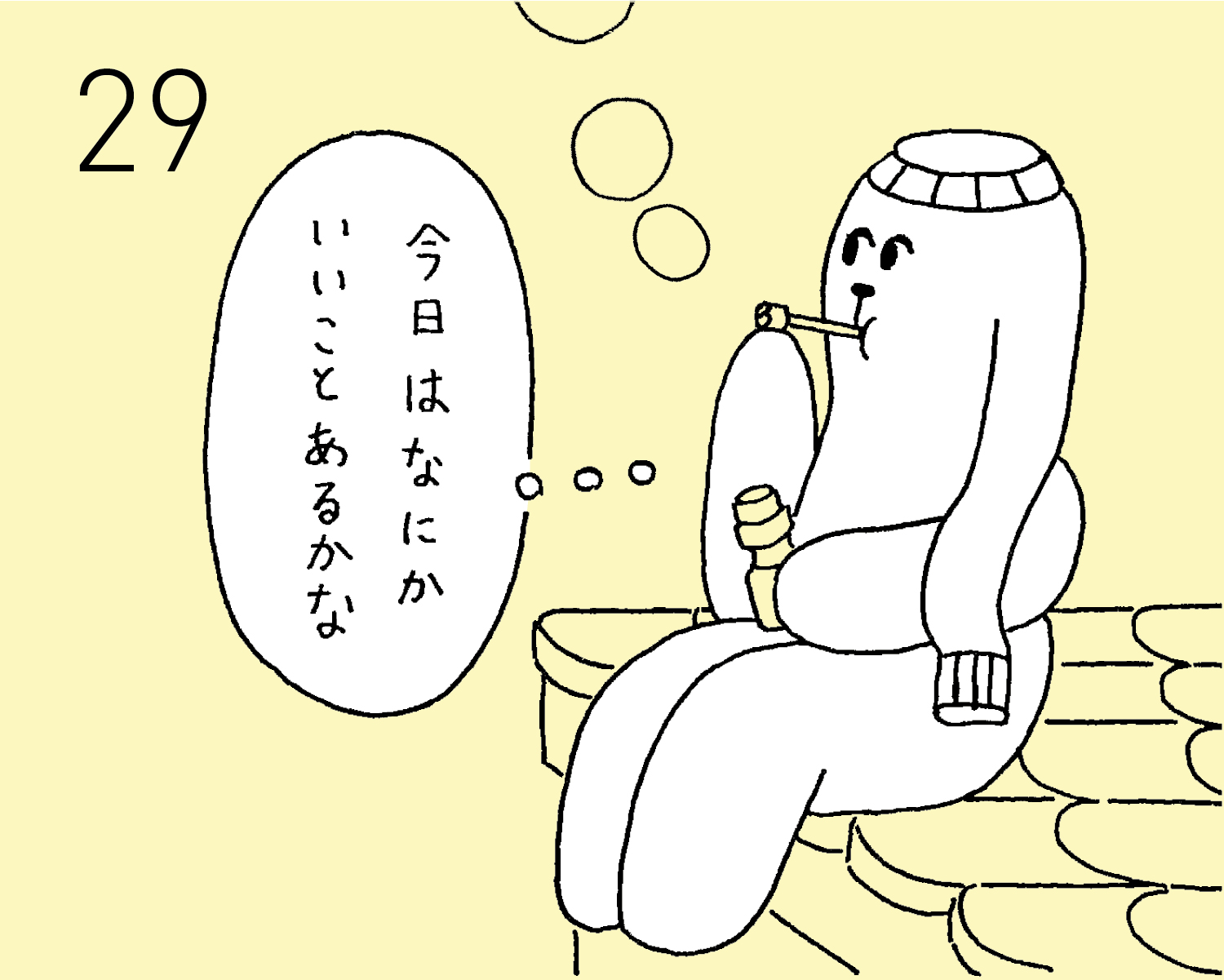知っておきたい日本の言葉、季節のあれこれ。
ギンザ淑女のニッポン歳時記 食用菊の別名「もってのほか」
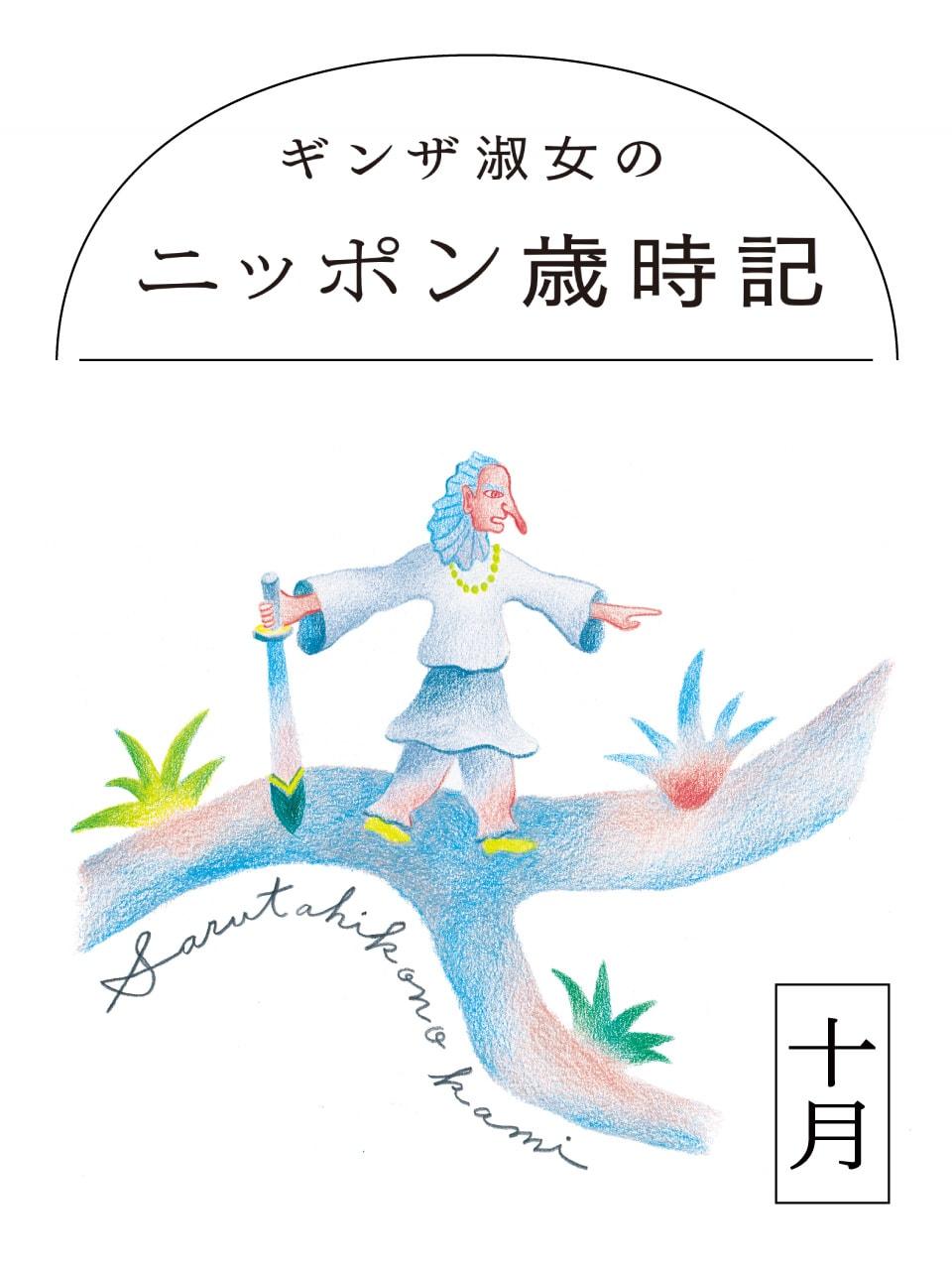
もってのほか
秋の花といえばまず思い浮かぶのが菊。1年中売られる食用菊の生産も本来は9月から11月頃が最盛期です。黄色や紫の美しい菊花をおひたしや酢の物にして食べると、秋そのものを体に取り込んだような気がします。この食用菊の別名は「もってのほか」あるいは「もって菊」。菊は天皇家の紋だから「菊を食べるなんてもってのほか!」、または「思っていたよりおいしいから」など、由来はいくつかあるようです。
今月の神様
猿田毘古神サルタヒコノカミ
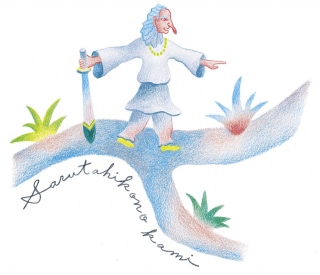
天上世界にいるニニギノミコトはアマテラスオオカミから、地上世界を治めてくるように命令され、地上(葦原中国あしはらのなかつくに)に降りていきます。すると道をふさいで待ち構えるサルタヒコが、道案内をしようと言いました。その姿は鼻がきわめて長く、目は鏡のように輝いており、のちに天狗のイメージにつながったと言われています。道の分岐点にいることから、方角の神、旅行の神、また道祖神としても祀られるようになりました。
今月の文様小物
萩紋の朱印帳はぎもんのしゅいんちょう
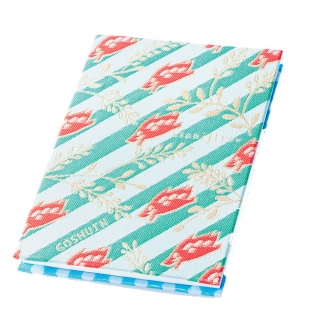
秋の七草のひとつに数えられる「萩」は、万葉集に一番多く登場する植物だとか。また鹿とともに詠まれることも多く、定番の文様として、蒔絵や色紙、染織などさまざまな工芸に頻出しています。丸い葉っぱがこぼれるようについた枝がしだれて、風に揺れるさまは、日本人にとっての秋のイメージそのもの。薄紫や白の小さな花をたくさん咲かせる様子は稲穂を思わせ、豊穣の象徴としても捉えられました。
萩と猪をデザインした織物の表紙の御朱印帳。キチジツ GOSHUINノート〈萩〉 ¥2,000(中川政七商店 渋谷店)
今月の和菓子
鳴子・雀なるこ・すずめ

抹茶と一緒に出てくることの多い干菓子ですが、この形を見て「はて?」と思う人も多いのではないでしょうか。ひねったような形の黄色い飴は、飛んでいる雀の姿をデフォルメしたもの。白い打物の干菓子は、「鳴子」をかたどっています。鳴子は稲穂が実る田んぼにつるし、木の板にぶら下げた木片が風に揺れてカラカラと音を立てることで害鳥を追い払うもの。干菓子は2種を盛り合わせることが多いのですが、鳴子と雀の組み合わせで、秋を連想できたら大したものです!
鳴子と雀*各1個入り ¥250*税込み*10月限定販売(亀廣保)
Photo: Hiromi Kurokawa Illustration: Hisae Maeda Text&Edit: Mari Matsubara