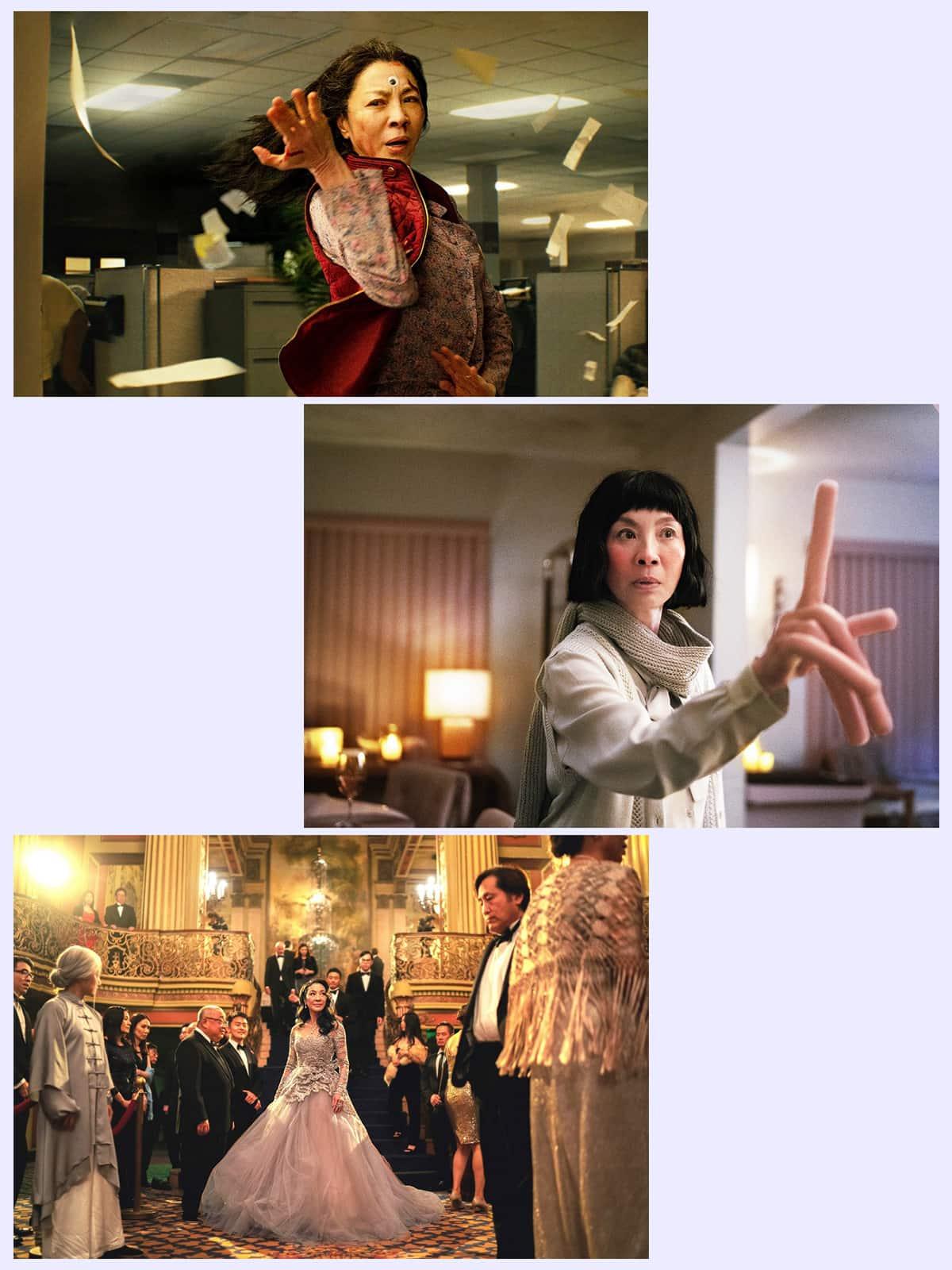認知症の症状を観る者に追体験させる演出が話題をさらった、自身の戯曲の映画化『ファーザー』で、第93回アカデミー賞脚色賞を受賞した、フランス人劇作家のフロリアン・ゼレール。長編2作目として、ヒュー・ジャックマンを主演に迎え、自身の戯曲「Le Fils 息子」を原作とした『The Son/息子』を監督。本作で、親と息子の心の距離を目を逸らすことなく描いた彼が、これまで語られてこなかった家族のメンタルヘルス危機にフォーカスした理由を語ってくれた。
監督フロリアン・ゼレールが逃げずに見つめた、メンタルヘルス危機と家族の関係

──戯曲を書き演出することと、その戯曲を脚色し、映画として監督することは、ストーリーテラーの挑戦として、どんな違いがあるのでしょうか?
一言では答えられませんが、ストーリーを語り、俳優と仕事をし、観客と感情を共有するという部分はどちらも共通していますね。本作の映画化を考えたのは、今この瞬間にこの物語を観客と共有したいと思ったからです。コロナ以降、メンタルヘルスの危機が世界中で広がっていますし、特に若い世代は、不安や孤独を抱えたり、うつ病になるケースも多く、痛みを抱える人がたくさんいる。その状況を問い、語ることが求められている中で「Le Fils 息子」というストーリーを語る必要性を強く感じました。そして、その方法のひとつとして映画館があった。見ているもの、探求しようとしている魂にできるだけ近づくことができる方法として、映画を選んだんです。
──確かに、本作では、家族で代々引き継がれるトラウマや、精神的な問題が語られていますね。
現代を生きている誰もが心の病を抱える可能性がありますし、親しい人や愛する家族の心の健康を気にかけていると思います。とはいえ、日本はどうかわからないのですが、ヨーロッパの人々は精神的な問題についてあまり話をしたがらないという状況がある。罪悪感と恥の文化が複雑に絡まっていて、自分たちの経験を他人とシェアすることを許さないんですね。でも、2018年に「Le Fils 息子」をフランスで上演したとき、公演が終わる度に、観客が出待ちをしていたんです。「おめでとう!」と言うためではなく、自分たちの話をするために待っていたんです。劇を通じて、彼ら自身も同じような立場に置かれていることに気づき、親も子も自分たちの話ができるようになったのだと感じた。その経験から、この映画をつくることで、みんなが話したがらないタブーを逃げずに見つめてみたいと考えました。たとえそれが痛みや苛立たしさをもたらす体験になるとしても、対話を開くために、試してみたいと。
──戯曲も世界中で公演はされますが、英語劇の映画に脚色すると、規模が大きくなり、広がるスピードも加速するという印象はあります。
そうですね。私はニューヨーク出身ではなくフランス人ですが、映画の舞台をニューヨークに設定した理由は、フランスの話でもアメリカの話でもなく、どんな国でどの階級にいても起こりうる話にしたかったからです。ニューヨークはあらゆる国の人々が集まるシンボルのような印象があったので。どこの場所にいても、今、私たちが対処しなければならない問題は同じなんじゃないかなと。

──ゼレールさんの母国語はフランス語なわけですが、舞台の翻訳も務める脚本家のクリストファー・ハンプトンさんと英語で脚色する作業は異文化理解的な面白さもあるのものですか?
とても面白い作業ですね。そもそも他言語で仕事をすることが好きなんです。なぜって、言葉が理解できなくても、俳優が何か素晴らしいことをしているとわかることはあると感じているから。たとえば、濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』で、さまざまな言語で話すいろんな国の俳優が登場するリハーサルのシーンがあったのを覚えています。あのシーンはとても巧妙で素晴らしかった。異なる言語を使用していても、真実や正直さ、本物であるとわかる方法はある。そもそも映画は、それ自体が言語ですから。
──前作『ファーザー』も今作も、ある種の居た堪れなさ、居心地の悪さを感じさせる鑑賞体験になっていますが、そういう効果をもたらしてくれた映画に影響を受けてきたからなのでしょうか?
映画を観る理由はさまざまだと思いますが、僕の場合、楽しみたいだけではなく自分を見つめるために映画館に行くんです。まるで鏡に映った自分を見ているような感覚になる作品が好きで。ときにそれが不快だったり、辛かったりしても、その経験を共有できることが映画の美しさだと思う。現実で辛い出来事にぶつかると、なんで自分だけがこんな酷い目に遭うんだろうと感じますよね。でも、そういうときこそ映画館に来ると、私たちはみんな同じ船に乗っているのだと思い出せる。人類という自分よりも大きなものの一部である、という感覚をもたらしてくれる。人生とは何かを認識させ、私たちは一人ではないと気づかせてくれる。それが映画であり、芸術がもたらしてくれるものだと思います。
──これまでに最も居心地の悪い感情を引き出された映画体験がもしあれば、聞かせていただけますか?
最初に浮かんだのは、デヴィッド・リンチ監督の『マルホランド・ドライブ』ですね。ナンセンスとしか思えないものを目の前にしたときの居心地の悪さを覚えています。観る者は物語の一部となって、そこに意味を見出すために、パズルを組み立てるようにすべてのピースで遊ぶことを強いられる。でも、現実もそうなんですよね。私たちは受け身ではいられないし、バラバラのピースを確実に意味のあるものにするために、自分の経験や潜在意識をフル活用するのではないでしょうか。
──現在43歳のゼレールさんは2人の息子さんの父親でもあるそうですが、この映画でも描かれているように、親としての無力感というものを日々味わっているのでしょうか?
もうそれは親であることの一部ですよね。映画で見せているのは悲劇的な状況ですが、そうでなくても、親であることは、常に無力感を経験し、自分たちがすべての答えを知らないことを受け入れ、自分たちを許すことです。それが辛くてしんどい作業であっても。
──息子さんと接しながら、自分もまた息子であったことを思い出されますか?
息子を育てることが、自分の過去の出来事や傷を癒すことにつながっていたと今は思います。そもそも、私たちは皆、誰かの息子であり、娘なんですよね、永遠に。そして、親になると、自分の親よりも良くあろうと、彼らとは違うことをしようとするんです。でも、それは簡単でないとわかる。ピーター役のヒュー・ジャックマンも、アンソニー・ホプキンスが演じる父親に対していい思い出がなく、彼よりはマシな父でありたいと願っている。でも、ああはなりたくないと思っている父がかつて自分に向けた言葉を、無意識で息子に言っている自分に気づく。それがすごく辛い。
──自分の中に、嫌だった父を見つけるわけですね。
そうなんです。世代で受け継がれてきたネガティブな循環を知性によって断ち切ることが、この映画のテーマだとも言えます。そうするためには、親として相当配慮し、子どもに対して関心を持つことが求められますけどね。タイトル『The Son/息子』は、息子ニコラスのことでもあり、かつて息子だった父親ピーター自身でもある。彼もまたこの物語において息子なんです。
──本作がデリケートなテーマやシーンを扱っていることから、プロデューサーのジョアンナ・ロビーさんが、撮影現場とオンラインでセラピーサービスを提供したそうですね。映画の現場ではまだ一般的とは言えない彼女の選択に対して、どう感じましたか?
タブー視されてきたトピックにまつわるあらゆる恥の感情にチームで抗うために、誰に対しても会話の場を開いていく必要がありました。できるだけ正直に真実を伝えるため、撮影中に生まれた繊細な感情を共有し、サポートするために、関係者全員が心理カウンセラーにアクセスできる環境が重要だったんです。俳優だけのためではなく、技術者スタッフのためにも役に立ったと感じています。家族や職場で大事な人が精神的な危機を経験しているスタッフにとっては、辛い記憶を蘇らせる可能性もあるので。もちろん、傷つけることが目的ではなく、感情を共有するためにこの映画を制作していたので、誰もが心地よく安全に過ごせるように提供されたセラピーは、撮影現場の会話をオープンなものにしてくれたと思います。
──日本では、アメリカに比べるとカウンセリングがまだ一般的に浸透していないように個人的に感じていますが、フランス国内ではどのように認識されていますか?
一般的と言えば一般的なのですが、アメリカのようではないですね。国の文化として、カウンセリングを受けることを恥じる人が多いように感じます。舞台が初上演された際も、父と息子の話であることは話題になっても、メンタルヘルスに関する物語だと言及する人はいなかったんです。どの国でも、アメリカでさえも、同じ現象が起きていると感じます。複雑な部分には踏み込まず、尻込みしてしまい、見つめようとしないんです。受け入れることが痛いし、辛すぎるから。でも、忘れてはいけないのは、罪悪感を感じる必要はないということです。私たちはなぜ人が苦しんでいるのか理解できないものなんです。それが自分の親や子の苦しみであっても。
──家族であっても、結局は自分ではない他者ですもんね。
そうですね。私たちは物語の上で、悩んでいる人々を追いかけますよね。幸せになれる要素があるのに、なぜそうならないのかと疑問に思う。その回答として、心理学的な、生物学的な、時には化学的な、さらに複雑な説明が必要になる場合もあります。そして、そこに答えがないとわかったときに、自分が答えを持っていないという事実を受け入れるのはとても難しい。たとえば、子どもの苦しみが理解できないとき、親は「私は何を間違えたのだろう?」とか「すべて私のせいかもしれない」と考えるようになるんです。罪悪感が自分の居場所を奪ってしまう。これこそが本当の問題なんです。もし、私たちが精神的な問題を身体的な問題と同じように見ることができたとしたら、お互いにもっと助け合うことができるんじゃないでしょうか。
──現実に生きていると、わからないことに対して確かな答えをつい求めてしまうものですが、本作は答えがないこともあるという道を示していますね。
答えがないことこそ、恐怖の正体なんですよね。大丈夫じゃなくて大丈夫だし、わからなくていいし、わからないのだとわかることも重要です。何度も言うように、この映画は悲劇を描いていますが、別の違う結末が待っていたかもしれない。もし違う会話をしていれば。もし助けを求めていれば。現実は、違う終わり方をしなくてはいけない。今こそ、逃げずに見つめるときだと強く感じてもらえたらと思います。
『The Son/息子』

再婚した妻のベスと生まれたばかりの子どもと暮らす優秀な弁護士のピーター。ある日、前妻のケイトと同居する17歳の息子ニコラスに「父さんといたい」と懇願され息子との新生活が始まる。ところが、転校したはずの高校に息子が登校していないことがわかり、父と息子は激しく言い争う。なぜ、人生に向き合わないのか?父の問いに息子が出した答えとは──?
監督: フロリアン・ゼレール
原作: フロリアン・ゼレール
脚本: フロリアン・ゼレール、クリストファー・ハンプトン
出演: ヒュー・ジャックマン、 ローラ・ダーン、 バネッサ・カービー、ゼン・マクグラス、ヒュー・クァーシー、アンソニー・ホプキンス他
配給: ギャガ
2022年/イギリス・フランス合作/英語/カラー/スコープサイズ/123分/原題:The Son
2023年3月17日(金)、TOHOシネマズ シャンテ 他にて公開
© THE SON FILMS LIMITED AND CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 2022 ALL RIGHTS RESERVED.
🗣️

Florian Zeller
1979年6月28日、フランス生まれ。 2002年、22歳でデビュー小説「Neiges artificielles」を発表。パリ政治学院で文学を教えながら小説家、劇作家として活躍。2004年に小説「La Fascination du pire」でフランスの最も権威ある文学賞のひとつ、アンテラリエ賞を受賞。2012年、戯曲「Le P è re」で認知症の父とその介護を務める娘の絆と喪失を描き、仏演劇界の最高賞で知られるモリエール賞作品賞を受賞。この戯曲は世界30か国で上演される。初監督作となった映画『ファーザー』(20)ではアンソニー・ホプキンスとオリビア・コールマンを主演に迎え、見事、ホプキンスにオスカーをもたらし、自身もアカデミー賞の脚色賞を受賞。
Text&Edit: Tomoko Ogawa