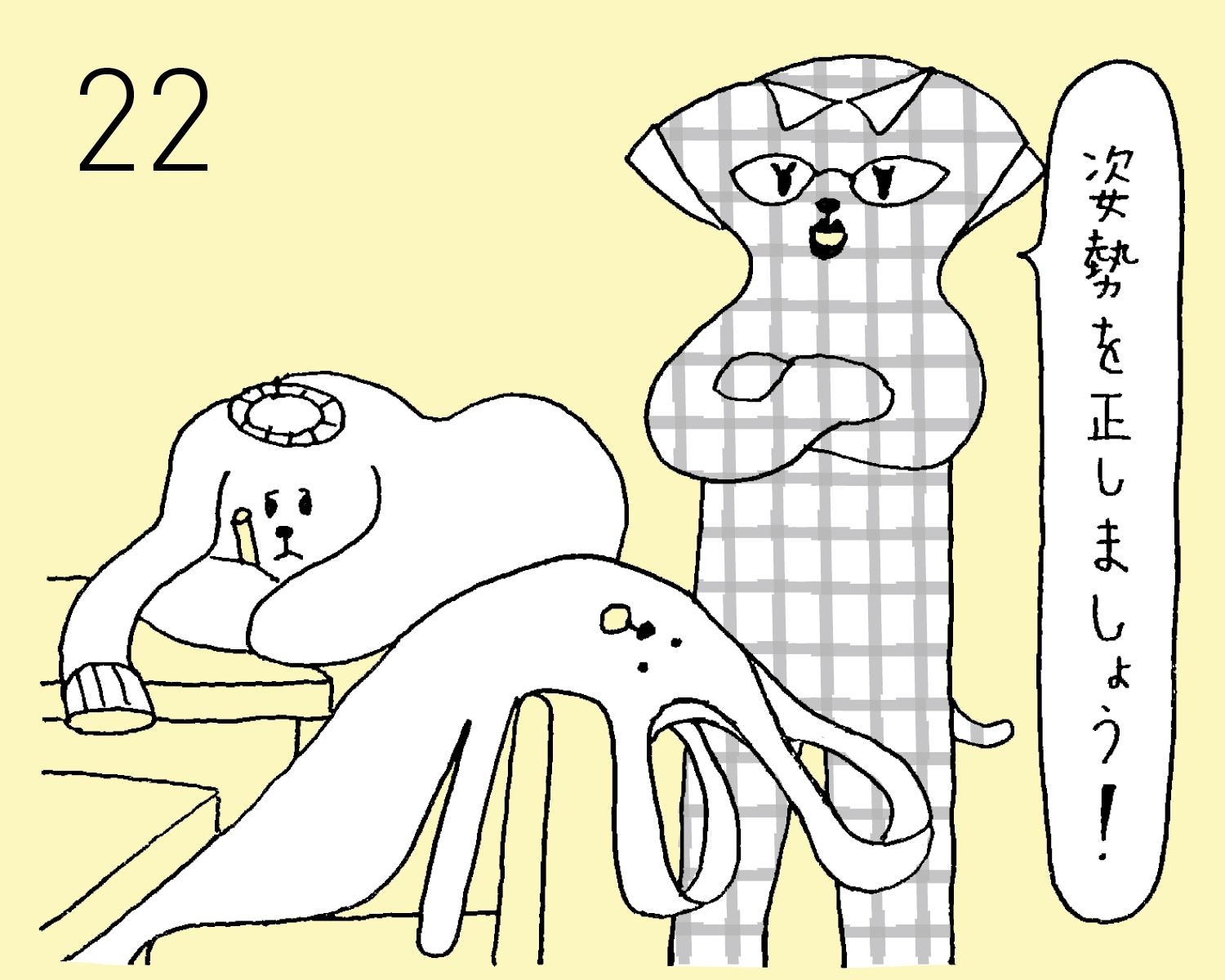映画『コール・ジェーン -女性たちの秘密の電話-』(3月22日公開)は、60年代〜70年代初頭のシカゴで当時違法だった、人工妊娠中絶を希望する女性たちを救ったグループ“ジェーン”の知られざる歴史を描く。『キャロル』の脚本家としても知られるフィリス・ナジー監督に思いを聞いた。
映画『コール・ジェーン -女性たちの秘密の電話-』フィリス・ナジー監督インタビュー
「今ある権利は当たり前のものではない」60年代米国に実在した女性団体の物語から伝えたいこと

──1968年のアメリカ・シカゴ。何不自由なく暮らしていた主婦のジョイは、二人目の子どもの妊娠によって、心臓の病気が悪化。中絶が許されていない時代ゆえに右往左往するうち、アンダーグラウンドな支援団体“ジェーン”に辿り着きます。映画を観るまで、このグループが実在したことを知りませんでしたが、勇敢さに驚きました。
私もプロデューサーが脚本の初稿を持ってきた時、「これが実話なんてありえない!」と思いました。違法にもかかわらず安全な中絶手術を提供し、自らその技術を学びさえした女性たちがいたという、信じられないような真実。もっと知られるべき歴史だと思いました。
──ジェーンについて広めることが、監督を引き受けた理由でしょうか?
そうですね。もう一つの理由としては、この作品がただ女性の苦しみだけ描いているわけではないこと。中絶を描くとなると、その後に命を落とすとか、処置を受けられないとか、悲惨な物語ばかり。この映画はそうではなく、女性たちがひどい状況を変えようと一念発起し、集団行動の力によって目的を成し遂げようとするんです。
私自身は、抗議し行動した世代です。1962年にニューヨークで生まれ、1980年代のエイズ危機において、人々が政府の無策に抗議した時代に育ちましたから。でも最近の学生たちは今ある権利が当たり前のものではなく、過去の世代によって勝ち取られたということを知りません。だからこの映画を作ることで、若い人たちになんらか影響を与えられたらと思ったんです。
──映画のテーマはシリアスですが、コミカルな面もあります。企画の当初からそうでしたか?
いえコミカルな要素は、途中から加わっていった覚えがあります。メインキャストのシガニー・ウィーバーやエリザベス・バンクスのような、天性のコメディアンをキャスティングすれば、自ずとある種の軽妙さが生まれるものです。この映画では人々に説教するのではなく、とにかく集団行動のパワーを示したかった。そして、中絶は女性のヘルスケアの一部であるべきだと伝えたかった。残念ながら、今のアメリカではそうではありません(*1973年の「憲法上、中絶は女性の権利である」と認めたロー対ウェイド判決が、2022年に最高裁によって覆され、現在も州によって中絶が禁止されたり、禁止に向けた協議が進められたりしている)。
ハリウッドの人々は基本的にリベラルです。そんな自分たちだけが満足に浸るための作品を撮るより、違う考えの人たちに訴えかけたいと思っていました。別に誇大妄想しているわけではないけど、もしかすると誰かがこの映画を観て「そうだったんだ。考えてみます」と言うかもしれない。そのためにも、ユーモアが効くのではないかと思います。
Text & Edit_Milli Kawaguchi