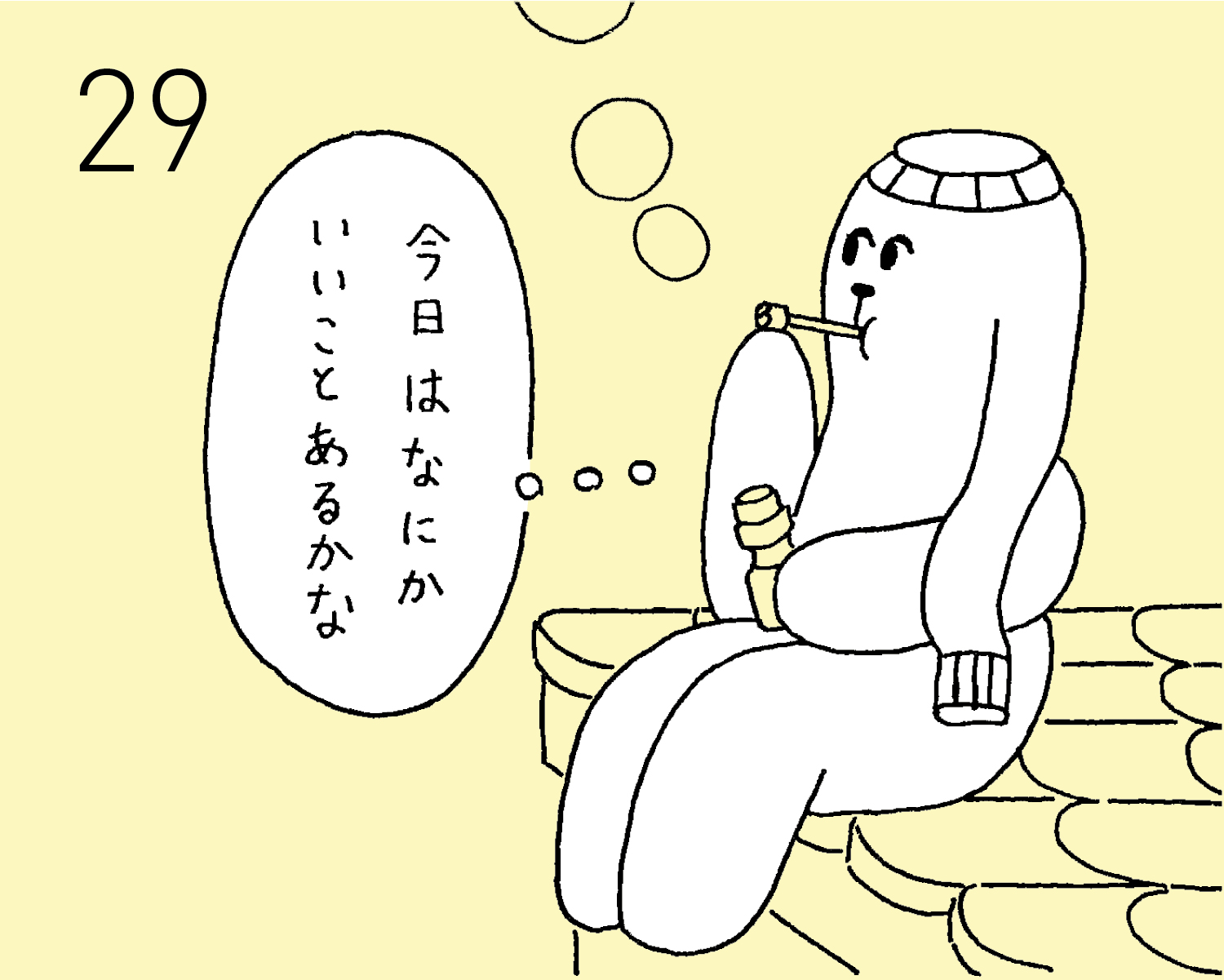現代のものにはない色や柄、フォルムに無性に惹かれるのはなぜだろう。時間という魔法にかけられて、それらはとってもチャーミングな輝きを放つ。ヴィンテージを愛する人に“いちばんのお気に入り”を見せてもらいました。
クローゼットの宝もの 大出由紀子さんのリーバイス®の66モデル

「高校生だった1986年に、裏原の『ヤンクス』という店で手に入れた〈リーバイスR〉の通称“66”(1970年代生産)です。古着が大好きで、地元の群馬県桐生市からよく原宿や渋谷のショップに遊びに行っていました。一緒にいたアメリカンヴィンテージに詳しい友達から『これは価値があるよ』とすすめられたのを覚えています」
希少性の高い501XXや、赤タブのLEVI’SのEが大文字で刺繡されたビッグEは、学生の大出さんには手が届かなかった。でも“66”なら当時はまだ1万円台。
「頑張ってバイト代で買って、10代後半から20代はヘヴィーローテーションではいていました。とにかく縦落ちが最高によくて、ビッグEと同じような感じの色になっています。ヴィンテージは前に持っていた人がどのように扱っていたかによってまったく変わってくるもの。これは前の持ち主がたぶんあまり洗わずにいたから、今の色に変化していったんだと思います」
幼少期からスカートをはいた覚えがないほど、筋金入りのメンズカジュアルウェア好き。ティーンの頃は『ポパイ』や、『メンズクラブ』の特集別冊を隅々まで読み込み、古着の深い知識をため込んだ。
「これは66の中でも“前期”と呼ばれているもの。バックポケットの内側のステッチで判別できました。中のタグに記されている数字が6だから、エルパソの工場で作られたもののようです」
デニムに限らず、昔のウェアは作られた当時に普及していた素材や機械をはじめ、生産方法もすべて進化してしまい、もう再現できない。だから貴重だともいえる。
「ヴィンテージへの愛はこの一本から本格的に始まって、ミリタリーやワークウェアにも広がりました。それらの機能性重視の衣服には当時の最先端技術が盛り込まれていて、素材や細部に意味があることがわかってきたんです。その根拠が理解できたときは感動を覚えました」
最後に脚を通したのは10年前。今もはきたいけれど両膝に穴が開いてしまい、これ以上は無理と判断し、しまっておくことに。
「私が着ていた服の中で最古のもの。身につけられませんが、一生持ち続けます」
🗣️
大出由紀子
おおで・ゆきこ>> デザイナー。1969年群馬県生まれ。1998年に吉原秀明とともに〈green〉を立ち上げる。2009年春夏シーズンをもって活動休止。2013年秋冬より〈HYKE〉をスタート。