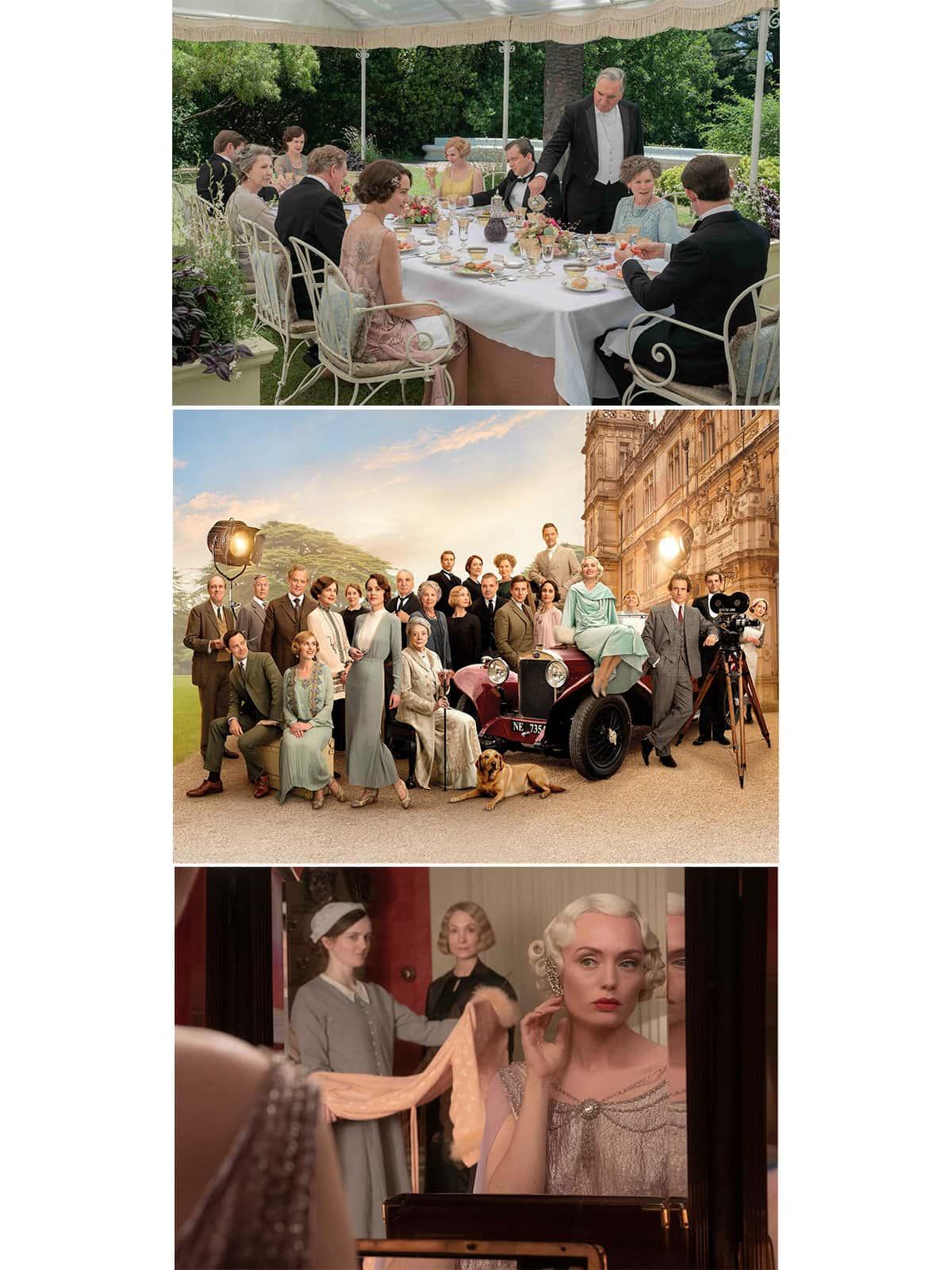嗅覚に不思議な力を持つ少女が、自分が生まれる前の、母と叔母の封じられた記憶にタイムリープする。『パリ13区』の脚本に参加したことでも知られるレア・ミシウスによる最新監督作。2022年のカンヌ国際映画祭で、LGBTQ+をテーマにした映画に授与されるクィア・パルムに選出された、これまで観たことのないSFファンタジースリラー『ファイブ・ビルズ』が2022年11月18日(金)に公開される。セリーヌ・シアマ、ジュリア・デュクルノーに続くフランス映画界の新鋭監督に聞く、彼女があえて映画で描きたいこととは?
フランスの新鋭監督レア・ミシウスが映画『ファイブ・デビルズ』で描く、前代未聞のタイムリープ・サスペンス

──前作の長編映画デビュー作『AVA』(2020/日本未公開)では13歳の思春期の娘といつまでも若くいたい母親の危うい関係を描いていましたが、今作も秘密を抱える母と“香り”の能力をもつ8歳の少女の物語です。母と娘の関係というのは、監督の核となるテーマだったりするのでしょうか?
確かにそうですね。ただあえて意識的に書いたわけではなくて、書くうちに自然とそういうストーリーになっていったんです。『AVA』は、どちらかというと、娘の方が母親をすごく嫌って距離を取ろうとして、母は娘をどうにか引き寄せようとする。本作はその逆の関係性の物語だと思います。これからあと18本くらい映画を撮るとして、他のテーマを軸にすることもあるでしょうけど、おそらく、親子というテーマはこれからもどんどん扱っていくとは思います。
──本作は少女の成長ドラマであると同時にファンタジーであり、タイムリープスリラーでもあって、ジャンルという枠組みを溶かしていくような作品になっています。監督は映画におけるジャンルをどう捉えていますか?
脚本を書き始めたときは、ファンタジーのジャンル映画にしようなんて全く考えてもいなかったんですけど、いろんな人物を生み出していくなかで、ヴィッキーという少女にはとても特別な能力として強力な嗅覚があるとしたらどうだろうと思いついたんです。
──プルースト効果のようですよね。
マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』は、マドレーヌの香りによって、幼い頃の記憶が突然呼び起こされる話ですが、ヴィッキーの場合、香りを嗅ぐと母親の過去の秘密に瞬間移動します。同じ嗅覚の力でも、ちょっと違う方向なんです。そこから、少し物語の方向性が変わっていきました。基本的に、主人公ありきでそこからどういったストーリーテリングにしていこうかというアイディアが出てくるので、新たなジャンルに挑戦するぞ、と意識することは特にないんですけど、今回はジャンル映画のコードを使うことによって、結果的に、自然主義から逸脱できたという側面があったかなと。
──映画の中では、自然さや現実的であるかに囚われる必要はないですもんね。
ジャンルというコードが、私たちが現実とはかくあらねばならないと信じているものに物語を閉じ込めることなく、自由に枠組みを超えて語ることを許してくれるんですよね。ただ、本作でジャンル映画のコードを100%使い切ったな、とは思ってませんけど。
──ファンタジーというジャンルのコードをもたらしてくれたヴィッキーは、カラスを鍋で煮て香りを調合するような、変わった女の子として描写されます。幼少期を振り返ったときに、自分も変わった女の子だったと思いますか?
小さい頃って、自分が変わっていることにあまり気づかないものじゃないですか。なので、自覚はなかったですね(笑)。ただ、一卵性双生児だったので、中身は全然違うのに、外見的なところばかりをすくって「二人はすごく似ているね」と周りから言わることが多かったんです。どちらかというと、見てわかるような変わり者ではなかったかもしれませんが、物語を書くことがとても好きで、物語の中で変わったところを表現していたんだと思います。この作品の中に出てくるような話を、既に子どもの頃に書いていたんですよね。
──そうなんですね。どこまでも自由に飛んでいけるような、動物にも近い逞しさと繊細さが介在していて、その純粋さから若干の恐怖も感じさせるヴィッキーを見ていて、少女時代の複雑な感情が蘇りました。
ヴィッキーって、おどろおどろしいような女の子ではなくて、チャーミングで愉快なところもあるんですよね。子どもの頃は、いつもヴィッキーのような、ちょっと孤独な子どもや動物が出てくるような物語を書いていたんです。そこには、片方の足を引きずっていたり、火傷をしていたり、少し変わった人が登場していましたし、今と変わらず、不安を呼び起こさせるような、自然というものについて描いていたと思います。
──多様性のチェックシートがクリアされていればキャンセルされずに安心、という考えが透けて見える作品も最近はあったりしますが、本作は、あえて架空の村を舞台に、さまざまな人種、健常者、障害者、さまざまな志向を持つ人たちの共同生活を、特に家族や友人の無意識の偏見に焦点を当てながら見せています。そうすることで、自ら疑い、問うことを促してくれる映画ですね。 元々は文学を志していたレアさんですが、 なぜ映画という方法を選ぶようになったのでしょう?
おっしゃる通り、多様性をきちんと表すと、政治性が出てくる。そこは私にとっての興味でもあります。なぜ映画でそれをやりたいかというと、映画ではそういったものが可視化されにくいというか、隠れてしまうことが多いんですよね。だから、私はそれをあえて描きたいなと。
──そういった考えにたどり着くまでに、影響を受けた作品はありますか?
人間はものすごく多様で、みんな異なるんだということを最初に知らしめた作品は、子どもの頃に観た、フォルカー・シュレンドルフ監督の『ブリキの太鼓』(79)でした。主人公オスカーが汚い大人たちを見て、「大人になりたくない!」と奇声を上げると、ガラスが割れる。彼は自分の成長も止められる不思議な能力を持っていて、小人症のサーカス団に合流することになります。今でも衝撃的で忘れられないのは、子どもたちが、カエル、おしっことかを混ぜたスープを作って、それをオスカーに飲ませようとするシーン。ちょっと人と違うというだけで、こうやって虐められてしまうんだという現実を実感した作品でもあります。
──レアさんは、アルノー・デプレシャン、ジャック・オディアールといったフランスの巨匠監督作品の共同脚本家としても活躍されていますが、自分で執筆・監督をするときと、脚本のみ担当するときで、マインドセットは変わるものですか?
「全然違います!」と言えたらいいんですけど(笑)、どちらも書く行為なので全然違うってことはないですね。ただ、アプローチは違うかな。ほかの監督たちと脚本を一緒に書くときは、彼らのビジョンに入っていって、彼らはどんなふうにその世界を見ているだろうということを想像します。しかも、私がこれまで共同執筆した方達は、とりわけ作家性が強い監督だったのでなおさら彼らのビジョンに同化することに努めました。
──彼らの視点に立つときに、意識していることはありますか?
私の個人的なタッチは大事にすること。私という存在を残しつつ、監督の視点に立つことで、さらなるアイディアや対話が生まれてくると思うんです。言ってみれば、私の中には、自分の映画のためのアイディアのタンクと、他の監督に対するタンクがそれぞれあるので、その時々で使い分けができているんです。私、気がついたんですけど、タンクの中身にある想像力っていうのは、枯れることがないんですね。想像力をたくましくすればするほど、容量が増えていく。最近はそんな気がしています。
──尽きない想像力なら18作といわず、もっともっと作品をつくってもらいたいですね。最近、娘さんをご出産されたそうで、おめでとうございます。生まれる前と後で、この母と娘の関係への見方に変化はありました?
面白いのは、出産してから、この作品で書いた娘と親の関係が現実になっていると実感することが多くて。生まれてまだ1カ月半くらいなのですが、私がお乳をあげていると、本当にヴィッキーみたいに私にしがみついてきて、私の匂いをクンクンと嗅いでいるようで、まさにヴィッキーと母ジョアンヌの関係がそこにある!と感じて、自分は予知能力があったのかも?と思えるような作品になりました。全然そんな才能ないんですけどね(笑)。
『ファイブ・デビルズ』

嗅覚に不思議な力をもつ少女ヴィッキー(サリー・ドラメ)はこっそり母ジョアンヌ(アデル・エグザルコプロス )の香りを集めている。そんな彼女の前に突然、謎の叔母が現れたことをきっかけに彼女のさらなる香りの能力が目覚める。やがてその力が、家族の運命を変える予期せぬ結末へと向かわせる。
監督: レア・ミシウス 『パリ13区』
脚本: レア・ミシウス、ポール・ギローム
出演: アデル・エグザルコプロス、サリー・ドラメ、スワラ・エマティ、ムスタファ・ムベング、ダフネ・パタキア、パトリック・ブシテー
配給: ロングライド
2021年/フランス/仏語/96分/カラー/シネスコ/5.1ch/原題:Les cinq diables/英題:The Five Devils/日本語
2022年11月18日(金) より、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、アップリンク吉祥寺ほか全国にて公開。
©2021 F Comme Film – Trois Brigands Productions – Le Pacte – Wild Bunch International –
Auvergne-Rhône- Alpes Cinéma – Division
🗣️
Léa Mysius
1989年、フランス、ボルドー出身。フランスの映画学校ラ・フェミスに入学後、映画技術を学びながら、脚本家、監督としての才能を発揮する。初の長編映画となる『アヴァ』(17)はカンヌ国際映画祭カメラ・ドールを含む4部門にノミネート。2021年、カンヌ国際映画祭正式出品されたジャック・オディアール監督とセリーヌ・シアマと共同脚本を務めた『パリ13区』が話題となったほか、アルノー・デプレシャン監督『イスマエルの亡霊たち』(17)、クレール・ドゥニ監督『STARS AT NOON』(22/未)でも脚本に参加するなど、現在、フランスで個性的な若手映画作家として最も注目を浴びる一人。