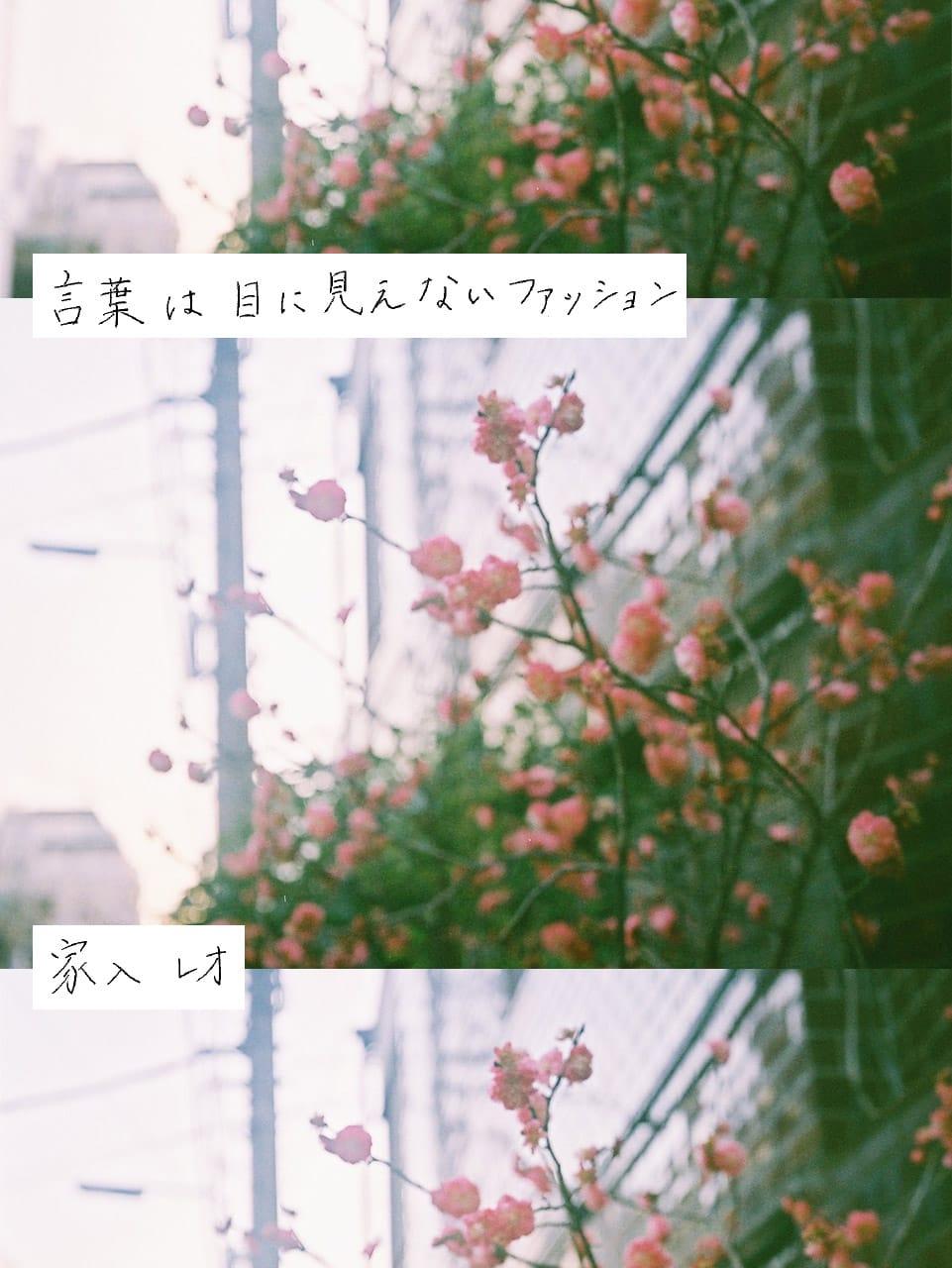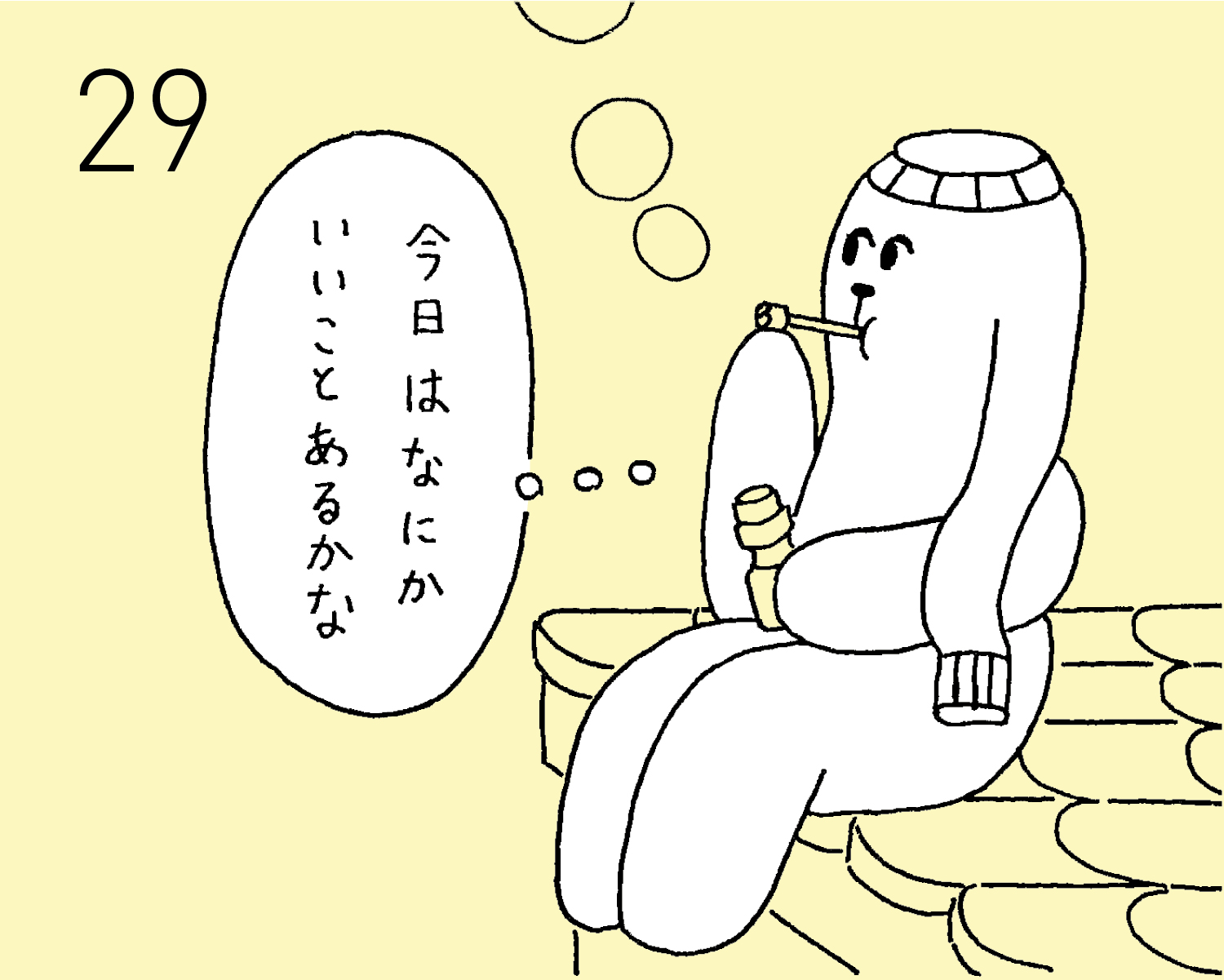クォーター・ライフ・クライシス。それは、人生の4分の1を過ぎた20代後半〜30代前半のころに訪れがちな、幸福の低迷期を表す言葉だ。28歳の家入レオさんもそれを実感し、揺らいでいる。「自分をごまかさないで、正直に生きたい」家入さん自身が今感じる心の内面を丁寧にすくった連載エッセイ。前回は、vol.89 お家の中の迷子。ニューアルバムについてのインタビューはこちら。
家入レオ「言葉は目に見えないファッション」vol.90
鋼の自己肯定感
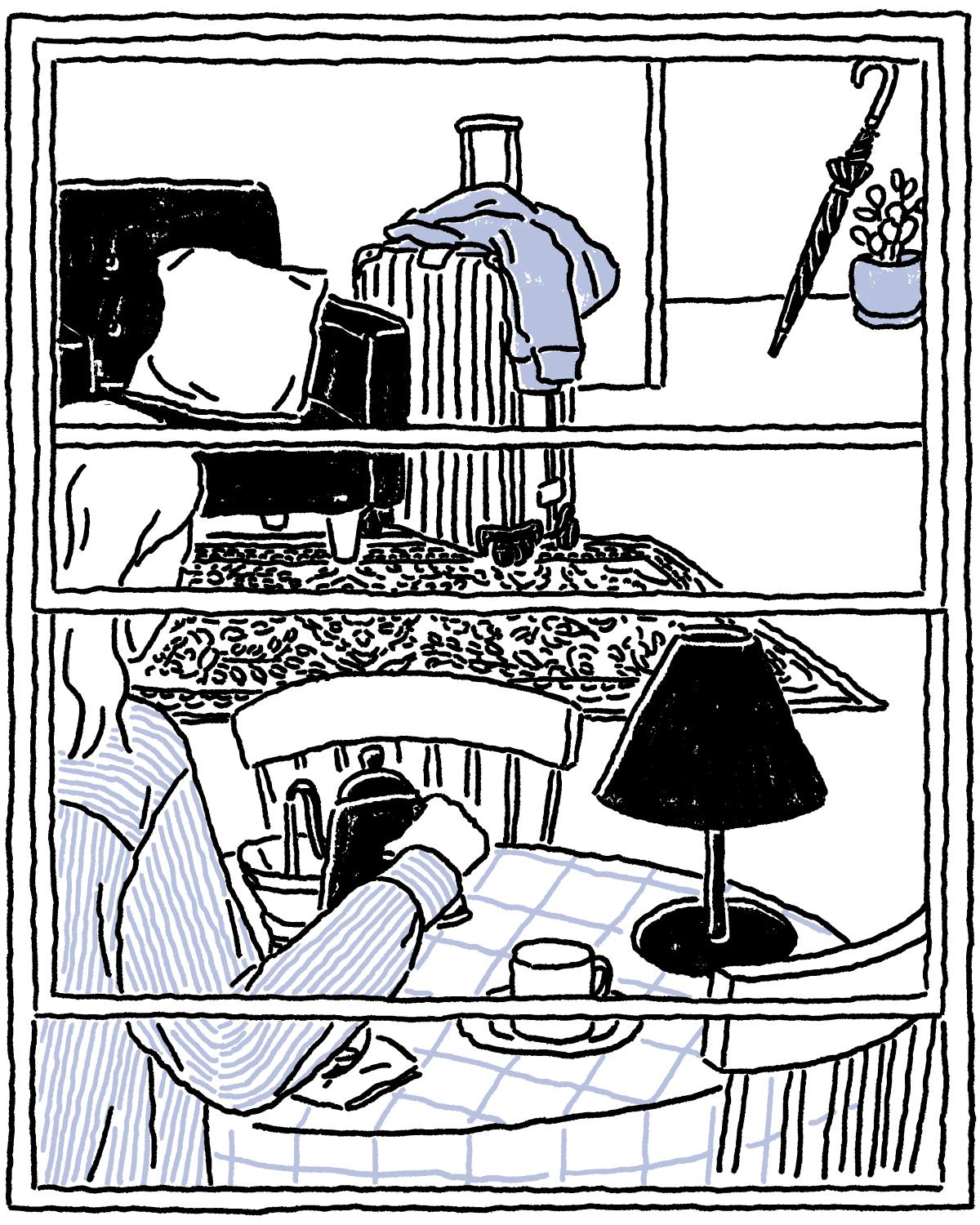
vol.90 鋼の自己肯定感
宮崎直子さんの著書『鋼の自己肯定感』を手に取ったのは、Instagramで本を紹介している文学系インフルエンサーの投稿がきっかけだった。ネットサーフィン中に、「この商品を購入した人はこんな商品も買っています」と関連商品を紹介されるAIレコメンド機能。過去の閲覧・購入データに基づいて、今興味のありそうな情報を提供してくれるし、それはもう素晴らしく効率的で便利なんだけど、心の何処かであまり頼りすぎずに生きていきたいなーと思っている自分もいて。だけどInstagramのフィード画面の投稿をタップして、スクロールしながら読んだ文章からは、読書が好きな気持ち、そしてこの本と出合って自分自身がどう変わったのか簡潔に書かれていて。自分の人生の時間を使って『鋼の自己肯定感』を読み進め、その感動を言葉にするアナログな姿勢は、買い物サイトのレビューとも、AIレコメンド機能のハイテクさとも違う信頼感があり、つい興味をそそられ購入に至ったのだった。
私はちょっとした空き時間や休日に本屋に行き、新書からはじまり本棚に並んでいる本のタイトルを読んでいくのがとても好きで。それは自分の心と対話する時間でもあるし、世の中で今どういう思想が支持されているのかを知ることができる場所でもあるからで。昨今「自己肯定感」という言葉、それと似た言葉を目にする機会が本当に増えた。これまで手に取ったその類いのハウツー本と『鋼の自己肯定感』が明らかに違ったのは、自己肯定感と自己有用感、自己効力感の3つについて解説されていることで、この3つを混ぜこぜにして語ることの危険性を知ることで、本当の自己肯定感とは何か理解することができた。
そしてさらに欲しかった答えが見つかった、と思ったのは、スタンフォード大学心理学教授のキャロル・ドゥエック氏の著書『マインドセット』が紹介されていた章。
ドゥエック教授は、子どもたちが様々な難易度のパズルを解くのを観察しているうちに、2種類の子どもがいることに気がついた。同じパズルを繰り返し解く子ども。失敗を恐れず次から次へと難易度の高いパズルに嬉しそうに挑戦する子ども。同じパズルを繰り返し解く子どもたちでいえば、1つ成功を収めたら、それ以上は挑戦しない。難しいことに挑戦して失敗しようものなら、自分は能力がないということになってしまう。だから失敗をひどく恐れる。一方で、次から次へと難易度の高いパズルに挑戦するタイプの子だと、今の自分の能力をさらに伸ばすことが生きる目的なので、失敗を恐れるどころか、失敗をそもそも失敗と思うことなく、新しいことに次から次へと挑戦していく。嬉しそうにどんどん難易度の高いパズルに挑戦する。この事象を「鋼の自己肯定感」で知って、社会そのものだ、と思った。同じパズルを解く子どもたちは防衛本能や生存本能が強いと言えるし、その安定の中で得られる安らぎがある。だけど私自身で言えば圧倒的に後者で、ルーティンや同じサイクルの中に身を置き過ぎると生きる希望を失くしてしまう。どっちが良いとか悪いとかの話じゃ無く、これは生まれ持った性質もあると思うし、自分が心地良いと感じる方に歩みを進めていくことが幸福への近道な気がしていて。今まで、目の前にある物をもっと大事にしなさい、と言われ育ってきた。そして実際どうして目の前にある物だけじゃ満足出来ない自分なんだろう?と悲しくなったり、自責の念にとらわれたりしてきた。だけど、それも人それぞれなのだ、と思えた時、自分を認めてあげることができた。本を読むこと、知識を得ることで点と点が線になる。
Text:Leo Ieiri Illustration:chii yasui