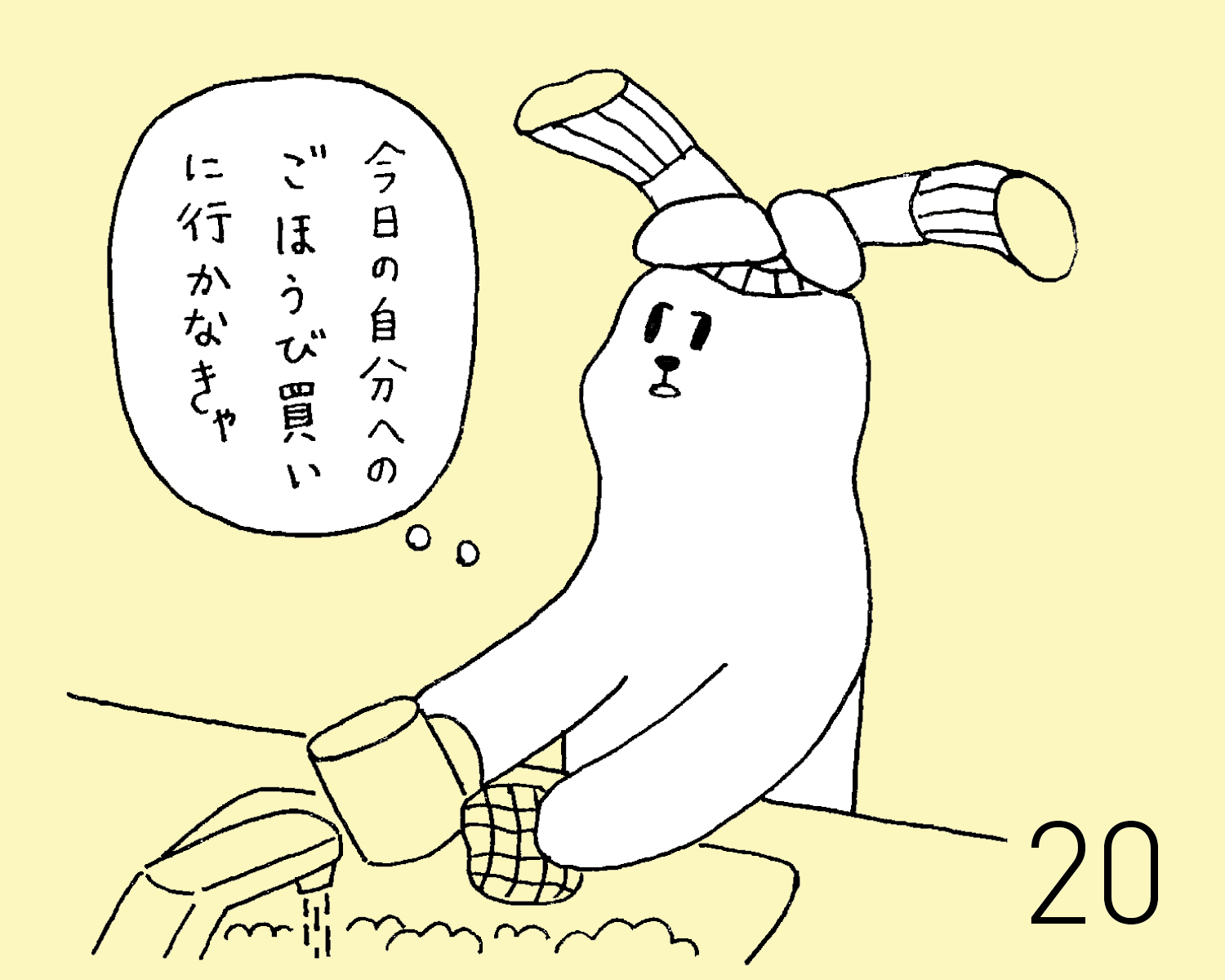専業主婦のエリザベートは夫と別れ、深夜ラジオの仕事に就き、そこで偶然、ある家出少女と出会います。主人公が人生を見つめ直し、第二の人生を始めていく姿を情緒的に描いた新作映画『午前4時にパリの夜は明ける』。繊細な心の揺れを捉えることで定評のあるミカエル・アース監督に話を聞きました。
深夜ラジオが結んだ主婦と家出少女の出会い。映画『午前4時にパリの夜は明ける』ミカエル・アース監督インタビュー

──1980年代のパリで、主婦エリザベート(シャルロット・ゲンズブール)の結婚生活が終わりを迎えるところから、この物語は始まります。彼女は一人で子どもたちを養うため、深夜放送のラジオ番組の仕事に就くことに。そこで家出少女のタルラ(ノエ・アビタ)と出会います。
この映画の「夜の声がすべてを明かす」というアイデアが気に入っています。劇中のラジオ番組の内容は、1970〜90年代にかけて放送していた「夜のこと(Les choses de la nuit)」というラジオ番組内の「あなたの名前は?」というコーナーから着想を得ました。一般人のゲストは真実を話すと誓ってから、自分の人生を語ります。唯一嘘がつけるのは、自分の名前だけ。司会者はスタジオにいますが、ついたてでゲストの姿を見ることができません。
深夜ラジオから聞こえる声は、人と人をつなぐ架け橋です。私の世代にとって、夜の声には特別な意味があります。今はそういう一般人参加型の番組が少ないし、当時ですら影響力は弱いものでした。司会者のヴァンダがエリザベートに言ったように、「もうラジオが夜を独占することはない」んです。でも今回、劇中に取り入れることで、映画に彩りを添えたいと思いました。
──タルラを家に招き入れ、年齢やバックグラウンドの違いを超えて交流していくエリザベート。演じているのは、シャルロット・ゲンズブールです。一緒に仕事をして印象的だったことを教えてください。
シャルロットの直観力、知性、感受性には目を見張るものがあります。ごく控えめな人で、私たちは作品や役について、そんなには話していなかったんです。それなのにいざ撮影が始まるとすぐ、エリザベートの感覚をきちんとつかんでいて驚きました。繊細なもろさと、どっしりとした力強さという、この役の二面性をよく理解してくれていましたね。
エリザベートはミドルクラスのごく平凡な女性ですが、知ってのとおりシャルロットは自身も家族も有名で、あえて言えば私たちとは違う世界にいる人です。にもかかわらずこの役を演じこなしていて、本当にプロ意識が高い。一言も文句を言わず、100%全力で取り組んでくれました。
──シャルロットが別のインタビューで「この映画では、自分自身のリズムでゆっくりしゃべっています。『もっと早く話した方がいい?』と監督に聞いたら、『あせらなくて大丈夫だよ』と言ってくれました」と話していたのが印象的です。そう伝えたのはなぜですか?
リズムというのは、監督によっても作品によっても変わるのかもしれません。この作品では基本的に、どこにでもあるような普通の日常が淡々と続きます。映画とは、決してクライマックスだけでできているのではなく、回り道も含まれています。その意味で、セリフ回しにしっかり時間をかけることが、役者にとっても大切なことだと考えました。
──そういえば、歌手活動もしているシャルロットには、ジャーヴィス・コッカーが作詞に参加した『5:55』という曲があります。今回の映画に似て、早朝を思わせるエモーショナルな雰囲気の歌詞ですが、もしや今作のイメージソースだったり?
いえ、その曲は知りませんでした。でも面白い! 私はジャーヴィスのファンで、前作『アマンダと僕』(18)では、エンディング曲を作ってもらったので。シャルロットの歌手としてのキャリアはほぼ知りませんでしたが、ぜひ聴いてみたいです。

──監督は、「喪失と再生の物語」を撮り続けています。『サマーフィーリング』(15)と『アマンダと僕』では大事な人の死を映し出していましたが、今回は「喪失」の部分がさほどは描かれません。それはなぜですか?
たしかにエリザベートにとっての喪失は、直接的には描かれません。どちらかというと周縁的に描かれているというか。それは夫との別れだったり、子どもの独立だったり、時間の経過だったり。とはいえ、喪失と再生の物語を撮っている点ではこれまでの作品と同じです。
夫に捨てられたエリザベートは、以前から住んでいるアパートで暮らし続けながらも、新しい現実に直面します。ラジオスタッフだけでなく図書館司書の仕事もかけもちして、一人で家を切り盛りしなくてはならない。彼女のように、壁に突き当たったとき、なんとか脇道にそれて自分を立て直し、道を切り拓いていく人々に私は魅了されます。
──これまでの作品の主人公は、比較的若い世代だったと思います。今回、子どもが独立し始める年齢の母親を主人公に据えたのはどうしてですか?
この映画は40代後半〜50代前半の、夫と別れた女性を主人公にしたいと思ったところから始まりました。というのもなかなかこの世代の女性が主人公の物語はないからです。彼女たちにも、別れがあれば、新しい出会いもある。そのことを映し出すのが、私にとって重要でした。
──エリザベートがタルラを家に招き入れたのはなぜだと思いますか?
タルラの持っている何かが、エリザベートの心に触れたんでしょうね。彼女自身も別れを経験し、精神的に弱っているところでした。同じくもろさがあるタルラを助けることが、逆説的にですが、エリザベート自身に力を与えたのではないかと思います。
──エリザベートが子どもたちの成長について感じる喜びと、少しの切なさが心に沁みました。子どもにとって初めての選挙に親子で行ったり、実家を出た娘の住んでいる家を訪ねたり。
今言ってくれた場面はとても重要です。特に娘ジュディット(メーガン・ノータム)の家を訪ねるシーン。一見なんでもないシーンですが、エリザベートはそこで初めて、娘が本当に自分のもとを去ったんだと実感するわけです。「これまで娘はバカンスに行っているみたいな気でいたけど、本当にうちから出ていったんだね」といったセリフを言っていたはず。このとき、娘だけでなく母自身も人生のページをめくっているんです。
ささいなシーンに感動することってありますよね。つまり、日常の中にこそ感動があるんだと、そこでは伝えたいと思いました。私が最も好きなシーンの一つですが、思いついたのは共同脚本家の女性(モード・アメリーヌ、マリエット・デゼール)の一人です。
──タルラがエリザベートの息子マチアス(キト・レイヨン=リシュテル)と娘ジュディットと映画館に忍び込み、エリック・ロメール監督の『満月の夜』(84)を観るシーンも楽しいですね。でもその後、住所のないタルラの「寒い日は暖を取るために映画館に行く」というセリフがあって、また違った意味を帯びてきます。
私が思春期の頃は、まだ実際に映画館の裏口から潜り込む人がいました。今ではかなり規制が厳しくなって、タダ観はできなくなりましたけど。その思い出から、タルラが「暖かいから」という単純な理由で映画館にこっそり入ってみたら、上映していた映画が案外面白く、物語に自分と重なる部分があると気づき、期せずして文化的なものに触れていたというアイデアを思いついて。苦労続きのタルラにプレゼントを送るつもりで書いたんですが、これも思い入れのあるシーンになりました。
『午前4時にパリの夜は明ける』

1981年、パリ。結婚生活に終止符を打ったエリザベートは、一人で子どもたちを養うべく、深夜放送のラジオ番組の仕事に就くことに。そこで偶然出会った家出少女のタルラを自宅へ招き入れる。ともに過ごすうちに、「家族」はそれぞれの人生を見つめ直していく。
監督・脚本: ミカエル・アース(『アマンダと僕』)
出演: シャルロット・ゲンズブール、キト・レイヨン=リシュテル、ノエ・アビタ、メーガン・ノータム、エマニュエル・ベアール
配給: ビターズ・エンド
2022年/フランス/カラー/ビスタ/原題:LES PASSAGERS DE LA NUIT/111分
シネスイッチ銀座、新宿武蔵野館、渋谷シネクイントほか全国にて絶賛上映中!
©️ 2021 NORD-OUEST FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA
🗣️
Mikhaël Hers
1975年、フランス・パリ生まれ。名門映画学校・La Fémisにて製作を学び、2004 年に卒業。初の長編作『Memory Lane』(10)がロカルノ国際映画祭でワールドプレミア上映されたのち、長編第2作『サマーフィーリング』(15)を手がける。前作『アマンダと僕』(18)では、ヴェネツィア国際映画祭オリゾンティ部門にてマジック・ランタン賞を受賞し、また東京国際映画祭にて東京グランプリ&最優秀脚本賞をW受賞。今作『午前4時にパリの夜は明ける』は第72回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に正式出品された。
Photo: Yuka Uesawa Text&Edit: Milli Kawaguchi