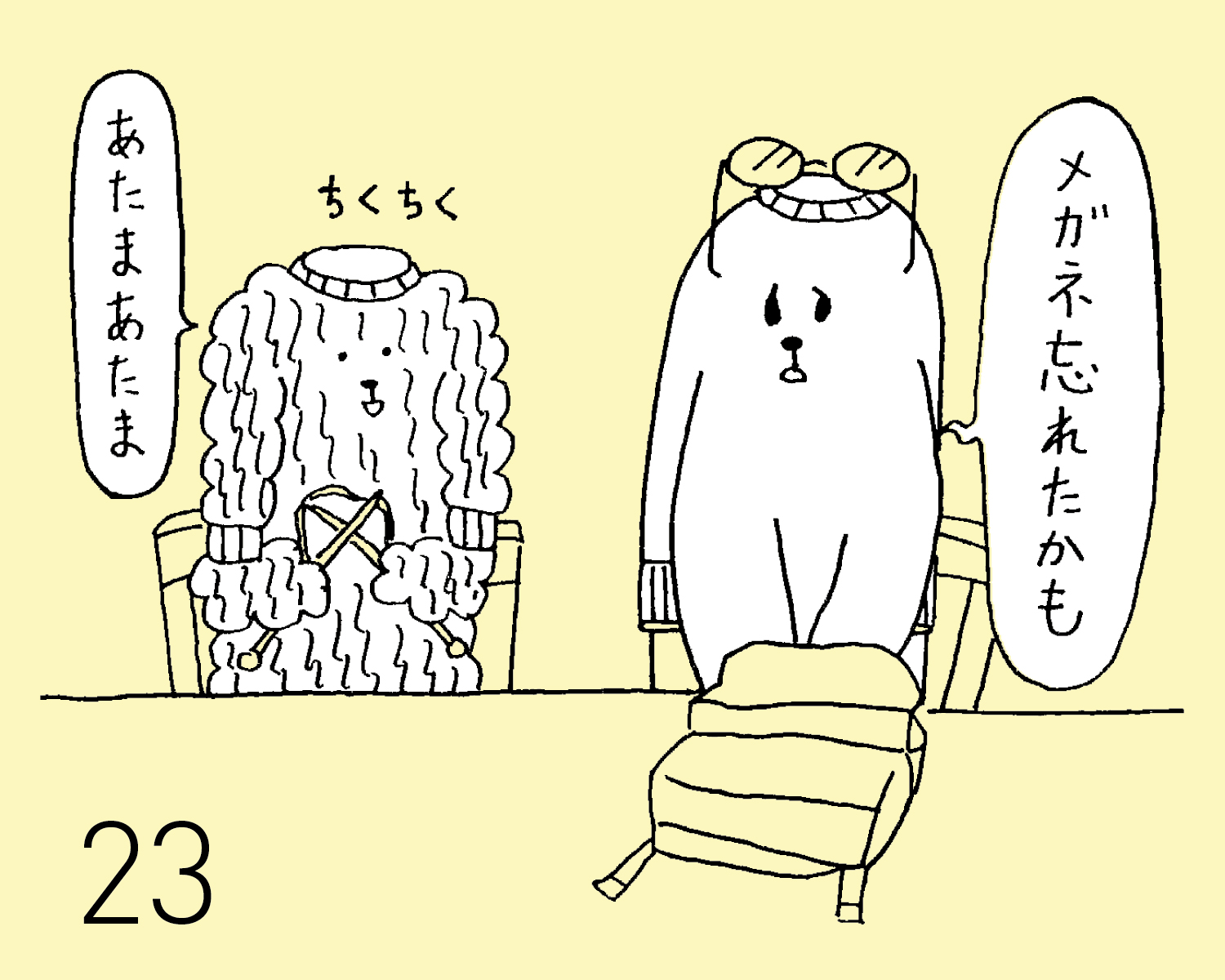2016年『淵に立つ』でカンヌ映画祭「ある視点」部門審査員賞を受賞するなど、国内外で高く評価される深田晃司監督最新作『LOVE LIFE』。ミュージシャンである矢野顕子さんが1991年に発表した『LOVE LIFE』の表題曲を聞き、映画化する構想を抱いたという深田さんが、20年の月日をかけて描いたある夫婦の物語だ。本作で、幸せな人生を手にしたはずの主人公・妙子を演じた俳優の木村文乃さんと深田さんに聞いた本作の魅力とは?
木村文乃主演×深田晃司監督。それぞれの『LOVE LIFE』に思いを巡らす。

──深田さんと木村さん、それぞれが現場に入って意外に思った側面はありましたか?
木村文乃(以下、木村):監督は、よくボタンを掛け違えて現場に来ます。
深田晃司(以下、深田):いや確かに。あの否定はしないです。あ、マズイと思って直してるのバレてんだ。そういう類いの話でいいんだったら、これ現場でみんなも言ってましたが、木村さんは着替えがものすごく早い。
木村:そうですね。
深田:テキパキと早くてびっくりですよ。それで聞いてみたら、「どうやったら早く着替えられるかを論理的に考えている」とおっしゃってて。衣装合わせのときも、一般的に男性の俳優さんは着替えが早くて、女性の俳優さんは結構時間がかかるという傾向があって、木村さんが着替えに入ったのでちょっと休憩みたいな気持ちでいたら、ピュッと行ってピュッと出てくる。
木村:座らせないっていう(笑)。現場に入る前から、リハーサルもそうですし、韓国手話の練習にもずっと来ていただいていたので、ある程度こういう人っていうのを事前に知れたので、あまり意外っていうところはなかったかもしれません。
深田:そうでしたね。この映画のための木村さんの一番最初の作業って、韓国手話の先生から手話を習うことだったと思うんです。クランクインの3カ月前頃かな。すごく印象的だったのは、木村さんがとても楽しそうに手話を習っていたんですね。やっぱり、準備時間がそこまで潤沢にあったわけではないし、他の仕事も抱えられながらの練習だったので、ここで大変そうだったら、きっと辛いだろうなと思ったんだけど、楽しそうな木村さんを見て、なんとかなるんじゃないかと安心したことは覚えてます。
木村:実際、本当に楽しくて。手話って、伝えるための手段だと思っていたんですけど、 本当に英語や中国語みたいな新たな言語を覚える感覚なんですよね。それが知れたことが嬉しかったですね。

ドレス(sacai )
──本作では、悲しい出来事に襲われた妙子が、夫・二郎(永山絢斗)と暮らしながらも、元夫でろう者のパク(砂田アトム)との交流で傷を癒していったり、二郎もまた元恋人と時間を過ごしたり、道徳的観点で見てしまうと登場人物の行動が矛盾しているようにも思える。でも、その感情と行動がなぜかわかるという自分にも気づかされます。お二人は、自分の中の矛盾に対して、普段どういうふうに対処していますか?
深田:たぶん、矛盾は、人から見てる方が矛盾として際立って見えるんだろうなと思っていて、自分の中だと、矛盾しているように見えてもどこか感情的にはつながっていたりする、ということがあると思う。なので、矛盾を見つけても、人ってそういうもんだという感じで、受け流している場合が多い。人としてどうかみたいな矛盾でない限りは。
木村:私は、あんまり考えてないですね。そんなに矛盾と思わないかもしれない。『LOVE LIFE』の登場人物たちも、ちゃんと人間してるだけなんだよねって思っちゃいます。たぶん、完璧な人なんていないですし、良いとか悪いという話をしてないので、気持ちよく見られるというか。
深田:そう言ってもらえるのが嬉しくて、映画を作るときに、理想的な人物を出したいとはまず思わないんです。理想をお客さんに示したとして、この人みたいに行動しましょう、と啓蒙するようなことは映画でやる意味はあんまりないんじゃないかと自分は思っていて。しかも、登場人物の行動の善悪を倫理的に裁いてほしいとも思っていなくて、自分には人間はこう見えてる、っていうものをただ示してるつもりなんです。でも「いや、この人ひどいよ」ってよく言われてしまうんだけど(笑)。
──言われれるんですね(笑)。
深田:まぁ、言われることもありますね。僕は日常でも、生まれついていい人も悪い人もいなくて、関係性の中で見え方が変わるだけだと思っているんですね。それに、登場人物に対してどう思うかは、むしろ観ている人自身の倫理感や、善悪に対する感情みたいなものによるんじゃないかなと。だから、この映画の登場人物を「この人の行動は許せない」と感じるか、「こういうこともあるよね」と感じるかによって、その人自身の考え方や哲学が炙り出されるといいなとは思っています。ただ、ちょっとだけ意識したのは、妙子だけが悪者にならないようにしようと。
──確かに、等しく人間らしい行動をしてました。
深田:今回は四角関係のメロドラマですが、女性が自分の感情に素直に動くことによって、男性が振り回される。常に男性が道徳的な安全圏にいる物語にはしたくなくて、男性、女性関係なく、人間なんて等しくこんなもんだというふうにしたかった。なので、ちょっと意識的にみんなそれなりに誰かを裏切ってるというシーンを作りました。

──監督である深田さんの人となりを事前に知れたことは、撮影現場での安心感につながりましたか?
木村:そうですね。現場は本当にいい一瞬のシーンを撮るためにみんなが集まっているので、心地いい緊張感みたいなものはずっとあるんですけど、今もそうなんですが、監督の隣にいるとすっごく安心するんですよ。猫とこたつ、みたいな気持ちになる(笑)。
深田:あー(笑)。
──ホーム感みたいなことなんでしょうか?
木村:それもあるんですかね。本当に優しい人って、ちゃんと伝えてくれる人だと私は感じていて、監督は気遣いをするという優しさの中に、伝える大事さを持ってらっしゃるので、たぶん安心するんだと思います。
深田:監督をやってると、他の監督さんの現場を知らないからわからないんですが、やっぱりスタッフをやっていた時代に、何も言ってくれない怖い監督さんって結構いたんですね。何も理由を言わないでNGを出すとか。ただ自分も、映画オタクとして映画ばかり観て育って、20歳くらいで実際に自主映画を作ろうと思ったときに、生身の俳優さんへの接し方がわからないんですよね。 ずっとスクリーンの中の俳優さんしか見てこなかったから、やっぱり無茶を言いがちなんです。自分のイメージ通りに動いてくれないので、「なんでできないの?」と俳優にも自分にもイライラしてしまう。
木村:はい。
深田:でも、25歳の頃に、留学くらいの気持ちで劇団「青年団」に入って、まず何か変わったかというと、周りに150人ぐらい俳優の同僚ができたんです。彼らと話をして、作り手の論理で行われる演出がいかに俳優にとってやりづらいものであるか、俳優を傷つける横暴さを秘めているかを知ることができた。自分もまだ全然、完璧にできているなんて思っていませんが、やっぱり俳優さんと接する上で勉強になりましたし、理由を言わないことはやめようと思うようになりました。
──わかっていると思っていることも実際はわからない、ということがすごく描かれている作品でもあると思いましたが、わからなさというものに対して、お二人はどう付き合っていますか?
深田:これはわからない、ということありますよねー。
木村:ありますね。まあでも、とりあえず、そばにいてみますね。
深田:それはえらい。
木村:まさに、今回「なんでなんで?」とずっと思いながら、妙子をやっていたので。でも、妙子を通して学んだことがあるとすれば、そこに対して突き詰めてもいい結果がない。
──突き詰めたところでわからないですんね。
木村:そうなんですよね。でも、好きな人にしかしないですよ。誰も彼もにはしないです。
深田:大抵のことはわからないことが前提である、という風に思った方がいいかなと考えていて。俳優さんに求めることも同じで、そういう意味でも、今回、木村さんはすごくいい匙加減で演じてくれたなと思うんです。
木村:よかったです。できれば、毎シーン毎シーンいいシーンにしたいじゃないですか。でもまあそうもいかない。そのまだわからない役と自分が、ものすごいこうガチッとリンクする瞬間ってあるんですよね。言葉とか理屈じゃなくて、あ、なんか今腑に落ちたみたいな感じって言うんですかね。

──監督をされていると、俳優さんのそういう状況が見て取れるものなんですか?
深田:どうだろう。木村さんの中であったのかもしれないんだけど、自分がちゃんとそれを見れていたかどうか。
木村:恥ずかしいぐらい、きっちり掬い取っていただいたと思います。
深田:相手のことがわからないと思えるかは、相手も自分のことがわからないかもしれないと思えるかどうかじゃないかと。 どんなに言葉を重ねても、多分100パーセントわかり合えるってことはあり得ないんだっていうことを前提にして、1%でもそこに近づけるために話していくことをなるべくしようとは思っています。
木村:今回、宣伝でインタビューをしていただきながら大変だなと感じるのが、たとえば役作りについて聞かれたりするんですけど、色々こう頭でガチガチに考えてから入ることを監督が望んでないから、ないんですよ。そこにあるものという感じだったってことくらいしか。だって、 すごく素敵な台本とそれを作ったご本人が現場にいるから、何かあれば監督に聞けるし。
深田:脚本家と監督が異なるケースも多いですもんね。
木村:いろんな人の意見が入ってきて、誰の意見が正しいの?みたいなことにもなってしまう場合もあるので、やっぱり、監督が揺るがずにいてくれて、決定権があるという現場は私たちにとってはすごくやりやすいですね。
深田:自分が比較的苦手なタイプなのが、人物のキャラクターや気持ちを説明し過ぎてしまう芝居なんです。俳優さんがそういう演技を求められることもあると思いますし、それが正解な時もあるんですが、脚本を読み込んで、性格、職業、感情も含めて現場に入ったらこう演じようと作り込んだキャラクターを上手に演じられると、見ていてすごくわかりやすい。
でも、私たちがこうやって生きていて、周りを見たときに、 人物像がわかりやすくアウトプットされている人ってあまりいないですよね。自分はこういう性格だから、こう喋ろうなんて意識しないし、究極を言えば、自分の本心だってわかっているかどうかも曖昧なのに、そんなに上手く説明なんてできるわけはない。そこを意識して脚本を書いていますし、俳優さんにもそう演じてほしいとは思っています。
──この映画は、矢野顕子さんの楽曲「LOVE LIFE」から派生した物語ですが、この曲を最初に聞いた時に、木村さんはどんな感想を抱かれたんでしょうか?
木村:ものすごくパワーを持った歌だなと思って、そりゃあここから物語も生まれるわと。恐ろしい曲ですよ。
深田:(笑)。そう、最初にね、お会いしたときにこの曲をかけさせてもらって。
──楽曲も映画も、自分の人生における「LOVE LIFE」について考えるきっかけをくれるものですね。答えを求めているわけではないのですが、お二人は自分の、もしくはこの映画の妙子、二郎、パクの「LOVE LIFE」ってなんだろうということについては考えましたか?
深田:自分の場合、「LOVE LIFE」という曲と映画はもうセットなので、歌詞のイメージになってしまうのですが、愛されることができるじゃなく、あくまで主体的に誰かを愛することができる。そこがこの歌の豊かさだなと。妙子という人物も、しっかりとした主体性の強い女性ですが、実は彼女も元夫パク、息子の敬太、再婚した二郎といった誰かとの関係性の中で生きてきた人で、その中でこれから彼女がどう生きていくかという話だと思っていて、「LOVE LIFE」の答えは、みなさんぜひそれぞれ考えてもらえたら。
妙子:妙子はそれをこれから探すというか、これから出会うんだろうなと思っています。
『LOVE LIFE』
妙子(木村文乃)が暮らす部屋からは、集合住宅の中央にある広場が⼀望できる。向かいの棟には、再婚した夫・⼆郎(永山絢斗)の両親が住んでいる。小さな問題を抱えつつも、愛する夫と愛する息子・敬太とのかけがえのない幸せな日々。しかし、結婚して1年が経とうとするある日、夫婦を悲しい出来事が襲う。哀しみに打ち沈む妙⼦の前に、失踪した前の夫であり敬太の父親でもあるパク(砂田アトム)が現れる。
監督・脚本: 深田晃司
主題歌: 矢野顕子
出演: 木村文乃 、永山絢斗、砂田アトム、山崎紘菜、嶋田鉄太 、三戸なつめ 、神野三鈴、田口トモロヲほか
配給: エレファントハウス
2022年/123分/G/日本
(C)2022映画「LOVE LIFE」製作委員会&COMME DES CINEMAS
TOHOシネマズシャンテほか全国公開
🗣️
深田晃司
1980年生まれ、東京都出身。1999年、映画美学校フィクションコース入学。2005年、平田オリザ主宰の劇団・青年団に演出部として入団。10年、『歓待』が東京国際映画祭日本映画「ある視点」作品賞、プチョン国際映画祭最優秀アジア映画賞受賞。13年、『ほとりの朔子』が、ナント三大陸 映画祭グランプリ&若い審査員賞をダブル受賞。16年、『淵に立つ』が第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査員賞、第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。18年公開の『海を駆ける』で、フランス芸術文化勲章「シュバリエ」受勲。ドラマ「本気のしるし』(19/メ~テレ)を再編集した「本気のしるしTVドラマ再編集 劇場版》』は、第73回カンヌ国際映画祭「Official Selection 2020」に選出された。
🗣️
木村文乃
1987年10月19日生まれ、東京都出身。映画『アダン』のオーディションでヒロインに選ばれ、2006年公開の同作品にて女優デビュー。同年、映画『風のダドゥ』で映画初主演。2014年、第38回エランドール賞新人賞を受賞。主な出演作は、映画『ポテチ」(12/中村義洋監督)、『くちびるに歌を」(15/三木孝浩監督)、『伊藤くん A to E』(18/廣木隆一監督)、『ザ・ファブル』シリーズ(19・21/江ロカン監督)、ドラマ『梅ちゃん先生』(12/NHK)、『マザー・ゲーム~彼女たちの階級~』(15/TBS)、『殺人分析班』シリーズ(15~19/WOWOW)、『サギデカ」(19/NHK)、『麒麟がくる』(20/NHK)、『七人の秘書』(20/テレビ朝日)など。